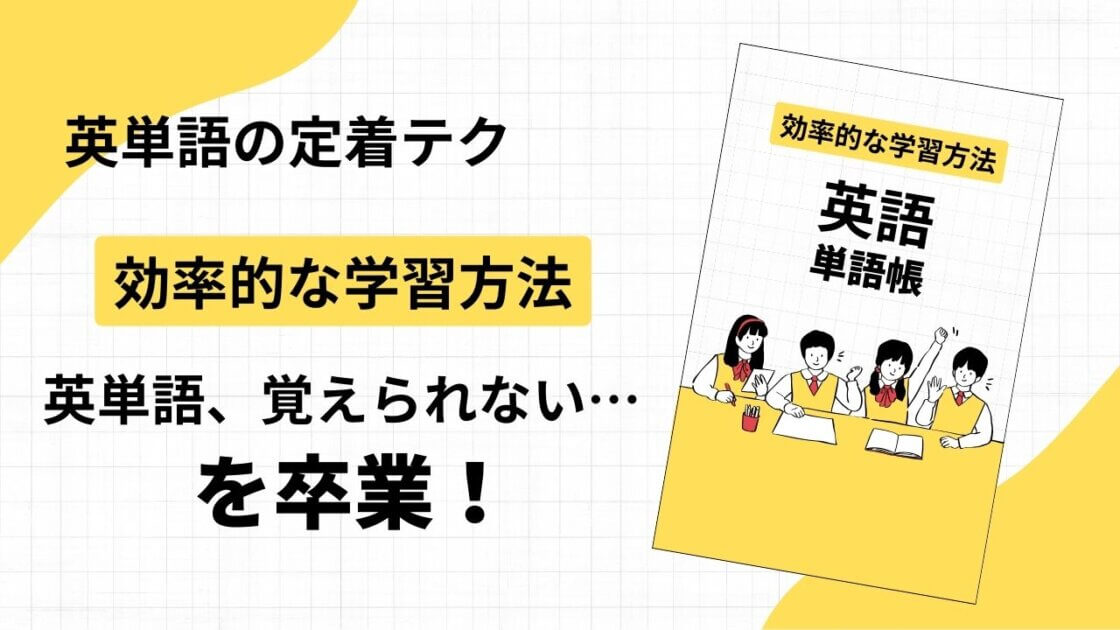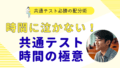「単語帳を回しても翌日には抜けてしまう…」
英単語が覚えられないという悩みは、多くの受験生が経験するものです。しかしこれは、努力不足の問題ではなく、記憶の仕組みと勉強の設計が噛み合っていないサインかもしれません。
脳の仕組みに合わせた学習法を取り入れることで、同じ時間でも定着度が大きく変わります。この記事では、科学的根拠に基づいた効率的な英単語暗記法を、具体的な毎日の取り組み方とともに解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
つまずきの正体
単語は「見ただけ」では定着しづらく、声に出すと覚えやすくなる現象を「プロダクション効果」と呼びます。黙読よりも音読のほうが記憶に残りやすく、文章レベルでも効果があることが研究で示されています。
しかし、声に出すだけでは不十分です。単語には「意味」「綴り」「発音」の3つの顔があり、それぞれ手がかりを増やすことで思い出しやすくなります。「二重符号化(Dual Coding)」を活用し、文字・音・絵を組み合わせると記憶の足場が二本立ちになり、片方が欠けてももう片方が助け舟になります。
また、意味の近い単語をまとめて覚える「セマンティック・クラスター」は初学者には干渉を生みやすいです。学習では「テーマ別(例:レストラン場面)」のように分ける方が混線を避けられます。
さらに、単語はさまざまな文脈で出会うほど定着しやすくなることが報告されています。「コンテクスト多様性(Contextual Diversity)」の考え方に基づき、教科書・ニュース・歌詞など複数の媒体で同じ語に触れる学習設計が効果的です。
記憶の骨組み
覚えにくい単語を残りやすくする方法を紹介します。
1. 声×口×耳の三拍子
単語を見て、口を動かして発音し、直後に自分の声を短く聞き返す。対象は「覚えたい語だけ」に絞ると効果が高まります。
2. 見える化×イメージ化
単語と短い絵・記号・図式を結びつけることで取り出しルートが増えます。抽象語は比喩や自分の経験に引きつけた一言メモでも代用可能です。
3. 意味の近さの干渉回避
ナイフ・フォーク・スプーンなど、意味が近い語は同日に入れず、別の日に分けます。初学者は干渉を避け、上級者になったら関連語をまとめて差分で覚えると効率的です。
4. 文脈の違いを広げる
教科書→ニュース→歌詞→解説動画の順で単語に触れ、各場面で短い自作文を一行ずつ作る。これにより、別ルートでの呼び出しが容易になります。
5. キーワード法
音が似た日本語と単語の意味をつなぎ、小さな絵を作る方法です。抽象語は、自分の体験や感情に寄せた短文と結ぶと記憶に残りやすくなります。
6. カタカナの呪縛への注意
外来語の発音に引っ張られると英語音とズレます。「耳→口→綴り」の順でオリジナル音を確認する習慣をつけましょう。
7. 似た語の渋滞回避
意味・音・綴りが似た語は日をずらして学習。さらに、声に出す→タイピング→手書きで扱うと手がかりが増え、記憶の区別性が高まります。
8. 親戚語の活用
英語と他言語で形・意味が似た同根語(コグネート)は覚えやすく、処理も速くなります。身近な語を正しい音・意味で使い直すことがポイントです。
毎日の設計
忙しい受験生でも実行できる一日の回し方です。
- 朝(通学中10分):アプリで10語を聞き、電車では口パクで発音。出てこなかった語だけメモ。
- 放課後(15分):“骨組みタイム”として、二重符号化+短文作成+干渉回避の三手を実施。今日の10語に集中。
- 夜(布団前5分):朝メモした出てこなかった語だけ音読。選択的音読で区別性を高める。
週に2回は「文脈の幅を広げる日」を設け、ニュース記事や歌詞などで同じ語に出会い、一行メモを作ります。教材は意味が似すぎる単語が連続するページは避け、場面別リストを小分けに回すと干渉を和らげられます。
キーワード法は“要救助語”に絞り、カタカナ便宜は認めつつオリジナル音に戻す習慣を守ります。モチベ波に備え、最低ラインを設定して小目標を達成することも重要です。
最後に
英単語は、がむしゃらに回すだけでは定着しにくいですが、声に出す・イメージを添える・干渉を避ける・違う文脈で出会う、という四つの軸を守ると伸びやすくなります。手がかりを増やし混線を減らすことで、同じ時間でも記憶の定着度が大きく変わります。