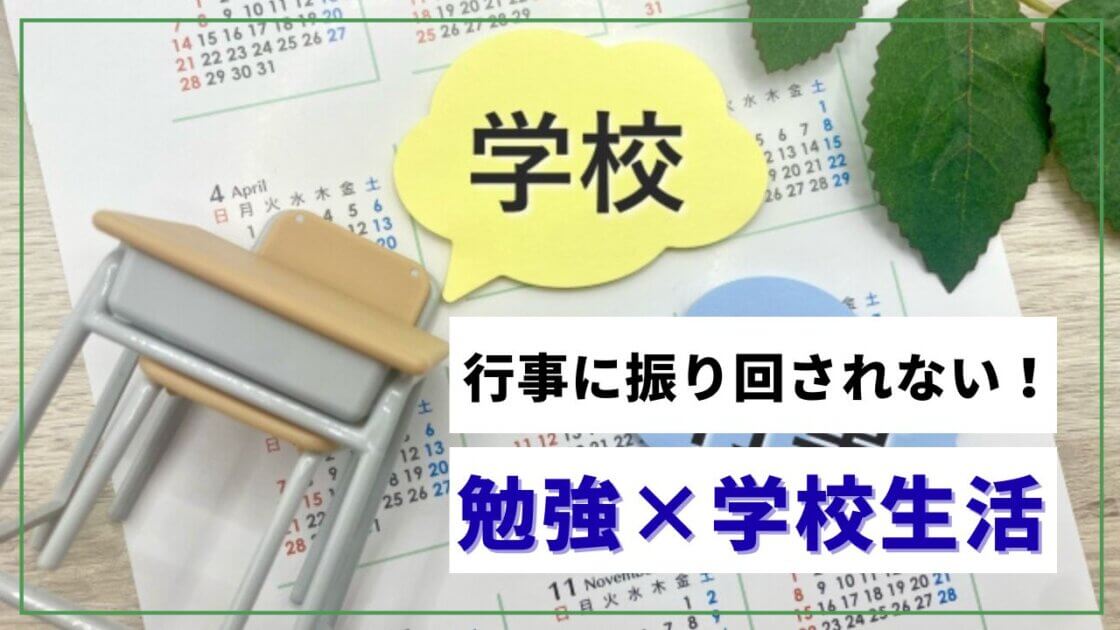「文化祭の準備で毎日遅くなる」「体育祭の練習で体力が尽きる」「合唱祭や修学旅行でリズムが崩れる」——。
こうした学校行事の時期、勉強が思うように進まないと感じる学生さんは多いのではないでしょうか。
学校行事は青春のハイライトであり、仲間との貴重な時間でもあります。しかし、受験期に重なると学習のペースが乱れ、気力や体力が追いつかなくなることもしばしば。
だからこそ、「行事を障害ではなく、前提条件として設計する」発想が重要です。
本記事では、行事シーズンの中でも学習を止めないための科学的アプローチと実践的な両立法を紹介します。
時間・体力・注意・感情の4つを整えながら、行事も勉強も両立する“現実的な戦略”を一緒に見ていきましょう。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
学校行事は「障害」ではなく「設計すべき前提条件」
「文化祭の準備で毎日遅くなる」「体育祭の練習で体力が尽きる」「合唱祭や修学旅行で勉強のリズムが崩れる」——。
学校行事は楽しくもあり、時に勉強のペースを乱す存在です。
行事は学校生活のハイライトですが、受験期には“時間と集中のリズム”を奪いがち。気合いだけで乗り切ろうとすると疲労が溜まり、翌週に響きます。
だからこそ、行事を“障害”として扱うのではなく、“前提条件として設計する”視点が大切です。
時間・体力・気持ちの三つを同時に整える発想が、現実的で持続可能な両立を生みます。
「時間が足りない」だけではない両立の壁
行事が重なると、「勉強時間が取れない」と感じる人が多いでしょう。
しかし実際は、時間だけでなく、注意・体力・感情の4つの要素が複雑に絡んでいます。
準備や本番、片付けまでの“見えない仕事”が多く、帰宅後の気力は残りにくいもの。
役割が増えることで決断の回数が増え、「判断の疲れ」が勉強の着手を遅らせます。
また、急な練習や係の呼び出しで予定が崩れると、修正作業に時間を取られ、焦りから質を下げてしまうことも。
さらに、注意の切り替えにも負荷がかかります。準備会議から英語長文へ、制作作業から数学の証明へ——。
このジャンプには頭の“歯車”の調整が必要です。逆に言えば、切り替えを前提にした時間の並べ方に変えることで、負荷は下げられます。
立ち仕事や移動が増える時期は体力の消耗も大きく、集中の深さが変わります。
人間関係の緊張も見逃せません。係の調整や出し物の方向性の違いがストレスになり、学習意欲を削ぐこともあります。
つまり、両立の壁とは「時間管理だけの問題」ではなく、時間・注意・体力・感情の4要素を束ねる仕組みが必要なのです。
科学で考える「行事期の勉強設計」
心理学・行動科学の視点から見ると、行事期の学習には以下のような工夫が有効です。
- ① 時間見積もりの楽観を防ぐ:「余白」を混ぜる
人は予定を楽観的に見積もる傾向があります。準備や片付けを含め、あらかじめ“余白時間”を設けましょう。 - ② 判断疲れを減らす:「迷い」を外に出す
制服や持ち物、勉強順序を定番化するだけで、意思決定の負担が減り、勉強への着手が早くなります。 - ③ 注意切り替えのコストを下げる:「似た処理」で科目を並べる
たとえば、「英単語→英文法→英長文」といった形で似た思考を続けると集中が続きやすいです。 - ④ 睡眠を優先する:夜は光を弱めて復習タイムに
遅くまでの作業は翌日の集中を削ぎます。寝る前に“軽い復習”を行い、睡眠で記憶を定着させましょう。 - ⑤ 適度な緊張を利用する:「リラックスの切り替え」
深呼吸や短い散歩で高ぶりを下げてから学習へ入ると、思考の幅が広がります。 - ⑥ 社会的支えを使う:「次の一手」を共有する
友人や家族と進捗を共有すると、継続率が上がるという研究もあります。叱咤より伴走が効きます。
実践編:行事期を乗り越える「運用設計」
ここからは、科学的知見をもとにした実践メソッドです。
- 行事カレンダー版の学習地図を作る
行事のピーク日や準備日、本番翌日を色分けし、それぞれに合う学習内容を割り当てましょう。 - 「前減後増」で負荷を調整する
行事の3日前から学習を軽くし、翌々日に少し増やす形にします。体力の波に合わせると効率が上がります。 - 「重タスク」「軽タスク」を常に2種類持つ
移動が多い日は軽タスク、静かな日は重タスク。どちらかしかできなくても進捗は積み上がります。 - 「行事期キット」を作る
カード・付せん・耳栓・短い問題集をまとめたポーチを携帯。机がなくても勉強を進められます。 - スロット学習で時間を刻む
15分・7分・3分の3段構成で勉強を設計。短くても「回す」習慣が波に強い勉強を作ります。 - 体力を足し算で守る
階段を使わない・荷物を軽くする・座る場所を選ぶ。小さな節約の積み重ねが集中力を残します。 - 視界と通知のノイズを削る
壁向きの席を選び、スマホは一日2回だけ確認。集中力の密度が戻ります。 - 「ゼロトレース片付け」で再開を軽く
勉強を終えるとき、机の痕跡を60秒で消す。未来の自分がすぐ始められます。 - 「夜のリセット」で翌日を守る
寝る前の10分を「今日の要点3行メモ」に。静けさが翌日の注意力を助けます。 - 「音の学習」で移動を活用する
用語の口頭再生や録音した教科書を聴くなど、手が塞がっていても進む学習を用意。
最後に:行事を「味方」にする設計思考
学校行事との両立は、単なる根性論ではなく“設計”の問題です。
時間・注意・体力・感情の4つを束ねる仕組みを整えれば、行事の多い時期でも学習の線は途切れません。
今日できる一歩は、
- 行事カレンダーに色をつける
- 行事期キットを作る
- 就寝前の三行メモを始める
——この3つです。
行事は避ける対象ではなく、「設計して味方にする対象」。
小さな整備が積み重なれば、どんなに忙しい季節でも「学びを止めない自分」を保てるはずです。