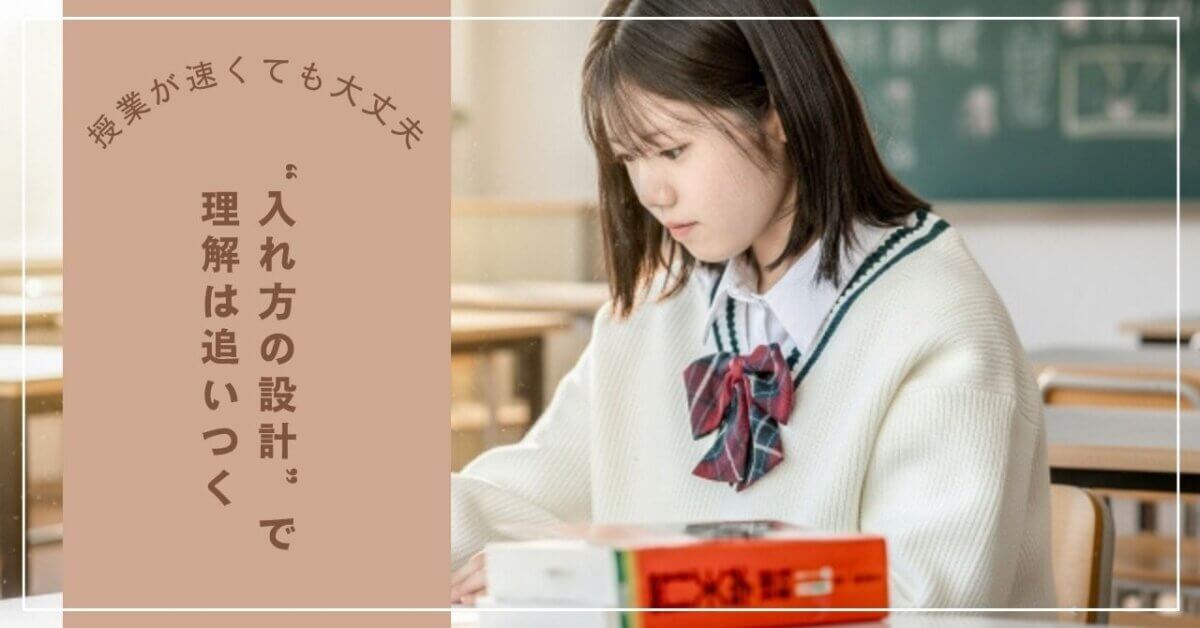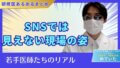「黒板の式が一行進むたびに、意味が抜けていく……」
「ノートは埋まってるのに、頭の中は空っぽ」
そんな経験、誰にでもあります。
授業についていけない原因は、決して“頭の良し悪し”ではありません。
実は、授業中に起こる“情報処理の渋滞”が、理解の遅れを生んでいるのです。
本記事では、学習科学の視点から「なぜ授業が速く感じるのか」を分解し、
明日から実践できる“追いつくための工夫”を紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
なぜ授業が速く感じるのか:遅れの正体は「情報処理の渋滞」
授業中、黒板の式が進むたびに頭が追いつかなくなる。
その理由は「難しい内容」だからではなく、脳が一度に扱える情報量を超えているからです。
ワーキングメモリ(作業記憶)は限界があり、余計な刺激や同時入力が重なるほど、思考の通り道は細くなります。
さらに、先生は“完成形の思考”を圧縮して話すため、前提を共有できていないと理解の橋がつながりません。
このずれを「前提の非対称性」と呼び、語彙や図の理解の差が大きいほど広がります。
授業の難しさは“内容”よりも“情報の入り方”にあるのです。
授業中の工夫:「受け身」を細切れに減らす
授業の理解度を上げるコツは、「写す」から「処理の節目づくり」へと発想を変えること。
- 合図→停止→要約の三拍子
新しい記号や定義が出たらペンを止め、10秒で「今の一言」を6〜10文字で要約。
例:「置換の導入」「平均の変形」「例外の除外」など。
ノートに短く積む要約が、後で見返したときの“道しるべ”になります。 - 例題→一問の交互配置
解法を聞いた直後に、同型の小問を一問だけ自力で解く。
「できたつもり」を壊し、理解の穴をその場で発見できます。 - 空欄補完ノート
板書をすべて写さず、導出の途中に空欄を残し、
〈この式の変形は?〉〈この矢印の根拠は?〉と自分の問いを書いて後で補完。
受け身を減らす“小さな生成活動”になります。 - 二択自問
〈この定義は集合Aだけ?〉〈場合分けは3通り?〉など、
声に出さずYes/Noで答える二択の質問をノートに。
思考を往復させるだけで、注意が持続しやすくなります。
さらに、視覚的にも整理します。
黒板の配置に合わせてノートを左右に整え、図と説明を近づけることで理解の線が保たれやすくなります。
三色ペンも“装飾”ではなく“ラベル”に――黒=事実、青=理由、赤=注意と役割を固定するだけで、検索スピードが上がります。
そして授業の最後に「泥だらけの一点」を書きましょう。
最も曖昧だった箇所を“きれいにまとめず”短く残す。
その一行が、次回の質問や復習の起点になります。
授業前後の30分設計――“理解の遅延”を縮める時間術
授業に追いつくためには、「前15分」と「後15分」の扱い方が鍵です。
- 前の15分:「予見と語彙の橋渡し」
その日の単元名と太字用語を3つだけ選び、
〈対数=指数を数に戻す装置〉のように“一言カード”で意味を再構成。
授業の冒頭で「既知の話題」として聞けるようになります。 - 後の15分:「再構成と一問転移」
授業ノートをそのまま写真で残すのではなく、
五行で“今日の核心”を書き直し、例題を少しだけ条件を変えて自作。
自分で問題を再構成することで、理解が道具化します。
また、週単位では「短い間隔の再学習」を。
月曜に授業、木曜に5分の要点再現、日曜に一問自作――この“間を空けた往復”が記憶を定着させます。
家庭でできる支援:「評価語」ではなく「工程語」で話す
親御さんができる一番のサポートは、「できた?」ではなく「どこで止まった?」「次は何を足す?」と聞くこと。
評価よりも工程を共有すると、子どもは自分で次の一手を決めやすくなります。
また、家庭の“初期設定”として、学習前の5分を静かな時間にするだけで集中の立ち上がりが安定します。
調子が悪い日は「今日は五行要約だけ」といった“引き算の設計”を。
継続は、フルコースではなく“続けられる一手”で支えるのがコツです。
最後に:理解は「量」ではなく「入れ方の設計」で伸びる
授業の速さに苦しむ背景には、情報処理の渋滞・前提のずれ・注意の残り香・分かったつもりの錯覚が重なっています。
だからこそ、「三拍子」「交互配置」「空欄補完」「語彙の橋」「五行要約」といった入れ方の設計が効くのです。
すべてを一度にやる必要はありません。
今日の時間割に“ひとつだけ”仕掛けを挿し込み、少しずつ前進を実感してみてください。
理解は、努力量ではなく「仕組みのデザイン」で加速します。