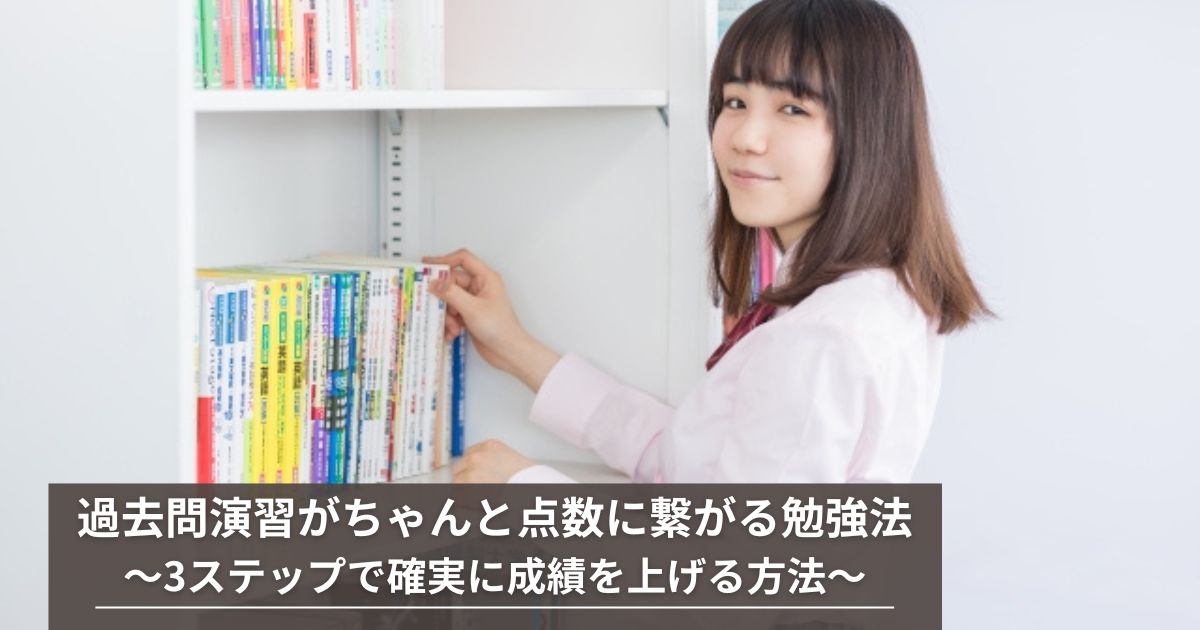過去問を解いているのに点数が伸びない──そんな悩みを抱える受験生は非常に多いです。
実はその原因の多くは「過去問の使い方」を誤解していることにあります。
「ただ解くだけ」「点数を確認するだけ」では、過去問の本当の価値を引き出すことはできません。
この記事では、過去問演習の“正しい目的”と“成果が出る使い方”を、効率の良い学習サイクルとともに分かりやすく解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
過去問演習の本当の目的を理解する
▼よくある誤解
受験生の多くは、
・「傾向を知るため」
・「時間配分の練習」
と考えがちです。
これらも大切ですが、過去問演習の本質からはズレています。
▼本当の目的は“距離測定”
過去問演習の本質は、
「自分と志望校の距離を正確に把握し、対策を立てること」。
ただ点数を見るのではなく、
●どこができていて
●どこが苦手で
●どこを伸ばせば合格に届くのか
を明確にし、その情報を使って学習計画を調整することこそが過去問の役割です。
▼最初は低得点で当然
多くの受験生のスタート地点は30〜40点前後。
そこから「どこを強化すべきか」を掴むことで、得点は確実に伸びます。
効果的な過去問演習の実践方法
▼時間配分の基本
過去問演習は 「解く時間」と同じか、それ以上の時間を復習に使う」 のが鉄則。
例:120分の試験なら、復習も最低120分。
▼復習を“本気でやる”
多くの受験生は「採点して終わり」ですが、それでは成績は伸びません。
本気で成績を伸ばす復習では、
●どう考えて間違えたのか
●どの知識が抜けていたのか
●解法のどこで躓いたのか
を徹底して確認します。
▼1週間単位の学習サイクル
最も効果が出るサイクルは以下の形式:
日曜:過去問1年分を解く(90分)+ 復習90分以上
月〜土:弱点克服に集中
次の日曜:別年度で成長確認
この「分析→強化→再テスト」のサイクルが成績アップの黄金ルートです。
課題分析と改善の具体的手順
▼3ステップの分析フレーム(課題→原因→改善策)
① 課題の特定
・どの問題を落とした?
・どの分野が苦手?
・どんな形式が弱い?
② 原因の究明
・知識不足?
・解法の理解不足?
・文脈や条件が読めていない?
③ 改善策の立案
・どの教材で補強する?
・どの練習法が最適?
・どれだけの期間で改善する?
▼具体例:英語の空所補充問題
よくある浅い分析:
→「空所補充が苦手だから練習しよう」
深い分析では、
・文法知識の抜け
・熟語の用法理解不足
・文脈理解の問題
など原因を細分化して対策を変えます。
文法弱い → 文法書で基礎固め
熟語弱い → 熟語帳で用法チェック
文脈弱い → 長文読解で慣れる
▼改善計画の立て方
・日曜:過去問→分析
・平日:弱点克服
・土曜:振り返り
・毎週の過去問で改善度を確認
具体的な数値目標も効果的:
✔ 熟語50個習得
✔ 文法書3章を完璧に
✔ 正答率を◯%改善
まとめ
過去問で成績を上げるためには、
✔ ①目的を正しく理解
→過去問は“弱点発見ツール”である。
✔ ②適切な時間配分
→復習に時間をかけるほど点数は伸びる。
✔ ③体系的な分析と改善
→課題→原因→改善策のフレームで実践。
過去問は「ただ解くだけ」では効果半減。
“分析して改善する”ことで初めて武器に変わります。
この方法を続ければ、必ず点数は伸びます。
焦らず、毎週着実に積み重ねていきましょう。