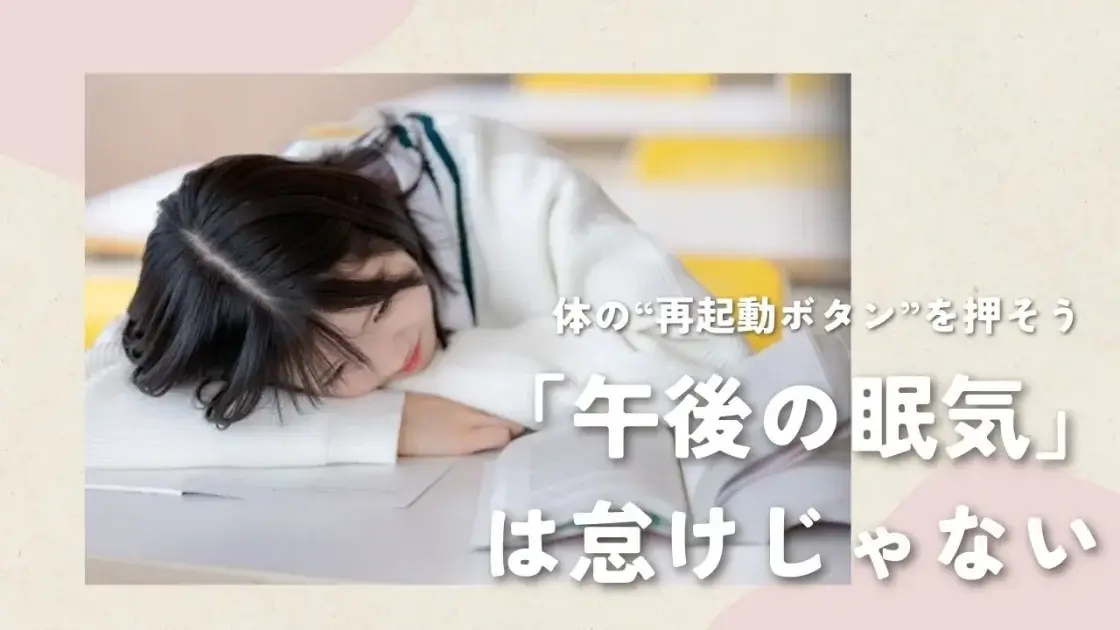昼食を食べたあとの授業や自習時間、どうしても眠くなってしまう…。
ノートを開いても頭に入らず、気づけば同じページを見つめ続けている。
そんな経験、誰にでもありますよね。
でもその眠気は「怠け」ではなく、体の自然な仕組みが原因です。
本記事では、眠気の正体を整理しながら、午後でも集中を取り戻すための
“科学的なリセット方法”を紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
午後が重くなる理由を知る
昼食後の眠気には、複数の生理的要因が重なっています。
- 血糖の波:炭水化物中心の食事を早く食べると、血糖が急上昇・急降下し、脳が“節約モード”に。
- 消化の負荷:脂質の多い食事や早食いは、胃腸に血流を取られ、全身のだるさを引き起こします。
- 体内時計の谷:午後1~3時頃は、覚醒度が自然に下がる時間帯。
- 姿勢・光・温度:薄暗い室内や前傾姿勢、ぬるい空気は眠気を助長します。
つまり、「眠い」は怠けではなく、体のサイクルが正常に動いている証拠なのです。
食べ方を整える ― “波”をなだらかに
眠気を和らげるには、血糖の上がり方を穏やかにすることがポイント。
- 食べる順番:「水→サラダ→主菜→主食」の順に。
- 早食い防止:一口ごとに箸を置き、噛む回数を増やす。
- 炭水化物の質:白米やパンだけでなく、雑穀や豆類を混ぜる。
- 量の配分:昼食を“腹八分”にし、午後に補食を回す二段構え。
- カフェインの工夫:食後15分以内に少量。10分の仮眠とセットにするのが効果的。
さらに、食後すぐに甘いデザートを摂るより、学習後のご褒美時間に回す方が安定します。
午後を動かす ― 光・姿勢・動きのリセット
眠気の波を越えるには、体のスイッチを外から入れることが大切です。
- 光を浴びる:昼食後に数分だけ外へ出て日光を浴びる。屋外が無理でも窓際でOK。
- 姿勢を整える:骨盤を立て、背中の中心で支える。足裏を床に広くつけて深呼吸。
- 空気を動かす:窓を開けて換気。冬は下半身を温め、上半身を薄着で調整。
- ミニ運動:座ったまま肩回しや足首回し。立てるなら階段を1往復。
- 仮眠の活用:10〜20分の“ナップ”で頭をリセット。長く寝ると逆効果なので注意。
- 自然を見る:校庭の緑や空を20秒眺めるだけで、視覚疲労が回復しやすい。
タスクの並べ方 ― 午後の“助走”を設計する
午後一番は、思考より動作から始めるのが鉄則です。
- 最初は手を使うタスク(グラフ作成、整理ノート、図を描くなど)
- 中盤に思考系問題(読解・証明・記述)
- 終盤に復習・暗記など“低負荷タスク”
曜日ごとに「午後一の定番作業」を固定化しておくと、習慣で動けるようになります。
健康面のチェックも忘れずに
強い眠気やだるさが続く場合、貧血・睡眠障害・薬の副作用などが背景にあることも。
「いびきが強い」「朝起きられない」「立ちくらみが多い」などのサインがある場合は、
早めに家族や学校を通じて医療機関へ相談しましょう。
最後に
昼食後の眠気は“敵”ではなく、“合図”として使える現象です。
血糖・光・姿勢・呼吸を整え、午後を“再起動”する設計に変えましょう。
今日からできる一歩として、
- 「サラダ先行」
- 「窓際で5分」
- 「十分快眠」
- 「階段2往復」
この中からひとつだけ選び、一週間続けてみてください。
午後の集中力は、微差の積み重ねで変わります。