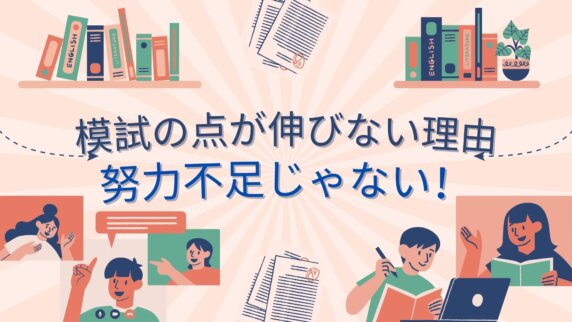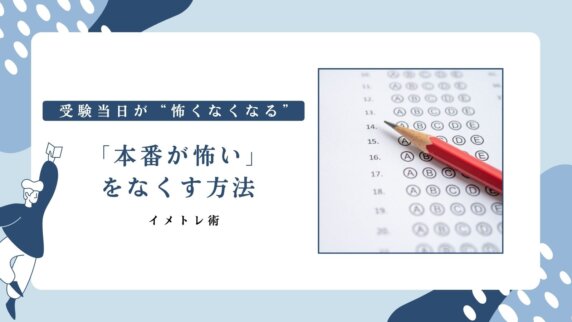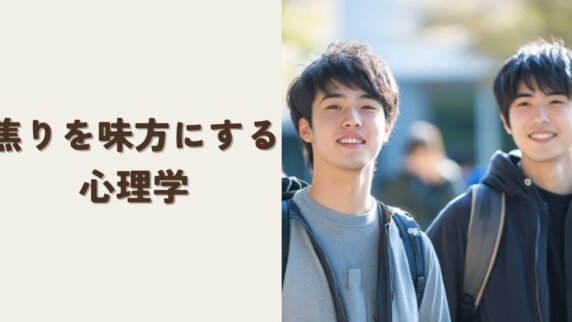 大学入試
大学入試 友人と比較して悩んでしまう高校生へ 受験期の人間関係の整え方
受験本番が近づくと、誰もが一度は経験する「比較の痛み」。
たとえば「模試で過去最高点」「志望校の先生にほめられた」──そんな話題を聞いた瞬間、胸がざわつくことがありますよね。
焦りや不安で勉強に手がつかなくなるときもあるでしょう。
でも、それは“特別な弱さ”ではありません。人が持つ自然な心理反応であり、扱い方次第で「学びの燃料」に変えることができます。
今回は心理学の知見をベースに、「比較で揺れた心」を整える実践策を、感情面と行動面の両方から整理していきましょう。