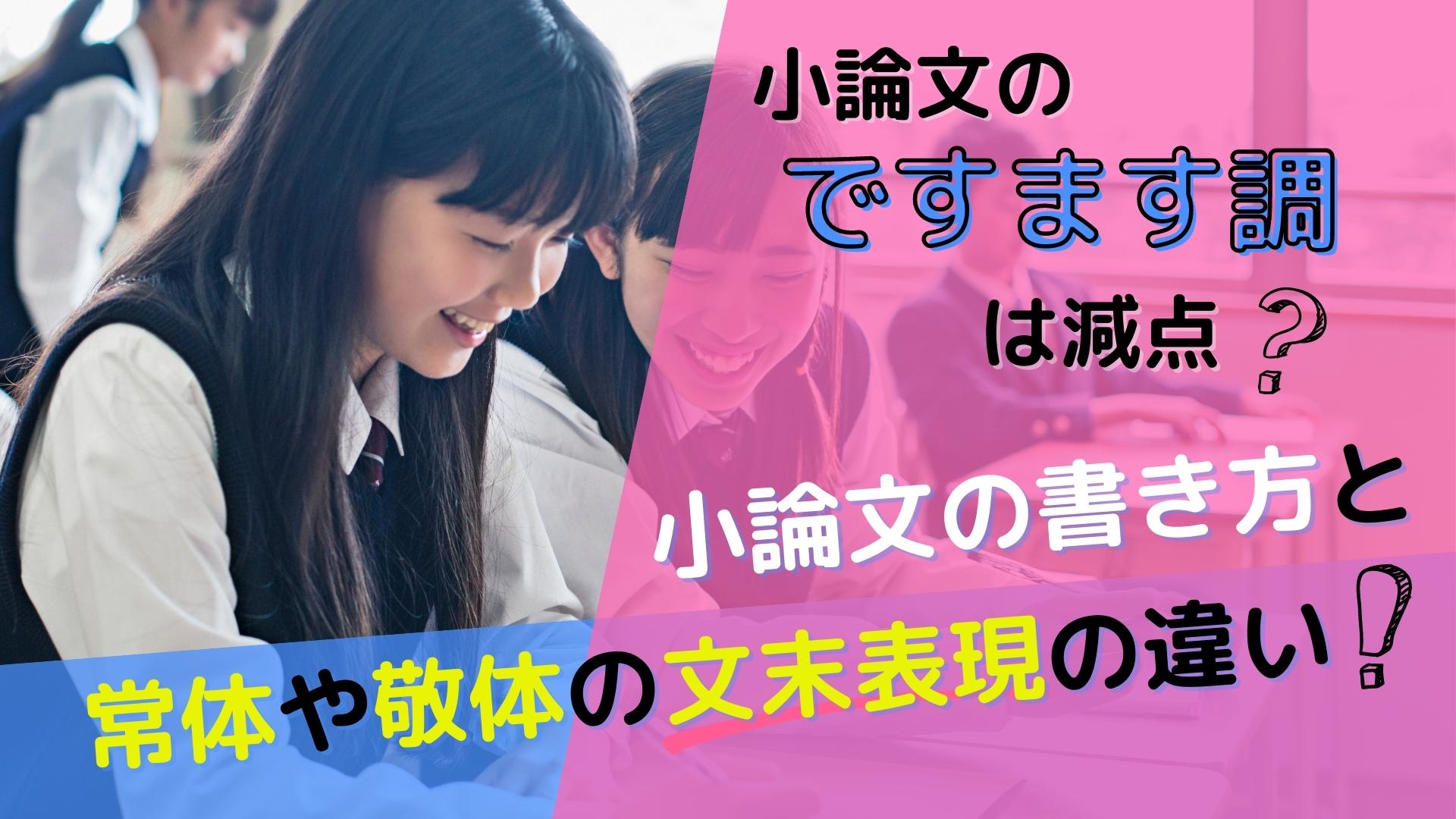大学受験や高校入試を控える皆さんから、「試験科目に小論文があるけれど、書き方がわからない」「ですます調で書いてしまったら減点されるの?」といった質問を多くいただきます。
実際のところ、「小論文」と「作文」は目的が異なるため、評価基準や適切な文体も変わってきます。この記事では、小論文にふさわしい書き方の知識と、「ですます調(敬体)」と「だ・である調(常体)」の使い方の違い、そしてなぜ「ですます調」を避けるべきなのかを、例文を交えながら詳しく見ていきましょう。
五十嵐写真02.png)
「小論文」の目的を理解し、適切な形式で書くことを意識すれば、どう書いたらよいかがイメージできますよ。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文をですます調で書いてしまった!これはまずい?
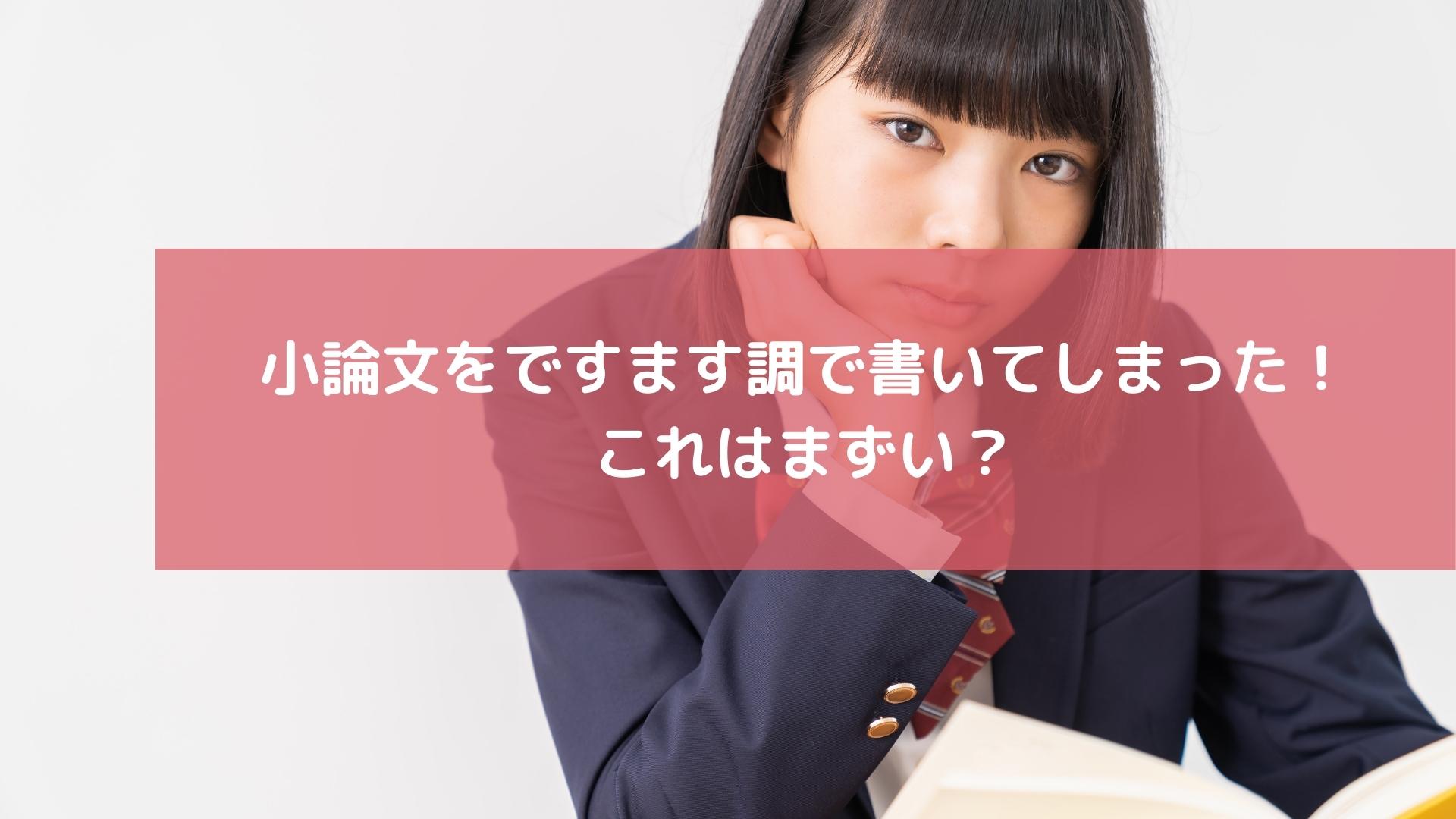
小論文の評価基準
一般的な小論文の評価基準は大きく分けて、必ず押さえる必要のあるポイントは次の4点になります。
問題に対して正しく論じているか
小論文の設問には、「~という観点から」「あなたの経験を踏まえ」「この資料(グラフ)の結果を利用して」など、論じる上での条件が示されていることがほとんどです。
問題文を正確に読み解き、その要求に沿って論理的に記述されているかが最初の評価ポイントです。例えば「解決策を述べよ」という問いに対して、原因分析だけで終わっていては評価されません。
文の筋が通っているか
制限時間があって緊張している状態で書いていると、途中で何を書いているのか分からなくなってしまうことがあります。文の流れがおかしくなっていないか、最初と最後で主張がずれてしまっていないかも気を付けましょう。
慌てずに、流れをざっとメモしてから書き始めるのもいいですよ。
自分の意見が述べられているか
限られた時間で焦って書いていると、途中で主張がずれてしまうことがあります。序論で提示した主張と結論が同じ方向を向いているか、全体を通して一貫性があるかが重要です。
書き始める前に、全体の構成をメモするなどして、論理的なつながりを意識することが大切です。
文章構成、表現は正しいか
「序論」「本論」「結論」など、基本的な構成に沿って小論文が書かれているか。また、きちんと段落付けや改行などの文章の基本ルールが守れているか。
それと、正しく原稿用紙を使えているかも採点のポイントです。
誤字脱字、指定文字数に対して大幅に少ない、または多い場合は減点の対象になります。
今回の記事で扱っている「文末表現」もこのポイントについての話になりますね。
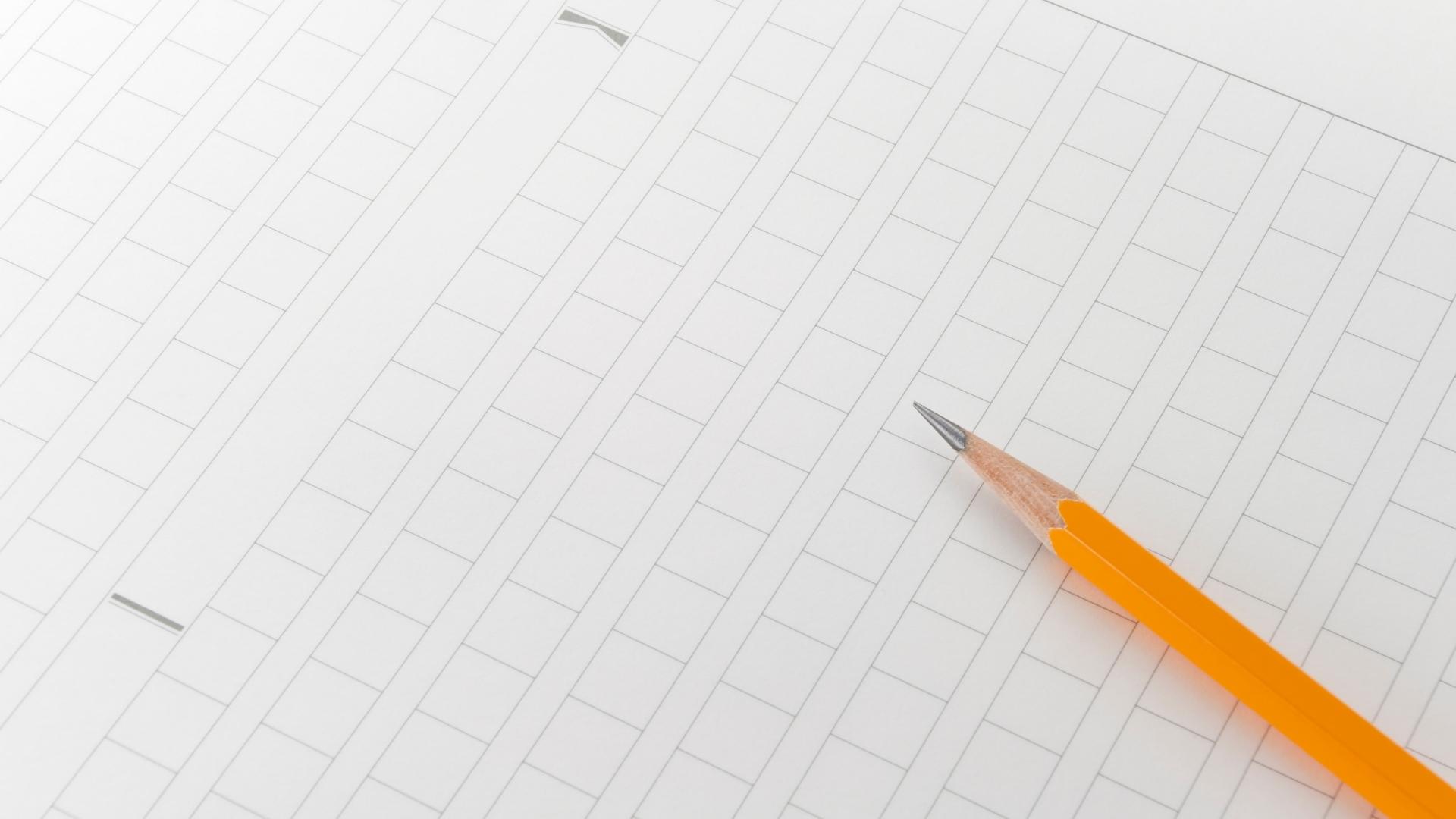
減点になることも?注意すべき文末表現
「文末表現」とは、文字の通り文の末尾の表現のことです。「~です」「~である」などの部分ですね。
小論文では、「思う」などの曖昧表現を避けましょう。
「思う」では主観的な表現になってしまいます。小論文は客観的観点から主張を述べる文のため「~と考える」「~である」などにします。
また、小論文は基本「だ・である調」を使用します。
「ですます調」にしてしまって大幅減点!ということはないと思いますが、特に「ですます調」と「だ・である調」の文末表現が混在しないよう、十分に確認しましょう。
次の項目で、「ですます調」と「だ・である調」の違いについて説明していきますね。
文末表現はどう使い分ける?
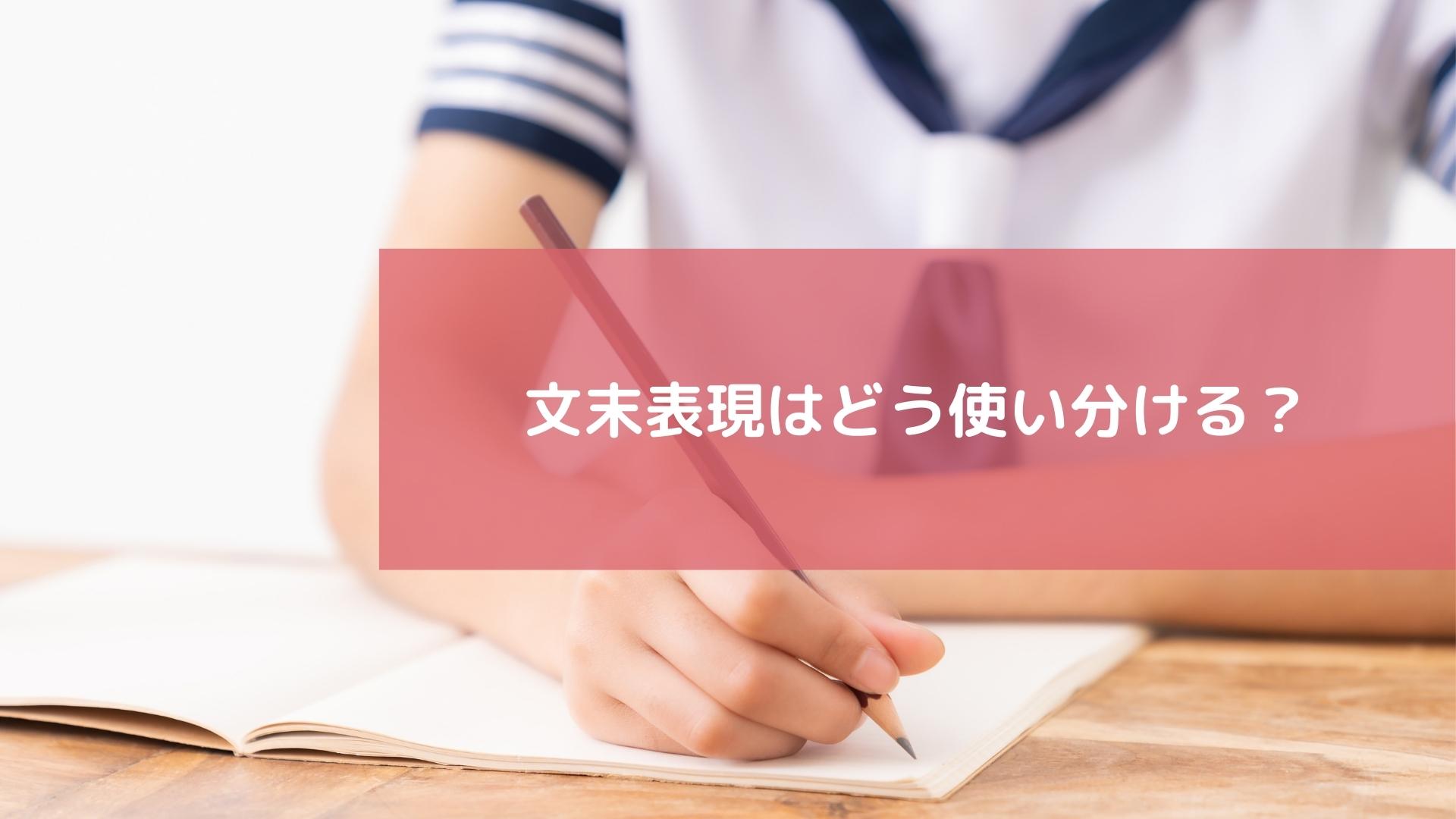
小論文で使われる常体「だ・である」
小論文では「だ」「である」が使われます。これらは「常体」と言われ、文末に敬語を用いない文章の様式です。
「~だ」「~である」以外にも、「~している」「~(かもしれ)ない」「~だろう(か)」「~べきだ」などの文末表現があります。
小論文はその名の通り、「論ずる」ための文です。
自分の考えを具体的事例や一般的・客観的な事実を用いて『筋道を立てて説明』し、論理的に相手を説得する、あるいは相手に納得してもらう目的で書きます(主観的は×)。
限られた字数で相手に「意志」や「意見」を分かりやすく伝えるために、簡潔で断定的な、説得力のある「常体」が使用されます。
続けてよみたいテーマ 【最新版】 小論文対策完全ガイド| 書き方から合格のコツまで徹底解説
作文で使われる敬体「です・ます」
一方、作文や読書感想文では「です」「ます」が使われます。これらは「敬体」と呼ばれ、使われている文字の通り丁寧語を文末に使う文章の様式です。
「~です」「~ます」以外には「ありません」「~かもしれません」「でしょう(か)」などの文末表現があります。
作文や読書感想文は、自分の考えや感じたことを他人に『伝える』(主観的でOK)ために書く文のため、読み手にとって丁寧でやわらかい表現である「敬体」を使用します。
小論文の基本構成を押さえよう ←まよったらこのページを確認
高校入試の小論文でもですます調はNG?

小論文の採点基準は学校によって異なりますが、基本的には「問題に合った意見や主張を正しく伝えられているか」が重要なポイントです。
特に高校受験では、「ですます調」などの文末表現はあくまでその次の要素なので気にしすぎる必要はないでしょう。
ただ、「ですます調」と「だ・である調」の混在は良くないので、文末が統一されているかどうかに気を付けましょう。
文末表現以外にも気を付けたい小論文の書き方
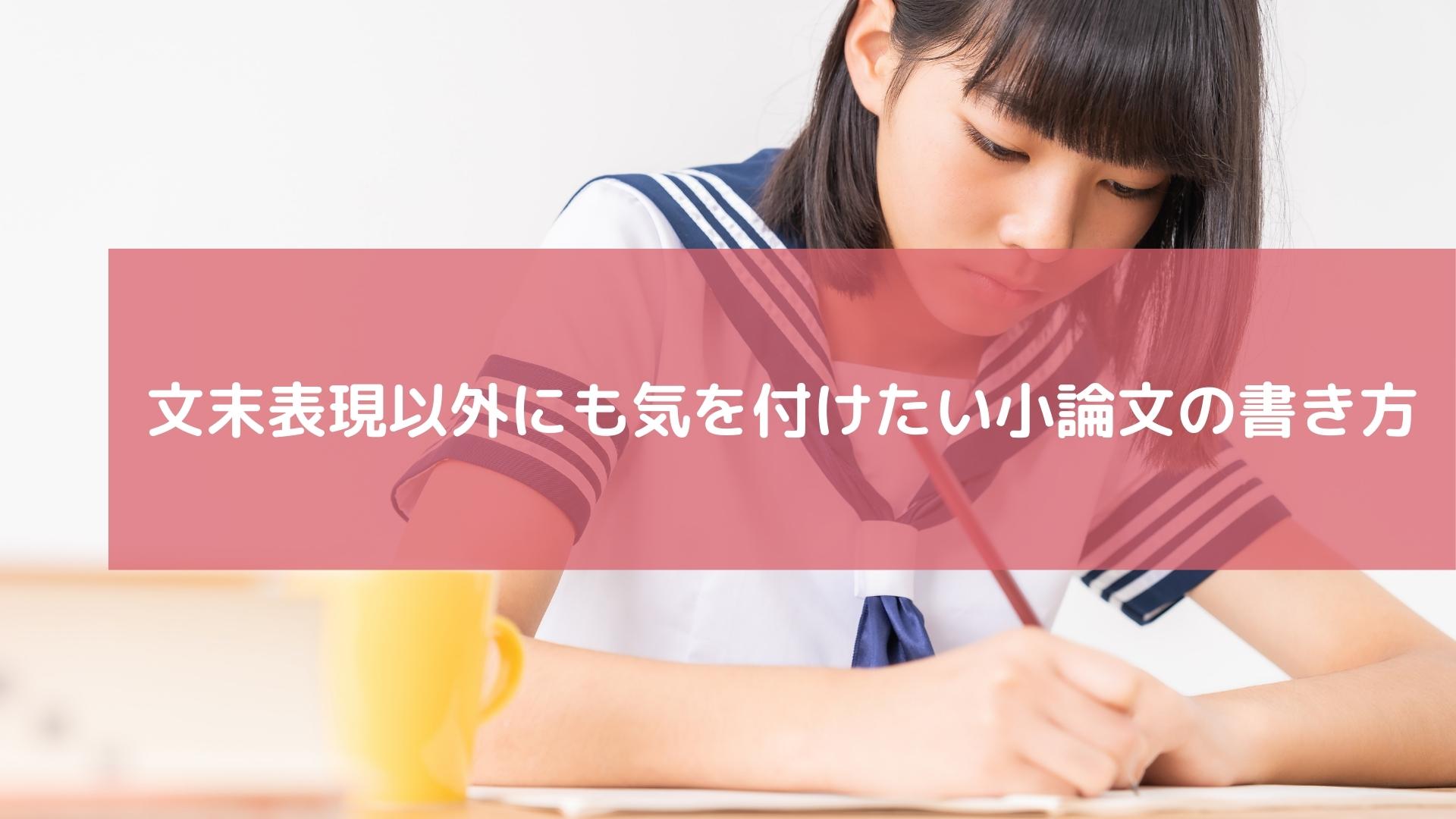
「ですます調」などの文末表現以外にも、小論文の文章表現で気を付けたい点があります。
話し言葉を使わない
「やっぱり」「たぶん」「どうして」「でも」・・・
つい普段通り使ってしまいそうになりますが、小論文の表現としてはNGです。
「やはり」「おそらく」「なぜ」「しかし」などに置き換えましょう。
また、「見れる」などの「ら抜き言葉」、「してる」などの「い抜き言葉」を使わないようにします。
略語を使わない
「ネット」「スマホ」「バイト」などの略語は、正式名称で書くようにしましょう。
コンビニエンスストアなどを書くときは「コンビニ」と略さないようにしましょう。ただコンビニエンスストアと書くと非常に長いので、書くときは注意が必要です。いな良い
一人称は「私」
「僕」「自分」などは基本的にNGです。
他にも、記号は極力使わない(!、?、…、「」など)ようにします。
まとめ

今回は、小論文の文体を中心に、書き方の基本を紹介しました。「ですます調」を使ったこと自体が、合否を大きく左右することは稀かもしれません。しかし、小さな減点が積み重なることで、結果に影響を与える可能性は否定できません。
良い小論文を作成するためには、以下の点を意識することが重要です。
- 正しい知識を身につける:文体や構成、言葉選びのルールを学ぶ。
- 練習を重ねる:様々なテーマで、指定文字数以内に文章をまとめる練習をする。
- 必ず添削を受ける:書いた文章は、自分では間違いに気づきにくいものです。学校や塾の先生に必ず添削してもらい、客観的なアドバイスを受けることが上達への近道です。
- フィードバックを改善する:アドバイスをもらったら、必ずそのアドバイスにしたかったものを永遠に反映させ、さらに添削してもらい、答案の精度を上げましょう。
これらの基礎を固め、自信を持って試験に臨めるように準備を進めていきましょう。
五十嵐写真02.png)
文章は自分で読んでいても間違いに気が付きにくいです。周りの人に読んでもらうか、専門の塾で指導してもらうのが安心ですよ。
:
📚 関連記事
📝 小論文の書き方完全ガイド – 文末の統一で差をつける
小論文の基本的な書き方、特に文体統一(「です・ます」調と「だ・である」調)の重要性について解説。初めて小論文を書く方におすすめの入門記事です。文体の統一は合格の最低条件であり、これができていないと内容が良くても高得点は望めません。
🎓 慶應義塾大学SFC(環境情報学部)小論文対策 – 2016年度過去問解説
7つの資料を読み解く特殊な出題形式の攻略法を動画で詳しく解説。「頭を柔らかくする」発想力と差別化戦略で160点/200点を目指します。未来から現在への逆算思考、モノではなくコト(サービス)への着目など、SFC特有の柔軟な思考法が学べます。
🏫 滋賀大学教育学部 総合型選抜試験 小論文攻略法
講義受講型小論文の対策方法と80%得点を取るための4ステップトレーニング法を詳しく解説。滋賀大学特有の「講義を聞いてから小論文を書く」スタイルの試験対策に最適です。地域に根ざした教育への情熱を小論文で表現する方法も紹介しています。