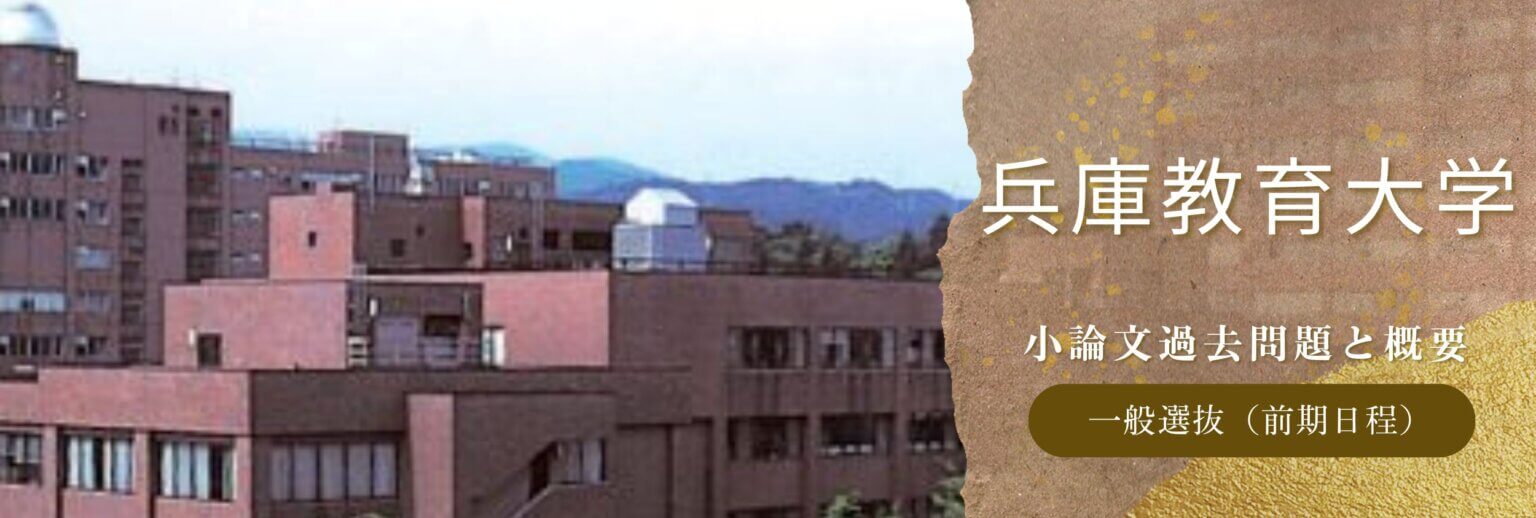記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文過去問題
R6年度 学校教育学部 学校教育教員養成 一般選抜(前期)小論文A
問題 次の文章を読んで、後の問い (問1~問3)に答えよ。
※本文省略
出典:齋藤孝『新しい学力』岩波書店 二〇一六、四六~五二頁による一部改変
問1 筆者は、「新しい学力」を育成する上での難点として、二重線部「まず何よりも、新しい学力を伸ばす指導方法を、教師や指導 どこまで実践できるのかということである」と述べている。筆者がこのような難点をあげる理由について本文の言葉を用いて二〇〇字以内で説明せよ。
問2 筆者は、二重線部「伝統的な学力」とはどのようなものであると考えているか、本文の内容に沿って八〇字以内で説明せよ。
問3 筆者は、「新しい学力」を育成する際の第二の問題点として、二重線部「評価の問題」をあげている。筆者がこのような問題点をあげる理由について本文の言葉を用いて六〇字以内で説明せよ。
R6年度 学校教育学部 学校教育教員養成 一般選抜(前期)小論文B
問題 次の惑星の表層環境に関する文章を読み、後の問い(問1〜問4)に答えよ。
※本文省略
出典:田近英一2008「惑星環境の変動と進化」,宮本英明ほか編『惑星地質学』東京大学出版会 p.87-88を一部改変
図1 惑星の内部構造の模式図
表1 地球型惑星の表層環境に関するデータ
図2 地球の大気組成の変化
問1 太陽系の惑星のうち、内側の4つを地球型惑星、外側の4つを木星型惑星と呼ぶ。惑星の内部構造については未解明のことが多いが、図1は内部構造を推定した模式図の1 つである。図 1 から読み取れる地球型惑星の内部構造の共通点を50 字以内で簡潔に述べよ。
問2 金星の平均受熱量は地球の1.91倍であるにもかかわらず、その有効放射温度は227K(-46℃)と地球の255K(-18℃)より低い。表1のデータを引用して、その原因を40字以内で説明せよ。
問3 表 1 にあるように金星の地表面温度は平均で 737K(464℃)と推定されている。表 1 のデータを引用して、地球より高い金星の地表面温度の原因を 50 字以内で説明せよ。
問4 表1 に示したように金星と火星に対して、現在の地球は大気組成が大きく異なっている。これは、本文中の下線部アにあるように地球の大気組成が変化してきた結果だと考えられる。図2は地球の誕生から現在までの大気組成の変化を推定したものである。まず、CO2と O2の比率がどのように変化してきたかを簡潔に記し、図2 から読み取れる地球上に起きた変化を190字以内で説明せよ。
出題意図
R6年度 学校教育学部 学校教育教員養成 一般選抜(前期)小論文A
児童・生徒に身に付けさせる学力は、学校教育において最も関心の高い内容の一つである。学力には、教科書の内容に象徴されるような、体系的にまとめられた知識を記憶し、再生できる力を基本とする「伝統的な学力」があるのに対して、平成元年の「新しい学力観」以降、課題を解決するために必要な思考力・表現力・判断力・行動力といった「新しい学力」の習得が求められている。この「新しい学力」は、「PISA型」と呼ばれたり「問題解決型」と呼ばれたりする学力であり、生きて働く学力でもある。この「新しい学力」に注目し、「新しい学力」を児童・生徒に習得させることがいかに難しいかを受験生に考えさせ、「新しい学力」を習得させる上での難点をどのように読み取ったかを問いたい。
問1~問3は、本文の内容を理解し、本文の言葉を用いてどの程度論理的に説明できるかを評価する。 問1は、「新しい学力」を育成する際の第一の難点として教師が指導方法を実践できるかという点があげられているが、筆者がその難点をあげる理由について本文の言葉を用いて説明できるかどうかを問う問題である。
問2は、「新しい学力」と対をなす「伝統的な学力」がどういった学力であるのかを本文から読
み取り、本文の内容に沿って説明できるかどうかを問う問題である。
問3は、「新しい学力」を育成する際の第二の難点として評価の問題があげられているが、筆者がその難点をあげる理由について本文の言葉を用いて説明できるかどうかを問う問題である。
R6年度 学校教育学部 学校教育教員養成 一般選抜(前期)小論文B
小論文Bでは、教員となるにふさわしい資質と能力を見るため、資料、図、表等の内容の理解度を問う。
今年度の題材としては、主として地球の表層環境に関わるテーマを取り上げた。予備知識の有無による影響を軽減するため、基礎的でありながらも一般的ではない事項を選択した。出題構成としては、問題文の内容を正しく理解する力、資料の意味することを文章に表現する力、資料中から必要なデータを探し出す力、資料に示されたことの意味を考察する力を問う形式になっている。
学部学科、コース
学校教育学部
クラス制を中心とした3つの学びの場により、学生の持てる力を最大限に引き出す。また、学生は4年間にわたる実地教育を通して、教員としての実践力を身につける。
4年間一貫した「クラス制」により、入学から卒業・就職まで、一人ひとりの成長を大切に支援する。1クラスは約20人の少人数教育により、大学教育や、学び続ける教員になるための基盤形成や、学校現場の課題に即した課題解決型学習(教職基盤探究、教職実践演習など)を行う。
2年次から学生は、教科教育系または幼年教育系の各グループにも所属する。教科教育系の学生は、国語、英語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・情報、家庭の10グループに分かれ、各教科の専門知識を高め、教科指導力を身につける。卒業時には、小学校と中学校の教員免許取得のほか、高等学校教員免許も取得可能。
幼年教育系の学生は、幼年期における子どもの生活、遊びなどに関する発達や、カリキュラムなどについて学ぶ。卒業時には幼稚園と小学校の教員免許を取得する。また、保育士資格も取得することができる。
3年次からは、教育学・心理学、各教科の教材研究・指導法(教科教育)、総合学習など広範なテーマから指導教員(ゼミ)を選択し、卒業研究に取り組む。教育学・心理学(教育理念、教育思想、人間の発達と適応問題、教育者のリーダーシップ、学校をめぐる人間関係、授業における教授と学習、学校心理学、特別支援教育)、各教科の教材研究・指導法(教科教育)、総合学習などのテーマがある。
併設の教育実習総合センターでは、教員として優れた資質能力を形成するための教育実習の支援や、大学院学校教育研究科と連携して教員養成の高度化に関する研究を推進している。また、教職キャリア開発センターでは、学生が教員・社会人となったあとにも、豊かで幅広い人間性を育み、主体的に学ぶ教師(学び続ける教師)を育成し、入学から卒業後も見通したキャリア開発を行っている。さらに、グローバル教育センターでは、国際社会に開かれた大学として、留学生や外国人研究者の積極的な受け入れや学生の派遣留学の支援、促進を行っている。
所在地・アクセス
兵庫教育大学のHPはこちら
入試情報はこちら
| 兵庫県加東市下久米942-1 | JR加古川線「社町」駅からバス20分 JR「三ノ宮」駅から中国ハイウェイバス55分「高速社」下車、 兵教シャトル便5分 JR「新大阪」駅から中国ハイウェイバス65分「高速社」下車、 兵教シャトル便5分 |