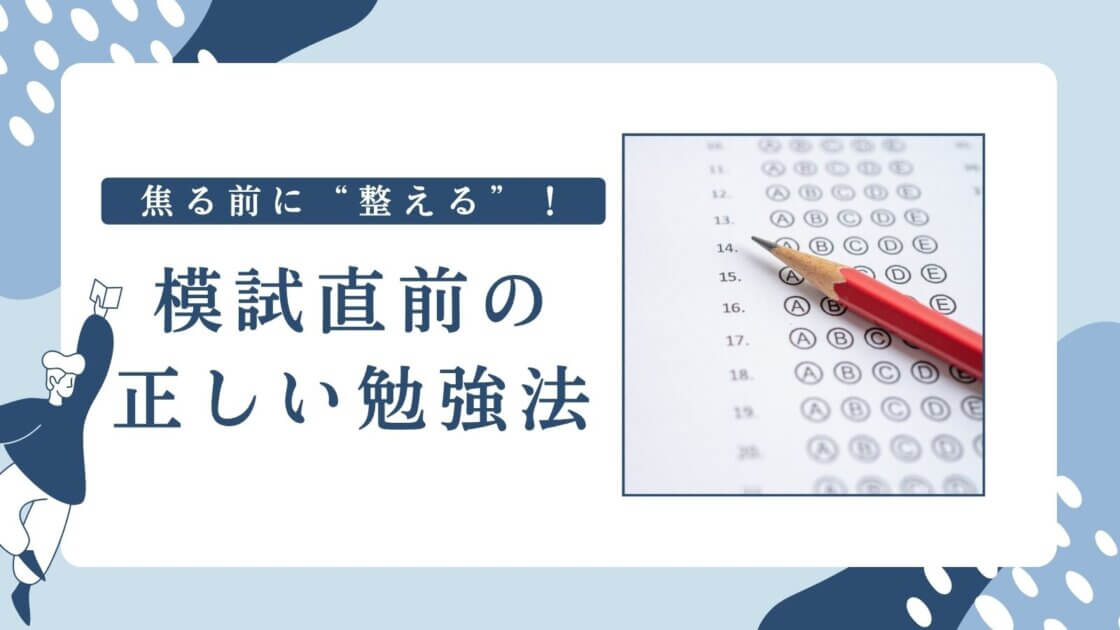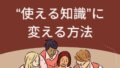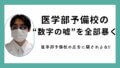模試を前にすると、「何から手をつけたらいいのか分からない」「この勉強で本当に大丈夫?」と、焦りと不安に包まれてしまう――そんな経験をしたことはありませんか?
どれだけ頑張ってきた受験生でも、直前になるほど迷いが生まれるのは自然なことです。
でも、その“迷い”の正体を理解し、正しい直前勉強の方法を知ることで、不安は確かな自信へと変わります。
今回は、模試直前にやるべき勉強・やってはいけない行動、そしてメンタルの整え方まで、心理学の視点を交えて分かりやすく解説します。
「直前期、何をすべきか分からない」と悩むあなたに贈る、“勉強迷子から抜け出す”ための実践ガイドです。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
勉強迷子の心理とは
模試が近づくと「何をすればいいのか分からない」「今の勉強が本当に正しいのか」と不安になる——そんな“直前の勉強迷子”は、真面目に努力を重ねてきた受験生ほど陥りやすい悩みです。
勉強時間はあるのに手が止まる。焦るほど集中できなくなる。これは単なる優柔不断ではなく、心理的な落とし穴なのです。
人の脳は、ゴールが近づくほど不安を感じやすい性質を持っています。心理学ではこれを「目標接近不安」と呼びます。
模試という“結果が出る場”が迫ると、「今のままで大丈夫?」「失敗したらどうしよう」という感情が強まり、学習の軸がぶれやすくなります。特に初めての模試や志望校レベルの模試では、不安が一層強く出る傾向があります。
さらに、勉強量が増えるほど「どこを優先すべきか」が見えにくくなるのも原因の一つです。基礎・応用・演習……多くの教材に触れているほど、復習の優先順位がつけられなくなるのです。
つまり、模試直前の“迷子状態”は「不安の増大」「選択肢の複雑化」「優先順位の不明確さ」が重なって起こる現象。
でも安心してください。これには明確な対策があります。ポイントは、「なぜ迷っているのか」を分析し、行動を整理すること。
典型的な迷走パターン
模試直前期の受験生がよく陥る“迷走パターン”は大きく3つあります。
① あれもこれも手を出すタイプ
不安のあまり「やっていない教材があると怖い」と感じ、全範囲を浅く復習してしまうケース。
結果的にどれも中途半端なまま本番を迎え、「復習したのに出せなかった」と後悔するパターンです。
② 今までの勉強を全否定するタイプ
SNSや友人の勉強法を見て、「自分のやり方は間違っていたのでは」と焦り、急に新しい問題集に手を出してしまう。
これは、直前期に最も危険な“勉強の軸を失う”パターンです。
③ 得意科目に逃げるタイプ
苦手科目に向き合うのが怖くなり、得意分野ばかり繰り返す。
安心感は得られても、得点にはつながりません。本番で弱点を突かれて落ち込む悪循環を招きます。
これらに共通するのは、「目的と手段の混同」。
直前期に必要なのは“安心するための勉強”ではなく、“得点につながる勉強”です。
不安を感じるほど、安心を求めてしまう——この本能を客観的に見抜けるかどうかが、成功の分かれ目です。
「量」ではなく「質」が問われる時期
直前期は、勉強の“量”ではなく“質”が勝負を分けます。
多くの受験生が「とにかく詰め込もう」と考えますが、それは逆効果。人間の集中力や記憶容量には限界があります。
心理学的にも、テスト直前期は新しい情報の吸収効率が落ちることがわかっています。
脳はすでに蓄えた知識を整理し、引き出しやすくする“再構築モード”に入るからです。
この時期に最も効果的なのは「新しいことを詰め込むこと」ではなく、「今ある知識を使える形に整えること」。
そのために有効なのが、基礎の再確認・頻出問題の演習・ミスノートの復習。
「出る可能性が高く、自分が落としやすいところ」に集中することで、得点効率が劇的に上がります。
また、知識を「引き出す練習」も忘れずに。
短時間で何度も繰り返すスパイラル復習や、制限時間を設けた即答トレーニングで“想起力”を鍛えると、本番での安定感が増します。
不安の正体を見抜く
直前期の不安は、悪者ではありません。
不安は完全に消すことができない感情であり、むしろ上手に使うべきエネルギーです。
不安があるから集中でき、不安があるから工夫が生まれます。
大切なのは、「不安を情報として捉えること」。
「この単元が不安」=“定着が甘いサイン”。
「何をすればいいか分からない」=“優先順位が整理されていないサイン”。
不安を“現在地の指標”として使えば、迷いが行動のヒントに変わります。
特に効果的なのが、「不安を感じたら基礎に戻る」習慣です。
不安が強いと、つい新しい教材に手を出したくなりますが、それは逆効果。
基礎や頻出問題に立ち返ることで、心理的にも安定し、自信が戻ります。
この「戻る習慣」がある人ほど、直前期の迷走が少ないのです。
優先順位の決め方
直前期の勉強で迷わないためには、“優先順位の明確化”が何より重要です。
「やることリスト」ではなく、「得点に直結するかどうか」で分類するのがポイントです。
1️⃣ 落としてはいけない分野
出題頻度・配点が高い基本事項。
英語なら文法・熟語、数学なら標準公式、日本史なら因果関係など。まずはここを完璧に。
2️⃣ 短期間で伸ばせる弱点分野
苦手だけど、克服すれば点数が伸びる“ボーナスゾーン”。
過去の模試で落とした問題形式に集中しましょう。
3️⃣ 時間があればやる応用・周辺知識
焦ってここに手を出すのはNG。余裕があるときだけ取り組めば十分です。
「とりあえず全範囲」ではなく、「得点効率」で考える。
限られた時間だからこそ、やらないことを決める勇気が必要です。
模試1週間前からの戦略
● 6〜5日前:基礎の総点検
基礎事項を100%引き出せる状態に。
頻出問題の解き直し、ミスノートの整理を中心に行いましょう。
● 4〜3日前:弱点の集中演習
「2〜3問分得点できるようになる」を目標に、苦手単元を集中攻略。
完璧を求めず、点につながる克服を意識して。
● 2日前:模試形式で演習
時間配分や集中の持続力を確認。結果に一喜一憂せず、出題傾向と弱点の最終確認を。
● 前日:整理とリラックス
新しいことは一切せず、知識の整理と自信の確認を。
睡眠を削って詰め込むのは逆効果。6〜7時間の睡眠を確保しましょう。
当日までのメンタル戦略
模試当日は「積み上げを確認する日」と捉えましょう。
合否を決める場ではなく、自分の位置を測るデータ収集の場です。
この意識を持つだけで、プレッシャーは大きく和らぎます。
不安を感じたら、それを「リスト化」してみてください。
「英語長文の時間配分」「世界史の年代」など、頭の中のモヤモヤを文字にすると整理が進みます。
その上で「今できること」「次に回すこと」を仕分けすれば、不安は“行動計画”に変わります。
当日の朝は、ルーティン化された行動で落ち着きを。
単語帳を5分見る、前回の反省を一行読む、試験会場の地図を確認する。
この一連の動きが、脳を“本番モード”に切り替えてくれます。
直前期にやってはいけないこと
1️⃣ 新しい教材に手を出す
直前期の新知識インプットは混乱のもと。
2️⃣ 得意科目ばかりやる
安心は得られても、得点は伸びません。苦手の底上げを。
3️⃣ 睡眠を削る
記憶の整理は睡眠中に行われます。睡眠不足は記憶力を下げる最大の敵です。
本番直前こそ、「やらない勇気」も戦略の一つ。
まとめ
模試直前に迷うのは、誰にでも起こる自然な現象です。
でも、その正体を知れば怖くありません。
不安を行動のサインとして読み取り、得点につながる部分に集中する。
1週間前から戦略を立て、前日は整理と休息に充てる。
このリズムを守ることで、直前期の勉強は確実に実を結びます。
模試はゴールではなく、次の成長のための通過点。
迷いを「焦り」にせず、「戦略」に変える受験生こそ、次の模試で飛躍的な結果をつかむでしょう。