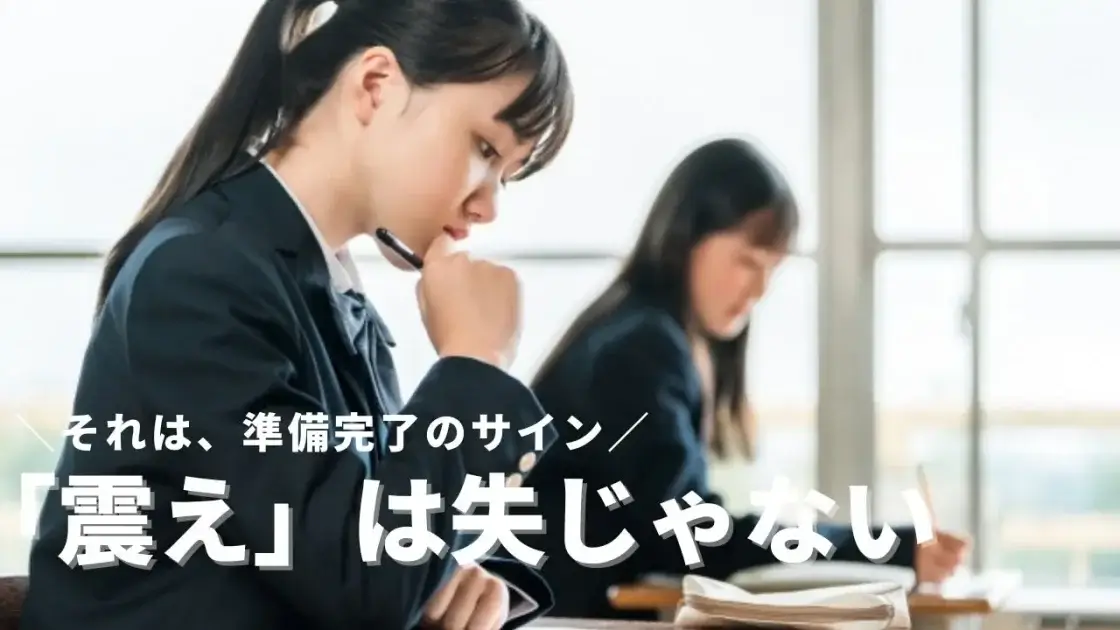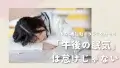答案用紙に名前を書くとき、指がこわばり、文字が震える。
その震えを見た瞬間に「もうダメだ」と感じてしまった経験はありませんか?
でも、実はその“震え”は、身体が試験に本気で向かっている証拠です。
緊張は悪ではなく、「準備完了のサイン」。
本記事では、緊張と震えのメカニズムを学びながら、
“震えても集中できる自分”をつくるための実践的な方法を紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
震えの正体――それは“異常”ではなく“準備完了の合図”
試験前、手が震えるのは「体が壊れている」からではありません。
緊張によって心拍数が上がり、交感神経が優位になることで、
誰にでも起こる“生理的振戦”が強く出ているだけです。
大切なのは、その震えを「終わりの合図」と捉えないこと。
むしろ「価値のある試験に挑んでいる」証拠と再解釈することで、
同じ身体反応が“準備完了”のエネルギーに変わります。
体を整える――“支点”と“リズム”で安定を取り戻す
震えを抑えようとするのではなく、「整える」発想に切り替えます。
- 呼吸のリズムで落ち着きを作る
鼻から4拍吸い、1拍止めて、口から6拍以上で静かに吐く。
「吐く息」を主役にすることで、心拍が自然に落ち着きます。 - 手の支点を増やす
手首や掌の一部を答案用紙に軽く預け、肘も机に乗せます。
ペンは親指・人差し指・中指の三点で支え、“太く軽く”握るのがコツです。 - 大きく書く勇気
小さく震えを抑えようとするより、最初の一行を大きく、太い線で。
動作のスケールを上げるほど、細かなブレは目立たなくなります。 - 試験前1分の“予熱”
入室後、肩をすくめて下ろす、手首をゆっくり回す――これだけで十分。
体に“脱力の合図”を教えると、初動の硬さが抜けます。 - 姿勢と視線の位置
骨盤を立てて深く座り、両足を床につけます。
問題文を凝視しすぎたら、一瞬だけ遠くの壁をぼんやり見てリセットを。
視線の切り替えが、緊張をほどくスイッチになります。
頭を整える――“揺れても走れる設計”をつくる
体が整ったら、次は思考面の操作です。
- 意味を変える「再解釈」
震えを「失敗の兆候」ではなく「燃料が回っているサイン」と言い換える。
「震え=準備完了」と心の中で唱えるだけで、注意が“外の作業”に戻ります。 - マイクロ目標で動作を止めない
各大問の最初の1分は「得点」ではなく「手順の完成」を目標に。
条件の書き出し、図の枠取りなど、“震えてもできる作業”を動かすことで流れが戻ります。 - 焦点を外に置く
手の震えや鼓動に意識を向けず、
「式」「関係」「条件」といった外部の対象に焦点を戻します。
等号や図形に“視線の居場所”を決めるだけで、注意が安定します。 - 前日までの“仕込み”
模試や過去問演習の前に、「今日の自分への説明書き」を2行。
「震えたら吐く息を長く」「最初は大きく書く」など、短文で十分です。
当日の自分を支える“言葉のハンドル”になります。 - “負荷ゆらし”の練習
少し雑音のある環境や短めの制限時間で演習を行い、
“完璧ではない環境”でも動作を回す練習をしておきます。
小さなストレスに慣れておくことで、本番が“想定内”になります。
当日の流れ――震えても崩れない動線設計
試験本番は、「最初の5分・各大問の1分・詰まった30秒」に動作の定義を。
- 入室〜開始前:予熱→配置→呼気
指を軽く開閉し、肘と手首を机に置き、長い吐息でリセット。
名前を書くときは一回り大きく、太く書く。震えに気づいたら「準備完了」と心で言い換えます。 - 各大問の冒頭1分:枠組み→外焦点→マイクロ目標
条件を書き出し、視線を公式に戻し、“手順を動かす”ことに集中。 - 行き詰まったとき:一点離陸→一語再起動→太字の一行
余白の小点を見て、心で「置換」「対称」など一語を唱え、
太字で一行だけ書き出す。動作が再び動き出します。 - 終盤:引き算の見直し
完璧よりも“読みやすさ”を重視。
配点の高い設問の「単位」「符号」「桁」だけを確認し、線を太く整えます。
震えは「敵」ではなく「合図」
試験の震えは、あなたが“真剣である証”です。
呼吸、支点、姿勢、視線、再解釈、マイクロ目標――
これらの設計を重ねれば、震えは動きを止める敵ではなく、
「集中のスイッチ」に変わります。
もし日常生活でも強い震えを感じるなら、
家族や学校、医療機関に相談することも大切です。
心と体の両面を整えながら、“揺れても進める自分”を育てていきましょう。