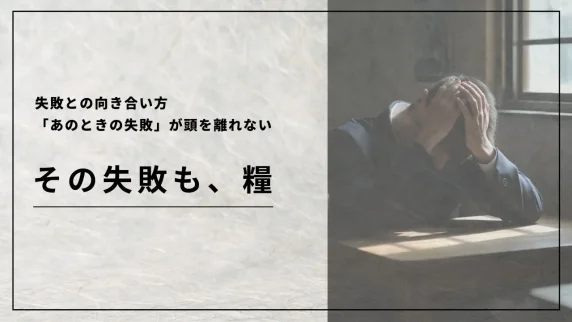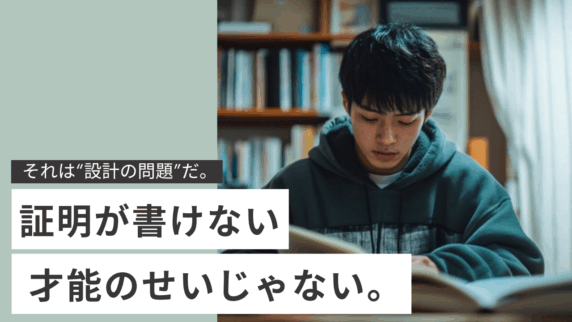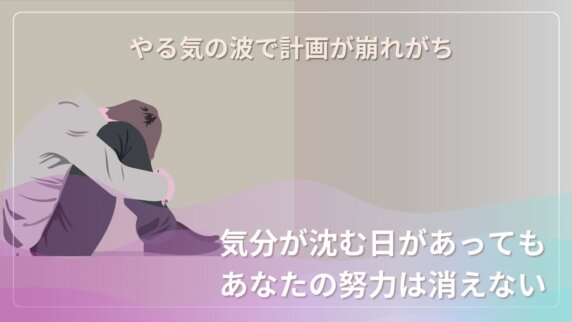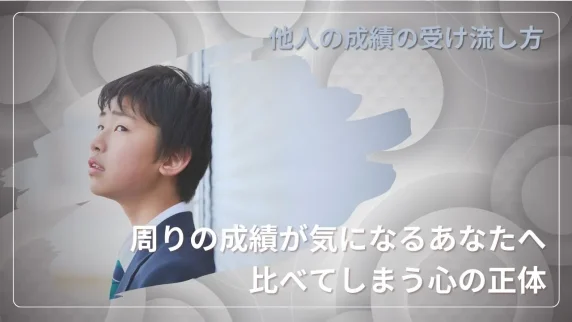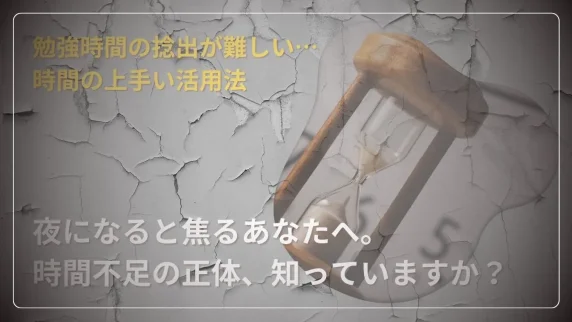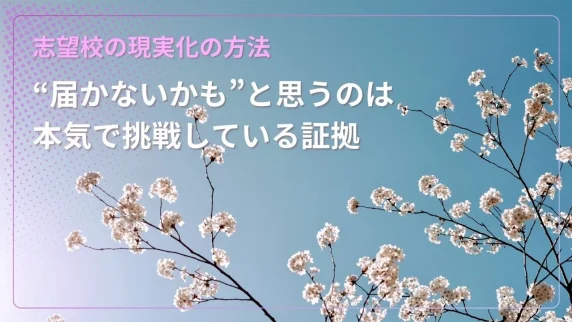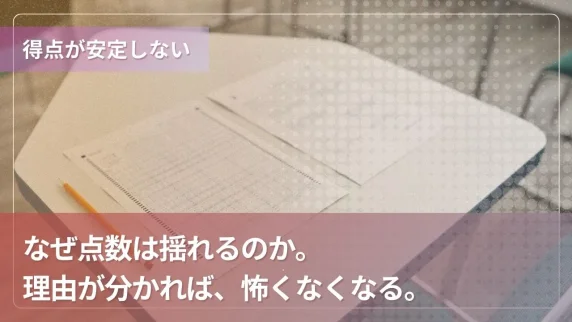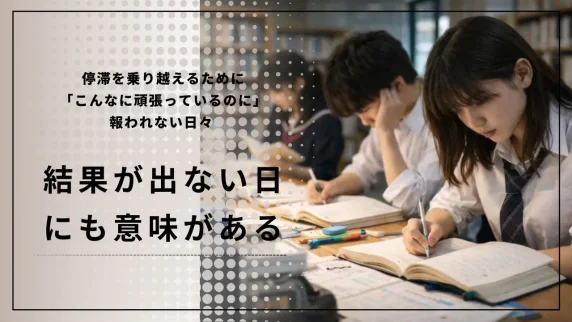 大学受験
大学受験 努力が結果に見合ってない受験生必見!――停滞を乗り越えるために
毎日机に向かっているのに、模試の点数が上がらない。
過去問も手応えはあるのに、結果がついてこない。
そんな日が続くと、「自分は才能がないのでは」と無力感が押し寄せます。
けれど、「やっても結果が出ない時期」は、誰にでも訪れる必然の過程です。
努力の成果は直線的に伸びるものではなく、溜めてから跳ねるように現れます。
この記事では、停滞が起こる理由を脳と心理の視点から整理しながら、停滞期を抜けるための考え方と行動の作り方をまとめます。