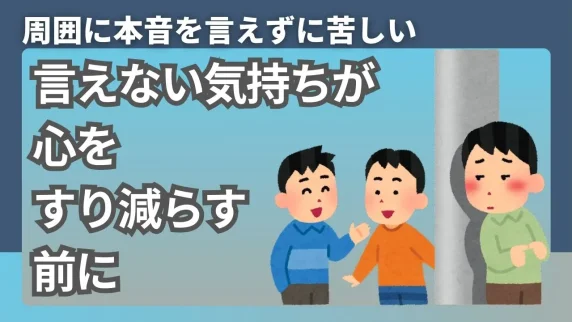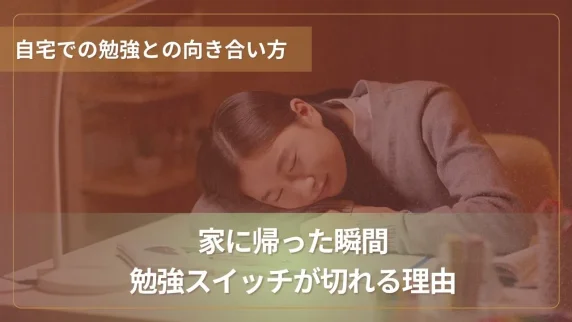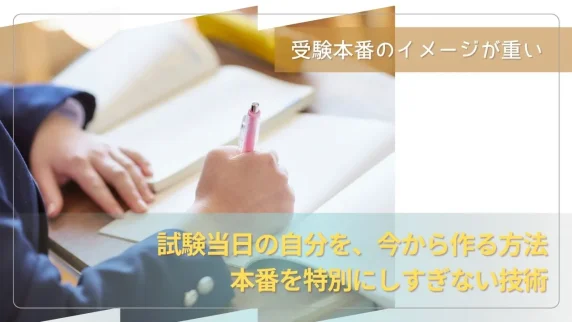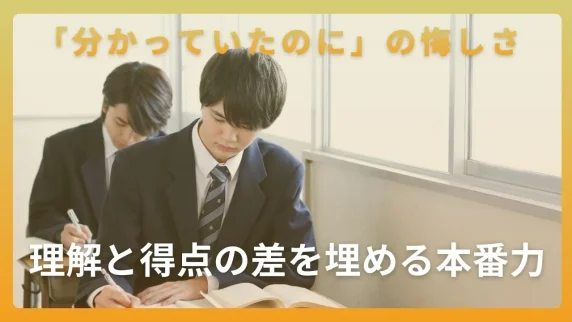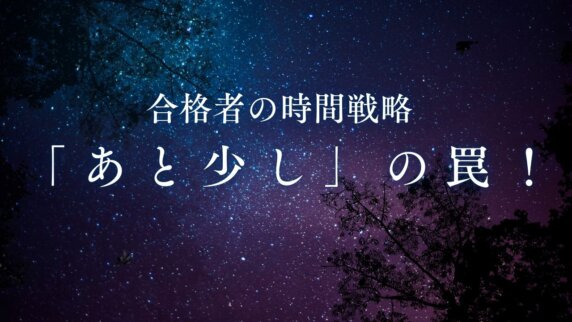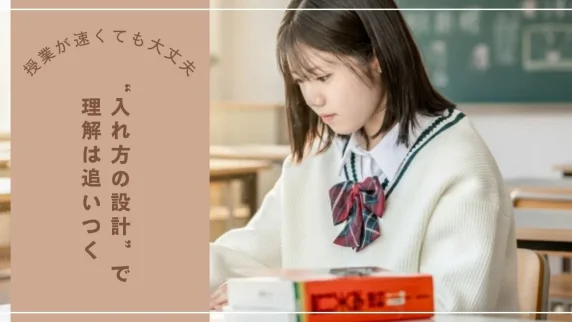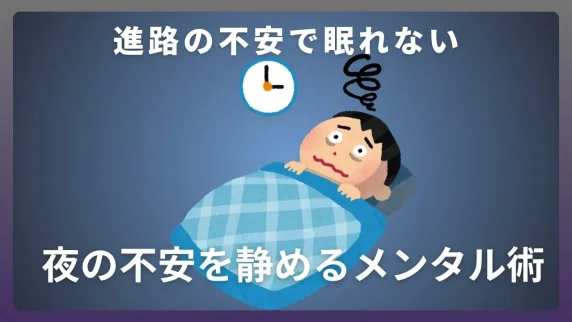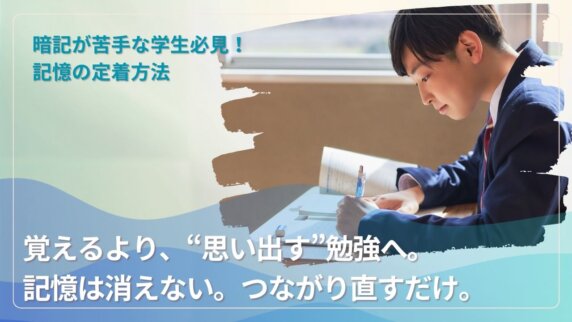 大学受験
大学受験 暗記が苦手な学生必見!― 記憶を定着させる勉強法
勉強しても、数日後には忘れている。覚えた英単語が出てこない。公式を思い出せない。——受験勉強の中で誰もが一度は感じる悔しさです。
「せっかく頑張ったのに、またやり直しか」と思う瞬間、努力が空回りしているように感じて心が折れそうになります。
でも、忘れることは失敗ではありません。脳の構造上、忘却は「正常な動作」です。
この記事では、忘れる仕組みを理解しながら、“思い出す経験”を軸に記憶を定着させる方法を整理していきます。
暗記が苦手だと感じる人ほど、「忘れる前提」で学ぶ設計に切り替えることで、伸び方が変わっていきます。