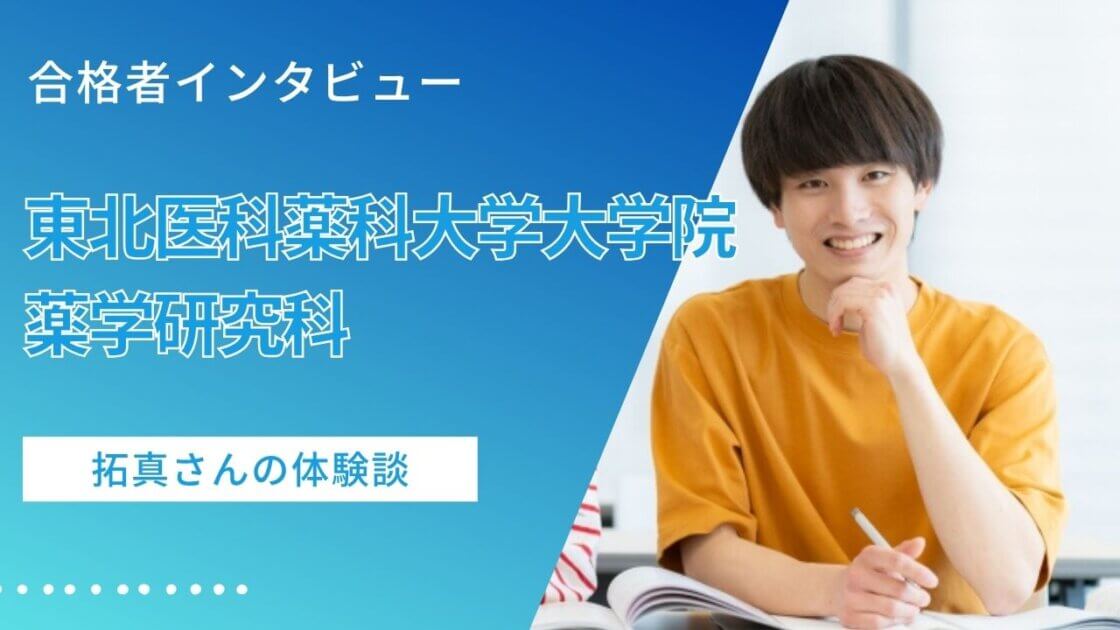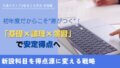こんにちは、スカイ予備校の校長、五十嵐です。
東北医科薬科大学大学院薬学研究科に進学した拓真さんは、小さな頃に出会った理科の実験から始まる“科学への憧れ”を持ち続け、困難な受験や大学での厳しい勉強を乗り越えて、今は研究室で実験漬けの毎日を送っています。
決して勉強が得意だったわけではない──そんな彼が薬学の道を選び、今も学び続ける理由とは?どんな子ども時代を過ごし、どんな受験生活を送ったのか、そのストーリーを追っていきます。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
理科の授業が「原点」だった小学生時代
小学生の頃の私は、おとなしく我慢強い子どもでした。でも一方で、「他とは違うことがしたい」という気持ちも強く、クラブ活動や音楽発表会では自ら手を挙げるタイプでもありました。
水泳、剣道、ゴルフ、将棋、くもん……。多くの習い事を経験できたのは、両親の「いろんなことをやらせてみよう」という方針のおかげです。
中でも印象的だったのは、小学校の理科の授業。先生の行う実験が面白くて、その時間がいつも楽しみでした。この体験が、私の“薬学の原点”になっています。
ちなみに、成績は意外と悪くて、漢字テストで50問中4点なんてことも。でも算数だけは得意で、くもんで鍛えた計算力のおかげで表彰されたこともありました。
中学ではバドミントンと駅伝の日々
中学生になっても内向的な性格は変わらず、友達は少ない方でしたが、バドミントン部と駅伝部に入りました。特にバド部の仲間とは今でも集まる関係です。
勉強では全国模試で平均以下という結果が出て、母に本気で叱られたのを覚えています。それをきっかけにすべての習い事をやめ、塾に切り替える決断をしました。
得意科目は理科と数学、苦手は英語と国語。高校受験では第一志望に落ちて、地元の有名私立高校へ進学することになりました。
独学と挑戦の高校生活
進学した私立高校は生徒数3000人のマンモス校。部活はやらず、生徒会執行部とよさこいサークルで活動していました。生徒会では会計を担当し、大人と話す力も自然と身についたと思います。
勉強面では英語が苦手すぎて赤点ギリギリ。一方、化学・物理・地理は得意科目で、教科書と問題集をとことん使い倒すことで理解が深まりました。
特に地理は、子どもの頃から観ていた『イッテQ』などの雑学とつながって、楽しく覚えられたのが勝因です。
受験期──独学の限界と仲間の存在
受験勉強は「黄色チャート」で基礎を固めるところからスタート。物理と化学は「重要問題集」でアウトプット中心に進めました。
英語は最後まで苦戦し、今思えば「長文読解を最初から重視すべきだった」と後悔しています。
地理は得意科目でしたが、資料集を併用することで効率がぐっと上がりました。今なら「9割を狙うなら日本史」というのも納得です。
夏期講習には参加せず、自習中心でしたが、今思えば講習に出た方が生活のリズムも質問の機会も得られて良かったと思います。
高校3年の春以降は毎日図書館で8時間以上勉強し、独自に「8コマ制スケジュール」を組んでいました。
しかし、英語が足を引っ張り、センター試験では国公立に届かず。私立薬学部には合格し、進学することになりました。
大学生活──実験の現場に立つ喜びと現実
大学に入ってからは、厳しい勉強に苦しみながらも、新しい経験にあふれた毎日を送りました。1~2年は必修科目が多く、3年以降は専門科目の難しさに直面。
過去問の共有が成績を左右するほどで、4年生の進級時には2割が留年していました。
私は大学院への進学を決め、今は研究室に所属して実験の日々。小学生の頃に憧れた“実験の仕事”を実際にやれていることに喜びを感じていますが、同時に「本当に好きじゃないと続けられない世界だ」とも実感しています。
医療系を目指す人・保護者の方へ伝えたいこと
医療系を志す皆さんには、心からエールを送りたいです。
確かにこの道は厳しく、遊ぶ時間もありません。でも、努力は必ず将来の糧になります。勉強できる今を、大切にしてください。
保護者の皆さんへ──私の両親は「一緒に勉強する空気」を作ってくれました。それが何よりありがたかったです。
子どもに「勉強して」と言うよりも、一緒に机に向かう時間を増やしてみてください。それが一番のサポートだと私は思います。