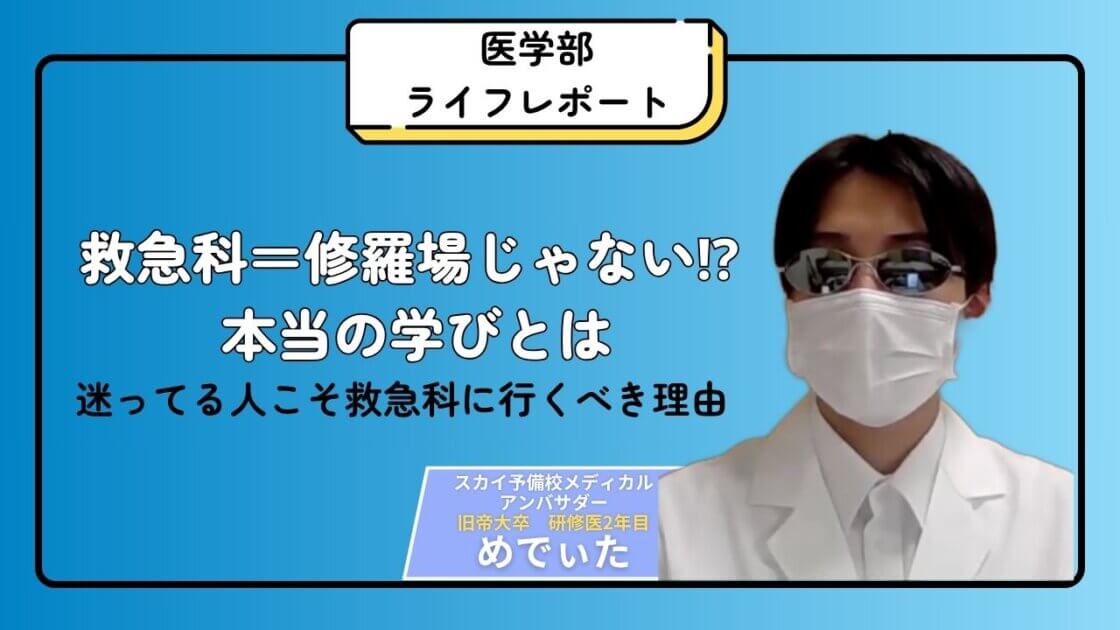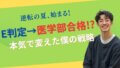【研修医めでぃた先生の医学部ライフレポート】「死にそうな人を診る」だけじゃない?研修医が救急科で得る“本当の力”とは
こんにちは!スカイ予備校メディカルアンバサダーのめでぃたです。
今回は「救急科の研修って、ぶっちゃけどうなの?」というテーマでお届けします💥
「ERドラマみたいな修羅場が毎日続くの?」
「寝れないんじゃ…?」
「自分にそんな重症患者を診る余裕あるのかな…」 そんな不安を感じているあなたに、
研修医のリアルな視点で「救急科研修の実際」と「得られる力」を解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
救急科の仕事、ざっくり言うとこの3つ!
救急って一言で言っても、実際はかなり多様です。
でも、ざっくり分けると研修医が関わる仕事はこんな感じ👇
① 「死にそうな人」を何とか持たせて、専門医につなぐ
→ いわゆる“重症初期対応”。CPA(心肺停止)、ショック、重度の外傷…
この対応の最前線に立つのが救急科です。
② 入院が必要か“グレーな人”を見極めて、入院 or 外来フォローに振り分ける
→ 腹痛、熱発、軽い意識障害、嘔吐…判断が難しい人のトリアージ。
③ “軽症”をしっかり軽症と見抜き、安心して帰ってもらう
→ 実はこれが一番難しい。風邪と思いきや髄膜炎だった…なんてことも。
救急は「すべての医師の基礎」
よく言われることですが、救急はすべての診療科の入り口です。
研修医にとってこれほど「ベースになる科」はありません。
- 呼吸苦→内科疾患?心不全?喘息?肺炎?
- 腹痛→外科系?婦人科?泌尿器?
- 頭痛→片頭痛?くも膜下出血?
このように、救急外来にはあらゆる科の“入口症例”が来ます。
しかも初見で、それを自分で鑑別して、判断して、動くことが求められる。
もちろん、最初から全部できる必要はありません。
上級医のサポートのもと、徐々にパターンを覚えて、思考回路を鍛えていきます。
内科も外科も学べる“貴重な場所”
救急外来には、内科疾患と外科疾患の両方がバンバン来ます。
- 呼吸苦/意識障害/熱発/脱水… → 内科的アプローチ
- 創傷/骨折/腹部外傷/やけど… → 外科的アプローチ
内科と外科を並行して扱う診療科って、実はかなり貴重です。
将来の進路に関わらず、「何となくの臓器ごとのあたり」がつけられるようになるのは、間違いなく大きな武器になります。
研修医の主戦場、それが救急
実際、救急科は研修医の出番が多い科でもあります。
- プレゼン・カルテ・指示出し
- 初期対応(採血・ルート・点滴・画像オーダー)
- 入院適応や科コンサルトの相談
上級医が後ろについてくれている前提で、
「自分が患者さんの第一印象を決める」ポジションになります。
緊張するけど…やっぱり面白い。
そして何より、全身を診る力、患者全体像を俯瞰する力が、自然と身についてきます。
働き方は?→夜勤あり。でも“若いうち限定”でやる価値アリ!
救急のネックと言えば、「ハードな勤務形態」でしょう。
実際、夜勤・当直・24時間勤務などは避けられません。
でも、これはむしろ「若いうちしかできない修行」と割り切るべき。
体力的にも精神的にもキツいけど、その分成長スピードがえげつない。
1か月前はアワアワしてたのに、
「入院・帰宅・科コンサル」まで自分で判断できるようになってる自分に驚きます。
救急科研修をオススメしたい人
- 総合診療力を早いうちに身につけたい人
- 初期対応力・判断力を鍛えたい人
- 自信をもって診察できるようになりたい人
- いろんな科を見てから進路を決めたい人
「自分に向いてる科がまだ分からない…」という人にこそ、まず救急で土台を作るのがおすすめです。
関連記事
◇研修医あるあるまとめ リアルな日常
◇小児科&産婦人科「命のはじまり」に関わる研修のリアル
◇メスを持つ覚悟と「手で覚える技術」外科体験
◇研修医の当直ルーティンってどんな感じ?
◇研修医の精神科ローテってどんな感じ?
おわりに:救急科は、未来の“どの科の医師”にも役立つ
救急科研修は、「専門医になる前の通過点」ではありません。
むしろ、将来どんな科に進んでも必ず役に立つ“思考力”と“行動力”を鍛えられる場所です。
あなたが救急で出会う症例と患者たちは、
これからの医師人生において、一生モノの経験になるはずです。
ちょっと怖そうに見えて、実は一番“教育的”。
それが救急科です🚑🔥