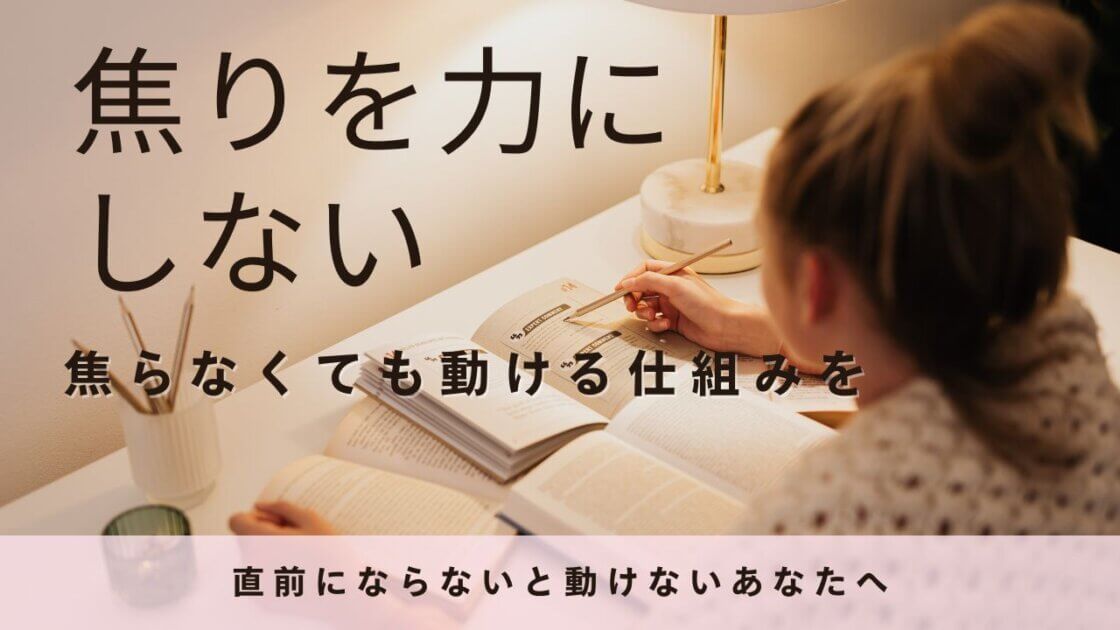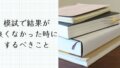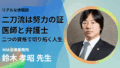模試や定期テストの前日になると、急にスイッチが入り、夜更かしして詰め込んでしまう――そんな経験はありませんか?
「追い込めば自分はやれる」と感じた翌日、眠気で集中が切れ、思うように力が出せず悔しい思いをする。
この“ラストスパート依存”は、意志の弱さではなく、人の動機づけの仕組みに原因があります。
この記事では、焦りのメカニズムとその抜け出し方を、心理学と学習設計の両面から紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
なぜ人は「直前」にならないと動けないのか
テストが近づくほどやる気が上がるのは、時間を含む動機づけの構造によるものです。
時間的動機づけ理論によれば、「価値が高いほどやる気は上がる」が、「締切が遠いほど先延ばしが起きる」構造になっています。
これがいわゆる「学生症候群」――余裕があると着手が遅れ、締切直前に一気に片づけるという現象です。
さらに、机上のスマホや通知は集中を分散させ、着手のハードルを上げてしまいます。
「夜更かしで頑張った自分」に満足しても、睡眠不足は翌日の集中力と感情の安定を奪い、結果的に“燃え尽き”を招きやすいのです。
焦りを和らげる“仕組み”で動きを変える
焦りは気合ではなく「設計」でコントロールできます。
おすすめは次の3つです👇
①「本番の内側に締切」を置く
模試や提出期限より前に“仮提出〆切”を自分で設定します。
たとえば、「模試の3日前に一度友人と答案を交換してチェックする」「講師に中間進捗を報告する」など。
自己設定の締切でも効果があり、先延ばしを抑える仕掛けになります。
②「If-Then計画」で自動的に動く
「もし19時に帰宅したら、まず数学の大問1を解く」のように、状況と行動をセットにしておくと行動率が上がります。
この“実行意図”は、意志ではなく条件反射的に行動を促す心理的トリガーです。
③「取り出す学習」で“直前頼み”を脱する
読む・覚えるだけでは記憶は長持ちしません。
問題を「取り出す」練習を挟むことで、理解が深まり、復習効率が上がります。
また、異なる種類の問題を混ぜて練習したり、復習の間隔を空ける「分散学習」を取り入れると、自然に早期着手が必要になります。
環境と体力の設計も、焦りの緩衝材になる
スマホは机から物理的に離す、別室に置くなど“見えない化”を徹底しましょう。
また、教材は「最初の一問」を付箋で用意し、30秒で着手できる状態を作ります。
夜の時間帯は「覚える→確認→見直し」と作業を軽くし、睡眠時間を削らない設計を。
短い集中+休憩をセットで回すと、結果的に学習量が増えることも多いです。
親や講師ができるサポート
家庭では「締切の先」を一緒に設計することがポイントです。
「今日の中間〆切はどこ?」と穏やかに問いかけ、達成を認める言葉を惜しまないようにします。
また、週に一度の“積み残し調整デー”をつくり、未消化の単元と休養の両方を確保しましょう。
叱咤よりも“段取りの共同設計”のほうが、子どもの自信を支えます。
塾での実践例
・授業の最初の5分で、各自がIf-Then計画を1行書く
・スマホは教室外の棚へ
・宿題には「仮提出〆切」を設定し、クラスメイト同士で提出チェック
・授業終わりに「次回の仮提出予定」を宣言
これだけでも、「本番直前しか動けない」状態から脱しやすくなります。
まとめ
直前だけ本気になる癖は、怠けではなく仕組みの欠如です。
動機づけは時間に影響され、環境は注意を奪い、睡眠は集中の土台を左右します。
だからこそ、「内側の締切」「If-Then計画」「取り出す学習」「見えない化」「睡眠の整備」という5つの設計を積み上げましょう。
完璧主義より、五分だけ着手する小さな成功体験を積むことが、最も現実的な対策です。
焦りを力に変えるのではなく、焦らなくても動ける仕組みをつくる。
それが“ラストスパート依存”を抜け出す第一歩です。