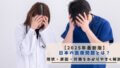記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文過去問題
R7年度 総合管理学部 総合管理学科 一般選抜(前期)(A・B方式共通)
問題1 資料1を読んで、以下の(1)から(3)の問いに答えなさい。
※資料1本文省略
(1) 下線部の㋐㋑㋒の漢字の読みをひらがなで書き、㋓㋔のカタカナを漢字で書きなさい。
(2) 以下のアからオの記述について、資料1から読み取れる内容として、適切なものには○を、適切でないものには×を書きなさい。
ア 食料問題と食品ロスが関係しているのは、特に論理の飛躍もなく、容易に理解することができる。
イ 食べ残しは消費者の意識で全て改善可能である。
ウ 調理時の過剰除去については、家庭内よりも事業者側に課題が多く残っている。
エ 日本の食品ロスの背景には、過剰な便利さ、嗜好性、安全基準が存在する可能性がある。
オ 食品ロスの観点からも、食品の安全基準は高いほど良い。
(3) フードセーフティの背景にはどのような食品ロスが関連していると筆者は述べているか、具体的な食品ロスの形態を挙げながら、50字以内で答えなさい。
問題2 資料2を読んで、以下の(1)から(3)の問いに答えなさい。
※資料2本文省略
(1) 下線部①について、食品ロスの発生量の推移と目標値を表した図として正しいものを以下のアからカの中から1つ選び、記号で答えなさい。
※アからカ図省略
(2) 下線部②を日本語に訳しなさい。
(3) 下線部③となった理由について、資料2から読み取れる内容として、適切なものには○を、適切でないものには×を書きなさい。
ア 食品需給予測の正確さの向上
イ 飲食店・小売店の営業時間短縮
ウ 食べられる部分の過剰な除去の減少
エ 円安を反映した原材料価格の下落による余剰食品の減産
オ 未開封のまま廃棄された食品の減少
問題3 資料3を読んで、以下の(1)、(2)の問いに答えなさい。
(1) 以下のアからオの記述について、資料3から読み取れる内容として、適切なものには○を、適切でないものには×を書きなさい。
ア 食品ロス問題を「あまり知らない」「全く知らない」を合わせた割合は、全ての年代を比較して、70代以上、60代、50代の順に低い。
イ 食品ロス問題を「よく知っている」「ある程度知っている」を合わせた割合が全体平均よりも高いのは、10代、60代、70代以上である。
ウ 年代ごとに見ると、寄附による事故の責任の免除が効果的だと回答した割合が最も高いのは、60代である。
エ 年代ごとに見ると、寄附先による温度管理や衛生管理などの食中毒防止の取組が効果的だと回答した割合が、全ての年代で最も高い。
オ 寄附の取組として具体的に挙げられているもののうち、寄附した後の情報の開示は、効果的と答えた回答者の割合が最も低い。
(2) 資料3からわかる、食品ロス問題の認知度と、寄附の意識の世代間の違いを挙げ、その背景についてあなたの考えを100字以内で述べなさい。
問題4 今後の食品ロスに対してどのように取り組むべきか。事業者側と消費者側それぞれの立場から、資料1から資料3までを参考にしながら、あなたの考えを200字以内で論理的に述べなさい。
※資料1~3省略
資料1:小林富雄『増補 改訂新版 食品ロスの経済学』農林統計出版(2020年)1~5頁
資料2:The Japan Times, “Japan’s food loss hits a record low in fiscal 2022”, Jun. 21. 2024
https://www.japantimes.co.jp/news/2024/06/21/japan/society/food-loss-japan/
資料3:消費者庁「令和5年度第2回消費者意識調査」集計表(クロス集計)より作成
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003
R7年度 総合管理学部 総合管理学科 一般選抜(後期)(A・B方式共通)
問題1 資料1を読んで、以下の(1)から(3)の問いに答えなさい。
(1) 下線部🄐🄑の漢字の読みをカタカナで書き、下線🄒から🄔のカタカナを漢字で書きなさい。
(2) 二重下線部により、KAPOKKNOTが取り組んでいることは何か、本文中の言葉を使って述べなさい。
(3) 本文中の日本企業の事例を読み、どのようなビジネスが新しいラグジュアリーにあてはまるか、本文中の言葉を使って述べなさい。
問題2 資料2を読んで、以下の(1)から(4)の問いに答えなさい。
(1) 本文中にある209,000円は、何の金額か日本語で答えなさい。
(2) 本文中にある4分野から1つ選び、その分野の支援として必要なことを本文中から抜き出し、和訳しなさい。
(3) 二重下線部が支援に繫がる可能性のある分野はどれか、本文中にある4分野から1つ選び、その分野を選んだ理由を述べなさい。
(4) 二重下線部において最も人気を集めた活動は何か、具体的な活動内容を述べた箇所を本文中から抜き出し、和訳しなさい。
問題3 資料3‒1から資料3‒5を読んで、以下の(1)、(2)の問いに答えなさい。
(1) 資料3‒1は、過去1年間(2023年)の訪日外国人の滞在日数を示すグラフである。4~6日間の棒グラフをみると、アジア地域が他の地域に比べて大きい値を示している。この結果に対する他の資料を踏まえた考察として不適切な記述を、以下の①~⑧からすべて選び、記号で答えなさい。
① 資料3‒2では、アジア地域の40歳未満の訪日外国人の割合が他の地域に比べて低い。よって、若年層が長期滞在した結果だと考えられる。
② 資料3‒2では、アジア地域の40歳未満の訪日外国人の割合が他の地域に比べて低い。よって、若年層が短期滞在した結果だと考えられる。
③ 資料3‒3では、アジア地域の訪日外国人の来訪回数が多い人の占める割合が他の地域に比べて高く、複数回来訪する傾向にある。よって、長期滞在より短期滞在が主流である結果だと考えられる。
④ 資料3‒3では、アジア地域の訪日外国人の来訪回数が多い人の占める割合が他の地域に比べて低く、複数回来訪する傾向にある。よって、短期滞在より長期滞在が主流である結果だと考えられる。
⑤ 資料3‒4では、アジア地域の訪日外国人による観光地の土産店の利用率は他の地域より低く、ドラッグストア、空港の免税店の利用率は高い傾向にある。よって、ショッピング目的の短期滞在が多い結果だと考えられる。
⑥ 資料3‒4では、アジア地域の訪日外国人による観光地の土産店の利用率は他の地域より高く、ドラッグストア、空港の免税店の利用率は低い傾向にある。よって、ショッピング目的の短期滞在が多い結果だと考えられる。
⑦ 資料3‒5では、アジア地域における自然・景勝地観光と日本の歴史・伝統文化体験の項目は他の地域に比べて高い数値であり、ショッピングの項目は同程度の数値である。よって、自然・景勝地観光と日本の歴史・伝統文化体験の目的で短期滞在している結果だと考えられる。
⑧ 資料3‒5では、アジア地域における自然・景勝地観光と日本の歴史・伝統文化体験の項目は他の地域に比べて低い数値であり、ショッピングの項目は同程度の数値である。よって、ショッピング目的で短期滞在している結果だと考えられる。
(2) AIチャットサービスを使用して、以下のとおり、各地域の訪日外国人を対象とした取り組みを3案ずつ提案してもらった。AIの回答結果の中から、あなたが訪日外国人を増やすために最も有用だと考える取り組み案を地域ごとに1つ選択して番号で答えなさい。また、各案の選択理由について、資料3‒5を参考にそれぞれ述べなさい。〈AIの回答〉
ア ジア地域向け:1.地元の伝統文化体験、2.地元の食事体験、3.アニメ・マンガの聖地巡礼
欧州地域向け:4.歴史的な観光地の案内、5.日本酒の醸造体験、6.山岳キャンプ
北米地域向け:7.日本の伝統的な祭り、8.スポーツイベント、9.日本のアート体験
問題4 資料1から資料3を参考にして、新しいラグジュアリーを考慮した新たなインバウンドの取り組みを提案しなさい。また、その提案内容が新しいラグジュアリーとして有効な取り組みである理由について、各資料を適切に引用しながら具体的に述べなさい。
※資料1~3省略
資料1:安西洋之(著)、中野香織(著)「新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義」、株式会社クロスメディア・パブリッシング(株式会社インプレス)、2022年、p93、94、p148‒153より一部抜粋
資料2:Yukana Inoue, “Japan wants you to spend more with ‘luxury tourism’ ”, The Japan Times, April 26, 2024.
資料3:訪日外国人消費動向調査 集計表 2023年(令和5年)暦年【確報】をもとに作成
(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001734816.xls)
R7年度 文学部 日本語日本文学科 一般選抜(後期)
次の文章は、やなせたかし(一九一九年生まれ)によるものである。よく読んで後の問に答えよ。
※本文省略
出典:やなせたかし『アンパンマンの遺書』一九九五年二月、岩波書店
問 本文末尾の傍線部について、著者は自身に死が訪れた後にどのようなことが起こると推測しているか、そして、その起こると推測していることに対してどのような思いを持っているか。本文から複数箇所を根拠として示しつつ、七〇〇字程度で論じよ。なお、解答用紙へ記入の際は、正しい原稿用紙の使い方に従うこと。
R7年度 環境共生学部 環境共生学科 食健康環境学専攻 一般選抜(後期)
次の問題Ⅰおよび問題Ⅱに答えなさい。
問題Ⅰ 我が国では、人口の急速な高齢化に伴い骨粗しょう症の患者が年々増加しつつある。WHO
(世界保健機関)では「骨粗しょう症は、低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨折の危険性が増大する疾患である」と定義している。表1のとおり骨粗しょう症の危険因子は、除去できない危険因子と除去できる危険因子とに大別される。また、骨量は男女ともに年齢によって変化するが、特に女性は、図1に示すように閉経(月経が永久に停止した状態)に伴って骨量が著しく減少する。
骨粗しょう症の発症予防としてどのような対策が効果的と考えられるか、表1および図1から読み取れることを踏まえたうえで、あなたの考えを500字程度で具体的に述べなさい。
出典:日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、骨粗鬆症財団「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」p.50 図21より作成
図1 女性における骨量の経年的変化
出典:日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、骨粗鬆症財団「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」p.14 図8
問題Ⅱ 厚生労働省が策定した健康日本21(第三次)において、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的な方針に、野菜摂取量の増加が挙げられ、20歳以上の(1人あたりの)野菜摂取目標量を350g/日以上としている。厚生労働省が行った令和元年国民健康・栄養調査によると、日本人(20歳以上)1日あたりの平均野菜摂取量は、男性288.3g、女性273.6gである。図2は、平成27年~令和元年の国民健康・栄養調査結果から、1日あたりの野菜の摂取量が350g以上の者の割合を示したものである。
問1 図2から読み取れることを、200字程度で具体的に述べなさい。
問2 1日あたりの野菜摂取量を増やすためには、どのような対策が効果的と考えられるか、あなたの考えを400字程度で具体的に述べなさい。
出典:厚生労働省「平成27年~令和元年 国民健康・栄養調査報告」より作成
R7年度 環境共生学部 環境共生学科 居住環境学専攻 一般選抜(後期)
次の問題Ⅰおよび問題Ⅱについて答えなさい。
問題Ⅰ 次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。
※本文省略
出典:西日本新聞me 2021年4月11日『「福祉避難所」確保進まず 九州 対象者数未把握の県も』より一部抜粋 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/721670/
問1 災害時の避難生活において、生活が困難な方(要配慮者)は環境変化の影響を受けやすく、居住環境や情報提供などへのより細やかな配慮が必要と考えられる。予想される災害に向けて、避難所(福祉避難所を含む)の設置を計画する場合、どのような方策が必要であるか、あなたの考えを500字程度で述べなさい。
問題Ⅱ 内閣府では「国民生活に関する世論調査」において、これからの生き方として、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい(以下、物の豊かさ)」、「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい(以下、心の豊かさ)」の、いずれの考え方に近いかについて(図1)、また、「社会意識に関する世論調査」において、「日本の国や国民について、誇りに思うことはどんなことか」について(図2)、それぞれ経年的に調査している。
そこで、以下の問1、問2に答えなさい。
問1 図1および図2を考え合わせるとどのようなことが読み取れるか、あなたの考えを200字程度で述べなさい。
問2 問1を踏まえ、国民の「豊かさ」を実現するためにはどのような居住環境を実現していく必要があるか、住居、建築、都市、地域などの観点から、あなたの考えを具体的に5500字程度で述べなさい。
※図1、図2省略
図1「豊かさ」に関する意識の推移
出典:内閣府『「国民生活に関する世論調査」の概要』表21-参考より作成
https://survey.gov-online.go.jp/202412/r06/r06-life/gairyaku.pdf
図2「日本の誇り」の推移(複数回答)
出典:内閣府『「社会意識に関する世論調査」の概要』表11-参考1,表11-参考2より作成
https://survey.gov-online.go.jp/202501/r06/r06-shakai/gairyaku.pdf
学部学科、コース
文学部
人間文化の探究を通じて、言語、文学、歴史、思想などについて豊かな教養を持ち、地域社会および国際社会の発展に貢献する人材を育成する。
文学・言語を中心とした人文学の基礎的知識を身につけ、併せて全学共通科目により総合的な素養を身につけることで、幅広い知見と判断力を養い、広く多角的に物事をとらえ思考できるよう、カリキュラムを編成している。
日本語日本文学科では、日本のさまざまな時代の文学作品や古代から現代までの日本語を対象とし、歴史的・文化的背景を視野に入れて、読解・分析能力を養う。
英語英米文学科では、英語を通して人間と世界を理解することを目標とする。英語によるコミュニケーション能力を高め、言語・文学・文化を深く理解し、国際的視野を持って活躍できる人材を養成する。
環境共生学部
自然と人間が共存し、環境を有効に、また持続的に利用・保存していくことが求められるなかで、さまざまな問題を総合的にとらえ、問題解決するための知識の修得を目指す。
以下の3専攻制。
①環境資源学専攻では、地域の生態系を支配する環境要因や人間活動が及ぼす影響と、自然環境と人間活動との共生の基礎的理論などについて学ぶ。
②居住環境学専攻では、環境への負担や人間の健康などの視点を重視した住居、建築、都市、居住環境を研究する。
③食健康環境学専攻では、環境にやさしい食資源や地域の環境特性を考慮した食生活の設計、健康増進のあり方を学ぶ。
総合管理学部
公共・福祉、ビジネス、情報など、あらゆる分野での「総合管理力」を身につける。多様な専門分野や考え方を総合して創造的に課題を解決できる能力を持った人材の育成を目指す。
また、グローバル科目を設け、より深い国際的な知識と実践力の習得を目指す。地域活性化の方策や福祉サービスなどを学ぶだけでなく、地域社会や福祉の分野で実践的に活躍するために、グローバルから地域に至るあらゆる領域における知識と視点を習得する。
以下の3つの専門分野を設けている。
①公共・福祉分野では、公共経営、行政組織、行政法、商法、社会保障などを学び、企業経営の視点を備え、政府・自治体で活躍する力を身につける。
②ビジネス分野では、経営組織、経営分析、ファイナンス、金融、公共経済などを学び、公共性やリーガルマインドを備えた企業人として活躍する力を身につける。
③情報分野では、人工知能、情報デザイン、情報システム、情報通信技術(ICT)および情報管理のあり方を学び、公共機関や民間企業の情報部門などで活躍する力を身につける。
所在地・アクセス
熊本県立大学のHPはこちら
入試情報はこちら
| 所在地 | アクセス |
| 熊本県熊本市東区月出3-1-100 | JR豊肥本線「水前寺」駅から保田窪経由バスで20分 |