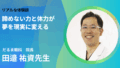英語の長文が読めない、数学の関数で止まる、古文の助動詞が頭に入らない──。
こうした“科目ごとの壁”は、誰にでも起こり得ます。
けれども、「感覚的に苦手だから」と片づけてしまうよりも、脳のしくみから原因を探り、戦略を立てるほうが、確実に解決へと近づけます。
つまり、「何が負荷になっているのか」「どんな学び方で乗り越えられるのか」を言語化してから動くことが大切です。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
つまずきの正体
学習の初期につまずきやすい理由の一つは、作業記憶への負荷が高すぎることです。
情報を同時に処理する量が多いと、理解の糸口が切れやすくなります。
ここで役立つのが「例題の分解(ワークト・エグザンプル)」。
手順を可視化することで負荷が下がり、理解の土台が整います。例題の分解は初学者に特に有効だと報告され、注意の分散を避ける設計が理解を助けると示されています。
一方で、「勉強しているのに身についていない」感覚が強いときは、学びの錯覚が疑われます。
ハイライトや読み返しは安心感を生みますが、長期記憶の強化には直結しません。再読の“流暢さ”が理解した気分を作る一方で、実力にはつながらない──この指摘は根強いものです。
そこで鍵となるのが「想起練習(テスト効果)」。
人は答えを見て覚えるよりも、「思い出そうとする」過程で記憶が強化されます。さらに「分散学習」と組み合わせると、定着が安定しやすいとされています。想起と分散は“望ましい困難”として、長期記憶を押し上げる代表的な方法です。
また、類題ばかりを解くよりも「交互練習(インターリーブ)」を取り入れることが効果的です。
異なるタイプの問題を混ぜることで戦略の見極め力が鍛えられ、演習中の得点感覚は下がっても、後日のテストで伸びやすいという“学びとパフォーマンスのズレ”が知られています。苦手科目こそ、この設計が効きます。
さらに、ミスを恐れて手が止まるときこそ、「エラーフルラーニング(誤りを含んだ学び)」の考え方が有効です。
誤答をあえて生み、その直後に正しいフィードバックを得ることで、記憶の定着が促進される可能性があります。誤りを“学びのヒント”として扱う姿勢が、苦手への向き合い方を変えていくのです。
設計と戦略
苦手の正体が見えたら、次は“手順の設計”に入ります。
まずは「いつ・何を・どうやって」の3点を固定し、想起→説明→休止→再挑戦の循環をつくりましょう。
「自己説明」を挟むと理解の結合が進み、手順の意味づけが深まります。
例題を声に出して因果をつなげ、「なぜこの式変形が必要か」「どの条件で使えるか」を言語化するのがコツです。
次に、「時系列の設計」。
分散学習では、復習間隔とテストまでの距離の関係が重要です。短すぎても長すぎても効果が落ちるため、科目の到達期限から逆算し、間隔を少しずつ伸ばす計画を組みましょう。
「交互練習」は「識別の練習」として設計すると分かりやすいです。
数学なら“関数・図形・確率”、英語なら“語彙・文法・読解”を混ぜてローテーション。解く前に「これはどの型か」を判断する練習を入れると、初見問題への耐性が高まります。
導入段階では「例題→自力演習」のサイクルを短く回すと安定します。
作業記憶の負荷を抑え、誤学習を避けるねらいです。
また、**実装意図(if–then)**を設定しておくのも有効です。
「証明で行き詰まったら、条件と結論を三語で言い換える」など、状況と行動を結びつけておくことで、行動の自動化が進みます。
さらに、「挑戦的で具体的な目標設定」や「進捗の見える化」も外せません。
進捗の記録や第三者への共有は、達成率と関連するとされます。学習ログや面談での共有は、理にかなった方法です。
そして、テスト前の緊張は“資源にアクセスする合図”として再解釈します。
「鼓動=準備が整ったサイン」と捉えるだけで、パフォーマンスが改善する研究もあります。
最後に、生活の基盤を整えること。
睡眠は記憶の固定を支え、運動は注意や実行機能を助けます。
“根性論”よりも、睡眠と軽い有酸素運動で「学びやすい身体」を整えることを意識しましょう。
実践の手順
ここからは、苦手科目を“設計図どおりに動かす”ための手順を整理します。
まず、単元の棚卸し。
できない問題を種類別に書き出し、「理解・手順・正確さ」のどこでつまずくのかを見立てます。
見立てがついたら、「例題の分解→自己説明→短い想起→再挑戦」の一巡を作りましょう。最初は量より“見える化”を優先するのがコツです。
次に、分散と交互の時間割を組み込みます。
英語なら「語彙・文法・読解」を小刻みに回し、翌日・数日後・一週間後に再テスト。
数学なら「関数・図形・確率」を混ぜ、解く前に“型の宣言”をします。成果は“後日”に出やすい設計だと心得ましょう。
誤答は“データ”です。
誤答に印を付け、同種のミスを集めて「誤答コレクション」を作りましょう。正答理由とセットで整理すれば、理解が強化されます。
また、行動脚本を用意しておくと効果的です。
詰まった瞬間の一手をあらかじめ決めておく──英語なら「主語と述語に下線」、数学なら「条件を書き出して図に戻る」など、if–then形式で机に貼っておきましょう。
進捗は“目に見える形”で残すのがコツです。
想起テストの結果を簡単に記号で記録し、週1回は誰かに口頭で共有しましょう。共有とモニタリングは、学習の継続を支える要因です。
さらに、「生産的失敗」の時間を挟むと、理解が深まります。
説明の前に少し試行錯誤するだけで、知識の“刺さり方”が変わります。誤りを恐れず、“失敗の活用”を設計に組み込むことが大切です。
生活面では、睡眠と運動のリズムを学習の前提に。
前夜は軽く復習、翌朝は“誤答コレクション”から再挑戦──これで睡眠中の記憶固定が活かされます。短い有酸素運動も注意の切り替えを助けます。
そして、メンタルの波を“合図”に変えること。
緊張が高い日は「これは準備のサイン」と読み替え、最初の一問に着手する。
この姿勢が、苦手科目の入口で効いてきます。
最後に
苦手科目は“才能”ではなく、“設計”で変えられます。
作業記憶の負荷を下げ、想起・分散・交互の三本柱を活かし、自己説明と誤りの活用を習慣に。
そして、if–thenの仕組みで行動を自動化し、進捗を共有する。
睡眠と運動を味方につけ、設計→小さな実行→振り返りの循環をつくれば、苦手は「できる」に変わります。
まずは、机の上に「最初の一問」と「詰まったときの一手」を置いてみましょう。
その瞬間から、変化は始まります。