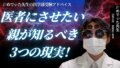記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文過去問題
R6年度 国際経済学部 一般選抜(A日程)
次の文章を読み、問いに答えなさい。
※本文、図省略
図1:実質GDP(付加価値総額)及び総雇用者数に占める製造業と成長3産業のシェア
出典:国民経済計算、労働力調査
表1:実質GDP(付加価値総額)と総雇用者数の変化
問1 本文では、サービス産業は設備をつくる産業ではなくどのような産業であると説明しているか。「専門・科学技術、業務支援サービス業」と「保健衛生・社会事業」の2つを例に取り上げてどのような産業であるかに触れたうえで、特にその制約について説明しながら、サービス産業の特徴について本文を200字以内で要約しなさい。なお、「専門・科学技術、業務支援サービス業」については、「専門サービス業」と略して構わない。
問2 表1は、図1の2008年と2021年における製造業と成長3産業の実質GDP及び総雇用者数を実数で示したものである。2008年と2021年における総雇用者一人当たりの実質GDPを製造業と成長3産業それぞれについて計算し、千円の位で四捨五入して万円単位で解答しなさい。解答欄に計算過程も記入すること。
問3
1)本文前半には「成長3産業の中では特に医療・福祉産業(医療、保健衛生、介護を含む)の
雇用の増加が著しい」との記述がある一方で、本文後半には「医療・介護産業では全国的に医師・
看護師・介護士の不足が言われ続けている」との記述がある。医療・福祉産業と医療・介護産
業はほぼ同義として扱われているため、以下では「医療・介護産業」に統一する。
以上のように、医療・介護産業の雇用は大きく増加しているのに、全国的に不足が言われ続けている。ある地域で不足している状況が確認される場合、雇用の絶対数の全国的な不足以外に、問1で解答したサービス産業の特徴と関連付けて考えると、その原因をどのように説明できるだろうか、120字以内で述べなさい。
2)筆者は本文の最後で規制緩和の重要性を述べているが、規制の緩和以外に労働供給の制約をいくらかでも緩和できると考えられる策について、①賃金、②労働環境の二つの用語を用いながら、80字以内で述べなさい。
R6年度 国際経済学部 一般選抜(B日程)
以下の文章を読み、問いに答えなさい。
※本文、図省略
出典:観光庁『令和2年版観光白書』第II部「新型コロナウイルス感染症への対応と観光による再びの地方再生に向けて」p.57、pp.76-81より一部改変
図1:国籍・地域別にみた訪日回数の構成比(%)
出典:『 令和2年版観光白書』図表II-31を再構成。
表1:東アジア4か国・地域別にみた1人当たり旅行支出(2019年単位:万円)と平均泊数(2019年単位:日)
表2:X 国から国内都市部への訪問率(%)と延べ訪問率(%)
表3:東アジア4か国・地域から国内2地域への訪問回数別延べ訪問率(2019年単位:%)
問1 表1には、問題文中の東アジア4か国・地域からの旅行客について、訪日回数ごとに集計した1人当たり旅行支出及び平均泊数が記載されている。表1の内容に関する次の問いに答えなさい。
問2 訪日外国人旅行者の訪問先都道府県を「都市部」と「地方部」の2地域に分ける。ここで「都市部」とは、三大都市圏のうち千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の8都府県を指し、「地方部」とは都市部以外の道・県を指す。ここでは、各地域の旅行者が複数の都道府県を訪問することを、訪問する地域の広がりと表現する。
観光庁観光戦略課観光統計調査室では、訪問先の地理的な広がりを把握するために、都市部と地方部でそれぞれ「訪問率(%)」「延べ訪問率(%)」という指標を使って調査している。これらの定義について次ページに示す表2を例に説明すると、X国からの訪日回数1回目の旅行客の東京都の訪問率(%)は、120/150=0.8、百分率表記で80.0%と定義する。X国から訪日回数1回目の旅行客の都市部への延べ訪問率(%)は8都府県の訪問率の総和で定義される。
問3 問2での定義から分かるように、訪問率が全体的に増えて旅行客がより多くの都道府県を訪問すると、延べ訪問率は増加する。表3は、問題文中にある4か国・地域からの訪日旅行者の訪問先について、問2で定義した「都市部」と「地方部」の延べ訪問率を訪日回数ごとに集計したものである。例えば表3の香港は、訪問回数が増えるほど地方部の延べ訪問率が増加している。これは、「訪日回数が増えるほど訪問する地域に広がりがみられ」るという問題文中の記述と整合的である。それらを踏まえて、次ページの問いに答えなさい。
1)表3の韓国と台湾の延べ訪問率から、訪問地域の広がりに関する両者の共通点と相違点を100字以内で記述しなさい。
2)2019年時点において表1に示される旅行支出と平均泊数に関する中国の特徴、表3に示される中国人旅行客の訪問パターン、及び問題文中の中国人旅行客の訪問意向に関する記述を参照し、地方部へ中国からの訪日リピーターを誘致することのメリットと、今後彼らを誘致するに当たっての地方部の課題について、あなたの考えを述べなさい。
R6年度 国際経済学部 一般選抜(B日程)
問1 表1の表側「国・訪問回数」ごとに2つの観光指標1人当たり旅行支出と平均泊数)の数値パターンを把握して文章化する学力を問うている。
1) 4か国・地域に共通して観察できる傾向とは、4か国・地域の数値に一貫して観察できるパターンのことである。ここでは訪問回数ごとの1人あたり旅行支出のパターンを簡潔に述べる。
2) 韓国とそれ以外の3か国・地域の違いについて簡潔に述べる。1人あたり旅行支出と平均泊数ともに、他の3か国よりも小さいという特徴を記述する。
問2 訪問率と延べ訪問率という受験生にとって初見に近い観光統計指標の基本的理解を問うている。各都道府県の訪問率は訪問者数の実数を用い、地域の延べ訪問率は地域を構成する都道府県の延べ訪問人数を考えるので、訪問率の単純な総和で求まる。地域内で複数の都道府県を訪問する旅行者が増えればそれだけ延べ訪問率は増える。表2は仮想的なA国による数値例であるが、訪日回数1回目よりも2回目以上の旅行客の方が、相対的に都市部のより多くの都道府県を訪問していることを例示している。(A)から(D)は問題文の定義に沿って計算するだけである。
問3
1) 表3の台湾と韓国に関して、訪日回数とともに変化する延べ訪問率のパターンを都市部と地方部それぞれで読み取り、共通点と相違点を明記させる問題である。
2) 表1、3と問題文という複数の情報源を組み合わせ、中国からの旅行客の地方への誘致について自分の考えを論述する能力を問うている。表1では、中国は1人当たり旅行支出が4つの国・地域の中で最大であること、平均泊数が他3か国・地域と比べても大きいという特徴がある。この特徴から、地方
にとって中国人旅行客は他と比べ経済的に大きな貢献をもたらすと考えられる。表3では、他の3か国・地域と比べて中国からの旅行客は訪日回数が増えると、都市部と地方部の両方で延べ訪問率が減少するという顕著な特徴がある。他の3か国・地域に比べて訪問する都道府県の広がりはむしろなく
なっていく傾向にある。加えて問題文最終段落にあるように、別の調査によると中国は訪日回数が増加しても再訪する地域は限られているが、「訪問経験のない地方」への訪問意向が、地方の延べ訪問率が中国よりも大きい台湾や香港以上に高い結果となっている。これらの読み取り作業により、「中国人旅行客の地方の訪問意欲は潜在的に香港や台湾よりも高いにもかかわらず、表3の地方部のデータを見ると、現実には地方部での地域的広がりは小さい」という2019年時点での現状認識が可能になる。中国人旅行客の地方への誘致を増やすという目的から、この現状認識を踏まえた課題を自由に解答す
ればよい。
出題意図
R6年度 国際経済学部 一般選抜(A日程)
問1については、本文中にあるサービス産業を特徴づける記述(設備を作る産業ではないこと、専門・科学技術、業務支援サービス業では科学技術研究が生み出すサービスそのものを付加価値とする産業であること、保健衛生・社会事業では、人と人との間のサービスのやり取りを中核とする産業であること、といった点について触れたうえで、付加価値がサービスの行なわれる「その場」で生み出されるため地理的な制約が重要な意味を持つこと等を指摘し、指定された字数内で要約することを求めている。
問2については、問いで示された内容を正しく理解し、計算することができる学力を問うものである。
2008年における製造業の総雇用者数一人当たりのGDPであれば、
111*100000000(万円単位 GDP )を1150*10000(総雇用者数)で割って965
2008年における成長3産業の総雇用者数一人当たりのGDPであれば、
98*100000000(万円単位 GDP )を1000*10000(総雇用者数)で割って980
2021年における製造業の総雇用者数一人当たりのGDPであれば、
118*100000000(万円単位GDP)を1050*10000(総雇用者数)で割って1124
2021年における成長3産業の総雇用者数一人当たりのGDPであれば、
119*100000000(万円単位 GDP )を1400*10000(総雇用者数)で割って850
問3の1)については、雇用が大きく増加しているのに全国的に不足が言われ続けている要因として、サービス産業の特徴としての地理的(空間的)な制約がある点をふまえて分かり易く記述することを求めている。
問3の2)については、筆者は本文の最後で労働供給不足を緩和する策として規制緩和の重要性を述べているが、規制の緩和以外に考えられるものを、所定の語句を使って示すことを求めている。
学部学科、コース
国際地域学部
教養教育と専門科目を総合して学び、国際的に活躍でき、また地方におけるグローバル化への対応能力に優れた、地域づくりを担う中核的な人材を養成。
300を超える科目を開設。バリエーションに富んだ科目群と魅力あふれる授業内容で、履修コースを越えた科目の選択も可能。以下の3コース制。
国際関係コースでは、世界、そしてアジア地域の国際的・地理的課題に実践的な英語力を使って取り組む。比較文化コースでは、国際地域学の基礎の上にさらに文化や言語に特化した授業を展開する。露中韓コースでは、新潟県と交流の深いロシア・中国・韓国の歴史や情勢、言語を深く学ぶ。
人間生活学部
人間についての深い理解に基づいて、「育」と「食」を中心に豊かなヒューマンライフを創造し、地域社会の発展に貢献できる人材を育成する。
子ども学科では、乳幼児保育・社会福祉の現場で中核として活躍できる人材の育成を目的に、教育・研究を行う。
専門科目は、保育の本質と目標、子どもの心とからだ、子どもの文化、保育の内容・方法、地域社会と福祉、実践演習、実習に関する科目の7科目群。
健康栄養学科では、生活習慣病の予防や健康の維持・回復に食と栄養の面から総合的に対応できる人材を育成する。
地域の食について深い理解を育むための科目もある。
国際経済学部
経済・産業・企業の仕組みを理解する経済学の最新の専門知識、データや情報の分析力、確かな語学力と国際感覚を備えた国際経済・地域経済のフィールドで活躍できる人材を育成する。
グローバルな視点からの実践力を習得し、4年間の体系的・段階的なカリキュラムにより、1最新の経済・産業・企業を理解、分析する能力、2データ・情報を読み解き、分析する力、3グローバルな活躍を支える確かな語学力を身につける。2年次以降は、国際経済への理解を深めることに重点を置く国際経済コース、地域経済への理解を深めることに重点を置く地域経済創生コース、データサイエンスの基礎とデータの利活用のスキルを修得し、経済・社会・地域の持続的発展と価値創造に貢献する人材の地域での育成に重点を置くデータサイエンス経済コースの3コースに分かれて学習する
所在地・アクセス
新潟県立大学のHPはこちら
入試情報はこちら
| 新潟県新潟市東区海老ケ瀬471 | JR白新線「大形」駅下車、徒歩約15分 JR「新潟」駅から新潟交通バス大形線約25分 「県立大学前」下車、徒歩3分 |