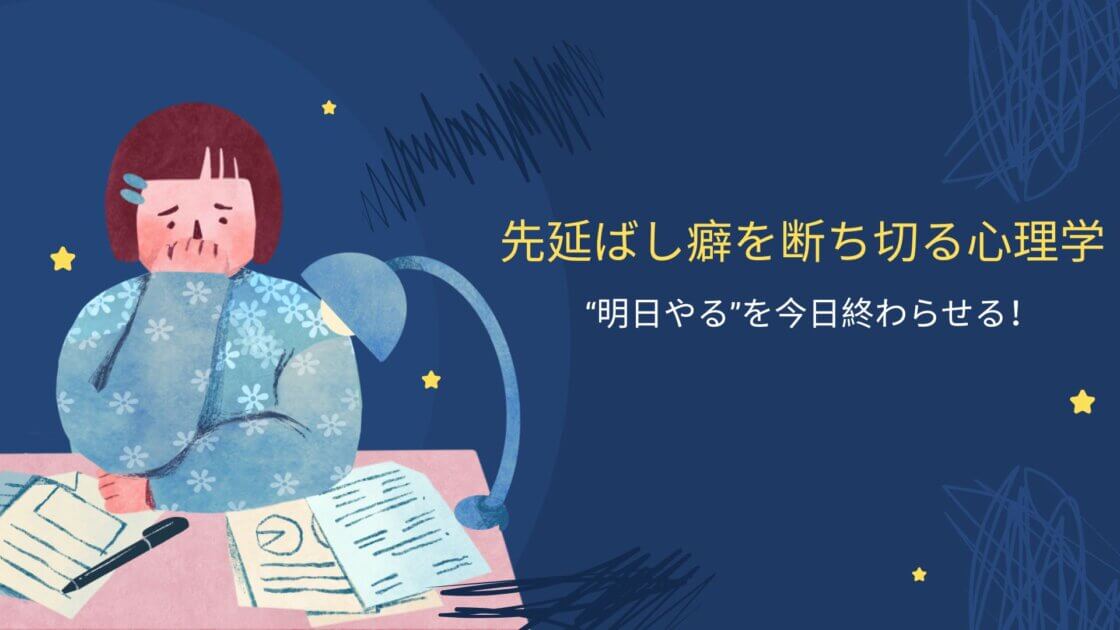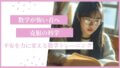受験本番が近づくほど、「あとでやろう」「今日は気分が乗らない」と感じる瞬間が増えていきます。
SNSを開いて気づけば20分、模試の直しを“明日こそ”と後回しにしてしまう──。
これは意志が弱いからではありません。先延ばしは「怠け」ではなく、「感情」と「時間の錯覚」が関係するごく自然な現象です。
この記事では、塾長の視点から「先延ばし癖を直すための実践的アプローチ」を、心理学的な視点と具体的な行動例を交えてお伝えします。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
先延ばしの正体
先延ばし癖の原因と聞くと、多くの人は「やる気が出ないから」と答えます。
英単語帳を開く前にSNSを少しだけ見て、気づけば二十分が過ぎてしまう。
数学の問題を前に「資料をそろえてからにしよう」と机を片づけ始める。
模試の直しを後回しにしてしまう。ベッドの中で「明日の朝やる」と先送りする──。
これらは意志の弱さというより、「感情のやりくりの失敗」に近いものです。
退屈・不安・面倒くささといった短期の気分を守ろうとして、人はタスクから離れます。
心理学ではこれを「短期の気分修復」と呼び、結果として長期の目標が後回しになるのです。
さらに、先延ばしは「未来の自分にツケを回す行動」でもあります。
いまの不快を避けると一時的には楽ですが、その負担は後日に積み上がります。
そこで重要になるのが、「いまの気分」と「未来の自分」をつなぐ橋渡しです。
そして、失敗した日の自分を強く責めると、次の行動が怖くなります。
そのとき役立つのが**自己への思いやり(セルフ・コンパッション)**です。
自分を責めるより「次の一歩」に目を向けることで、先延ばしとストレスの両方が軽くなります。
感情から着手する:科目別の“最初の一分”
先延ばしは気分の嵐に似ています。まずは「始動のハードルを下げる」ことが現実的です。
以下は、科目別に感情の抵抗を減らす“最初の一歩”の例です。
- 英語長文:最初の30秒で接続詞や指示語などにマークを付ける。訳や設問は後回しでOK。
- 現代文:最初の設問だけ精読し、本文の「読みの視点」を先に定める。
- 古文:最初の二文を声に出して読む+助動詞の終止形にマーカーを引く。
- 数学:定義を書き出し、一問だけ式を置く。“方針を3行書く”だけでも十分。
- 理科:公式の形(例:F=ma)を欄外に下書きし、代入は後回しにする。
どの科目も「成果」ではなく「着手」をゴールに置くのがポイントです。
失敗した日は自分を責めず、「最小単位から再開」するほうが継続できます。
環境トリガーを減らす
どんなに気合いを入れても、環境の摩擦が強いと小さな火は消えます。
特にスマートフォンは集中を奪う最大の要因です。
- 机の上に置かない(別室・玄関・電源オフ)
- 机上は「参考書一冊+ノート一冊+筆記用具のみ」
- SNSの見張り役は“友人との事実報告”で代用(宣言型は非推奨)
また、進捗は**「見える・触れる・数えられる」**形で記録します。
紙のチェック欄、スタンプ、週末の家族報告など、「公開度」が高いほど維持効果が上がります。
時間の錯覚を利用する
先延ばしの背景には、「時間の見積もりの偏り」があります。
たとえば「前回より早く終わるはず」と過信する計画錯誤、
「今の快楽を優先し、努力を未来に送る」**現在志向(プレゼントバイアス)**です。
これを防ぐには、次の3つの方法が効果的です。
- 締切の前倒しと分割設定
課題を段階締切に分け、宣言とごほうびを組み合わせて“進めるきっかけ”を増やします。 - 未来の自分を“近く”に感じる
志望校のキャンパスで学ぶ自分をイメージする「エピソード未来思考」は有効です。 - 勉強の価値を一時的に底上げする
英単語をゲーム化する、好きな飲み物をセットにするなど、努力と快を抱き合わせる設計です。
これらを受験生活に落とし込むと、過去問演習や就寝前のルーティン改善にも活かせます。
とくに「夜のふるまい(スマホ・就寝時間)」は翌日の集中力を左右します。
最後に
先延ばしは根性不足ではなく、感情と時間の錯覚が交わる現実的な現象です。
だから、解き方も現実的に組み立てる必要があります。
- 感情のハードルを下げる「始動の一分」を設計する
- 環境の摩擦を下げて「見える化」する
- 計画錯誤と現在志向を前提に「分割締切+未来の自分」を意識する
合わない方法は無理に続けず、「刺さる手」を残せば十分です。
まずはノート一行、設問一つ、音読二文。
そこから火が点きます。今日の“一歩”が、明日の集中をつくります。