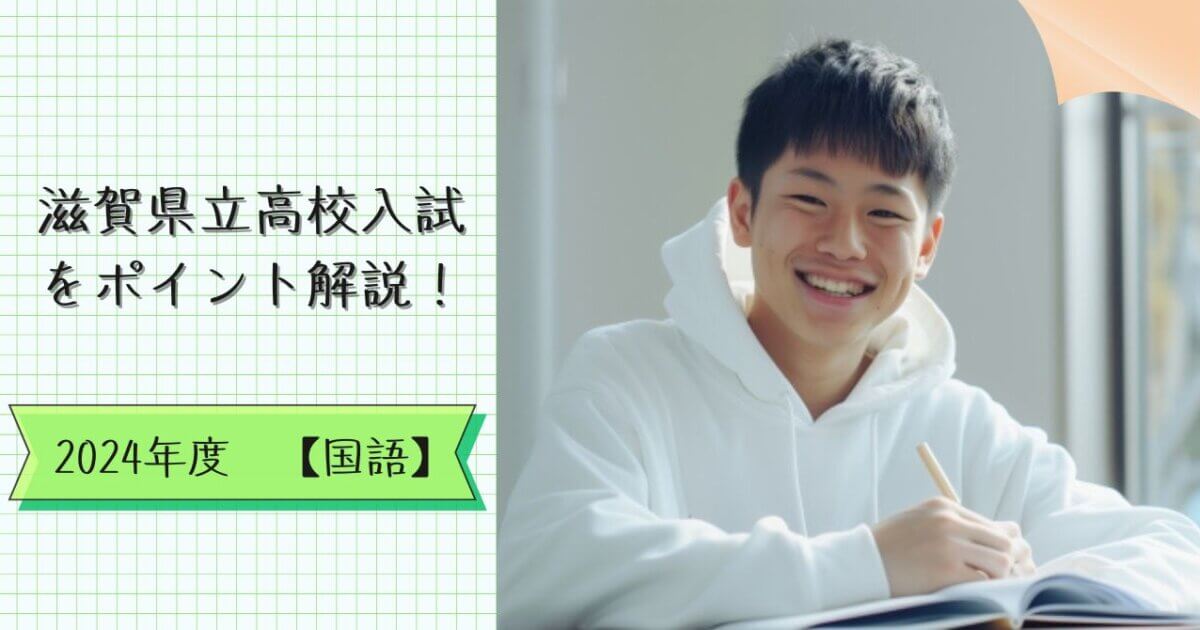2024年度滋賀県立高校入試では、論理的文章・論理的文章・知識問題の3題構成になっています。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
大問1(論理的文章)
幸田正典『魚にも自分がわかる―動物認知研究の最先端』からの出題です。
〈解答〉
1、エ
2、対象個体~のだろう
3、イ
4、四頭のチンパンジーすべてに鏡像自己認知ができたと考えられる状態を作るため。
5、鏡の中の個体を自分以外の個体だと認識しているなら鏡像の印を触ろうとするはずだが、チンパンジーは鏡を見てすぐに自分の額に印がついていると認識して額を触り、触った指先についた印の匂いを嗅ごうとしたから。
〈解説〉
1、四字熟語(選択肢)
チンパンジーが鏡に映った印を見て、すぐに自分の額を触ったのなら、鏡に映るチンパンジーが自分であることを認知できているということになる。
空欄の次の段落で、「迷わず自分の額を触る」と言い換えられているので、「【空欄】することなく」は「迷わず」という意味だとわかる。
2、内容読解(抜き出し)
「動物が認識したかどうかは、彼らの動きや反応、ときには表情などを注意深く観察し、『行動で返事をさせる』」しかない。そのとき、人間ならこういう状態であるだろうと推測し、判断するということになる。それを、「対象個体に感情移入をして、『きっとこう感じている、思っている』のだろう」と表現している。
3、内容読解(選択肢)
①「威嚇や攻撃的な振る舞いをする」=B
②「鏡に向かって腕を振ったり体を揺すったりなどと、普段はしない不自然な行動をとる」=D
③「鏡に向かって自分の口を開いて中を調べたり、普段は見えない股間などを調べたりする」=A
4、理由説明(40字記述)
「チンパンジーに、鏡像自己認知ができたと思われるまで、長時間鏡を見せる」という説明に着目する。「鏡を見せて一〇日が過ぎ」というのは、「長時間鏡を見せる」ことと同じ意味であるので、その目的は、「チンパンジーに鏡像自己認知ができたと思われる」ようにするためだとわかる。
5、理由説明(100字記述)
この結果の内容を押さえる。実験により、「額の印に気づいて」いないチンパンジーは「鏡を覗き込んだあと、なんと四頭すべてが自分の額の印を触」り、「さらに、触った指先をじっと~嗅ごうとした」という結果が得られた。
「印が鏡の中の個体についていると認識したのなら、自分の額ではなく鏡像の印を触ろうとするはず」なのに、「迷わず自分の額を触るのは、鏡像は自分であると認識している」ということになるのである。
大問2(論理的文章)
神野紗希『俳句部、はじめました―さくら咲く一度っきりの今を詠む』からの出題です。
〈解答〉
1、「風光る」が春の暖かな日差しが輝く様子を表すのに対し、「風冴ゆる」は冬の寒く澄んだ大気の様子を表す。
2、切れ字
3、夏
4、エ
5、例:中学1年生の担任の先生に、「人生はプラスマイナスゼロである」と言われたことがある。幸せなことがあれば、その分辛いことがあり、辛いことがあればその分幸せなことがある。懸命に努力を重ねるという辛いことをやれば、その分幸せなことが起きると考えて、以前よりも頑張れるようになった。
〈解説〉
1、内容読解(50字記述)
「風光る」は、「輝く日差しに、見えるはずのない風までまばゆく感じる、春の光量を言いとめた季語」で、「風冴ゆる」は、「大気が澄んでさえざえと吹き渡る風」だと説明されている。
2、俳句の技法(記述)
「けり」と「や」が切れ字である。切れ字は、句を切る働きをする助詞や助動詞のことで、詠嘆や強調といった意味をもつ。
3、季語(1字記述)
直後に「同じような考え方」とあるので、「竹の秋」に注目する。「竹は春から夏にかけ黄葉・落葉するため、他の木々にとっての秋のようだから、春の竹のさまを『竹の秋』という」と【本の一部】で解説されている。ただ、それと同じだと言われても、「麦秋」の季語を答えるのは難度が高い。「収穫の秋」という発想から、麦が最も実るであろう季節を想像しよう。
4、内容読解(選択肢)
アについて、「季語によって示される風景とまったく同じ風景を目にすることで」が誤り。俳句は
「教室の風景をそっくり写し取ることもできる」ものだが、風景が季語の表すものとまったく同じである必要は本文では述べられていない。
イは、「自分を取りまく世界を好ましく思ってより美しく感じられる」が誤り。「解像度がぐっと上がる」の説明になっていない。
ウは、「体験不足を補う」が誤り。
5、作文(100字~140字記述)
ある言葉との出会いをきっかけに、ものごとの見方や考え方が変わった経験を書く。
大問3(知識問題)
〈解答〉
1、①胃腸 ②裁判 ③幕 ④修 ⑤製品
2、①たいせき ②こうけん ③しずく ④した ⑤あいまい
3、①ウ ②イ
4、①幸くあれ ②においける ③ア
〈解説〉
1、漢字の書き取り(記述)
「オサめる」が出題された。このような同音異義語には注意しておこう。
2、漢字の読み(記述)
「堆積」・「貢献」・「滴」・「慕」・「曖昧」の読みが出題。
3、
①接続語の働き(選択肢)
「つまり」は「転換」ではなく、「要約」である。
②副詞(選択肢)
二段落目に注目する。「母親が子どものことばをまねており、しかも子どもに模倣することを促している」と説明している。母親の行動自体は、無意識のものではないことがわかるので、アの「たまらず」やウの「おもわず」は不適である。
また、エの「たゆまず」は「心が緩まずに」という意味なので、前後の文脈に合わない。
4、
①発言箇所(抜き出し)
やや難しい。「言ひし言葉」がヒントになるが、「幸くあれ」か「幸くあれて」で迷う。「あれ」が命令形として一つのまとまりをなしていることから判断する。
②現代仮名遣いに(記述)
「にほひける」を「においける」に改める。
③和歌の解釈(選択肢)
Aは「防人歌」となっていることを押さえる。防人は、北九州沿岸の防備のために東国から集められた兵士であり、故郷の家族や親しい人と別れを経験していることが多い。Aの歌では、「父母」との別れが詠まれている。
Bはざっくり解釈すると、「人の心は分かりません。故郷では花が昔と変わらないよい香りで咲いている」となる。「変わる人の心」と「変わらない梅の花の香り」という対比で考えるとよいだろう。イとウはAの解釈が明らかに誤っているので切る。あとは、アとエを比べればよいが、エの「他人の過去の経験について聞いたことをもとにして」の部分がBの歌からは判断できないので誤り。