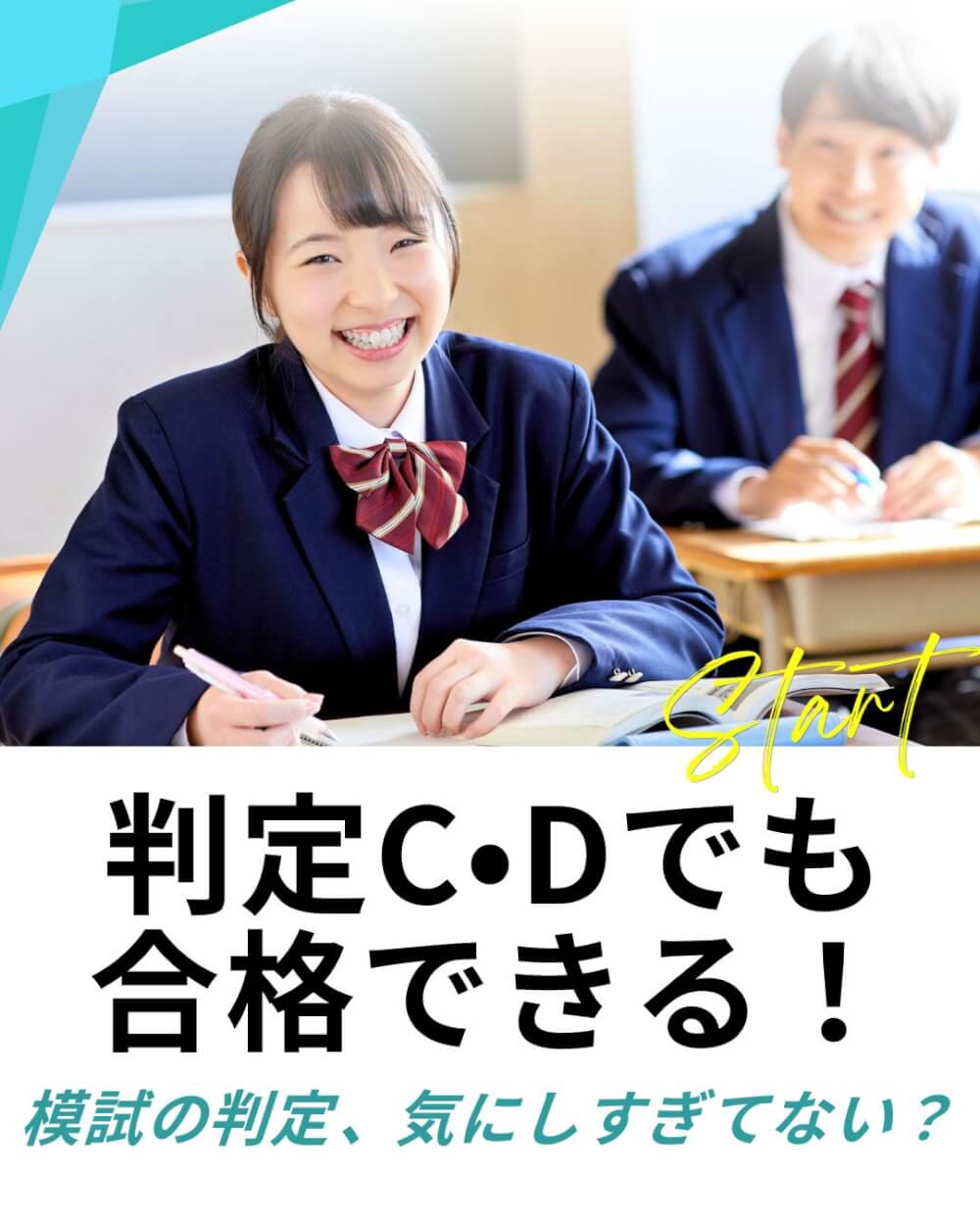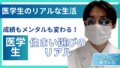模試の判定が思うように上がらず、自信をなくしてしまう――。多くの受験生が必ず一度はぶつかる壁です。努力しているのに偏差値が伸びない、自分だけ取り残されているように感じる…。しかし、判定という数字は“今この瞬間の一部”を切り取った指標に過ぎず、あなたの未来や可能性を決めるものではありません。今回は、判定に振り回されず、成長を積み上げ続けるための考え方と戦略をご紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
自信が揺らぐ瞬間—判定が与える心理的影響
模試でC判定・D判定が続くと、「自分には才能がないのでは?」という不安が頭を支配し、勉強の意欲までも削られてしまいます。判定は“今のあなた”を映し出す鏡のようなものだからこそ、数字が低いと自分の価値まで否定された気持ちになるのです。
しかし理解しておきたいのは、判定は「実力のすべて」ではないということ。
あくまで一時点を切り取ったスナップショットにすぎず、未来を左右する決定打ではありません。
とはいえ、頭では理解していても、感情は簡単には切り替わりません。努力と結果が比例してほしいと願う人間の心理が、自信喪失を引き起こしてしまうのです。
自信喪失が起きる「心理メカニズム」
● 自己効力感の低下
「自分はやればできる」という感覚が弱まると、行動の質が下がり、勉強の成果が得られにくくなります。
● ラベリング効果
「自分はC判定の人間だ」と決めつけてしまうことで、成長の芽を自分で摘んでしまう危険があります。
● 比較思考によるダメージ
SNSや友人のA判定を見ると、自分の努力が無価値に思えてしまいます。しかし成長スピードは人それぞれ。波があるのが普通です。
判定が上がらない本当の理由
判定が伸びない理由は“勉強量が足りない”だけではありません。
① 勉強の方向性がズレている
- インプットばかりで演習不足
- 基礎が弱いまま応用へ進んでいる
- 知識が整理されておらず引き出せない
量より「質」を見直すべきタイミングです。
② 判定にはタイムラグがある
基礎固めや応用力の育成期は“地下で根を張る期間”。
表面的な点数は伸びなくても、内部では力が育っています。
③ 模試の条件に左右されている
- 出題の癖
- 範囲の相性
- 形式の慣れ
判定は絶対評価ではなく「条件つきの相対評価」でしかありません。
判定に振り回される危険性
悪い判定を見ると、つい勉強法を大きく変えたくなります。しかし焦って方法を変えると、一貫性が失われ、かえって成績が下がることも。
● 危険な行動
- 勢いで教材を総入れ替えしてしまう
- 判定だけで志望校を下げる
- 判定=自分の価値と勘違いする
どれも「未来の成長」を自ら閉ざしてしまう行為です。
判定を超える“成長指標”を持とう
模試の数字は、あなたの成長のすべてを表しません。そこで重要なのが「自分だけの成長指標」を設定すること。
◆ 例:毎週記録する成長ポイント
- 英単語の正答率が10%アップ
- 数学の大問が時間内に解けた
- 苦手テーマの問題が2回目で解けた
- 記述で根拠を明確に書けた
これらは判定には見えませんが、確実に“合格力”につながる成長です。
合格力を積み上げる3ステップ
判定に依存せず、内側の力を育てるための流れを3つに整理します。
① 基礎の底上げ期(足場づくり)
偏差値が停滞するときの多くは「基礎の抜け」が原因。
英語は文法を2周、数学は教科書レベルを徹底——遠回りに見えて最短ルートです。
② 実戦演習期(得点技術の習得)
知識だけでは点は取れません。
時間配分・順番の組み立て・見直しの習慣など“得点技術”を磨く時期です。
③ 本番想定期(応用力・対応力の強化)
未知の問題に対する柔軟性、緊張下での思考力、時間内の戦略構築など、本番で求められる総合力を鍛える段階です。
自信を取り戻すための思考法
✔ 過去の自分と比較する「成長思考」
- 偏差値50 → 55になっている
- C判定 → B判定に上がった
- 前より解ける問題が増えた
小さな成長を拾う習慣をつけましょう。
✔ 志望理由を紙に書き出す
数字では測れない「自分の原点」を確認することで、モチベーションが内側から湧いてきます。
判定は未来の可能性を決めない
多くの合格者が夏までC判定・D判定だったというのは珍しくありません。
彼らが合格できたのは「数字以外の成長」を信じ続けたからです。
判定が上がらない時期こそ、“根を張る期間”。
地中で根が伸びている植物のように、見えないところで力が育っています。
まとめ
「判定が上がらない」「自信が折れそう」――これは受験生なら必ず通る道です。しかし、判定は未来を決めるものではなく、あなたの価値も決めません。
- 判定に振り回されず
- 自分の成長指標を持ち
- 基礎→得点力→本番力のステップを積み重ね
- 過程を大切にする
数字が停滞する時期こそ、本質的な力が育っています。
あなたの物語の結末は、判定ではなく“これからの行動”が決めるのです。