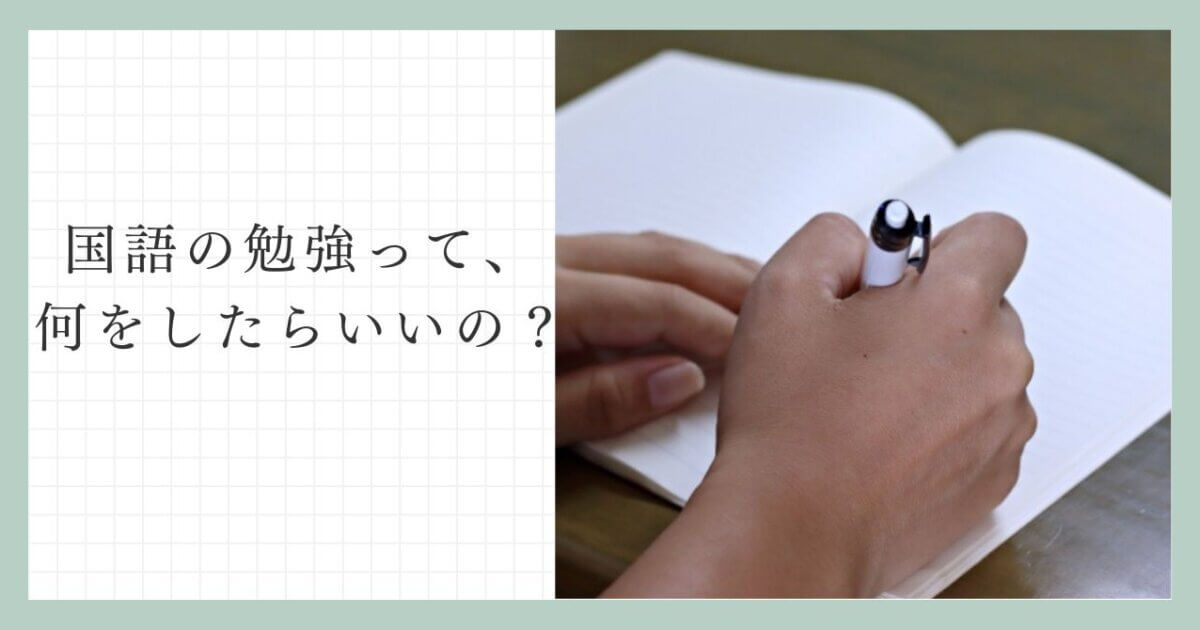学校の定期テストって、問題集や授業プリントをなんとなく見直して終わり…になりがちですよね。
でも、現代文や古典は「やった分だけ点が伸びる勉強法」がきちんとあります。
ここでは、
- ① 現代文のテスト対策(4ステップ)
- ② 古典のテスト対策(考え方と優先順位)
に分けて整理しておきます。
「何を、どの順番でやればいいのか」をはっきりさせてから取り組んでみてください。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
現代文の勉強法(学校のテスト対策)
1-1 まずは「漢字・語句の意味」をチェックする
一番最初にやるのは、語句と漢字の確認です。
テスト範囲になっている本文を読みながら、
- 意味があやしい語句にチェックを入れる
- 意味を辞書やプリントで確認する
- できれば「漢字で書けるか」までセットで覚える
という流れで進めてください。
授業で「語句の意味調べプリント」が配られているなら、それはテスト対策用のヒント集です。
少なくともそのプリントに載っている語句は、
- 意味
- 使い方(どんな文脈で使われるか)
まで押さえておきましょう。
このとき、難しすぎる漢字に振り回されないことも大事です。
たとえば、芥川龍之介『羅生門』に出てくる「蟋蟀(こおろぎ)」のような漢字は、定期テストではまず書かされません。
基本的には、常用漢字レベルをしっかり固める、これで十分です。
1-2 本文の「大事な箇所」に線を引く
次にやるのは、本文の流れをつかむ作業です。
授業で「フローチャート(流れ図)を書きましょう」と言われたことがあるかもしれませんが、これはとても有効な勉強法です。
やり方自体はシンプルで、
本文の大事なところに線を引いていく
だけです。
評論文の場合のポイント
評論文では、次のような接続語の直後がポイントになることが多いです。
- 「つまり」
- 「すなわち」
- 「しかし」
- 「そして」
これらのあとに続く文は、
「筆者の主張」や「話のまとめ」になっていることが多いので、意識して線を引いてみてください。
小説文の場合のポイント
小説文では、**5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように)**を意識しながら、
- 登場人物の感情の変化
- 行動のきっかけとなった出来事
に線を引いていきます。
理想を言えば、
自分で線を引いた部分を読み返すだけで、
本文のおおまかな内容が思い出せる
という状態にしておくのがベストです。
※教科書に直接たくさん線を引いてしまうと、テスト前に「何が大事かわからないページ」になりがちです。
本文をコピーするなどして、そのコピーに書き込みをするのがオススメです。
1-3 自分で「予想問題」を作ってみる
一歩レベルを上げて、テスト範囲の本文を使って自分で予想問題を作るのも非常に有効です。
問題だけでなく、模範解答も自分で作ります。
ここで作るのは**読解問題(記述)**です。
避けた方がいいもの
- 選択肢問題(マーク問題)
選択肢問題は、一見簡単そうですが、
- 誤った選択肢(ひっかけ)の作り方
- 選択肢同士のバランス
などを理解していないと、レベルの低い問題になりやすいです。
そのため、自作問題としてはオススメしません。
おすすめは「傍線部◯◯とはどういうことか」問題
シンプルに、記述式の説明問題だけを作りましょう。
- 「傍線部◯◯とはどういうことか。」
という形の問題で十分です。
理由説明問題(「なぜ◯◯と筆者は言っているのか」など)もありますが、こちらは意外と難しく、最初から取り組むと挫折しやすいです。
まずは「どういうことか」問題に慣れてから挑戦するのがよいでしょう。
「傍線部◯◯とはどういうことか」とは、言い換えると、
◯◯の内容を、より詳しく説明しなさい
という意味です。
そのため、
- 「つまり」「すなわち」などの直後に出てくる、短くまとまった言い回し
に傍線を引いて問題にすると作りやすくなります。
解答の作り方
模範解答は、次の手順で作ります。
- 本文の中から、使えそうな部分をそのまま抜き出す
- 必要に応じて、抜き出した文同士をつなぐ
- 指示語(「それ」「このこと」など)があれば、何を指しているのか本文から探し出して補う
- 必要であれば、
- 理由
- 原因
- 対比
- 最後に自分で読み直し、
- 文章がつながっているか
- 意味が通るか
たとえ最初は「模範解答っぽくないな…」と思っても大丈夫です。
この作業自体が、
- 本文の読み取り
- 要点の整理
- 日本語で説明する力
をバランスよく鍛えてくれるので、確実に国語力アップにつながっています。
1-4 問題集で演習して「読解力の底上げ」をする
学校のテスト範囲とは直接関係しないことも多いですが、
市販の問題集で読解力を鍛えておくことも、長期的には大きなプラスになります。
特に、記述問題の解答の作り方が詳しく解説されている問題集は、先ほどの「予想問題作り」にも役立ちます。
例:おすすめの一冊
- 『記述の手順がわかって書ける!現代文記述問題の解き方―「二つの図式」と「四つの定理」』(河合塾シリーズ)
記述問題を、
- どう整理して読むか
- どう構成して書くか
という「手順」が丁寧に解説されています。
これを一冊やり込むだけでも、「なんとなく書く」状態から「狙って点を取りにいく」状態に近づけるはずです。
古典の勉強法(学校のテスト対策)
古典については、古文でも漢文でも、基本的な勉強の柱は同じです。
本文を、きちんと現代語に訳せるようになること。
これが最優先事項です。
もちろん、
- 古文:品詞分解ができている(特に用言・助動詞)
- 漢文:返り点・送り仮名を踏まえて、書き下し文にできる
ことはセットになります。
2-1 まずは「文法」「単語」を最優先
古典は、多くの受験生にとってはほぼ外国語です。
立ち位置としては、英語と同じと考えてください。
つまり、最初にやるべきことは、
- 単語を覚える
- 文法事項を押さえる
という、語学の基本作業になります。
古文で優先すべきもの
- 用言(動詞・形容詞など)の活用
- 助動詞の意味・接続・活用形
- 超重要古文単語(頻出語)
これらをまず押さえてから本文に取り組むと、
「何となくフィーリングで読む」状態から抜け出しやすくなります。
「英語よりラク」なポイント
英語に比べると、
- 覚えるべき単語数
- 文法事項の量
はかなり少なめです。
文法書の厚さや、単語帳の収録語数を比べてみると、違いは一目瞭然です。
2-2 本文訳を「自力で最後まで通せるか」が勝負
古典のテスト対策として一番効くのは、
テスト範囲の本文を、自分の力で最後まで現代語訳できるようにしておくこと
です。
そのために、次のようなステップで進めます。
- 文法書や授業ノートを見ながら、まずは丁寧に品詞分解・書き下しをする
- 一文ずつ現代語訳をつくり、意味を確認する
- 何度か繰り返し訳して、ノートを見なくても訳せるかをチェック
- 最終的には、本文を読んだときに「内容の流れ」が頭の中でスッとたどれる状態にする
古典は、しっかり時間をかければ、比較的点に結びつきやすい科目です。
英語や数学ほど、膨大な知識や問題数を必要としません。
だからこそ、
- 「古典は苦手だから…」と最初からあきらめない
- 単語・文法にしっかり時間を投資する
これだけで、周りとの差を一気に縮めることができます。
最後に
現代文も古典も、
- なんとなく問題を解く
- とりあえず解答解説だけ読む
といった勉強では、なかなか点数が安定しません。
- 語句・漢字の確認
- 本文に線を引いて構造をつかむ
- 自分で予想問題+模範解答を作る
- 古典は「単語・文法 → 本文訳」の順に攻める
という具体的なステップに分けて取り組むことで、テスト勉強が「作業」から「実力アップのトレーニング」に変わります。
この流れで一度テスト勉強をやり切ってみて、
「どこでつまずいたか」「どこまでならできたか」を一緒に振り返っていけば、次回のテストではさらに精度を上げていけますよ。