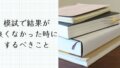「理系に憧れるけれど数学が不安」「安定を勧める親と、表現の道に惹かれる自分」「学部の違いがよく分からない」――進路に悩む高校生は多いものです。
進路の悩みは“情報不足”だけでなく、“決め方の設計不足”からも生まれます。考えるほど選択肢が増えて決められない…そんな状態を抜け出すには、「自分らしさ」「現実条件」「試し方」の3軸で組み立てる視点が有効です。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
悩みの正体は「自分・情報・決定」の渋滞
進路で悩むとき、心の中では3つの渋滞が起きています。
それは、「価値観のもつれ」「情報の過多」「決定への不安」。
他人の物差しに影響されて自分の軸が見えなくなったり、情報が多すぎて比較ばかりになったり。
「一度決めたら戻れない」という思い込みも、不安を大きくしてしまいます。
でも実際には、進路は分岐と合流の連続。大学でも社会でも“やり直せる道”は開かれています。
「興味・得意・価値」の3つで自分の軸を立てる
最初に大切なのは、「興味」「得意」「価値」を重ねること。
- 興味:やってみたいと心が動く対象
- 得意:努力が結果につながりやすいこと
- 価値:達成したときに満足を感じること
この3つが交わるほど、日々の学びや仕事に手応えを感じやすくなります。
興味は移り変わっても、「何をしているときに楽しいか」という“行為の型”で考えると、軸がぶれにくくなります。
情報は「軸 → 要件 → 候補」の順で整理する
情報収集のコツは、いきなり大学を探さないこと。
まず自分の軸を決めてから、「立地・費用・カリキュラム」など要件を3つ前後に絞り、そこから候補を探します。
順番を守るだけで、検索迷子から抜け出せます。
また、学部と職業の関係は“一本道”ではなく“多対多”。同じ学部から多様な職業へ進む道もあれば、同じ職業へ複数の学部から進む道もあります。学部は扉の鍵ではなく、扉の入り口の一つです。
「安い実験」で仮説を試してみよう
進路は、頭で考えるだけでは決まりません。
オープンキャンパスで気になる研究を一つ選び、質問を3つ用意して行ってみる。
大学のシラバスや研究室ページを見て興味が湧くテーマを探す。
小さな行動を重ねることが、自分の仮説を確かめる一番の近道です。
“二路線プラン”として、第一候補と第二候補を同時に育てるのもおすすめです。
家族との対話は「事実→感想→希望→相談」の順で
家族や先生と話すときは、感情よりも行動の線で共有しましょう。
「この2週間でこう調べた」「こう感じた」「こうしたい」「この点を相談したい」——この順で1分話すと、建設的な会話になります。
また、候補ごとに「満たし度」を三段階でメモし、違和感も書き添えると、後の見直しがスムーズです。
決め方は「冷却期間」を置いてから
情報収集・比較・仮決定の締切を別に設け、仮決定から一週間は“冷却期間”にします。
冷却のあとに再確認して最終決定するだけで、考えすぎによる疲れが減ります。
そして、選ばなかった道に小さく触れてみることも大切。
第二候補の本を一章だけ読む、関連イベントに一回だけ参加する——そんな“あえての小さな後悔”が、心を整理してくれます。
進路は「つくりながら選ぶ」もの
最初から正解を当てようとしなくて大丈夫。
進路は、つくりながら選ぶプロセスです。
今日できる一歩は、興味・得意・価値を一行ずつ書き出してみること。
そして、気になる学部のシラバスを読み、来週に一つ“小さな実験”をカレンダーに入れてみましょう。
焦らず、止まらず、進路を“自分の手で設計する”ことが、何よりの正解です。