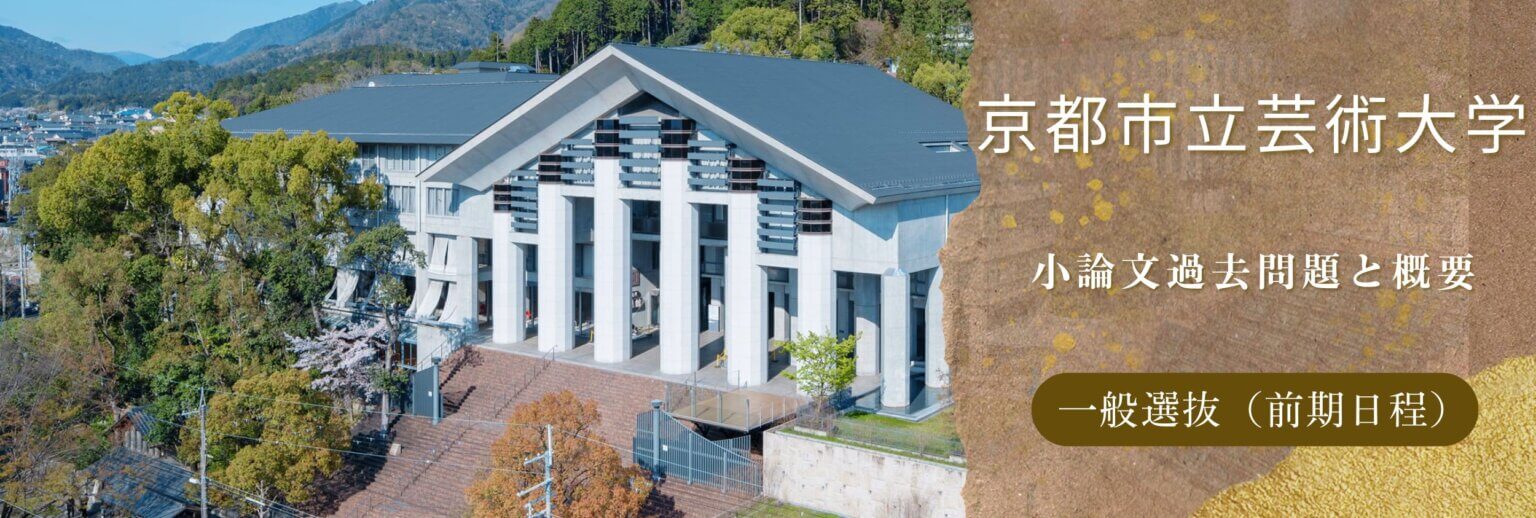記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文過去問題
R6年度 美術学部 総合芸術学科 一般選抜(前期日程)
別紙の問題文は、藤幡正樹(一九五六~)による著書『不完全な現実デジタル・メディアの経験』
の第一章「不完全さのリアリティ」第一節「不完全さの克服」という文章である。藤幡正樹は八〇年代初頭より活動を開始し、コンピュータグラフィックス、アニメーション、コンピュータを使った彫
刻、デジタル・メディアを用いたインタラクティブな作品を発表しているアーティストです。この文章
を読んで、以下の設問に答えなさい。
※本文省略
【出典】藤幡正樹『不完全な現実デジタル・メディアの経験』(NTT出版、二〇〇九年)一五頁|二二頁
設問一 この文章を三〇〇文字以内で要約してください。
設問二 著者は、視覚メディアが現実感に与える影響について論じています。この考え方にあてはまる
具体的な事例を、あなたの日常生活の経験から提示し、簡潔に説明してください。
設問三 文章中の「不完全な現実」というキーワードに対してあなたの興味を持ったところを述べ、そ
こから芸術をはじめとする創造行為や鑑賞行為に対するあなたの考えをのべなさい。
出題意図・評価のポイント
出題意図
この文章は、人間の知覚が捉える現実の不完全さと、その不完全さをメディアと芸術を介して考察する観点を示しています。この文章を本学の総合芸術学科の小論文入試の問題文として取り扱う意図は、情報技術が私達の身をとりまく社会基盤となった現代において、芸術を考える上で切っても切れなくなったデジタルメディアと人間の知覚知の関係性を考察する力を問うことにあります。
この論考は、視覚メディアが私たちの現実認識にどのように影響を与えているかを考察しており、これはメディアアートや現代美術のみならず、あらゆる芸術様式を理解する上で重要な視点を提供しています。この視点を通じて、受験者が批判的思考能力および、多角的な視点から芸術を考える能力を有しているかを評価することができます。
評価のポイント
設問1
他者の書いた文章を読んでその内容を的確に理解する文章読解力、ならびにその内容を要約として提示する言語表現能力があるかどうかを評価しました。
設問2
問題文の内容をどの程度理解し、関連する芸術分野の知識を持ち合わせているか、そしてそれらを批判的に考察できるかを評価しました。
設問3
文章の内容を自身の知識や経験に基づいて発展的に応用し、自身の興味関心と照らし合わせて論理的に表現できるかを評価しました。
総合芸術学科では、広く様々な芸術作品や創作活動、あるいは美術教育や社会における美術の在り方などについて学ぶことになります。芸術や創造行為自体が、世の中の極めて多様で広範な事象を対象にするものですから、必然的に、総合芸術学で視野に入れ、考えるべき事柄も多岐にわたります。まずは普段から、興味の対象を狭く限定せず、色々な作品や文章に触れる経験を積み重ねてもらいたいと思います。
また、今回の小論文の設問でもはかっているように、他者の考えを的確に理解し、与えられた前提にのっとって、その上に自らの論理を構築していく力も必要です。要約に際しては、問題文からの文字通りの引き写しだけでは、制限文字数内で文章の趣旨をまとめられないこともありますので、自身の言葉でまとめ直すことも大切です。
2問目3問目の設問では、どのような文章や設問が出てもこの具体例を書こうと決めてきたかのような文章もありましたが、本学の試験ではそういった回答は求めていません。先にも述べたように、豊富な知識や経験を蓄えることは大切ですが、他人の制作物である芸術作品を学ぶ専攻であるからこそ、まずは他者の考え(小論文問題の場合は文章の趣旨)に寄り添ってその内容を正しく理解し、そのうえで適切な例を選びつつ、自身の考えを他人に伝わるように具体的に論じるという手順を大切にしてみて下さい。
学部学科、コース
美術学部
1年次前期に総合基礎実技を設け、造形活動全般の基礎的思考および実技を総合的に体験。その後、各科別または専攻別基礎実技を行い、専攻を選ぶ。
美術科は5専攻制。制作を通して個性の伸長を図り、創造性を養う。日本画専攻には、古画鑑賞と技法を学ぶ教室がある。油画専攻では、油彩をはじめとする技法を学びつつ、複合的な絵画表現を追究する。彫刻専攻では、さまざまな事象を独自の視点でとらえる。版画専攻では、複製メディアの可能性を探究する。構想設計専攻では、メディア表現も含めて実験・制作を行う。
デザイン科は2専攻制。総合デザイン専攻では、幅広いデザイン領域の技法や技術を修得する。デザインB専攻では先端的・実験的に新たな価値を創造する。
工芸科は3専攻制。陶磁器専攻では、素材・技法・焼成を研究し、創作活動を行う。漆工専攻では、漆・木・その他の素材を対象に、漆芸の諸技法を学ぶ。染織専攻では、型染・ろう染・織物の技法・材料を研究し、制作する。
総合芸術学科では、美術史・造形芸術を考察するための基礎となる芸術理論の教育・研究を行う。
音楽学部
音楽学科では、1年次から7専攻に分かれ、個性を尊重し創造性を育む専門的な音楽芸術の教育研究により、幅広い教養を併せ持つ優れた音楽家や研究者となり得る人材を育成する。
教育内容は、講義・演習・実技に分かれる。講義・演習では、音楽理論関係、音楽学関係の科目などを開講し、実技では教員との1対1の個人レッスンを中心とした専攻および副科の実習と、合唱・管弦楽・オペラ・各種室内楽など、集団教育を中心とした実習を行っている。
作曲専攻では音楽作品の実作を行う。指揮専攻では、指揮者として必要な学習と研究を行う。ピアノ専攻では、独奏を中心に、ピアノ重奏、他楽器の伴奏、室内楽などを実習として行う。弦楽専攻および管・打楽専攻では、実技レッスンに重点を置き、独奏を中心に、合奏、室内楽、オーケストラ、吹奏楽を実習として行う。声楽専攻では歌唱実技の個人レッスンを中心に重唱やオペラを実習として行う。音楽学専攻では、音楽文化のグローバル化に対応できる人材育成を目指す。
所在地・アクセス
京都市立芸術大学のHPはこちら
入試情報はこちら
| 京都府京都市下京区下之町57の1 | JR各線・近鉄京都線・地下鉄烏丸線 「京都」駅下車、徒歩6分 京阪電車「七条」駅下車、徒歩7分 |