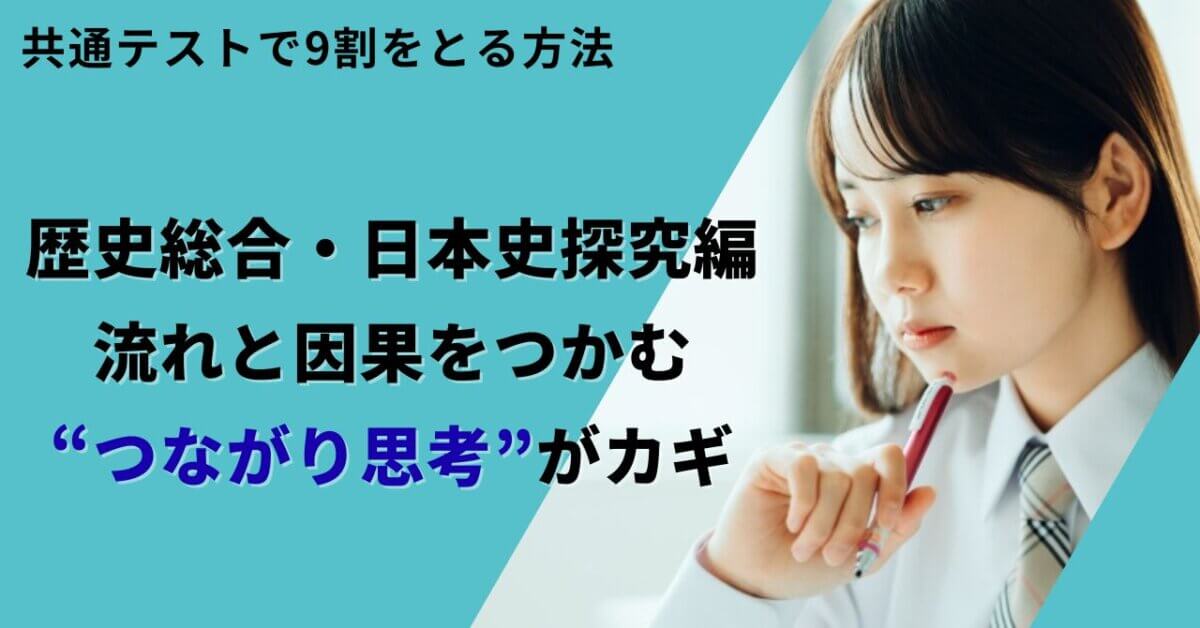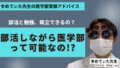単なる暗記から「思考科目」へと進化した日本史
かつてのセンター試験時代、日本史は「年号と用語の暗記ゲー」と揶揄されるほど、知識偏重の科目だった。しかし、共通テストではその姿が大きく変わった。出題の中心は「歴史総合+日本史探究」にまたがるテーマ型の複合問題。図表や資料を読み解きながら、歴史的な因果関係を捉える力、複数の史料を比較して真偽や立場を読み取る読解力が問われるようになっている。
つまり、求められるのは「知識を軸にした思考力」。単なる暗記では太刀打ちできないが、逆に言えば、知識を「つなげる」視点を持ち、流れと背景を理解していれば、確実に高得点が狙える科目でもある。
この記事では、歴史総合・日本史探究で共通テスト9割を取るための実践的な戦略を、「出題傾向の分析」「分野別対策」「本番対応力の養成」という3つの軸から丁寧に解説していく。資料問題への慣れや、用語を“意味ごと”覚えるための方法論も紹介するので、暗記が苦手な人もぜひ最後まで読んでほしい。
次章では、まず全体の出題傾向と戦略的な学習計画について解説する。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:歴史総合+日本史探究の出題傾向と学習戦略
出題形式の変化
共通テストの日本史は、「単独の出来事や年号を問う」スタイルから、「複数の史料や出来事を組み合わせて理解を問う」形式へと変化。
特に「歴史総合」と「日本史探究」を組み合わせた問題では、時代をまたいだ比較、思想や制度の変遷、国際関係との関連性などが問われる。
資料問題とテーマ史的出題の特徴
- 資料には多様な視点があり、「誰が、どの立場から書いたか」や「根拠となる事実の特定」が求められる。
- 「都市と流通」「民衆運動と国家の対応」など、テーマに沿った時代横断型の設問が出題される。
有効な学習戦略
- 【1】教科書・資料集の「流れ重視」精読
用語の暗記ではなく因果関係の理解を重視。図説・コラムも活用。 - 【2】年表と地図を使った「横断理解」
年表・地図で時系列や地域的関係性を整理し、変化の全体像を把握。 - 【3】史料問題対策
「誰が・何の目的で」書いたかに着目。原文やくずし字にも慣れておく。 - 【4】問い方への対応演習
設問文の長さや複雑さに慣れ、正解に必要な情報を見抜く練習を継続。
第2章:頻出テーマ別攻略法と“背景理解”のコツ
【1】開国と近代化:因果と対比の構造に注目
- 開国による外交変化、制度改革、欧米との比較視点がよく問われる。
- 江戸→明治への変化と、欧米制度との違いに焦点を当てる。
【2】民衆運動と国家:資料とのリンクに注意
- 自由民権運動・農民運動などが定番。一次資料と背景・目的・対応をセットで学習。
- 例:「秩父事件=農民の抗議→政府の弾圧」など因果で整理。
【3】戦後復興と高度経済成長:経済史はグラフ・資料付きで
- 実質GNP・工業出荷額などの資料を読み解く設問が頻出。
- 「なぜその変化が起こったか」を問う練習が重要。
【4】外交と国際関係:多角的視点で考察する
- 日清・日露・大東亜共栄圏など。日本・国際社会それぞれの立場に注目。
- 「誰にとってどういう意味を持ったか」を意識した思考が鍵。
【5】社会変化と文化:生活史・民俗学的資料に注意
- 庶民生活・女性の地位・教育の変遷などが出題。
- 統計資料やアンケートを読解・推察する力が必要。
第3章:実戦演習と試験対応力の養成
【1】過去問・予想問題の活用法
- 「解いた後の分析」が重要。資料から情報をどう引き出したかを自己分析。
【2】選択肢処理力を磨く
- 「明確な誤り」ではなく「微妙な誤り」に注意。
- 「どこが間違っているか」を見抜く練習を重ねる。
【3】資料問題の“構造”に慣れる
- 複合資料は「視点」「主張」「相互の整合性」を見抜くことが重要。
- 凡例・注釈・引用元を素早く把握し、メモ習慣をつける。
【4】設問パターンを覚える
- 「資料AとBをふまえて」「当てはまらないものを選べ」など、問いのパターンを分類して練習。
【5】時間配分とマーク精度の管理
- 資料・設問が長いため、配分シミュレーションが不可欠。
- 「悩んだら仮マーク→後回し」の判断力を練習段階から養う。
まとめ:思考の軸を持ち、知識を“つなげる”ことで得点力は劇的に伸びる
- 暗記ではなく、背景理解・因果関係・設問構造の読解が求められる。
- 「なぜ起きたか」「何が変わったか」を問い続けながら学習を進める姿勢が重要。
- 学習戦略・テーマ別深掘り・実戦演習の3本柱で、9割得点は十分に実現可能。
- 最終的には「自分の中の歴史の軸」を持つこと。それが思考力を深め、得点力に直結する。
- 地道な理解と思考の積み重ねが、本番で大きく花開く。