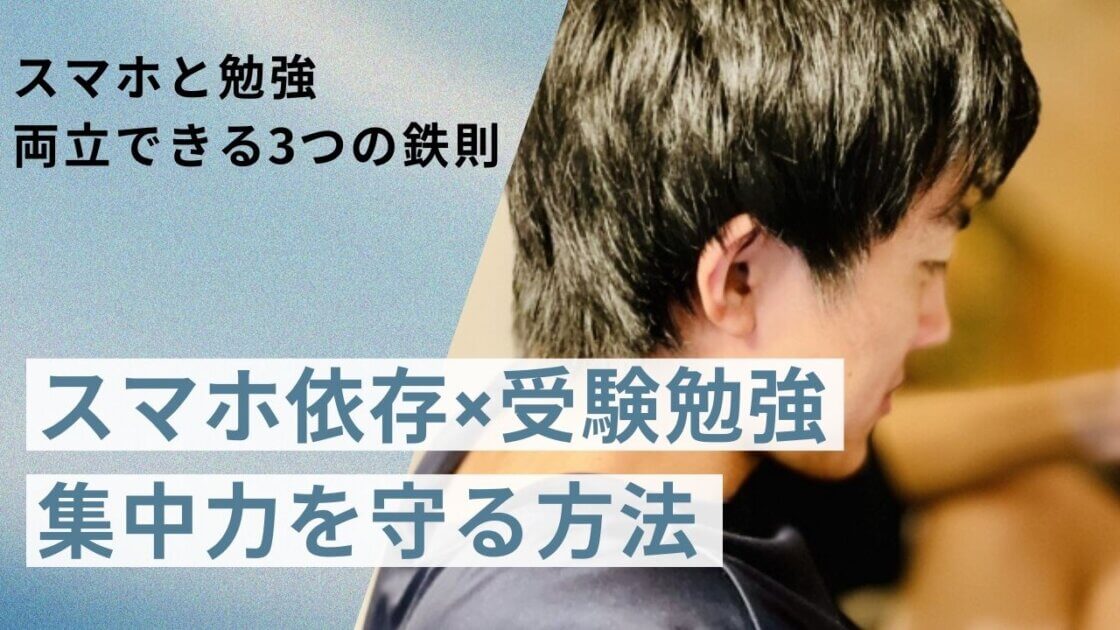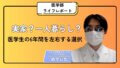「英単語を3分やるつもりが、通知一発で20分消えた」――これは多くの受験生が経験している現実です。スマホは便利な道具である一方で、勉強や集中をそっと蝕む存在でもあります。科学的な研究からも、その影響は無視できないと示されています。今回は「スマホ依存と受験勉強」というテーマで、集中力を奪う仕組みと、具体的な回避法をわかりやすく整理してみました。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
スマホが集中力を奪うメカニズム
スマホは“触っていなくても”近くにあるだけで脳の余力を削る、と実験で示されています。机の上・ポケット・別室と比較すると、離すほど推論や記憶のパフォーマンスが上がりました。いわゆる「Brain Drain(脳のしずく抜け)」仮説です。
さらに、通知音やバイブレーションは無意識に注意を奪い、作業を中断させます。数式や長文読解で途中の筋を見失うのも、この“横やり効果”が原因です。
通知ゼロは逆効果?
通知を完全に遮断すると、不安が増して逆に何度も確認する人もいます。実験では「通知を一日3回にまとめて受ける」方法が、ストレス低下や集中改善につながると報告されました。現実解としては、“時間帯ごとのまとめ受信”が取り入れやすいでしょう。
学校での方針と効果
イギリスの学校では、携帯禁止の導入後に成績が改善した例が報告されています。特に下位層の伸びが大きいのが特徴です。ただし、禁止だけで万事解決とは限りません。授業設計や活用ルールと合わせて考えることが大切です。
夜のスマホと睡眠
就寝前の強い光やスマホ使用は、眠気を促すメラトニンを抑え、入眠を遅らせます。受験期は「寝る前1時間は暗く・静かに」を合言葉に、紙媒体に切り替えるのが効果的です。翌朝の覚醒や集中も安定します。
マルチタスクと学習の質
SNSや動画を勉強と並行して使うと、理解や記憶の質が落ちやすいことがわかっています。特に学習と無関係のマルチタスクは負の影響が強いのです。辞書アプリなど“学習関連の利用”は必ずしも悪ではないため、科目ごとに「スマホを使う場面」を決めておくと安心です。
実践できる工夫
- ハード面:学習中はスマホを視界外、できれば別室へ。机の引き出しより“二歩以上離す”ことが効果的です。
- ソフト面:iPhoneやAndroidの「集中モード」「フォーカスモード」を使い、SNSなどをブロック。就寝前はグレースケール表示で刺激を減らしましょう。
- 行動面:「If–Thenプラン(実行意図)」を活用し、「もしタイマーを押したら、スマホを廊下に置く」と行動を固定すると続きやすくなります。
- モチベーション面:“誘惑バンドル”で勉強後に小さなご褒美を組み合わせましょう。
最後に
スマホは敵ではありません。ただし「近い・鳴る・夜に明るい」の三拍子が揃うと、集中と睡眠を大きく乱します。だからこそ、
- 学習中は視界外に置く
- 通知はまとめ受信
- 就寝前は光を減らす
この3点を基本に運用しましょう。さらに、実行意図と小さなご褒美を組み合わせれば、受験期でもスマホと賢く付き合えるはずです。