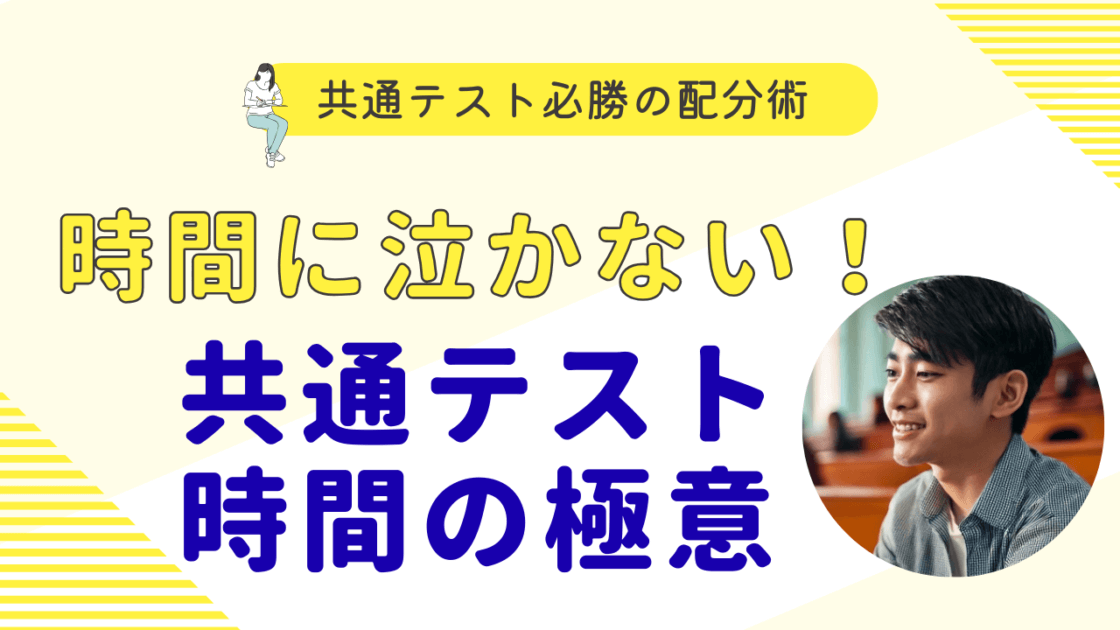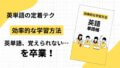共通テストでは、時間配分の失敗が得点に直結することがあります。国語で大問一つに粘りすぎたり、英語リーディングで長文に時間を取られたり、数学で計算の重い問題に固執したりするケースは珍しくありません。本記事では、時間配分でつまずく原因を押さえつつ、科目ごとに具体的な配分設計と本番運用のコツを紹介します。計画的に取り組むことで、落ち着いて解答できるようになります。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
出発点:速さと正確さのバランス
まず押さえておきたいのは「速さと正確さのトレードオフ」です。
- 速く解こうとすると誤答が増える
- 慎重に解くと未着手が増える
意思決定研究では、この関係を調整することで単位時間あたりの得点(報酬率)を高められると報告されています。問題ごとの「かけられる上限時間」を意識して配分を決めることが重要です。また、短い小休止(マイクロブレイク)を設けると、集中力の維持に役立ちます。
配分設計:科目別の戦略
英語リーディング
- 資料・図表・長文が混在
- 最初の3分で全体像を把握し、情報検索型問題を先に解く
- 推論中心の長文は後半に配置
国語
- 配点と読解負荷のバランスを重視
- 根拠が拾いやすい設問から解く
- 大問ごとの構造把握が必要な場合は精読を優先
数学
- 「トライアージ三層」で配分
- 道筋が立つ問題
- 処理量がある問題
- 方針が立たない問題
- ①→②→③の順で取り組み、見直し時間を3〜5分確保
本番運用のポイント
- 最初の1〜2分で「全体設計」を行う
- 解答順序を「成果の早取り→粘る→見直し」に固定
- 読解モードを切り替え、精読・スキミングを使い分け
- 微小休止(深呼吸や肩回し)で集中力を維持
- マークシートの転記やチェック方法も事前に決めておく
練習の工夫
- 高速演習(標準時間の8〜9割)で速度域を拡張
- 精度優先演習(標準時間の1.2倍)で手順を確認
- プレテストや事前仮説で集中の質を高める
- 「もし〜なら、〜する」という実行意図を設定し、迷った際に行動を切り替える
まとめ
時間配分の失敗は、実力不足だけでなく設計の問題でも起こります。
- 公式の時間枠と出題構造を把握
- 「速さと正確さ」「読みのモード切替」「三層トライアージ」「見直し予約」の四本柱で配分表を作成
- 模試で微調整し、本番は全体設計→成果の早取り→粘る→見直しの順路を固定
- 微小休止を活用して集中力を維持
個々の得手不得手に応じて最適解は異なります。演習のたびに計測と改善を繰り返すことで、当日の落ち着きと得点につながります。今日からの一回一回の練習が、本番の自信につながるのです。