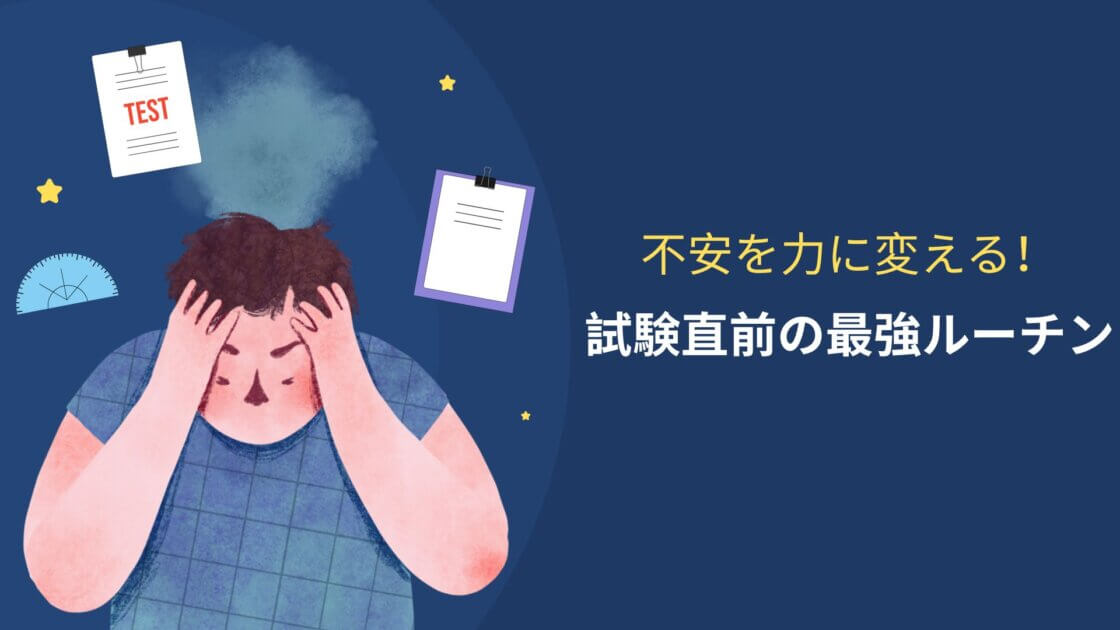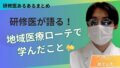受験本番が迫ると、多くの生徒が同じ悩みを抱えます。
「眠れない」「頭の中が不安でいっぱい」「直前にやるべきことが分からない」──。
これは特別なことではなく、誰もが通る道です。大事なのは、この不安をどう扱うか。
不安は決して消すものではなく、向き合い方を変えるだけで「エネルギー」に変わります。
今日は塾長の立場から、直前期をどう過ごせばいいのかをお伝えします。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
不安の正体
試験の直前には小さなトラブルがつきものです。
模試の判定が振るわず胸がざわつく、前夜に心拍が上がって眠気が遠のく、過去問の失敗が頭から離れない──こうした反応は多くの受験生に共通し、決してめずらしい現象ではありません。
心理学では、不安が注意の配分を乱し、刺激に引きずられて目標への集中が落ちると説明されます。この枠組みは「注意制御理論」と呼ばれ、緊張下での処理効率低下やミス増加を説明してきました。理屈が分かれば「自分だけがおかしい」と思わなくて済みますし、まず仕組みを知ることが出発点です。
とはいえ、不安があるからこそ身体は動きます。不安を「邪魔な敵」と決めつけず、「戦うための燃料」と再解釈するだけで成績指標が改善した研究もあります。GRE実験では、動悸や手汗を“役に立つ準備反応”だと伝えられた群が、実際の得点で有利だったと報告されました。
また、直前期のモヤモヤは「頭の中の渋滞」と表現できます。心配事をいったん外に書き出すエクスプレッシブ・ライティングは、思考のループを緩め、試験場面の不安や自己監視を下げる効果が示されています。ただし書き方や対象者で効果の差が出ることもあるため、前々日までに10分・非評価・提出なしの安全な条件で行うのがよいでしょう。
さらに、マインドフルネスは思考の暴走に巻き込まれにくくする練習です。短期プログラムでも不安低減が示されており、直前期は“短時間・毎日・同じ手順”で慣らすのが現実的です。
睡眠は「最後の伸び」を支える土台です。専門学会は13〜18歳に「8〜10時間」の睡眠を推奨しています。カフェインの摂取は就寝6時間前までに控えると安全です。直前期は勉強を詰め込みたくなりますが、睡眠後の記憶固定(コンソリデーション)効果を活かすため、眠りと覚醒のリズムを守ることが重要です。
備えの設計
直前期の不安に当日だけで立ち向かうのは荷が重いです。
二〜三週間単位で小さな習慣を積みましょう。
まず「進捗の見える化」です。日ごとに演習セット数・見直し回数・就床時刻をチェックボックスで可視化すると、焦燥の正体が“未完了タスクの数”として分かります。模試やテストの返却では「振り返り用シート」を使い、ミスの発生源を型で分類して次回作戦に直結させます。
次に「意味づけの再設計」です。科目内容を自分の将来や関心に結び直すユーティリティ・バリュー介入は、直前期ほど効きます。英語長文なら「読みたい分野の英文を一段落混ぜる」、化学なら「進みたい学部のトピック例を一問挟む」などです。
行動切り替えの摩擦を減らす「事前プラン」も有効です。If–Then形式の実行意図やMCIIを使い、「不安で手が止まったら、設問だけ声に出して読む」「心拍が気になったら、30秒呼気長め呼吸に切り替える」など、条件反射的に最初の一歩へ戻せます。
呼吸と身体の整え方も短期間で効果があります。心拍変動を高めるレゾナンス呼吸は、1日5分×2回を2週間ほど慣らすと当日にも活用できます。軽い有酸素運動やマインドボディ系の短時間運動も不安低減に寄与します。
睡眠設計は「就床・起床の一貫性」が重要です。昼寝は30〜60分までに抑え、起床後に日光と軽いストレッチを取り入れると睡眠慣性を抜けます。睡眠と詰め込み勉強は背反ではなく、“眠りで固める学習”として理解してください。
当日の準備
当日は“自動運転に乗る”ルーティンを作ります。プレ・パフォーマンス・ルーチン(PPR)を設定し、会場到着〜最初の1分の手順を固定して練習します。例えば「肩を回す→手首をひと撫で→試験番号を書く→深呼吸→最初の設問黙読」です。
次に「再評価」です。ドキドキを「身体が燃料を回している証拠」と言葉にして受け止め、自己監視を弱め作業面へ注意を戻します。うまく切り替わらない場合は、30〜60秒の呼気長め呼吸で落ち着きの着陸地点を作ります。
「心配の後回し」も有効です。一日のどこかに心配タイムを設け、不安をメモして棚上げし、試験中はメモ→深呼吸→問題文の順で注意を戻します。
自己価値を支える自己肯定(セルフ・アファメーション)も役立ちます。「自分が大事にしていること」を短く書き、緊張の中でも学ぶ意味を再確認します。
配点と時間配分の安全装置も重要です。配布後1分で大問ごとの点と見込み時間を割り振り、難問には仮撤退ラインを設定します。演習段階から小テスト形式を繰り返すと、当日の記憶検索が安定します。
最後に「眠気・だるさ」対策。前夜寝不足が心配なら、会場入り2〜3時間前に15〜20分の仮眠、起床後に日光と軽いストレッチで覚醒を引き上げます。カフェインは普段の習慣に合わせて少量を摂取、ぶっつけ本番は避けましょう。
最後に
直前期の不安は意志の弱さではなく注意と身体の仕組みに由来します。
再評価・進捗の見える化・実行意図・レゾナンス呼吸・睡眠設計の五本柱を二〜三週間でルーチン化すると、当日の“自動運転”に乗りやすくなります。
当日は短いPPRとセルフ・トークで“今ここ”に注意を戻し、配点と時間の安全装置で焦燥を抑える設計が有効です。
万人に同じ正解はありません。小さく試し、記録し、翌日に微調整する循環を回すことが、合格までの最後の一押しになるでしょう!