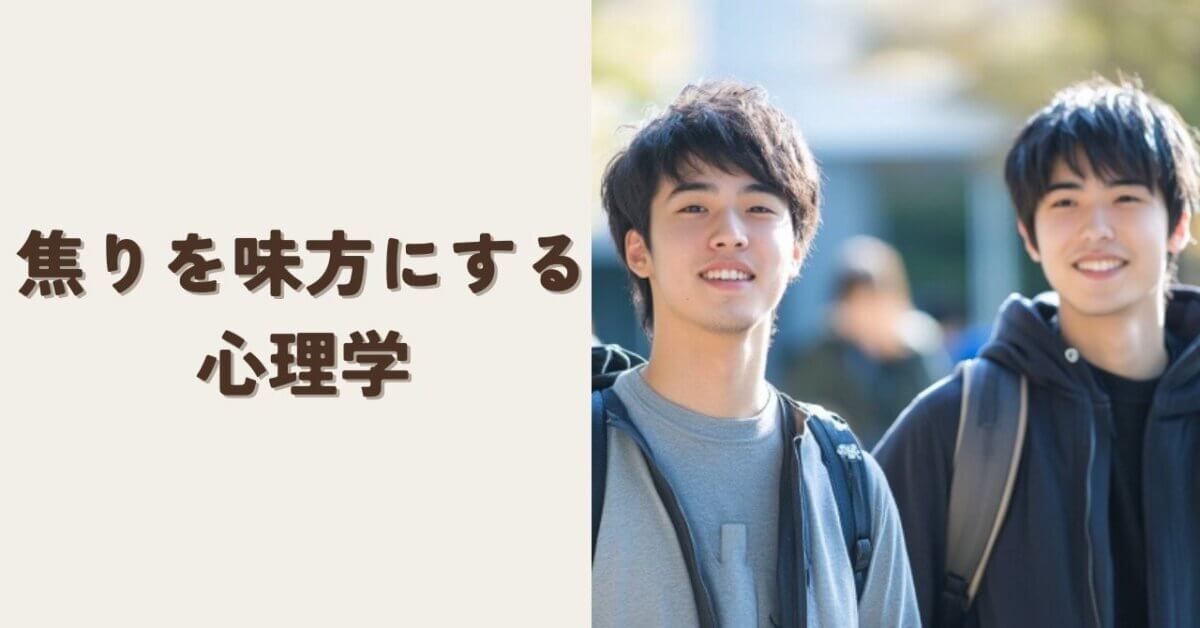受験本番が近づくと、誰もが一度は経験する「比較の痛み」。
たとえば「模試で過去最高点」「志望校の先生にほめられた」──そんな話題を聞いた瞬間、胸がざわつくことがありますよね。焦りや不安で勉強に手がつかなくなるときもあるでしょう。
でも、それは“特別な弱さ”ではありません。人が持つ自然な心理反応であり、扱い方次第で「学びの燃料」に変えることができます。
今回は心理学の知見をベースに、「比較で揺れた心」を整える実践策を、感情面と行動面の両方から整理していきましょう。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
比較してしまう原因
自慢を聞いたときの心の動きには、「社会的比較」があります。人は自分の現在地を他者と比べて評価する傾向があり、これが自己評価の基準になります。比べる相手が自分より先に進んでいると、「上方比較」が生まれやすいのです。
とはいえ、上方比較は悪いものではありません。脳は「どうすれば自分も近づけるか」を学ぼうとして注意を向けます。実際には、脅威を感じると「評価は下の相手に」「学びは上の相手に」という“分業”も起こるとされます。これが「嫉妬」という感情の複雑さにつながります。
嫉妬には「悪意的な嫉妬(相手を下げたい)」と「良性の嫉妬(自分を高めたい)」の2種類があります。後者は痛みを伴っても前進の原動力になりやすいのです。
つまり、自慢を聞いたときに「自分は今どちらのモードにいるのか」を見分けることが大切です。
また、SNSでは比較がさらに増幅されます。合格報告や勉強量の“切り取られたハイライト”に触れることで感情が揺れやすく、受動的にスクロールするほど気分が沈む傾向も報告されています。閲覧の姿勢が心の状態を大きく左右するのです。
さらに、“謙虚なふりをした自慢(ハンブルブリッグ)”は聞き手の好感度を下げるとされます。もしモヤッとしたら、それは自分の受け取り方だけでなく、相手の印象管理の癖によるものかもしれません。こうした知識をもつだけでも、反応を客観視しやすくなります。
まとめると、自慢で心が揺れるのは「比較→評価→感情」という自然な流れです。ただし、比較の“方向”や“見方”しだいで、成長にも停滞にも転びます。だからこそ、次に「心の整え方」を学ぶ必要があります。
心の整え方
まず取り入れやすいのは「距離をつくる」技法です。
自分の名前を使って三人称で独り言を言うだけでも、視点が外にずれ、冷静さを取り戻せます。
例:「○○、今は少し焦ってるね。でも、やるべきことは――」。
また「時間の距離」を取るのも効果的です。
「一週間後の私はこの出来事をどう見るだろう」と想像するだけで、刺激が和らぎます。感情が整理され、思考が事実寄りに戻るのです。勉強前の30秒ワークとしても使えます。
次に「自己肯定の幅を広げる」こと。
「自分が大切にしていること(家族・探究心・仲間など)」を1分で書き出すだけでも、脅威への耐性が高まりやすいと報告されています。
さらに「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」の練習も有効です。
「誰でもこう感じることはある」と言葉にするだけで、不安や落ち込みが和らぎ、次の行動を選び直しやすくなります。
そして、「リフレーミング(解釈の組み直し)」を試してみましょう。
「友人は先に良い方法を見つけただけ。私は今、基礎固めの時期」と言い換えるだけでも、心が落ち着きます。
SNSを見るときは「目的を持つ・時間を区切る・自慢の多いアカウントは一時ミュート」。
受動的閲覧を減らすだけでも、気分の質は改善しやすいといえます。
最後に、“冷却ルール”を設けるのも効果的です。
「自慢を聞いたら5分だけ席を立つ」「水を飲んで深呼吸を3回」──こうした動作を挟むと、勉強への再接続がスムーズになります。
行動の設計
ここからは、実際の勉強の手順に落とし込みましょう。
まず「比較でざわついた直後の15分」の行動をテンプレート化します。
おすすめは次の3ステップ:
①今日の気づきを3文で要約
②最重要タスクを1つ書く
③最初の問題を1題解く
次に、“if–thenプラン”を作ります。
「もし友人の点数自慢を聞いたら、『おめでとう』と言って席に戻り、英語リスニング1回分から始める」など、状況と行動をひも付けます。
さらにスマホ対策として、「通知が光ったら画面を伏せる」「SNSは休憩10分だけ」といった具体的な動作を決めておくのもおすすめです。これも研究で効果が示されています。
また、「いつも同じ場所・同じ合図で同じ勉強を始める」と、習慣化が進みます。
習慣は“環境の手がかり”で自動的に立ち上がるため、比較で乱れた集中を平常運転に戻す助けになります。
友人関係での言葉の使い方
自慢を聞いたときに使えるスクリプトを準備しておくと安心です。
①共感の一言:「そうなんだ、すごいね!」
②質問で流す:「どの問題集が効いた?」
③行動の宣言:「私は今、英文和訳をもう一巡りするね」
この3段階で、相手を尊重しつつ自分の行動に注意を戻せます。
比較を“学び”に変えるメモ術
「3Cメモ」で比較を行動に変換します。
Claim(主張)・Context(条件)・Cost(自分の課題)を一行ずつ。
例:「Aさんが英語の点数アップ → 週5で音読 → 自分は発音練が不足」。
焦りをToDoに変えるこの方法は、良性の嫉妬を“推進力”に変える道具になります。
SNSとの付き合い方
SNSは「窓の管理」が鍵。
起動時に最初に見えるものを“自分の指標”に設定します。
たとえば固定ツイートを「今週の三指標(睡眠・勉強・復習)」にする。
他人のハイライトより、自分の軸を目に入れる習慣をつくりましょう。
保護者へのアドバイス
お子さんが落ち込んだ日は、「点数」ではなく「行動の進み方」に注目を。
「今日はどの単元を、どこまで進めた?」と尋ねるだけで、自己効力感が保たれます。
また、短い価値づけ作文を一緒に行うのもおすすめです。
親子で“比較から行動へ”の視点を共有することが、安定につながります。
最後に
友人の自慢で心が揺れるのは、人間らしい反応です。
でも仕組みを理解し、距離の技法と小さな計画を組み合わせれば、それは学びの推進力になります。
比べることを止めるのではなく、「いつ、何を見るか」「見たあと、どう動くか」を磨くこと。
感情の一歩外側に立ち、生活の手がかりで再始動する設計が、受験期の安定をつくります。
今日出会うかもしれない“自慢”も、明日のあなたの一歩につながります。