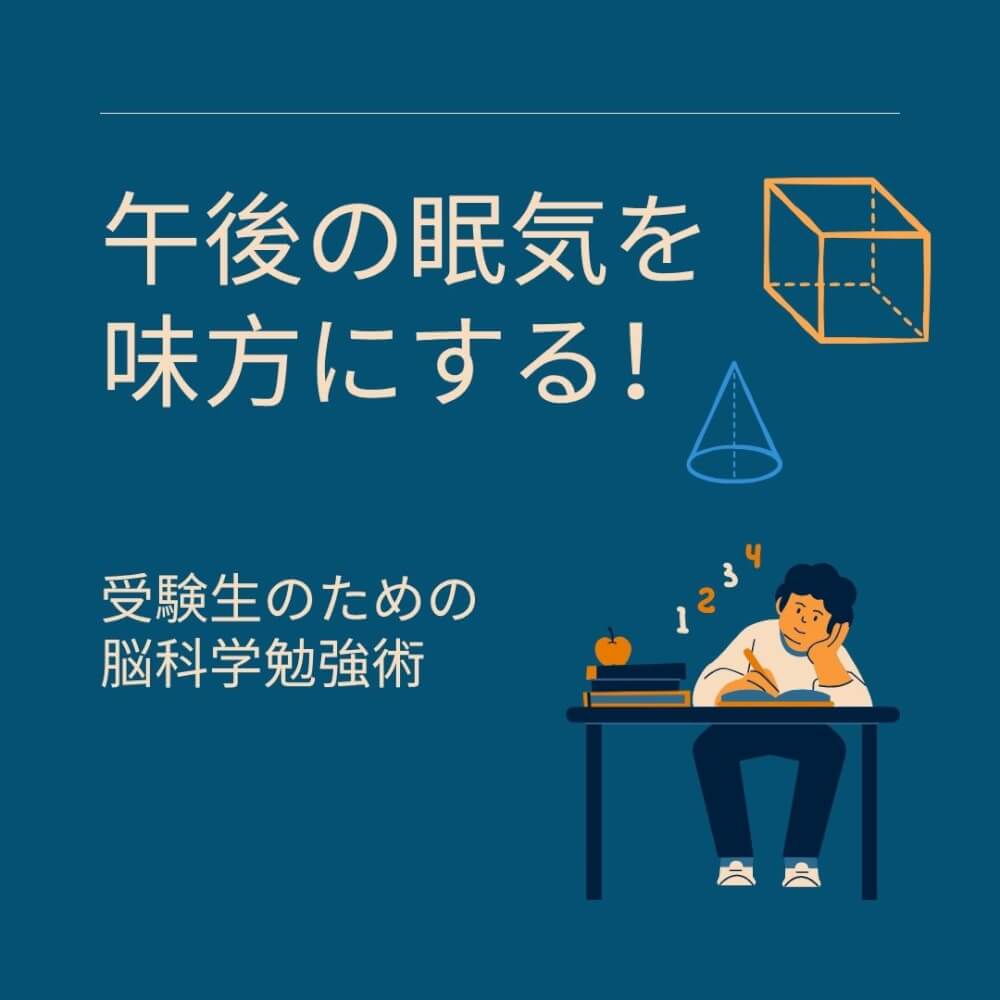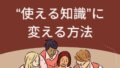「昼食のあと、眠くて全然集中できない……」
そんな悩みを抱える受験生は多いはずです。
実はこれは“意志の弱さ”ではなく、体の仕組みによる自然な反応。
しかし、工夫次第で午後のパフォーマンスは劇的に変わります。
本記事では、生理学・脳科学・心理学の観点から眠気の原因を整理し、午後を“得点力の時間”に変える方法を具体的に紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
昼食後に眠くなるのはなぜ?
昼食後に強い眠気を感じるのは、サーカディアンリズム(体内時計)の影響によるものです。人間の覚醒度は13〜15時ごろに自然と低下します。さらに、炭水化物中心の食事によって血糖値が急上昇・下降し、脳内ではセロトニンやメラトニンが分泌されて眠気を誘発します。
加えて、食後は消化に血液が集中するため脳の血流が一時的に減少します。つまり、眠くなるのは体の正常な働きなのです。
食事と体調で眠気をコントロールする
眠気対策の第一歩は「食事内容の見直し」です。
- 血糖値を安定させる食事:白米より玄米、野菜から食べるベジファーストを意識。
- 量を控えめに:腹八分目で消化負担を減らす。
- 脂質を抑える:揚げ物やラーメンは午後の集中力を奪う。
- 水分補給を忘れずに:脱水は眠気を強める。食後30分〜1時間後のカフェイン摂取も効果的。
また、夜更かしが続くと昼の眠気は倍増します。
「睡眠時間を削って勉強する」は逆効果。脳の記憶定着は睡眠中に強化されるため、7時間以上の睡眠が午後の集中力を高めます。
食後は背筋を伸ばして座る、5〜10分の軽い散歩をするなど、血流を促す習慣も有効です。
午後学習術:眠気を前提に戦略を立てる
眠気を“ゼロ”にするのは不可能。だからこそ「眠気を前提にした学習設計」が重要です。
- 午後の最初は軽いタスクから
英単語チェック、ノート整理などのルーティンワークでウォームアップ。 - 集中力が戻ってきたら重い課題へ
過去問演習や記述問題など、本番形式の勉強を配置。 - 15分仮眠の活用
NASAの研究でも「15分の仮眠」が認知機能を高めると報告。30分を超えると逆効果なので注意。 - 光と音で覚醒を促す
自然光を取り入れる、明るい照明や適度なBGMで眠気を抑制。
脳科学が示す「眠気の正体」
脳がエネルギーを消費するほど増える物質「アデノシン」が、眠気の主因です。午前中に勉強で脳を酷使すると昼過ぎにアデノシンが蓄積し、強い眠気を感じます。
一方、体を動かす・冷水で顔を洗う・光を浴びることで、覚醒系神経(ドーパミン・ノルアドレナリン)が活性化。脳が「活動モード」に切り替わり、集中力を再び高めることができます。
科学的に正しい「午後の使い方」
教育心理学の研究では、午後の集中力を高めるポイントとして次の3つが挙げられます。
- ポモドーロ・テクニック
25分集中+5分休憩を1セットとし、短い集中を繰り返す。集中力の波をコントロールできる。 - 仮眠+軽運動の組み合わせ
スタンフォード大学の研究では、仮眠後の軽いストレッチが最も覚醒効果を高めると報告。 - 時間帯ごとの学習区分
13時台はインプット、15時以降はアウトプット。脳の覚醒リズムに沿った内容配置が効率的。
メンタル面との向き合い方
「午後は眠くなる=意志が弱い」と思い込むのは逆効果。
眠気は自然現象であり、自分を責める必要はありません。
むしろ、「眠気を前提に動く」という考え方が成功の鍵です。
眠くなる時間を仮眠・ストレッチ・軽作業に充てれば、午後の時間を“戦略的に利用する”ことができます。
不安や焦りは眠気を強めるため、「今日はこれだけやる」と小さな目標を設定して達成感を積み重ねましょう。
まとめ
昼食後の眠気は、誰にでも起こる自然な現象です。
しかし、食事・睡眠・姿勢・学習内容を工夫すれば、眠気は“コントロール可能”です。
- 食事内容を整える
- 仮眠や短時間集中法を取り入れる
- 午後の学習内容を軽→重に切り替える
- 眠気を前提にしたスケジュール設計をする
眠気を敵ではなく「体のリズムの一部」として理解すれば、午後の時間を制することができます。
午後を制する者が受験を制す——それは、科学的にも間違いではありません。