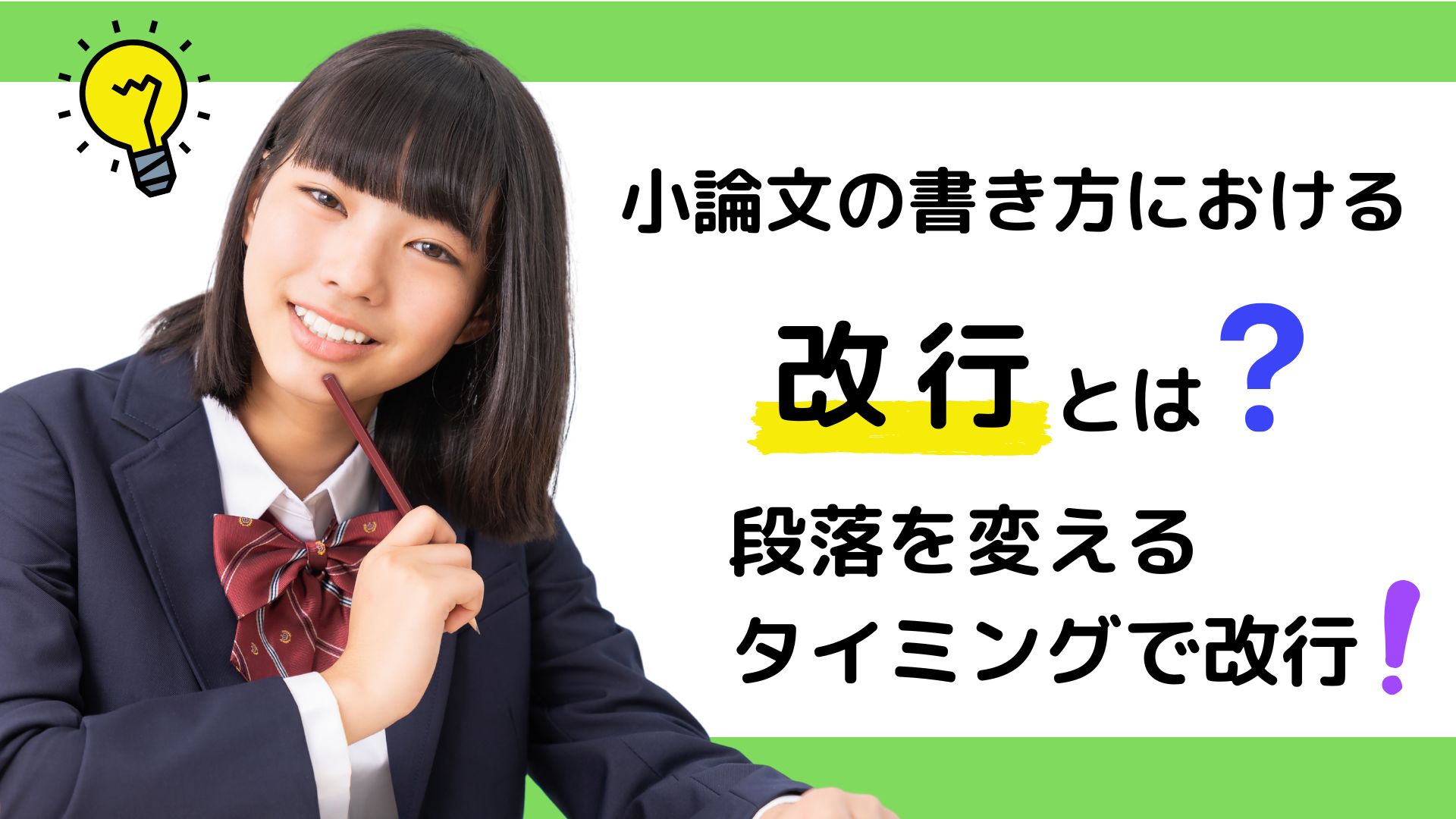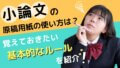大学受験における総合型入試の試験科目は大学によって様々ですが、面接と小論文が選ばれていることが多いです。
小論文は作文と違い論理的に自分の意見を述べるものですが、「書き方がよく分からない!」「作文と同じように改行してもよいの?」と悩む人がたくさんいます。
そこで今回は小論文の書き方がよく分からない!!と悩む方のために、小論文の書き方における改行について解説していきます♪

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
小論文の基本的な段落構成とは?
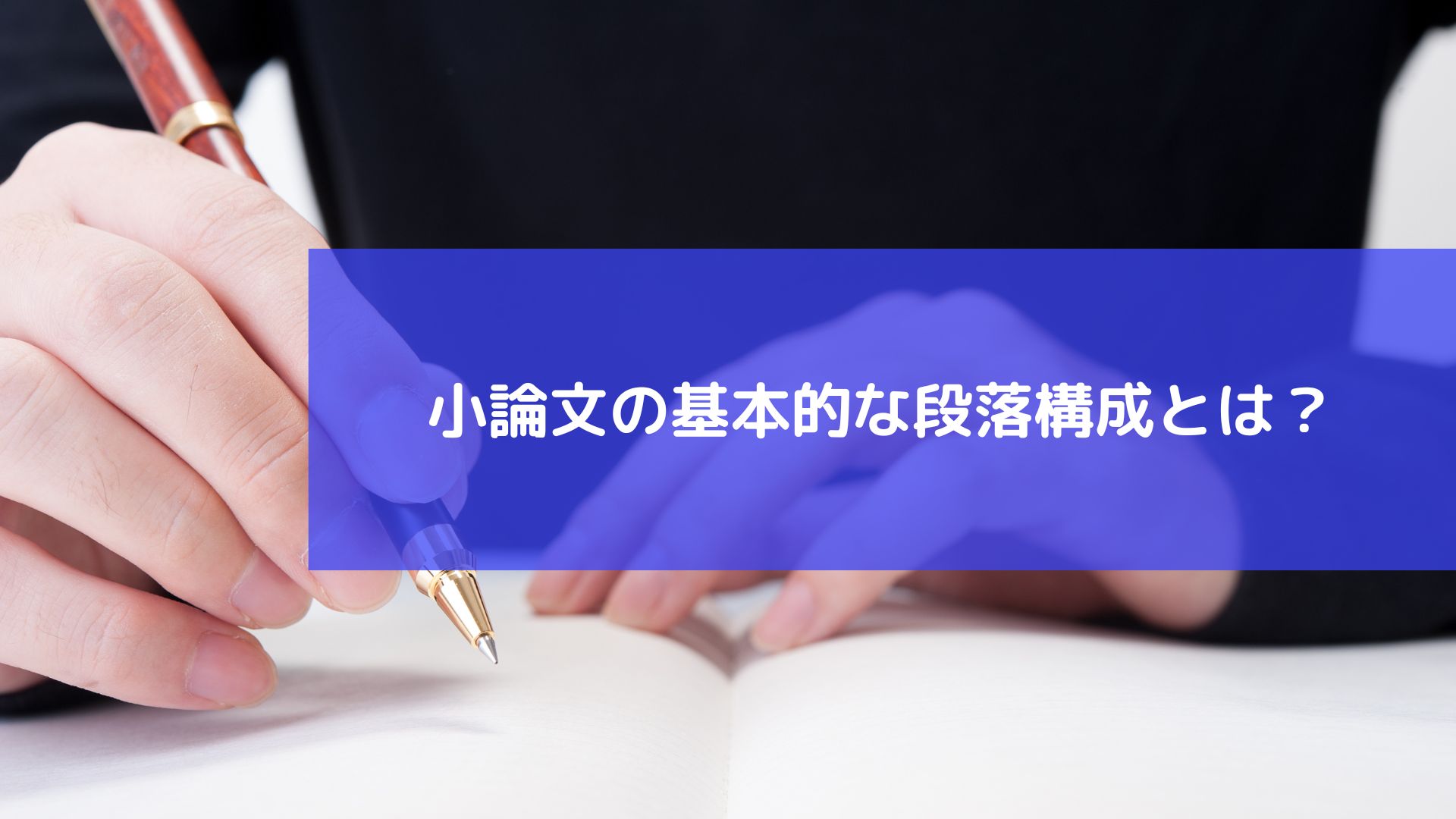
小論文はどのような手順で書いていくとよいのでしょうか?
まずは小論文の基本的な段落構成について解説していきます!
基本は序論・本論・結論の段落構成
小論文は自分の考えさえまとめて書いておけば良いというものではありません。きちんと相手に自分の意見が伝わるように、論理的な文書を作成する必要があります。そのためには、正しい日本語の表記を心がけることも重要です。
そのため、小論文は基本的に「序論」「本論」「結論」の3つを意識して書きましょう!
五十嵐写真02.png)
では「序論」「本論」「結論」という各構成要素の意味と、それぞれに書いていく内容を確認していきましょう。
序論で問題提起
序論で主に書いていく内容は、問題提起です!
主題に対して現状どのような問題を抱えているのかという点が主な内容となります。
まずは問題を提起した上で論理を展開していきましょう♪
本論で自分の意見提示
本論では、どんどん自分の意見を書いていきましょう!
ここが小論文の主となります。
序論で提起した問題に対して、どのような経緯で自分の意見を持ったのか、なぜそう思ったのか、具体的に述べていきましょう!
結論でまとめと解決策を提示
結論ではまとめと問題に対する解決策を書きましょう!
序論で問題を提起し、本論で自分の意見を述べたら、あとは結論で今後どのようにしていくと良いのかという問題解決へと論理を展開していきましょう。
五十嵐写真02.png)
序論で挙げた問題、本論での自分の意見、結論の解決策がそれぞれ論理的に繋がっていくことが大切です。この基本構成をしっかり活用することで、読み手にとって分かりやすく、説得力のある文章になりますね。
小論文における改行とは?
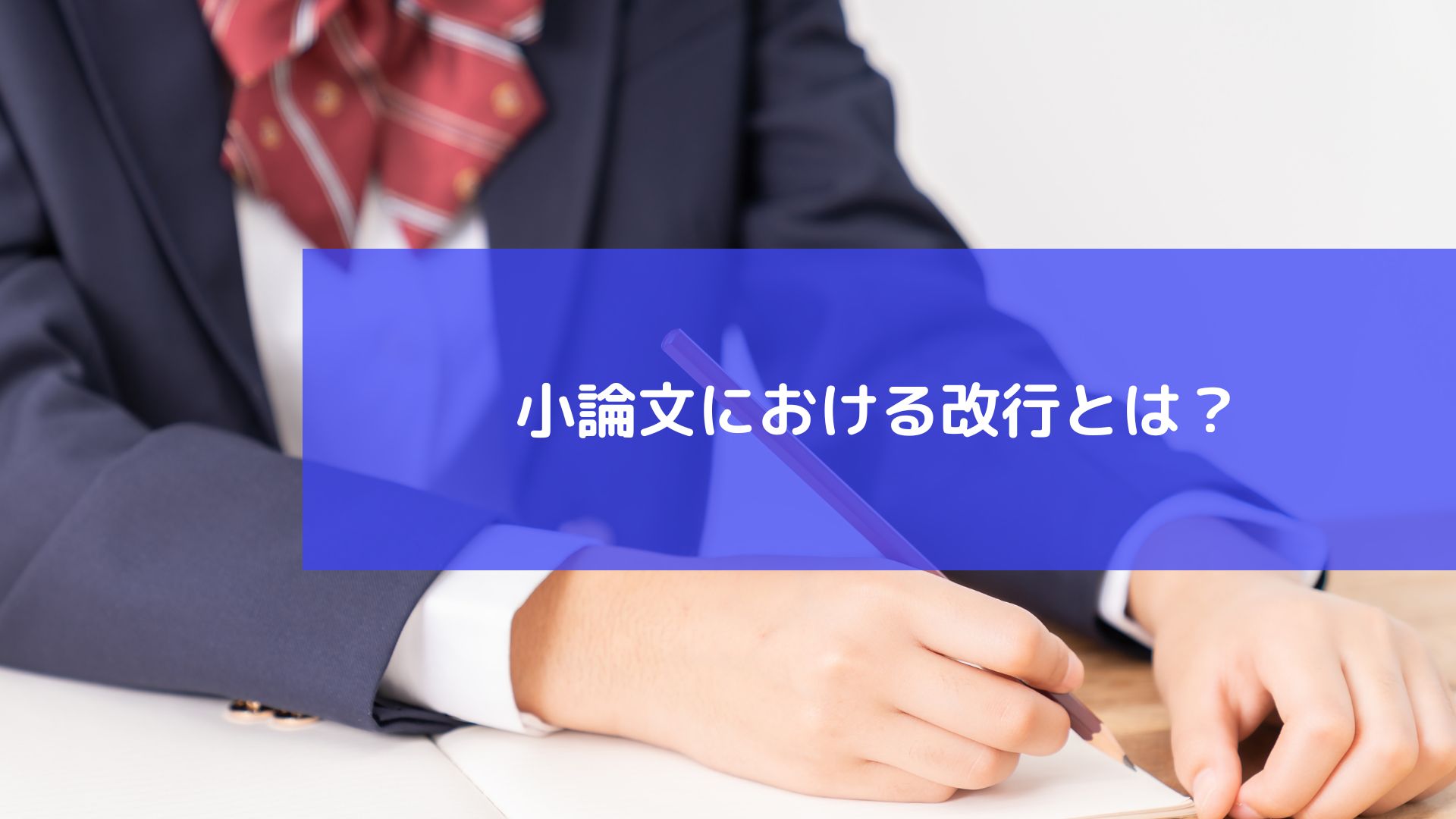
ここまで小論文の基本的な構成について解説してきました。
では、序論・本論・結論それぞれの構成の内で内容を記述していく際に、「改行」はどのタイミングで行うべきなのでしょうか?この用語の正しい意味と使い方について、詳しく説明します。
段落を変えるタイミングで改行
改行は基本的に、話の大きな区切りとなる段落を変えるタイミングで行います。小論文における改行は、単に行を改めるだけでなく、『ここから話が変わります』という読み手への合図という重要な意味を持ちます。通常、PCやワープロで文章を入力する際はEnterキーを一度押す操作で改行できますが、小論文ではこの機能をむやみに使用してはいけません。
序論・本論・結論は大きな構成の枠組みですが、その中でも複数に段落が分かれると思います。
その意味のまとまりである段落が変わるタイミングで、改行をしましょう!特に段落が変わる場面でもないのに文章の途中で改行してしまうと、読みやすさを損なうだけでなく、文字数稼ぎだと見なされる可能性があります。
五十嵐写真02.png)
改行しすぎないように気をつけましょう。
改行時は1マス空ける
新しく段落を始める際のルールとしてもう1つ覚えておいてもらいたいのは、「改行時には1マス空ける」ということです。これは「字下げ」と呼ばれる日本語の表記ルールです。行の頭、つまり段落の前に1文字分のスペースを設けることで、ここから新しい段落が始まることを明確に表示します。手書きの原稿用紙だけでなく、PCでテキストを作成する場合も同様です。このルールを守ることで、文章全体の見た目が整い、格段に読みやすくなります。
改行のタイミングを例文で紹介

例文1
近年インターネットやSNSの普及により手軽に様々な情報を得ることができるようになった。今まで知らなかった分野に興味を持つことや個人や企業関係なく簡単に広告を行うことを可能にし、インターネットやSNSの普及による恩恵は素晴らしいものである。
その一方で、インターネットやSNSによる弊害も多く存在する。誰もが自由に意見をすることができるという特性が悪用されているのだ。
例文2
新型コロナウイルスの感染拡大により、日本を含む多くの国々ではロックダウンや緊急事態宣言といった国民への自粛行動が余儀なくされた。感染が長期化する中でマスクの着用が義務化され、正義感から国民が国民を取り締まろうとする「自粛警察」なるものも現れ国民の不安や我慢が限界を迎えようとしている。
ここで今国民に必要とされていることは、「相互の姿勢」であると考える。日本中で感染が拡大している新型コロナウイルスに対して、誰が正義ではなく、国民1人1人がお互いに協力し合う姿勢がなければこの状況を打破することはできない。
上記の例文のように話の流れが変わるタイミングで段落を変え、同時に改行を行うことが大切です。前の段落の後、次の段落に移ることで、文と文の論理的な繋がりが明確になります。読み手が内容をスムーズに理解できるよう、この点を意識して文書を作成しましょう。
まとめ
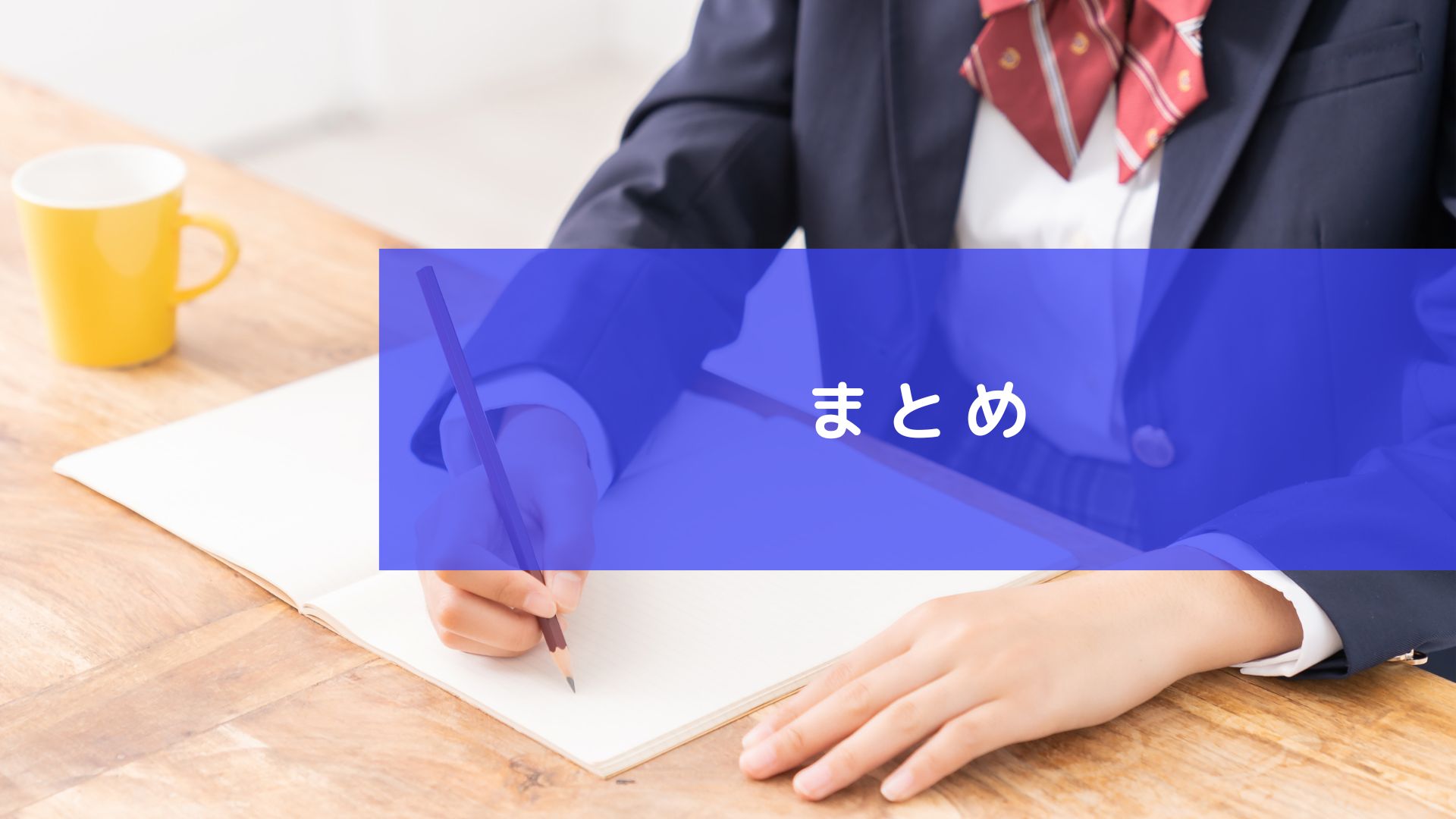
今回は小論文の書き方、その中でも特に「改行」という操作の意味と使い方について解説しました!小論文は作文と違い、論理的な段落構成で自分の意見をまとめなくてはいけません。今回説明したポイントをしっかり活用し、正しい改行ルールを使用して、読みやすい答案を作成してください。
小論文に苦手意識を感じてしまう人もいるかもしれませんが、今回解説してきたように基本的な構成や段落・改行のタイミングさえ掴んでおけば大丈夫です。あとは試験本番までに、これらの知識を活用して実際にいくつか小論文を書く練習をしておくと、落ち着いて本番に挑めますよ!ぜひこの機会に、ご自身の小論文の書き方を改めるきっかけにしていただきたいです。
スカイ予備校では小論文の書き方やコツなど他にも大学受験に役立つ情報を利用できます。興味がある人は是非、まずはLINE登録からお願いします!