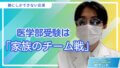推薦入試を考えている高校生にとって、「評定平均値」は合否を左右する重要な指標です。
しかし、「どうやって計算されるの?」「どこまで成績が影響するの?」と疑問を抱く人も多いでしょう。
ここでは、評定平均値の基本的な算出方法から、入試での扱われ方、そして上げるための具体的な工夫までをわかりやすく解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
評定平均値の算出方法
評定平均値は、(履修した科目の評定の合計値)÷(科目数)で求めます。
小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで表示するのが一般的です。
原則は5段階評価ですが、学校によっては10段階評価を採用しているところもあります。
この場合、10段階を5段階に換算する基準は高校ごとに異なるため、学校に確認しておくのが安心です。
また、評定の対象となる学期は受験時期によって異なります。
- 秋の推薦入試(9〜11月頃):高1学年末・高2学年末・高3一学期の成績
- 冬の推薦入試(1月以降):高1〜高3二学期までの成績
既卒生は高3学年末の評定を用いるのが一般的です。
評定平均値はどう使われるのか
一般入試では評定平均値が合否に直接影響することはほとんどありません。
しかし、推薦入試では合否を大きく左右する要素になります。
特に「指定校推薦」や「公募推薦」では、一定以上の評定が出願条件になっている大学もあります。
たとえ条件が明記されていなくても、実際には高い評定が求められるケースが多いです。
例えば、国公立大学の医学部では4.5以上を目安とすることが少なくありません。
評定平均値を上げるためのポイント
3-1. 定期テストと提出物を大切に
最も効果的なのは、定期テストで点数を取ることと、提出課題を期限内に出すこと。
授業態度も評価対象ですが、点数や提出物の方がより明確な基準になります。
授業中に先生が強調した部分や、繰り返し説明した内容は出題されやすい傾向があるため、注意深く聞き取るようにしましょう。
3-2. 担当教員に相談してみる
推薦入試を目指すことを早めに伝えるのも有効です。
教員から評価の付け方や、重点を置いているポイントを聞けるかもしれません。
また、将来的に推薦書の作成をお願いする場合にも、日ごろの関係づくりが役立ちます。
3-3. 高3からでも間に合う?
評定は高1・高2の成績も含まれるため、高3からの巻き返しには限界があります。
それでも、目標ラインまであと少しという場合は、最後まで粘る価値があります。
まずは志望校の必要評定を確認し、戦略的に時間を使いましょう。
3-4. 自分に合った環境で勝負する
同じ「4.5」でも、学力の高い環境とそうでない環境では実際のレベルが異なります。
しかし、入試制度上はすべて同じ4.5として扱われます。
もし学校内でコース分けがある場合、競争が激しすぎるクラスよりも、評定を上げやすい環境を選ぶという考え方も一つの手段です。
まとめ
評定平均値は、努力と戦略次第で確実に上げられる指標です。
推薦入試を目指すなら、早めの情報収集と、日々の積み重ねが合否を左右します。
自分の現状を客観的に把握し、どのタイミングでどのように点を稼ぐかを意識して行動しましょう。