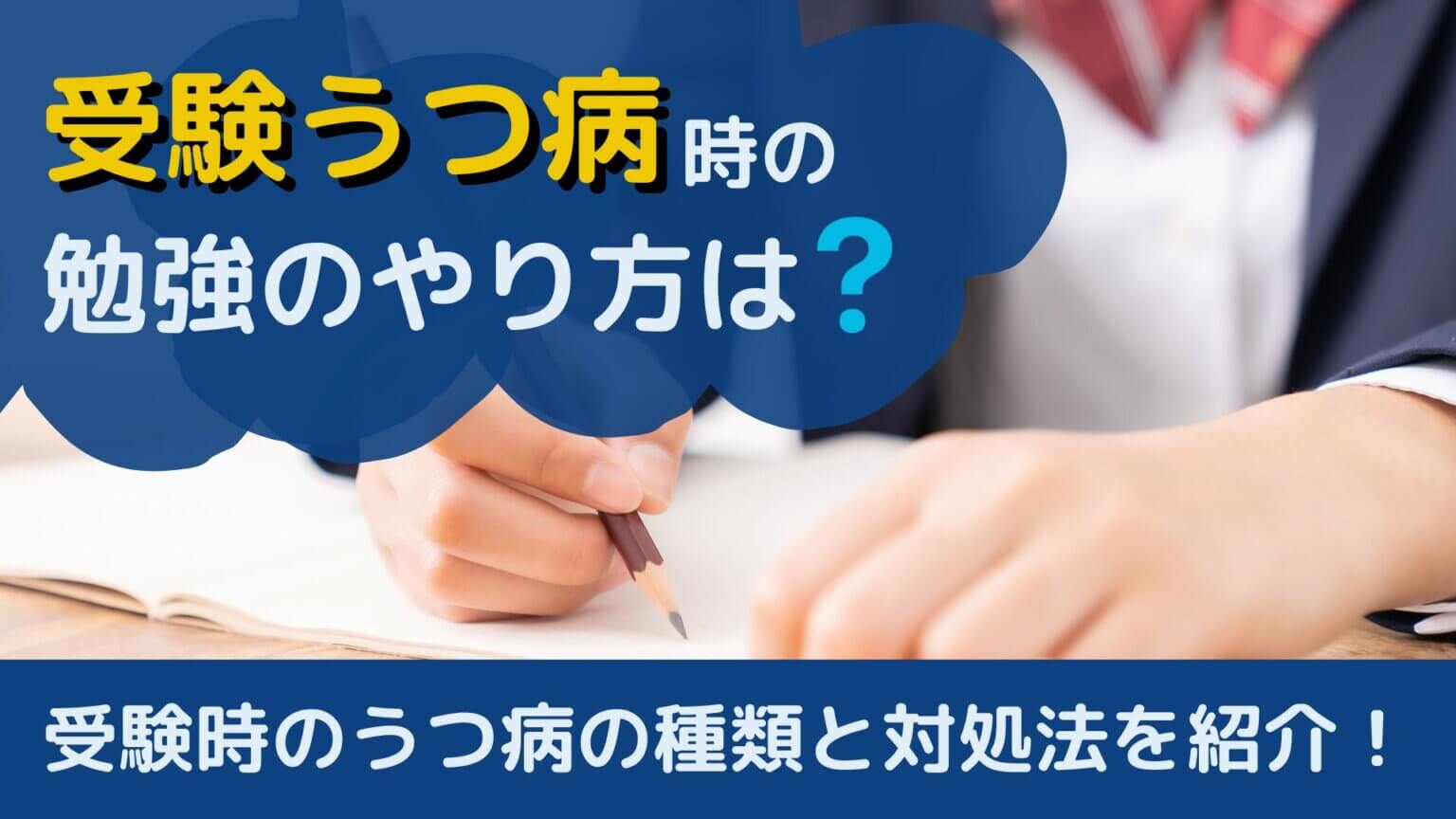受験期の特殊な環境は、これまで経験したことのない強いストレスを心に与え、いわゆる「受験うつ病」を発症してしまうケースが多いです。多くの受験生が悩んでいるこの問題は、決して特別なことではありません。
受験うつ病になってしまった場合、やる気が出ずに勉強をどうしたらいいか、勉強と休養どちらを優先したらいいか悩んでしまいますよね。
私の身内が高校受験の際に受験うつ病に近い状態になった経験から、今回は受験うつ病の種類とその対処法について、医療機関との連携も視野に入れてご紹介します。うつ状態の時の勉強のやり方についても解説しています。
五十嵐写真02.png)
無理しないことと、早めの対処が重要です! 本人だけでなく、周囲のサポートが大切になります。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
受験勉強時のうつ病の症状は?
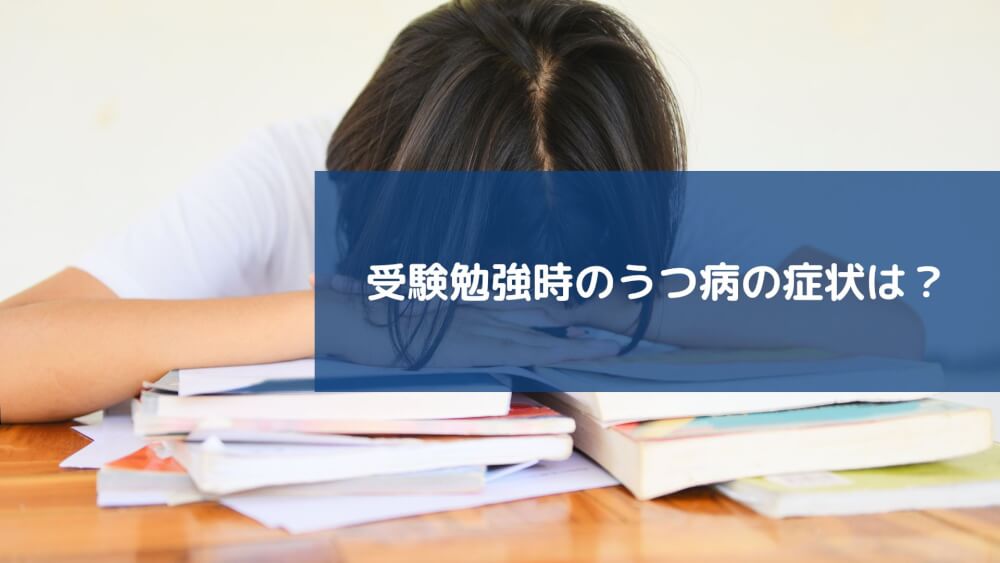
「受験うつ病」といっても「受験期に起こるうつ病」であるだけなので、一般的なうつ病の症状があてはまります。
- 一日中気分が落ち込んでいる
- 何をしても楽しめない
- 眠れない(逆に寝すぎてしまうこともあります)
- 食欲がない
- 疲れやすい
- ものの見方や考え方が否定的になる
参考:うつ病|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
うつ病は、精神的ストレスなどが原因で脳がうまく働かなくなっている状態です。
その結果勉強が頭に入らない、そもそも勉強する意欲が出ない、ひどい場合は学校に行くことを始め全てがおっくうになり、日常生活すらままならなくなってしまいます。
以下にうつ病のチェックシートの一例を載せておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
参考:「うつ」自己診断チェックシート|京都・医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 (eijinkai.or.jp)
受験時のうつ病の種類とその原因は?

受験時のうつ病の種類と原因を知ることで、原因を極力避け症状を緩和することができるかもしれません。
- モチベーション喪失型
- プレッシャー型
- 比較・競争型
受験うつ病の種類にはこの3つがあります。
モチベーション喪失型
受験が近いのに問題が解けず合格できる気がしない、勉強する範囲が広すぎて終わる気がしないなど、無力感をきっかけに発症するパターンです。
「こんな状態じゃどうせ合格しない」「こんなに努力しても失敗する」と自身の評価が下がり、さらに無気力になるという負のループに陥ってしまいます。 そんな時は、「この志望校に見合った人間だから受験する機会ができた」と思考を転換し、過度な思い込みを避けることが大切です。
プレッシャー型
先生や家族からかけられる期待に応えようとして、過剰な負担を感じる場合に起こりがちです。
「勉強に集中できない」「全てが嫌になって逃げだしたくなる」と感じるかもしれませんが、周囲の期待と自分の人生は切り離して考える必要があります。 親は子どもが進んだ道で納得するしかありませんし、目の前の志望校に受からなかったら将来への道が全くなくなるわけでもありません。周囲からの言葉は「心配されているんだな」くらいに受け止め、深く気にしないようにしましょう。

比較・競争型
受験に限らず、SNSが発達した昨今は、半強制的に周囲の順調な報告が目に入り、自分がうまくいっていないと落ち込みますよね。SNSや模試の結果など、他者の順調な報告だけを見て焦りや劣等感を強く感じることからうつ状態になる場合があります。
しかし、SNSはあなたの将来に何もしてくれません。受験期はSNSや友人との交流はほどほどにして、休養と勉強に集中しましょう。塾の友人などとの関係も大切ですが、過度な比較は心の不調につながります。
受験うつ時の対処法は?
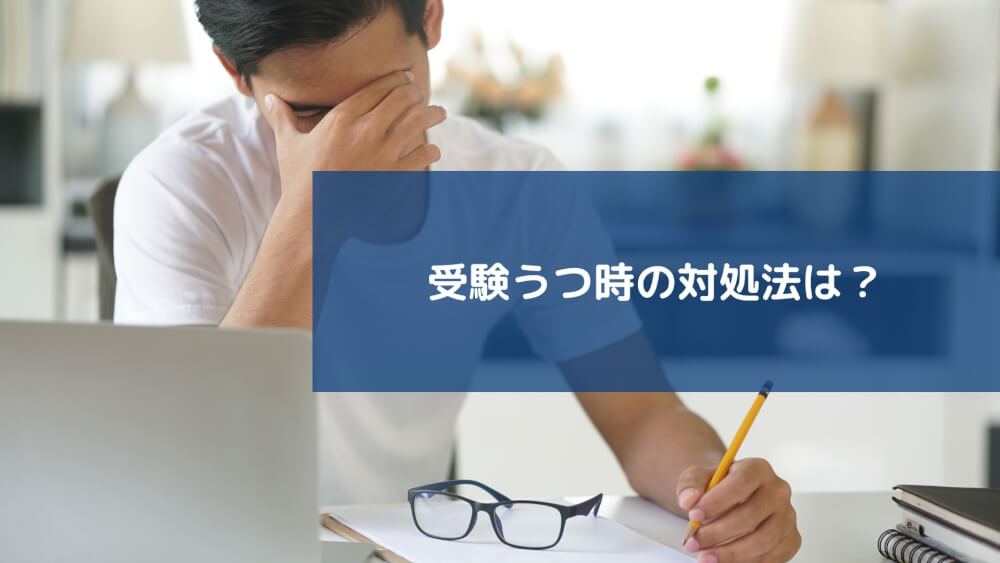
どうやら受験うつ病っぽい、と感じたらどうしたらいいでしょうか?
結論としては、悪化する前に早めに専門の医療機関へ相談することをお勧めします。それとあわせて普段の生活でできる対処法もご紹介します。
自分がうつであることを自覚し専門医へ相談
「精神科や心療内科なんて大げさな…」「そこまでひどい状態じゃない」とためらうかもしれません。しかし、うつ病は風邪と同じ病気の一種であり、放置すると悪化し、回復に時間がかかります。
心の不調を感じたら、まずは専門のクリニックを受診しましょう。医療機関のイメージが先行しがちですが、行ってみると案外他の科の病院と違いはありません。Webサイトなどで予約し、気軽に医師に相談してみてください。本人が行きたがらない場合は、家族など周囲の人がサポートし、医療につなげることが有効です。
薬に依存せず有酸素運動を取り入れる
クリニックでは、診断に基づいて薬物療法(抗うつ薬など)が行われることがあります。薬に抵抗がある人もいるかもしれませんが、副作用の可能性も含めて医師から十分な説明を受け、納得した上で治療を受けることが大切です。
近年では、薬を使わない治療法としてTMS治療(経頭蓋磁気刺激法)といった選択肢もあります。これは脳の特定の部分に磁気で刺激を与え、機能の回復を促すものです。
また、治療と並行して、有酸素運動もおすすめです。ウォーキングや軽いジョギングは自律神経を整え、睡眠障害の改善も期待できます。日光を浴びながらのウォーキングはさらに良い効果があります。食事のバランスを整えることも心と身体の健康に不可欠です。
無理に勉強せず治療に専念する
これらの対処法でも改善が難しい時は、無理に勉強するのはやめましょう。うつ状態で気力と脳の働きが低下している時に勉強しても効果は出にくいです。
とにかく回復することに専念した方が、結果的に早い回復につながります。少し元気になってきたら、焦りから無理をせず、できそうなら横になってできることから始めましょう。
- 解説動画を観る
- 要点が書かれたテキストを眺める
- 簡単な一問一答の問題集や受験対策アプリを解く(解けないと落ち込むので簡単なものを)
くれぐれも無理は禁物です。塾や予備校に通っている場合は、事情を伝えて学習計画の相談に乗ってもらうなど、サポートを活用しましょう。
まとめ

今回は「受験うつ」についての記事をお送りしました。 受験勉強は限られた時間の中で行う必要があり、精神的に追い込まれてしまう受験生は少なくありません。
志望校に合格することももちろん大事ですが、「元気に」通学できなければ意味がありませんよね。気付かぬうちに無理をしていないか、自身の心の状態に注意を向けましょう。
思い詰めたり自信がなくなったりするのは、自分を客観的に見られなくなっていることも原因です。一人で悩んでいるなら、進路や勉強の悩みを相談できる受験のプロ(塾や予備校)の手を借りることも検討してみてくださいね。あなたの状況を理解し、適切な目標設定や学習法を案内してくれるでしょう。