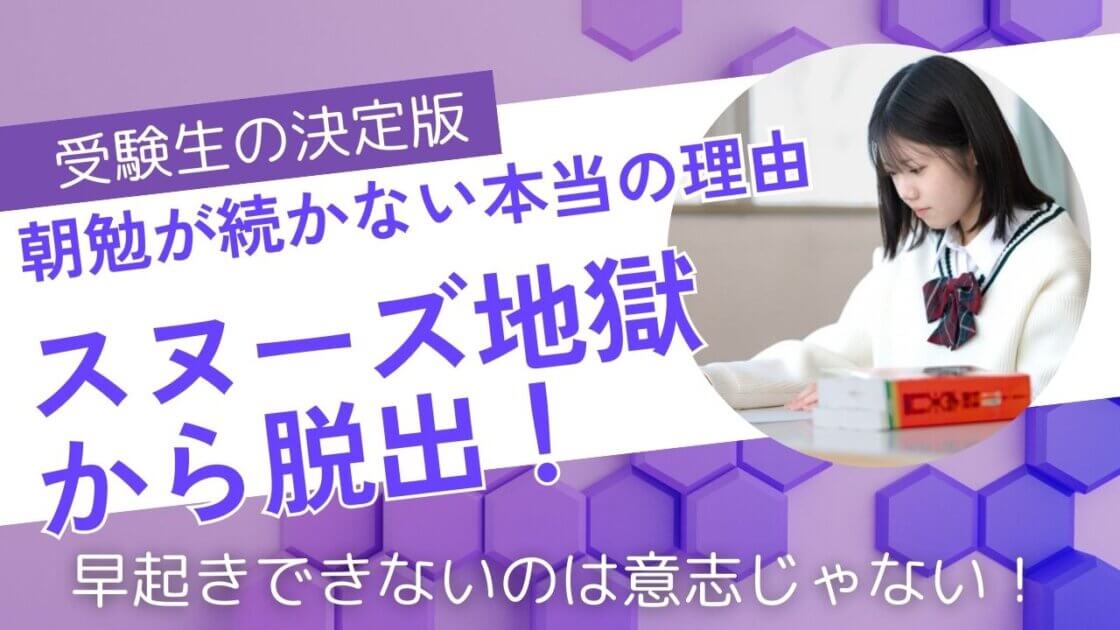朝勉強は効率的だと言われる一方で、「早起きが苦手でなかなか続かない」という受験生の声をよく聞きます。アラームを何度も止めてしまい、気づけば登校時間ぎりぎりになっている──そんな経験は多くの人にあるでしょう。実はこれは意志の弱さではなく、思春期特有の体内時計のずれと生活習慣とのミスマッチが大きな原因です。では、どうすれば朝勉を習慣化できるのでしょうか。今回は、体内時計の整え方から起き方の工夫、朝勉の戦略まで具体的に整理していきます。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
朝勉ができない背景
朝勉は効率がいいと言われていますが、早起きが苦手で難しいという声は少なくありません。アラームを止め続け、登校直前まで眠ってしまうこともよくあるでしょう。しかし、この「朝のつまずき」は意志の弱さではなく、思春期に特徴的な体内時計の後ろ倒しや、睡眠習慣とのズレが背景にあります。思春期は眠気ホルモンであるメラトニンの分泌が遅れて始まり、夜型に傾きやすいのです。さらに、早い登校時刻や夜のスマホ使用が加わることで入眠が遅れ、起床時の眠気が強まります。こうした現象は研究でも繰り返し確認されており、「気合」だけで解決するのは難しいといえます。
ただし、朝勉をあきらめる必要はありません。起床直後の眠気の正体である「睡眠慣性(sleep inertia)」は、光や音、起き方の設計で軽減できるからです。さらに、睡眠時間の不足も見逃せません。アメリカ睡眠医学会は13〜18歳に1日8〜10時間の睡眠を推奨しており、これを満たさないと集中力や学習効率が低下するリスクがあります。まずは「必要な睡眠量を確保すること」が大前提になるのです。その上で、体内時計の整え方、起き方の工夫、そして朝勉の設計を順に押さえていくことが大切です。
体内時計を整える
朝勉を続けるためには、まず体内時計を安定させることが重要です。
- 起床時刻を毎日そろえる
週末の寝だめは「ソーシャル・ジェットラグ」を生み、月曜朝を一層つらくします。一方、起床時刻を一定に保つと体内リズムが安定しやすいと報告されています。 - 朝の強い光を浴びる
起床直後に光を浴びると体内時計は前進し、次第に眠りやすいリズムになります。カーテンを開ける、屋外に出るなどが効果的です。曇りの日や冬場は「夜明け再現ライト」や起床用ライトの活用も有効です。 - 夜は光を控える
就寝前のデバイス使用は入眠を遅らせ、睡眠を乱します。SNSや動画を控え、照明を落とすことが優先です。 - カフェインを管理する
夕方以降のカフェインは眠りを妨げるため、就寝6時間前から控えましょう。起床後に少量とるのは有効ですが、午後遅くの摂取は避けます。 - 夜の過ごし方を整える
寝る前に軽いストレッチや入浴で体温を一度上げて下げると、自然に眠りにつきやすくなります。朝は日光と軽い運動、夜は穏やかな習慣が体内時計を整えます。
起床の技術
朝の眠気を乗り越えるには「起床の工夫」が欠かせません。
- アラームを工夫する
スヌーズは眠気を長引かせるので、1回で起きられる設計にしましょう。メロディのある音楽は覚醒を助けると報告があります。 - 光を取り入れる
起床と同時に照明や自然光を浴びることが有効です。ドーンシミュレーションも眠気を軽くする可能性があります。 - 起床後のルーティンを固定する
水を飲む→洗顔→軽いストレッチ→机に座る、と決めて毎朝繰り返すと習慣化がスムーズになります。机に座ったらまず簡単な課題を解き、助走をつけるのがおすすめです。 - クロノタイプに合わせる
夕型の人は朝に新しい課題を詰め込まず、前夜の復習や授業の予習など軽めの作業を朝に回すと続けやすいです。 - 短い昼寝を取り入れる
午前がどうしてもつらい日は、放課後に10〜20分の仮眠を取り入れましょう。長すぎる昼寝は逆効果なので注意が必要です。
朝勉の戦略
朝勉を「続ける」には、学習の設計も工夫が必要です。
- 起床直後は新しい勉強ではなく「復習」や「確認」タスクを優先。
- 机上は前夜のうちに整え、朝はすぐ勉強に入れる状態にしておく。
- 朝の時間割を固定化する(例:想起10分→基礎演習20分→授業確認10分)。
- 通学時間は音声学習で効率を高める。
- 食事は軽めにし、眠気の戻りを防ぐ。
- 家族の協力を得て、光や朝食の習慣を整える。
無理にすべてを朝に集める必要はなく、夜の質を上げて朝は確認に徹する戦略も有効です。
まとめ
朝勉が続かない背景には、思春期特有の体内時計のずれや生活習慣の影響があります。そこで「体内時計を整える」「起床の技術を工夫する」「朝勉の設計を見直す」の3つを組み合わせることが大切です。朝は新しい学習よりも復習や整頓を重視し、夕型の生徒は夜の勉強の質を上げることでバランスをとりましょう。どうしても改善しない場合は、医療者に相談することも選択肢のひとつです。