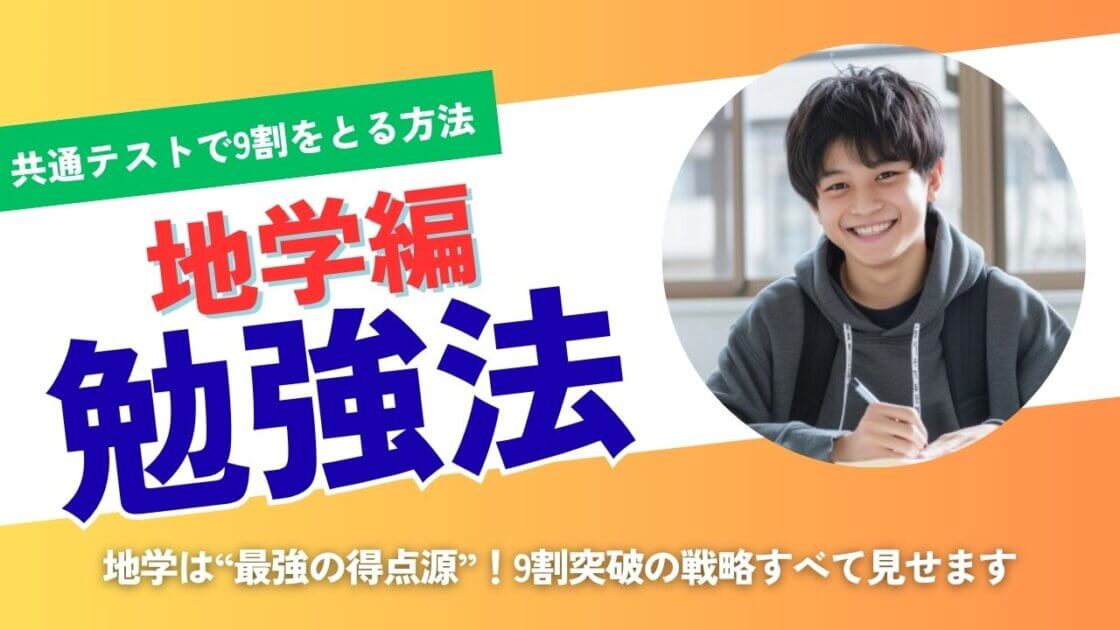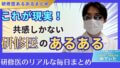今日は、「共通テストの地学で9割を狙う」ための具体的な戦略について、お話ししたいと思います。
地学という科目は、「暗記科目」として捉えられがちですが、それだけでは通用しないのが共通テスト。
実際には、図表やグラフを読み解く“思考力”と、基礎知識の“定着”のバランスが問われる、非常に“戦略的”な科目です。
しかし、逆に言えば──
「出題傾向を理解し、頻出テーマを重点的に学習し、思考の型を身につける」
この3つを押さえれば、地学は最も安定して高得点が狙える科目とも言えるのです。
私がこれまで指導してきた生徒たちの中にも、「地学で9割を突破した」例は少なくありません。
努力が得点に直結しやすい。それが地学の魅力なのです。
この記事では、地学の共通テストで高得点を狙うためのステップを、「出題傾向」「暗記の構造化」「実戦演習」の3本柱で解説していきます。
皆さんの学習の指針になることを願っております。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:出題傾向と頻出テーマの分析
共通テスト地学は「毎年似た構成」「頻出テーマの繰り返し」「図表の活用」が特徴です。
◆高頻出分野を押さえよ
以下の分野が特に出題率が高く、重点的な対策が必要です:
- 天文学(惑星運動、星の一生)
- 地震・プレート(波の伝わり、プレート境界)
- 地質年代と化石(示準化石・示相化石)
- 気象(天気図、気圧配置)
- 火山・岩石(マグマ、噴火タイプ)
◆図表・グラフの読み取りを制す者が勝つ
文章より図やグラフを重視する問題が多いため、視覚情報を読み解く力が差を生みます。
◆出題パターンを「型」として体得
「このテーマはこう問われる」と形式を知っておけば、本番での迷いが激減します。
第2章:知識の構造化と暗記法
暗記のボリュームに圧倒されがちな地学。
しかし、「整理」「視覚化」「比較」ができれば、負担は激減します。
◆図解によるインプット強化
・プレートの動き
・天体の運行
・火山活動
こうしたテーマは必ず“図にして”覚えるのがコツです。
◆時系列整理で気象・天体を攻略
時間の流れとともに変化するテーマ(前線、星の動きなど)は、「経過順」で理解することが重要です。
◆比較で混同を防ぐ
例)示準化石 vs. 示相化石、正断層 vs. 逆断層などは、表で違いを並べて覚えると定着しやすい。
◆アウトプット型暗記で知識を“再現”可能に
・自分で説明できるか
・白紙に図を描けるか
・逆形式で一問一答ができるか
この確認が本番での“初見対応力”に直結します。
第3章:実戦演習と時間配分の管理
知識を「得点」に変えるには、演習をどうこなすかがすべてです。
◆過去問は宝の山
5年分は必須。最初は時間無制限で構わないので、“形式に慣れる”ことを重視しましょう。
◆シャドー演習で集中力を鍛える
10~15分の小演習(分野別)を繰り返し行い、苦手なテーマを潰していくと効果絶大。
◆おすすめ時間配分
・各大問:15分×5題=75分
・見直し・再挑戦:15分
計画的に時間を使えば、ケアレスミスも激減します。
◆直前期の最終調整
・苦手テーマノートの見返し
・模試形式の再演習
・“再現性”の確認(思考手順をたどれるか)
「知っている」ではなく、「使える」状態で仕上げていきましょう。
まとめ:地学は“最も伸びしろのある武器”である
地学は、理科科目の中でも特に“戦略が通用する”科目です。
範囲の広さに圧倒されることもあるでしょうが、「出題の型」を押さえ、「図で理解」し、「繰り返し演習」を重ねることで、確実に9割を狙える実力が身につきます。
他の科目で伸び悩んでいる受験生にこそ、地学を武器にしてほしい。
これを読んでいるあなたが、地学を“得点源”に変えて、共通テストで確かな自信を持てることを、心から願っています。