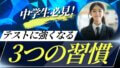お子さんが受験期に入ると、保護者としての悩みは尽きません。
「勉強に口を出しすぎても逆効果では?」「スマホ時間が長くて集中できていないのでは?」
「睡眠不足が続いているけれど大丈夫?」「塾や教材、どれを選べばいいのか迷う…」。
こうした小さな心配は、積み重なると大きな不安になりますよね。
一方で、関わりすぎれば自主性を損ないそうで、放っておけば勉強の遅れが気になる…。
その“ちょうどいい関わり方”をどう見つければいいのか、迷う方も多いはずです。
実は研究からも、親の関わり方次第で学習成果や心理的な安定が大きく変わることが分かっています。
「どんなサポートがプラスに働きやすいのか」「何を避けた方がいいのか」。
具体的なデータや実践的な工夫を知っておくと、不安はぐっと小さくなります。
この記事では、保護者の方が抱えやすい代表的な悩みを整理しながら、心理学や教育学の知見をもとにした“実際に家庭でできる関わり方”をご紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
保護者のよくある悩みと関わり方の土台
「勉強へ声をかけたいけれど、口出ししすぎが怖い」「スマホ時間が長くて集中が続かない」「睡眠が足りず朝がつらい」「どの塾・教材が合うか選べない」…。保護者の小さな不安は積み重なると大きな悩みになりますよね。
実は過去のメタ分析では、中学生において「学業に意味づけを与える関わり(例:進路や科目の価値を一緒に言語化)」は成績にプラスに働く一方、「宿題への過度な直接介入」は逆効果になりやすいと示されています。
つまり、励ます・意味づける・見守る を基本線に据えることが安全策です。
自律性を尊重する関わりの効果
自律性を支える養育は、学業達成・自己調整・心理的健康と良い関連があると報告されています。両親からの一貫した「任せ方」と「温かさ」が揃うと効果が安定しやすいのです。
一方で「グロースマインドセット」など流行の合言葉に頼りすぎるのは危険。標語ではなく、日々の生活に直結する支援を積み上げる 方が再現性が高いと考えられます。
睡眠と生活リズムの重要性
思春期には8〜10時間の睡眠が推奨されています。
特に注意したいのは 夜の強い光やスマホ画面。メラトニン分泌を抑え、入眠を遅らせ、翌日の集中力を削ぐ要因です。
✅ 就寝前1時間は画面オフ
✅ 照明を温かい間接光にする
✅ 起床時刻を固定する
これだけで翌朝の“起きやすさ”が変わります。
スマホとの付き合い方
全国調査でも「動画・SNSを1日3時間以上使うと正答率が下がる」傾向が報告されています。とはいえ、全面禁止は現実的ではありません。
👉 勉強前に機内モードにする
👉 学習アプリ専用のホーム画面を作る
など、使い方を設計して味方に変える のが建設的です。
家でできる学びの工夫
家庭で押さえるべきは 「時間管理」「学習法」「感情調整」 の3点です。
1. 時間管理
「もし〜なら〜する」という 実行意図 を子どもに作ってもらいましょう。
例:「19:30になったらリビングで英語を10分音読」。
これは研究でも大きな効果が確認されています。
2. 学習法
効果的なのは 分散学習×想起練習。
「短時間で繰り返す」「必ず思い出すテストで締める」ことが記憶定着を強めます。
3. 感情調整
- 試験直前の心配の書き出し → 不安軽減に効果あり
- 価値づけの自己記述 → 成績低下を防ぐ効果あり
どちらも家庭ですぐ実践できる低コスト介入です。
やる気を引き出す工夫
勉強開始がつらい日は「ご褒美と作業の抱き合わせ(テンテーション・バンドリング)」が効きます。
例:「好きな音楽は英単語アプリ中だけ」「推し配信は理社の小テスト後」。
行動開始のハードルを下げる現実的な方法です。
情報・教材・経済の整理
- 選択肢は3つまでに絞る → 決め疲れを防ぐ
- 進学資金はシミュレーターで試算 → 不安を数字で見える化
- 手続きは大人が責任を持つ → 子どもは学習に集中できる
本番までの学習戦略
- 模試は“点数の日”ではなく“弱点発見の日”。48時間以内に復習。
- 家庭での短い小テストを分散して繰り返す。
- 週1回の保護者同席レビューで「実行意図」を更新。
- 入試直前は「心配の書き出し」を儀式化。
さらに、2週間前からは 本番と同じ時間に練習 し、生活リズムを合わせていきましょう。
最後に
受験期の家庭は、保護者の関わり方ひとつで「不安の温床」にも「学習の基地」にもなります。
- 意味づけを一緒に言語化する
- 自律性を尊重する
- 実行意図と分散学習で小さな一歩を積み重ねる
- 睡眠・光・スマホを整える
これらを少しずつ実行するだけで、学力もメンタルも安定しやすくなります。
不安は尽きませんが、今日できる一手を行動に変えること が一番の解決策です。