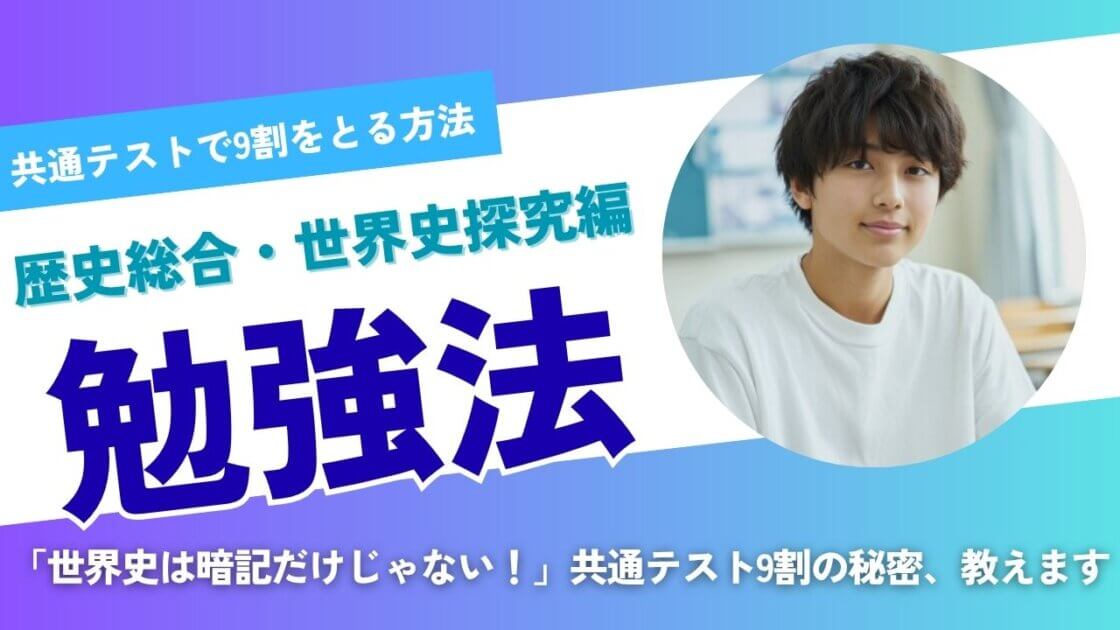共通テストの世界史、以前は「暗記一辺倒」で点が取れた時代もありました。しかし、今や世界史は「読んで考える科目」へと進化しています。資料を読み、因果をつかみ、異なる文明や時代を比較しながら世界の流れを把握する。こうした“視点”が、共通テストにおいて最も重視されている力なのです。
本記事では、共通テストにおける歴史総合・世界史探究で9割を狙うための実践的な戦略を、出題傾向から演習法まで丁寧に解説します。受験生の皆さんに、世界史を“得点源”に変えるための武器をお届けします。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章|共通テスト型世界史の出題傾向とは?
共通テストでは、単純な知識の再生ではなく、「資料の読解」と「比較・因果的思考」が中心です。
- 資料付き設問が主流
文章資料、図表、年表、条文などが毎年登場。読解と処理のスピードが鍵。 - 地域横断・時代比較が頻出
ヨーロッパとイスラーム、日本と東南アジア、冷戦期の複数地域など、“同時期の世界”を比較する問題が多い。 - 因果関係や影響の理解が重要
なぜ起こったのか?どう影響したか?背景を含めた論理的思考力が試される。 - 資料集・論述参考書も活用すべし
資料集や論述形式の参考書を使って、視点の獲得と語彙の補強を行うことで、設問処理力が上がる。
第2章|頻出テーマ×「因果」と「比較」で得点源に
- 宗教と国家の関係性の変遷
政教一致・分離・対立の歴史を軸に、ヨーロッパ・イスラーム・中国の動きを比較して整理しよう。 - 交易ネットワークと経済圏
商品・担い手・影響という3要素で、各交易ルートを構造的に理解。横断比較がカギ。 - 帝国主義と植民地支配
本国と植民地の構造的関係や抵抗運動を、「支配する側・される側」双方から分析。 - 冷戦と第三世界の台頭
アメリカ vs ソ連 の構図に加え、非同盟諸国の独自外交を比較視点で整理する。 - 「縦×横」整理の実践
テーマごとに、「時代の流れ(縦)」と「地域比較(横)」を表や図でまとめるのが効果的!
第3章|実戦演習と“本番力”の鍛え方
- 過去問より模試を活用
「共通テスト型模試」で資料・設問への慣れと時間感覚を養う。 - 資料から問題を作る“逆演習”
自分で問いを作る→出題者の視点を理解できる最強トレーニング。 - 見直しノートでミスを資産化
「なぜ間違えたか」「どうすれば防げたか」を言語化して、弱点を“見える化”。 - マークミス防止術も演習のうち
マークは大問ごと、声出しチェック、本番前の“模試形式演習”でミスを予防!
最終章|世界史が「苦手」から「最強の得点源」へ変わる瞬間
共通テストの世界史は、“ただの暗記”では通用しません。
資料読解、因果理解、地域比較、出題者視点の把握——こうした力が、9割への鍵です。
- 知識×思考=世界史力
- 暗記×構造化=応用力
- 復習×演習=安定得点力
この3つの掛け算が、世界史を“自分の武器”にするための土台になります。