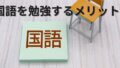国語が苦手だと感じている受験生は少なくありません。本文を何度読んでも筆者の主張が見えず、選択肢もどれも正しく見える。そんな読解の「霧」を抜け出すには、ただ読むのではなく“構造で読む”視点が必要です。本稿では、評論・随筆・小説に共通する読解の仕組みを分解し、「構造」「推論」「設問対応」の三段階で読みを再設計する方法を紹介します。読む力はセンスではなく、順序と型で伸びるのです。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
読解の壁
国語の読解が苦手という声を、とてもよく聞きます。評論文で筆者の主張が見えず、段落ごとの役割が分からない。小説では情景描写に気を取られて、人物の心の変化をつかみ損ねてしまう。そのような迷いから、選択肢問題になると似た表現に惑わされ、どれも正しく見える感覚になるでしょう。また、設問文の条件読み落としで得点を落とすこともありますよね。こうしたつまずきは努力不足ではなく、読みの仕組みと練習の順番が合っていないだけだといえます。
読解は「語・文・段落・全体」という層を行き来しながら、筆者の意図を再構成する作業です。文章は語彙と文法だけでなく、接続関係や段落構成といった「構造の合図」を使って意味を流します。研究では、文章構造の理解や結束性の手がかりをつかむ練習が、読み取りの助けになると議論されています。つまり、表面の言い換えや言葉の難しさに引っかかっても、構造という“足場”を押さえれば前に進みやすいといえます。
また、読みの核には推論力があります。筆者が書いていない行間を、根拠にもとづいて補う力です。本文の語句と文脈をつなげて「だから~と言える」と道筋を作る感覚が、設問の正誤判断を支えます。さらに、読みの途中で自分に説明する「セルフ・エクスプレイン(自分への解説)」は、情報をただ追う読みを避ける助けになります。読み終えてからではなく、段落ごとに「ここで何が新しく、前とどうつながるか」を声に出して確認するとよいでしょう。
ここまでの話を受験勉強に落とすと、まず「本文の構造を先に探す→推論でつなぐ→設問で検証する」という順番に組み替えることが出発点です。語の難度や長さに圧倒されても、順番が決まっていれば迷いが減ります。次の章では、そのための手順を科目内で使えるかたちに整理します!
型で読む
評論文・随筆・小説のどれでも、入り口は「構造の合図」を拾うことから始まります。接続詞や指示語、対比や例示などは、筆者の意図が見えるサインです。最初に段落冒頭の接続表現に丸印を付け、「しかし/一方で」は対立、「たとえば」は例示、「つまり」は要旨化の合図と見立てます。次に、各段落の主張を十数字ほどの短い日本語にまとめ、段落間の関係を矢印で描きます。本文を全部読んでから要旨を作るのではなく、読みながら「今段落の役割」を即座に言い表すのが大切です。
小説では、叙述の焦点に注目します。語り手が見ている対象、比喩が指している感情、景の移り変わりが心情とどう連動しているかを追います。会話文では「言った内容」より「言い方」と地の文の補足に着目します。たとえば、同じ「ありがとう」でも、直前の叙述に「固く」や「視線を落とし」とあれば、素直さではなく距離感がにじんでいると読めるでしょう。つまり、言葉の意味より語り手の配列に目を向けるのが有効です。
語彙は読みの燃料です。ただし、語句の暗記だけに時間をかけると、文脈処理が弱まります。未知語に出会ったら、前後五行の言い換え表現や対比語から意味を仮置きし、読み進めながら修正します。一般に、同段落内にはヒントとなる同義語や上位概念が置かれます。語義を辞書で確定するのは読み終えてからで十分です。さらに、漢語の接頭・接尾の意味(「超」「再」「無」「〜化」「〜性」など)を押さえておくと、初見の語でも当たりを付けられるでしょう。
要約は得点に直結します。段落要旨を並べ替えて、重複を削り、因果や対比の骨格を一本に直します。要約練習のコツは、「誰が・何を・どう主張し・なぜそう言うか」を各段落で一つだけ拾うことです。拾いすぎると雑音が増え、少なすぎると筋が折れます。また、要約は設問の検証にも役立ちます。選択肢が要旨から外れていれば、どれほど言い回しが本文風でも不適合と判断しやすいです。
推論の精度を上げるには、段落ごとに三つの問いを当てます。「何が新情報か」「どこと結び付くか」「書かれていないが成り立つ一歩先は何か」の三つです。たとえば「AはBよりCだ」という主張が出たら、「なぜその順序なのか」「例示は何を支えているのか」を本文の文証に戻って確かめます。ここで大切なのは、自分の常識に頼らず、本文内の語や構造で補う姿勢です。また、自分への説明を短く声に出すと、論旨のずれに気づきやすいでしょう。
読みの手順を習慣化するために、毎回同じ「開始ルーティン」を用います。読む前に設問の種類だけをざっと見て、「要旨/指示語/下線部説明/表現効果/心情理由」などの出題型を頭に置きます。そのうえで本文に入り、段落ごとに合図拾い→要旨化→自分への説明を繰り返します。読み終えたら、設問に戻って本文の該当箇所を必ず線で囲い、根拠の語を丸で囲みます。つまり、本文→設問→本文という往復を“型”として固定すると、毎回の出来の波が小さくなるといえます。
ここまでで構造と推論の型を整えました。次の章では、得点に直結する設問対応を、設問タイプ別に細かく解いていきます!
設問対応
要旨問題は、段落要旨のつなぎ方を見抜く設問です。選択肢の常套パターンは「範囲の拡大縮小」「因果の逆転」「対比の片落ち」「例と主張の取り違え」です。本文の骨組みに対応づけ、選択肢の文中に本文の語が“どの順番で”現れているかを確かめます。語が合っていても、並び順が本文の論法と違うなら不正解のことが多いでしょう。迷ったら、本文側で「要旨を一文で言い直す」作業を挟むと判断しやすいです。
指示語問題は、直前直後の内容だけでなく、段落の主張に結び付く“まとまり”を探します。「これ」「それ」「そして」などの指示が指す範囲を、文単位ではなく“内容の塊”として特定します。選択肢では、指示の範囲が広すぎたり狭すぎたりすることで誤りが生じます。本文に戻って、指示語の直後に置かれた言い換え表現を併せて確認すると、範囲のぶれを抑えられるでしょう。
下線部説明は、言い換えの筋が鍵です。比喩なら評価語と対象を分け、評価の方向(肯定・否定・揺れ)をはっきりさせます。評論なら、下線部の前後三行に補助説明があることが多いです。その説明を“素”にして、難しい語を平易に置き換え、論旨の役割語(対比の相手、原因、結果、目的)を補って一文にします。また、説明文の語尾は推測ではなく「〜と述べている/〜を表している」と本文の態度に合わせるのが大切です。
表現効果は、語の働きを「視点・距離・リズム・強調」に分解して考えます。たとえば体言止めがあれば、余韻や焦点化の効果を指摘しつつ、何に焦点化しているのかを本文語で特定します。繰り返しは、同義反復による強調か、語の幅をずらす階段的強調かで読み分けます。比喩は、共通点だけでなく“ずれ”が何を示すかまで踏み込みます。つまり、効果語だけでなく対象の内容を本文語で答える姿勢が大切です。
小説の心情理由は、地の文の描写語と会話のズレを根拠にします。会話が軽くても地の文が重いなら、表出と内心がずれているという読みになります。情景の変化(光・音・温度・距離)は心情の動きとリンクします。表層の出来事を並べるのではなく、「変化前→きっかけ→変化後」という三点で書くと説得力が上がるでしょう。また、人物相関で立場が逆転する瞬間を見つけると、山場の心情が明確になります。
実戦での練習は「短時間・高密度」に寄せます。大問一題をすべて解かなくても、要旨・指示語・下線部説明など型ごとに切り出して鍛えます。本文の構造把握だけを三題連続でやる、要約だけを五分間で二題処理する、といった練習が効率的です。演習後は、本文に「どの合図が役に立ったか」「どの推論が外れたか」を印で残します。外れた推論は、本文のどの語を読み落としたのかを突き止め、次回の注意語に昇格させます。さらに、週に一度は自分の解答を友人や先生に読み上げ、根拠の出し方が本文に即しているかをチェックするとよいでしょう。
最後に、背景知識の扱いです。ニュースや他教科の学びが、評論文の理解を助けることがあります。ただし、設問判断は本文内に閉じるのが安全です。背景知識は推論の候補を広げる“発想の源”として使い、最終判断は本文の語と構造に戻して行います。こうした切り替えができると、似たテーマでも迷いが減るでしょう。つまり、本文外の知識は広げるために使い、答えを確定するのは本文の証拠で行うのが大切です。
最後に
読み負けの正体は、語や長さではなく、構造と推論と設問対応の順番が定まっていないことにあります。だからこそ、入り口で「合図を拾う→要旨化する」という型を置き、中盤で「推論を本文語で結ぶ」意識を持ち、終盤で「設問タイプ別の検証」を徹底するとよいでしょう。小説は焦点と描写語、評論は論の骨組みと因果・対比、共通するのは“本文に戻る往復”です。
今日からできる一歩は、小さな型の固定です。段落冒頭の接続語に丸、要旨を十数字、推論を一言、根拠語に印。これだけでも、手の動きが読みを支えます。練習は短時間で高密度に、型ごとに分解して回すと定着が早いでしょう。また、外れた推論を次の注意語に変える循環が、受験期の伸びを作ります。つまり、読解はセンスではなく設計です。設計が決まれば、得点は安定して上がるでしょう!