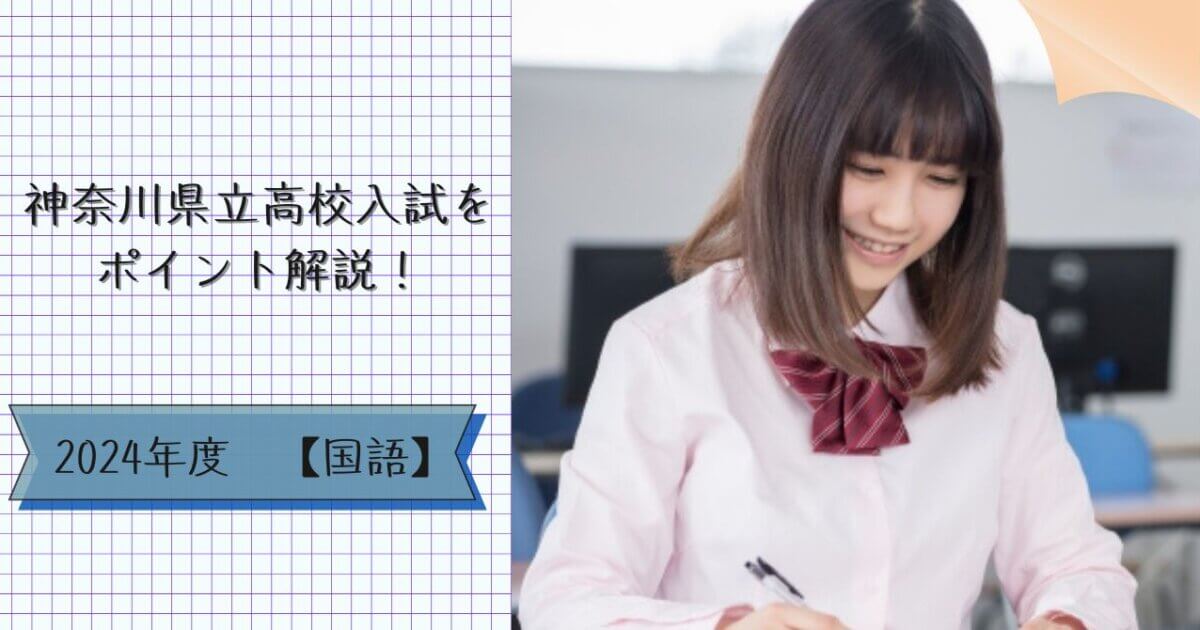2024年度神奈川県立高校入試では、漢字の読み書き+短歌・文学的文章・論理的文章・古文・
論理的文章の5題構成になっています。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
大問1(漢字の読み書き)
〈解答〉
(ア)a3 b4 c4 d2
(イ)a1 b4 c2 d3
(ウ)1
〈解説〉
(ア)漢字の読み(選択肢)
「固唾」・「辛辣」・「逸材」・「拙い」の読みが出題。
(イ)漢字の書き取り(選択肢)
傍線部の漢字と同じ漢字を含むものを選ぶ問題。 a紅潮
1、潮流 2、包丁 3、兆候 4、山頂 b沿革
1、塩分 2、声援 3、実演 4、沿岸 c資格
1、司会 2、投資 3、雑誌 4、詩集 d推しはかる
1、反省 2、心酔 3、推移 4、斉唱
(ウ)短歌の鑑賞(選択肢)
2について、「激しく音を立てる」様子を「かがやく」と表現するのは無理があるので、誤り。
3について、「瀑布のごとくかがやく階段」は、「瀑布のような階段」という意味である。目の前にあるのは「瀑布」ではなく、「階段」のはず。
4について、階段を降りる人を流れ落ちる滝の水に見立てるのは無理がある。また、「かがやく」と平仮名を用いることで「感動」が強調されるわけでもない。
大問2(文学的文章)
高森美由紀『藍色ちくちく』からの出題です。
〈解答〉
(ア)3 (イ)3 (ウ)2 (エ)1 (オ)4 (カ)4
〈解説〉
(ア)理由説明(選択肢)
「年頃になったより子は真っ黒な父が恥ずかしかった」ので、父が「学校に寄っ」たときは「こっそり帰っていた」。「ある時、こそこそすることが理不尽に思えた」より子は「憤」り、父を「罵っ」てしまう。そのときの父の顔は、「深く傷つい」ているのに、「情けないような笑みを懸命に浮かべてい」る顔であった。「まずいことを言ってしまったとより子はヒヤリとした」のである。
1について、「『父』が仕事で汚れた姿を気にしていた」が誤り。また、「からかう」という表現も「罵る」と合わない。
2について、「本心ではないことを言ってしまった」が誤り。
4について、「『父』に感謝しつつも」が誤り。また、「自分の行動が許せなくなっている」も言い過ぎである。
(イ)内容読解(選択肢)
父は「自分は真っ黒でみっともない。だから一緒には行けない。あとから馬で行く」と決めていたが、そこにより子が一緒に行くと言い出した。
「父は初めは戸惑っていた」が、「ついに折れた」のである。
「はにかむ」は「恥ずかしがる」という意味。ただし、馬で嫁入りするという世間体が悪い行動に対してではない(もしそうなのであれば、あとの娘との会話も変わってくるはずである)。娘と一緒に行くことが嬉しくも気恥ずかしかったのである。この点を押さえていない2と4は誤り。
1について、「娘に恥をかかせることはないと安心して晴れやかな気持ちになっている」が誤り。
(ウ)内容読解(選択肢)
「生家がどんどん遠ざか」り、「切なくなっ」たより子は、故郷を離れるペースを落とすべく休憩を提案するが、「大丈夫だ」といわれてしまう。「どんどん流れていく」景色にさらに切なくなっている。
(エ)内容読解(選択肢)
嫁入りという晴れの日に、自分が子どもの頃に刺繍を縫った下ばきを父が履いているのを見て、より子は「照れくさくて嬉しくて、どういう顔をしていいのか決めかね」ている。
それで、父に顔を見られない「父の後ろに座っていてよかった」と思っているのである。
2について、「『父』の顔を見て泣いてしまうのが不安で後ろに座った」が誤り。また、「後ろに座っていてよかった」とより子が思った理由の説明も誤っている。
4について、「嫁入りの日には泣かないと決めていた」が誤り。また、この時点でより子は泣いてもいない。
(オ)内容読解(選択肢)
「親というものはどこまで考えているのだろう~真っ黒になってより子たちを養ってくれていた」ことに思いを致すとともに、「やっと父に謝ることができ」て父からも許され、より子は感極まって泣いている。
(カ)内容読解(選択肢)
1は、「目の前に広がる故郷の風景を見て心を和ませ」で切れる。
2は、「結婚祝いで洗濯機を贈られたことをきっかけとして、『父』と再び言葉を交わすようになるまでの過程」で切れる。
3は、「一緒に嫁入り先に向かう~期待を高めていく」で切れる。
大問3(論理的文章)
〈解答〉
(ア)1 (イ)2 (ウ)4 (エ)1 (オ)4 (カ)1 (キ)2 (ク)2
(ケ)3
〈解説〉
(ア)接続詞挿入(選択肢)
A:衣服を使ってのコミュニケーションの難点として、「細かいニュアンスを伝えることができない」・「意味の変化が早すぎる」・「広がる範囲が狭すぎる」に加え、「伝播していく過程で~内容を検証できなくなっている」点を指摘している。「さらには」か「そして」が入る。
B:直前の段落で、「衣服は、それだけで意味を持つ単語とは言い難いし、ファッションも、文法の存在する言語の一種とは言い難い」と述べているが、直後で「視覚的な情報に言語が必ず添えられる」と述べ、ファッションと言語の関わりが皆無ではないことを付け加えている。
(イ)文法(選択肢)
連体修飾格の「の」を選べばよい(例:私のペン)。
1は主格、2は接続詞「のに」の一部、4は準体言である。
(ウ)対義語(選択肢)
「需要」の対義語は「供給」である。
(エ)理由説明(選択肢)
解答の中心として、「ただ書かれたままのメッセージを伝えているわけではない」・「文字が書かれているからといって~場所や状況が違うということもない」を押さえる。
(オ)内容読解(選択肢)
直前の「衣服が、形や色の組み合わせによって言語として機能し、意味を伝えうるのではない か」に着目する。さらに「つまり」と続いて「衣服は、言語化できない感情や感覚を~発信することも可能だ」と言い換えられている。
(カ)理由説明(選択肢)
「衣服の意味は、着ている人が所属する社会集団によって~それがどんな意味をもつか確定することはでき」ず、「結局、流行の服の解読を試みたところで、ただ『新しい』という社会的な合意しか見つからない」ので、筆者は「強引な読み」と述べているのである。
3は解答要素として必要なキーワードを含んではいるが、本文には述べられていない内容になっているので誤り。
(キ)内容読解(選択肢)
「むしろ同じ対象に、いくつもの意味を読み出せる」という要素を正しく書けているのは1と2。1は、「個人に合った意味を選択することができ」るという本文にはない内容を述べているので誤り。
(ク)内容読解(選択肢)
まずは傍線部の「そういった無駄とも思える言語活動」の指示内容を考える。「マスメディアでは、流行についての解説や評論が~跡形もなく消えていく」を押さえよう。
しかし一方で、「言語活動によってはじめて~警鐘を鳴らすことができるようになる」と述べている。
(ケ)内容読解(選択肢)
1は、全体が本文にはない内容となっている。
2は、「衣服と文字が歴史的にどのような関係を作り上げてきたかを分析する」が誤り。 4は、「ファッションにおける流行に惑わされない方法」が誤り。
大問4(古文)
『古事談』からの出題です。
〈解答〉
(ア)1 (イ)2 (ウ)4 (エ)3
〈解説〉
(ア)内容読解(選択肢)
「このこと」とは、顕季と義光との領地争いのことである。
「理非顕然(=道理にかなっているかどうかが明白であるさま)」であるのに、白河法皇が「未断」であることを「術なきこと」だと述べている。
(イ)内容読解(選択肢)
顕季が涙を流したのは、白河法皇の発言を受けてのことである。
「道理に任せて裁許せしむれば~猶予するなり」を押さえよう。道理に任せて判断すれば、土地は顕季のものになるが、それだと武士が邪念を起こすのではないかと懸念していた、というのである。
(ウ)内容読解(選択肢)
「ここに心中に御計らひのやむごとなきを思惟す」とあるので、2は誤り。
1は「領地を失ったばかりか家来まで手薄になってしまった」、3は「気落ちしていることに同情した」がそれぞれ誤り。
(エ)内容読解(選択肢)
1は、「領地を譲ることを自ら『白河法皇』に願い出た自分の判断」が誤り。 2・4は、全体が誤り。
大問5(論理的文章)
〈解答〉
(ア)3
(イ)偶有性を確保しつつ、人間が何かを達成するときの手助けとなる
〈解説〉
(ア)内容読解(選択肢)
Ⅰ:2段落目の冒頭「技術の発明や改良を考えるのが楽しい研究者の側から何ができるかを追求していくだけではなく」と、最終段落の「昔から発明、改良されてきたさまざまな技術の多くは、人間の肉体的な重労働を軽減するものだった」に着目する。答えは3か4に絞れる。
Ⅱ:筆者は、「『他でもあり得た』部分が確保されている」ことを重視している。したがって、4は誤り。
(イ)内容読解(25字~35字記述)
【Aさんのまとめ】の第1段落に注目する。Aさんは、人間が充実感を得て幸せに暮らすために は、「自分で何かを達成する」ことが必要だと述べている。さらに【文章2】で述べられている「偶有性」も確保するべきだと第2段落で説明しているので、以上の2点を制限字数内にまとめればよい。