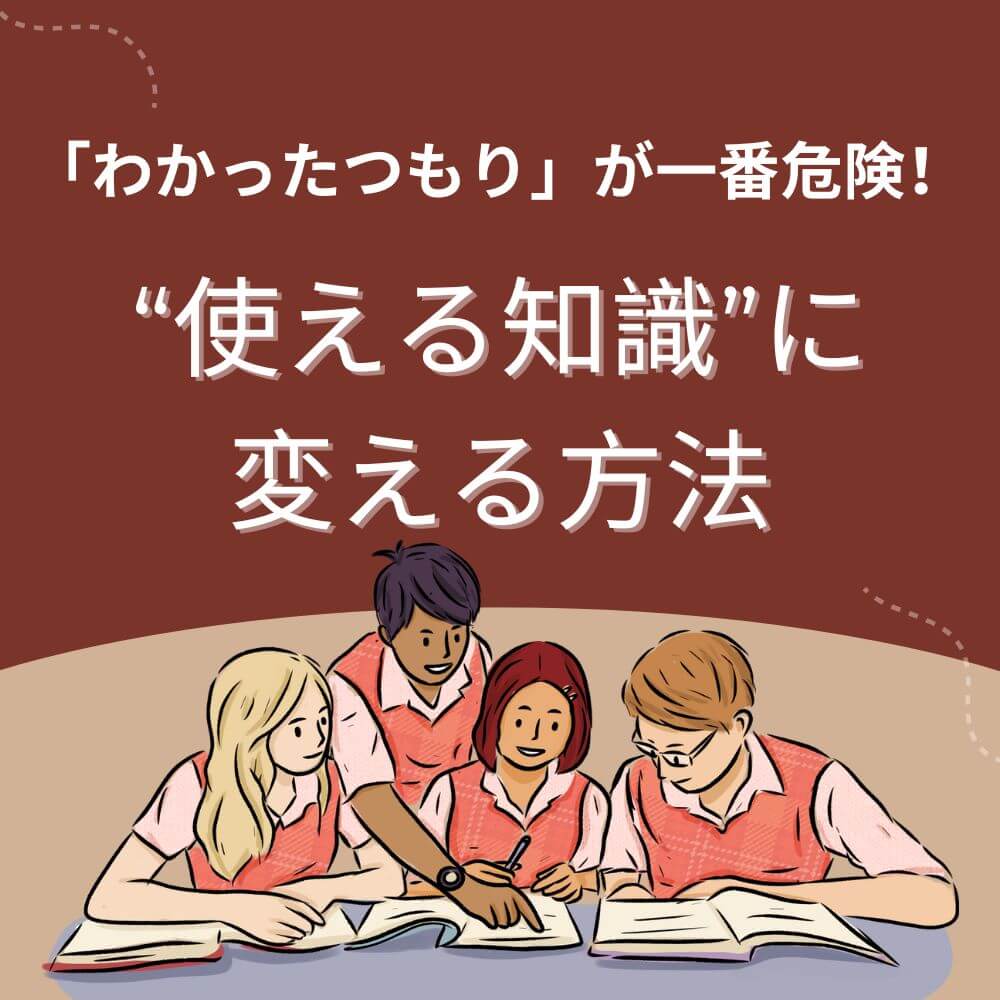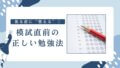参考書を読んで「もう大丈夫」と感じたこと、ありませんか?
授業を一通り受けて「なんとなく理解できた」と思っていたのに、模試や過去問で思うように点が取れなかった——。
そんな経験をしたことがある人は多いはずです。
この「理解したつもり」、実は心理学で「流暢性の錯覚」と呼ばれる現象。
人は“スラスラ読める”“理解できた気がする”という処理のしやすさを、「身についた」と錯覚してしまうのです。
けれど、その“なんとなく”は、本番では力になりません。今回は、そんな「つもり学習」を抜け出し、本当に使える知識に変えるための方法を解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
「理解したつもり」の正体
教科書を読み返して内容が追えると、「理解できた」と思いがちです。
でも、それは“情報の流れを処理できただけ”の状態。
脳が「スラスラ読める=理解した」と勘違いしてしまうんですね。
この錯覚の怖いところは、学習の進行を止めてしまうこと。
「もうわかった」と思ってしまうと、復習や演習の優先度が下がり、定着が浅くなります。
少し形式が変わるだけで解けなくなるのは、そのせいです。
しかもこの現象、意外にも上位層ほど陥りやすい。
処理スピードが速い人ほど、「理解した」と思いやすいんです。
だからこそ、「本当に理解できているか?」を自覚的に点検する姿勢が欠かせません。
「理解」と「定着」はまったくの別物
勉強における「理解」と「定着」は似ているようで全然違います。
理解とは、内容を整理して説明できる状態。
一方、定着は、それを自在に使える状態です。
入試で必要なのは後者。「わかる」だけでは得点に結びつきません。
例えば、数学の公式を「なぜそうなるか」まで理解していても、問題の中で使いこなせなければ意味がない。
英語でも、文法を頭で知っているだけでは長文読解に活かせません。
知っていることと、使えること——この差が合否を分けます。
そして、理解と定着をつなぐ鍵がアウトプット。
脳は「使った情報」ほど記憶に残る性質があります。
自分で説明する・演習する・想起する。
この“能動的な学び”こそ、記憶を長期化させる最大のポイントです。
「つもり学習」を引き起こす心理
なぜ人は「理解したつもり」に陥るのでしょう?
それは、人間が不安から逃れたい生き物だからです。
勉強は基本的に「努力と不安の連続」。
難しい問題に挑むたび、「できない自分」と向き合うことになります。
その不安を避けようと、「わかった」と思いたくなるんですね。
でも、その安心感が油断を生みます。
「もう大丈夫」と思ってしまうと、復習や演習を後回しにしてしまう。
結果として「勉強してるのに伸びない」状態に陥るわけです。
特に、授業を聞く・動画を見るなどの“受け身学習”は要注意。
理解できた気分にはなりますが、実際には定着していません。
まずは、「今の自分がどの段階にいるのか」を常に点検すること。
「読んで理解」「説明できる」「使える」——この3段階を意識するだけで、学びの質が変わります。
失敗例から見る「理解止まり」の危険性
ある受験生は、化学の教科書を何度も読み返しても点数が伸びませんでした。
原因は、「用語を見ればわかる」だけの状態にとどまっていたから。
実際には、自分で説明したり、条件が変わっても対応する力が育っていませんでした。
別の生徒は、英語の文法問題集を完璧にしても、長文で点が取れませんでした。
それは、文法を“知識”として覚えただけで、運用力が伴っていなかったためです。
「読めばわかる」は理解ではありません。
「何も見ずに説明できる」「別の問題でも使える」「一度間違えても修正できる」——
この3つをクリアして初めて、“本当の理解”に到達します。
「使える知識」に変える実践法
“つもり学習”を脱するには、受け身から能動へ切り替えることが大前提。
ここで効果的なのが次の2つです。
① 自力説明法
教材を閉じて、自分の言葉で内容を再構成します。
たとえば歴史なら「なぜその戦争が起きたか」「社会がどう変化したか」を説明する。
英語なら「この構文がなぜこの形になるのか」を自分で図にして話す。
説明できない部分こそ、“理解したつもり”で止まっている証拠です。
② セルフテスト
自分で問題を作る、解説を隠して解く、間違えた理由を言語化する。
この「問い直す学習」は記憶を定着させ、応用力を伸ばします。
“なぜ間違えたか”“どうすれば解けたか”まで考えることで、使える知識に変わります。
応用力を育てる4ステップ
学習は段階的に積み上げることが大切。
いきなり過去問に挑むより、以下の4ステップを意識しましょう。
1️⃣ 基礎理解:用語や原理を丁寧に押さえる。丸暗記ではなく「なぜ?」を考える。
2️⃣ 自力説明:自分の言葉で説明し、構造化する。
3️⃣ 演習・応用:基本→標準→応用へステップアップ。形式が変わっても引き出せるか確認。
4️⃣ フィードバック:間違いの分析。「自信があったのに間違えた」問題は要注意。
このサイクルを回すことで、「知っている」から「使える」へと成長します。
深い理解をつくる「思考の癖」
“つもり学習”から抜け出すには、表面的な暗記ではなく「構造的に考える」力が必要です。
数学なら定理同士の関係を考える。
英語なら構文の使われ方、類似表現との違いを整理する。
こうした「比較・関連・再構成」の思考が、知識を断片から体系へ変えていきます。
また、異なる科目を横断して考えるのも効果的。
日本史と世界史をつなげて考える、数学の公式を物理で応用するなど、知識のネットワークを広げることで応用力が飛躍します。
自己点検の仕組みをつくる
最後に、「理解したつもり」を防ぐには定期的な自己点検が欠かせません。
おすすめは、週1回「自分模試」を設定すること。
制限時間を設けて解き、自己採点し、「なぜ間違えたか」を記録します。
また、単元ごとに以下のチェックリストを作るのも効果的です。
- 読んで理解できる
- 説明できる
- 問題で使える
- 別形式でも使える
どの段階にいるかを見える化すれば、“つもり”のまま進むリスクを防げます。
「できていない自分」に気づくことは、成長の第一歩です。
まとめ:わかるだけでは、戦えない
「理解したつもりになる」――それは誰にでも起こる自然な心理です。
でも、対策次第で結果は大きく変わります。
大切なのは、受け身ではなく能動的な学びへ切り替えること。
そして、想起・説明・演習・応用というサイクルを回し続けること。
知識を“構造化”し、定期的に点検すれば、「わかったつもり」は確実に“使える力”に変わります。
受験で問われるのは、「どれだけ覚えたか」ではなく、
「どれだけ使いこなせるか」。
今日から“読む勉強”をやめて、“使う勉強”に変えていきましょう。