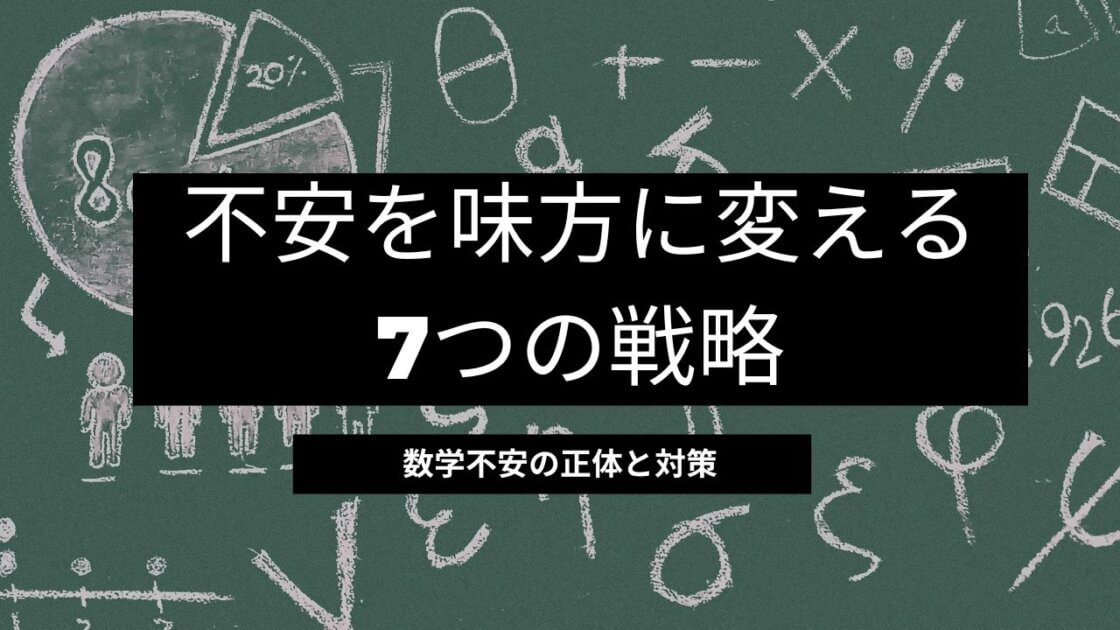「数式を見るだけで緊張してしまう」「文章題になると頭が真っ白になる」──そんな経験はありませんか?
実はこれ、単なる苦手意識や努力不足ではなく、心理学や脳科学の研究で“数学不安症(Math Anxiety)”と呼ばれている現象です。
大学受験において数学は避けて通れない科目だからこそ、この“不安の正体”を知り、正しく対策を取ることがとても大切になります。
この記事では、研究成果をもとに数学不安のメカニズムを整理し、その克服法を7つの戦略に分けて紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
数学不安とは?その正体
数学不安は「数学に関連する活動で不安や恐怖を感じ、成績や学習行動に悪影響を及ぼす状態」を指します。
研究では、数学不安と成績には中程度の負の相関(おおよそ r = −0.28)があることがわかっています。
さらに、脳科学の視点からも「数学に直面する前から痛みに関連する神経回路が反応する」ことや、「不安によってワーキングメモリ(頭の作業台)が圧迫され、途中式が保持できなくなる」ことが示されています。
また、数学文章題の理解には算数力よりも語彙力や構文理解が大きく影響していること、そして「女子は数学が苦手」という社会的な刷り込みが成績を下げる“ステレオタイプ脅威”もあることがわかっています。
つまり数学アレルギーは単なる能力不足ではなく、「心理・言語・社会」の要因が複雑に絡み合った現象なのです。
数学不安を和らげる7つの戦略
1. 小さな成功体験を積む
段階的に理解できる課題を積み重ねることが恐怖回路を弱める鍵です。実際、個別指導を受けた生徒では不安の低下が確認されています。
2. 不安を「集中のサイン」に変える
試験前のドキドキを「失敗の前触れ」ではなく「集中の準備」と再解釈するだけで成績が上がることが報告されています。
3. 具体から抽象へ(CRA学習法)
具体物(ブロックや図)→表象(グラフや数直線)→記号(数式)と段階的に学ぶと理解が深まり、不安も軽減します。ジェスチャーを取り入れるのも効果的です。
4. 比較して学ぶ
解法を比較しながら「どこが同じでどこが違うか」を言語化することで理解が進みます。誤答を比較することも有効です。
5. 言語的負担を減らす
文章題は数直線やバー・モデルなどで図示してから式に変換することで、読解負担を減らし理解がスムーズになります。
6. 呼吸法で整える
試験直前に「鼻から4秒吸い、6秒吐く」を繰り返すリズム呼吸を取り入れると、不安が和らぎ集中力も回復します。
7. 基礎計算の自動化
Cover–Copy–Compare(カバー・コピー・コンペア)法で計算を練習すると、短期間で基礎スキルが安定し、安心感が得られます。
実践!4週間の学習プラン
- 第1週:不安の棚卸し
どの場面で不安が強まるかを書き出し、弱い部分から克服していきます。 - 第2週:具体から抽象へ
関数なら「ゴムひも → グラフ → 式」のように段階的に理解を進めます。 - 第3週:比較学習と文章題の工夫
正解と誤答を比べて理解を深め、文章題は図式化して処理。家庭でも親子で取り組めます。 - 第4週:試験本番対策
呼吸法で整え、最初はやさしい問題から取りかかる。終わったら「工夫メモ」を残し、次につなげましょう。
保護者にできるサポート
- 言葉を図や式に変換する手伝いをする
- 姿勢や呼吸を一緒に整える習慣をつける
- 小さな達成を一緒に喜び、次の学習計画につなげる
まとめ
数学不安は根性や努力不足の問題ではなく、心理・脳・言語・社会的要因が絡む現象です。
克服のためには、
- 小さな成功体験
- 不安の再解釈
- 具体から抽象への学び
- 比較学習
- 言語負担の軽減
- 呼吸法
- 計算力の安定化
といった複数の方法を組み合わせることが大切です。
今日から少しずつ取り入れるだけで「怖さ→回避」のループを「整える→一歩進む」に変えることができます。
数学への恐怖は必ず弱められる──そう信じて一緒に取り組んでいきましょう。