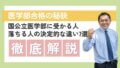医学部=人生安泰?それ、本当にリアルですか?
「医学部に入れば一生安泰」「華やかなキャンパスライフが待っている」そんなふうに思っている人、きっと少なくないですよね。でも、正直に言います。それ、幻想です。
もちろん、医学部に入るまでの道のりはとても厳しい。でも本当に大変なのは、入ってからなんです。
僕自身、「入っちゃえばなんとかなるでしょ」と思っていた一人でした。
でもその考えは、入学してすぐに打ち砕かれました。
毎日の授業に追われ、試験に追われ、レポートに追われ、寝不足のまま次の課題……。
そんな生活が、1年、2年と続いていきます。
そしてその中で、甘さや未熟さ、人との距離感と何度も向き合わされました。
医学部とは、単に「勉強ができる」だけではやっていけない場所。
人間力そのものが問われる、厳しい環境なんです。
今回は、僕自身の体験や周囲の仲間たちの話をもとに、
「医学部入学後に絶対に知っておきたい7つのリアル」を、包み隠さずお伝えします。
受験を目指す高校生、医学部を夢見る中高生、そして子どもを応援する保護者の方に向けて、
本当に役立つ情報をまとめました。
この“7つのリアル”を知っているかどうかで、入学後のスタートがまるで違ってきます。
本気で医学部を目指すなら、今こそリアルを知ってください。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格85名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
【リアル①:授業は“詰め込み”で量がえげつない】
まず最初のリアル、それは授業と課題の「量」がとんでもないということ。
高校までは、1日に学ぶ内容も限られていて、しっかり復習する時間も確保できたという人が多かったかもしれません。 でも医学部に入ると、その常識は一変します。
授業は1日5コマから6コマが当たり前。しかし一コマ60分。「え、それだけ?」と思うかもしれませんが、問題はその後。
その授業すべてに関連するレジュメや教科書、教員指定の文献を読み込まなければならず、 そのうえで毎週のようにテスト、課題、レポート、実習の予習・復習が容赦なく課されます。
たとえば、僕が2年生のときの1週間を例に出すと:
- 月曜は生理学の講義と解剖実習
- 火曜は薬理学の講義と解剖実習
- 水曜は解剖学の講義と解剖実習
- 木曜は生化学の講義と解剖実習
- 金曜は生理学の講義と解剖実習
しかもその間に、生化学の小テストも入ってくる。
1日休むだけで、「その日の分の内容+関連する課題」が翌日以降に重なり、 結果として1日休んだツケが2週間続く`みたいな事態になります。
医学部の授業はすべて連続性があって、積み上げ式。 「昨日の内容が理解できていないと、今日の講義が何を言っているのかわからない」 という状態が続くので、“とりあえず出るだけ”では無意味です。
さらに、暗記量も常識を超えます。 細胞の構造、代謝経路、神経の走行、筋肉の起始停止、ホルモン、疾患の分類、 薬の名前とその作用、副作用、代謝経路……。
これらすべてを、試験前に一気に詰め込む必要があります。 「今までの試験勉強とは次元が違う」と、多くの学生が口をそろえて言います。
高校まで優等生だった人ほど、医学部に入った途端に「人生で初めて落ちこぼれた」と感じることも。
「努力すれば追いつける」という考え方すらも、現実には厳しい。 最初から全力で走り続けるしかない。
これが、医学部に入った学生がまず最初にぶち当たる“現実”です。
【リアル②:解剖実習でメンタルやられる人もいる】
次のリアルは、“解剖実習”の精神的インパクトです。
医学部のカリキュラムの中でも、解剖実習は最も重要で、そして最も重たい授業のひとつです。 実際のご遺体を用いて、人間の体の構造を学ぶ。そう聞いただけで、「えっ…?」と感じた方もいるかもしれません。
けれどこれは、すべての医学生が通る道であり、“医師になる”という覚悟を試される瞬間でもあるのです。
実際、僕の学年でも、解剖実習の初日に教室に入っただけで涙を流してしまった人、 緊張と不安で手が震えてしまい、手袋をうまくはめることができなかった人が何人もいました。
それくらい、精神的には本当にきつい経験です。
なぜかというと、そこには“リアルな死”があるからです。 教科書ではなく、実際のご遺体。そこに向き合うというのは、ただの知識を得る行為ではありません。
私たちは、ただ観察する側ではなく、「直接触れる」側になります。 メスを入れるときの感触、筋肉や神経の質感、骨の硬さ、 そういったものすべてが、“人間”を強烈に感じさせるのです。
そして何より大切なのは、そのご遺体が、 すべて「未来の医療のために」との想いで、 自らの意志で献体してくださった方のものであるということ。
その事実は、医学生にとってものすごく重く、そしてありがたいものです。
私たちは、ただの“教材”としてではなく、 “人生の最期をかけて教えてくれる先生”として、 一人ひとりのご遺体と向き合います。
解剖実習は、 医学生にとって「命に真正面から向き合う」最初のステージであり、 “医師としての覚悟”を持つきっかけになる、かけがえのない学びの場でもあるのです。
終わったあとの成長実感は、言葉にできないほど大きいです。
「人間の身体って、こんなに緻密なんだ」 「命って、こんなにも尊くて、重たいんだ」
そんなリアルな感覚を、机の上ではなく、 “人間そのもの”から学ぶ。
これも、医学部の現実です。
そして何より、医師という職業の第一歩であることを、全身で実感できる体験なのです。
【リアル③:サークル・バイト・恋愛は“できる”、でも地獄を見る可能性も】
「医学部って、やっぱり勉強だけ?サークルとかバイト、恋愛なんて無理なんじゃ?」 そう思っている人、正直多いと思います。でも、実際のところは──できます。ただし“覚悟”が必要です。
医学部にもサークル活動はたくさんあります。 バスケ、軽音、茶道、ダンス、地域ボランティアなど、多種多様。 他学部との交流もあるし、文化祭や学園イベントも充実しています。
バイトをしている人も多く、家庭教師、塾講師、飲食店、ジムの受付など、自分に合った働き方を選んでいる人もいます。 さらに恋愛。もちろんカップルもいますし、学内で付き合ってそのまま結婚する人も珍しくありません。
つまり、やろうと思えば全部できる。これは事実です。
でも、問題は「どれだけ計画的に時間を使えるか」。
僕自身、軽音部に所属しながら、趣味である筋トレのために週5−6回ジムに通い、土日に病院の夜勤のバイトもしていました。 その生活は最初は楽しいものでした。でも、期末試験が近づくにつれ、一気に崩壊します。
「この日バイト入れちゃったけど、明日解剖のテストだ…」 「サークル合宿が最高すぎて、帰ってきたらレポート締め切り過ぎてた…」
そんな後悔の連続。試験の結果はガタ落ちし、自己嫌悪に陥る。 最悪の場合、それが進級にも影響する。
これは医学部あるあるです。
医学生は、1年中テストや課題、実習、レポートに追われています。 ミニテストや口頭試問が毎週あるのも当たり前。 つまり、「空いてる時間」なんてないんです。
そこで必要なのが、自分のスケジュールを客観的に見る力。
「今はちょっと遊んでも大丈夫な時期」なのか、 「もうすぐ試験だからすべて抑えるべき時期」なのか。 このフェーズ管理ができていないと、全てが破綻します。
逆に、このスキルが身につけば、 バイトも趣味も恋愛も楽しめるし、心にも余裕が出てきます。
事実、試験期間前に全予定を完全にシャットアウトし、 その分試験が終わったら旅行や推し活を全力で楽しんでいる人もいます。
大切なのは、「忙しいからできない」じゃなくて、 「忙しいからこそ、どう工夫して楽しむか」。
医学部は“勉強の場所”であると同時に、“人生経験の場所”でもあります。 戦略的に動けば、6年間を思いっきり充実させることは可能です。
でもそれは、「本気で自己管理ができる人」だけに許される自由なんです。
【リアル④:試験のスパンが短すぎて常に追われる】
さて、次に紹介する医学部のリアルは、 「試験のスパンが短すぎて、常に何かに追われている状態が続く」ということです。
一般的な大学では、学期末に試験がまとめて実施されることが多いですが、 医学部では、そういった“学期末一発勝負型”ではありません。
むしろ、毎週何かしらのテストがあるのが当たり前の世界なんです。
たとえば、
- 解剖の授業では、毎週のようにミニテストが実施される
- 生理学や薬理学では、ユニット(章)ごとに中間試験があり、成績に直結
- 実習科目では、レポート提出+口頭試問が求められ、対話形式で知識を問われる
こういった評価項目が複合的かつ頻繁にやってくるため、 「今週はテストがない」という感覚は、ほぼありません。
むしろ、「この1週間のうちに何個の課題と試験をこなせばいいんだ?」 というレベルの過密スケジュールになることも。
さらに試験の内容も非常に厳しく、 「講義10コマ分まるごと出題」や、「参考資料も含めた内容から出題」など、 対策範囲が広すぎて、“復習していなければ太刀打ちできない”構成になっています。
しかも、それぞれの試験において“一発アウト”のリスクも高い。
科目によっては、1回の試験を落としただけで再試験が確定。 再試験もただの救済措置ではなく、
- 内容が本試よりも難しい
- 合格点が高めに設定されている
- 落ちたら留年の危機 というケースも珍しくありません。
そのため、常に一定の緊張感を持ちながら、学習を継続する必要があります。
僕自身も、試験対策には“日々の積み重ね”が最も大切だと痛感しました。
おすすめなのは、
- 毎週末にその週の授業を全て復習する“定点チェックデー”を作る
- グループで定期的に小テスト対策のクイズ出し合いをする
- 過去問や要点ノートを定期的に更新・整理しておく
こうすることで、“溜めない学習サイクル”を維持できます。
また、医学部は“賢い人ばかり”が集まる環境なので、 「周りがどんどん先に進んでいる」ような焦燥感も生まれやすいです。
その中で自分のペースを保ち、 確実に前に進むには、地道な習慣化こそが最大の武器になります。
医学部の試験はマラソンです。 目の前の1本1本の試験を、丁寧に、粘り強く、積み上げていく覚悟が求められる。
それが、医学部という場所で生き抜くための鉄則です。
【リアル⑤:進級・留年は現実的に起こる】
「医学部って、入るのが難しいから、入ったらあとはなんとかなるんじゃない?」 そんなふうに考えている人、もしかしたらあなたもその一人かもしれません。 でも、現実は違います。
医学部には“進級”というもう一つの大きな壁があります。 しかも、それは想像以上に高く、そしてシビアなものなんです。
僕の周りでも、まじめに授業に出ていたし、課題も提出していたのに、 たった1科目の試験で足を取られ、進級できなかったという人がいました。
医学部では、基本的に「すべての科目で合格」が求められます。 一つでも落とすと、進級判定に引っかかり、再試験対象になります。
その再試験、優しそうに聞こえますが── 実は本試験より難しいケースが多い。 ・出題範囲がより広い ・応用問題が中心 ・採点が厳しく、合格ラインが高い などなど、ただの“救済”ではないのです。
そして、それでも落ちてしまったらどうなるか。
- 同期とは別の学年になり、ひとりでやり直すことになる
- 精神的なダメージが大きく、モチベーションが著しく低下する
- 経済的にも、学費や生活費が1年分延びてしまう
さらに、奨学金や貸与型の支援を受けている人にとっては、 「留年=返還開始の遅延や手続き変更」など実務的な負担も発生します。
ここで忘れてはいけないのが、 試験以外の“出席率・提出物・態度”なども進級条件に影響するという点です。
- 授業の出席が3分の2以下で試験の受験資格を失いアウト
- 実習中の態度が悪いと減点される
- レポートの未提出があると、成績がそもそも付かない
つまり、医学部では“日々の行動全体”が評価対象になっているのです。
進級できるかどうかは、期末試験で決まるのではありません。 1年365日、毎日の積み重ねで勝負が決まる。
そしてそのプレッシャーの中で、学生たちは自分の限界と向き合い続けます。 だからこそ、逆に言えば
- 計画的に勉強し続ける力
- 生活リズムを崩さない自己管理
- 休むべきときに休めるメンタル
この3つが備わっていれば、進級は十分可能です。
甘くはない。でも、コントロールできるものでもある。 それが、医学部の進級と留年のリアルです。
【リアル⑥:人間関係は“濃すぎて”しんどくなることもある】
医学部のリアルとして見落とされがちなのが、人間関係の濃さと、そのストレスです。
一般的な大学では、選択科目の多さやクラス替え、ゼミのバラバラさによって、広く浅い人間関係が築かれる傾向があります。 しかし、医学部はまったくの逆。
6年間、基本的に同じメンバーと同じ授業・同じ実習・同じ試験を受け続けます。
つまり、まるで“中高のクラスが6年間固定されたまま”のような状態です。
毎日顔を合わせるからこそ、仲の良い友人ができると安心感はあります。 勉強を教え合ったり、一緒に試験勉強したり、メンタル面でも支え合える貴重な存在になるでしょう。
でも、一度こじれると逃げ場がないのもまた事実です。
- 特定のグループで浮いてしまう
- 実習で苦手な人とペアになる
- 噂が一気に広まりやすい狭さ
- SNSトラブルが日常にも影響する
こういった問題が起きても、学年全体がほぼ固定なので、“物理的に距離を置く”ことが難しい環境なんです。
特にグループワークが頻発する実習期には、 「人とどう関わるか」「どこまで感情を出すか」「どこまで受け流すか」といった、 高度な人間関係マネジメント能力が問われます。
さらに、医学部には本当にいろんな人がいます。
- 自信満々のエリートタイプ
- 極度にマイペースな人
- 感情の起伏が激しい人
- 協調性に欠ける天才型
これらの人々と毎日関わる中で、 「自分の常識が通用しない」と感じる瞬間が必ず出てきます。
だからこそ大事なのは、“誰とでも仲良くしようとしない”勇気を持つこと。
無理してすべての人に合わせようとすると、確実に消耗します。 大事なのは、心を許せる数人の友人がいること。 それが何よりの支えになります。
また、必要があればSNSをシャットダウンしたり、 一時的に自分のペースに集中する時間を確保するのも有効です。
人間関係は医学部でもっとも地味に、でも確実にメンタルに響く要素です。 だからこそ、“自己管理”の一環として人付き合いも考えるべき課題なんです。
【リアル⑦:それでも「医師になる道」に誇りを持てる】
ここまで、医学部の過酷さやリアルな現実について、6つの側面から紹介してきました。
勉強量の多さ、精神的な負荷、人間関係の難しさ、試験や進級の厳しさ── どれも決して甘い世界ではないことが伝わったと思います。
でも、それでもなお僕が「医学部に入ってよかった」と思える理由。 それがこの最後のリアル、それでも医師になる道には誇りがあるということです。
もちろん、日々の生活は過酷です。 深夜まで続く勉強、連続する試験、削られる自由時間、時には孤独や不安と向き合う時間もあります。
でもその合間に、ふと感じるんです。
- 解剖実習で静かに黙祷したとき、
- 実習で患者さんから「ありがとう」と言われたとき、
- 医師の背中を間近で見たとき。
「ああ、自分は今、本当に誰かの命に向き合う側の人間になろうとしているんだ」 と実感する瞬間があります。
最初は、「なんとなくカッコいいから」「安定してるから」そんな理由で目指したかもしれない。 でも、実際に学んでみて分かるのは、この仕事には覚悟が必要だということ。
それでもなお、この道を選んだことに誇りを感じられるのは、 それだけ多くの人の“命”と“人生”に関わることができるからです。
仲間もいます。 自分と同じように苦しみながらも、一歩ずつ前に進もうとする仲間たちの存在。 同じ目標に向かうことで生まれる絆や、困難を乗り越えた先の達成感。
こうした経験を通して、医学部での6年間は、 ただ勉強するだけでなく、人として大きく成長する時間になります。
受験生であるあなたにとって、今は医学部が遠い場所に感じるかもしれません。
でも、今の努力はすべてこの道に繋がっていて、 その先には“医師になる”という確かなゴールが待っています。
「医者になるって、やっぱりすごいことだな」 「この道を歩んでよかった」
そう胸を張って言える未来が、あなたを待っています。
だから今は、しんどくても、大変でも、 このリアルを知ったうえで、それでも前に進みたいと思えたなら、あなたはもう立派な挑戦者です。
そして、僕たちはそんなあなたを、心から応援しています。
【まとめ&エンディング】
ここまで、医学部入学後に絶対知っておきたい7つのリアルを紹介してきました。
あらためて振り返ると
- 授業は“詰め込み”で量がえげつない
- 解剖実習でメンタルやられる人もいる
- サークル・バイト・恋愛は“できる”、でも地獄を見る可能性も
- 試験のスパンが短すぎて常に追われる
- 進級・留年は現実的に起こる
- 人間関係は“濃すぎて”しんどくなることもある
- それでも「医師になる道」に誇りを持てる
というラインナップでした。
もちろん、これらは僕自身の体験や、周囲の仲間たちの声をもとにした“リアル”です。
誰にとっても当てはまるわけではないし、 「こんなふうに乗り越えたよ」という人もいれば、 「そこまで大変じゃなかったよ」という人もいます。
でも、ひとつだけ間違いなく言えるのは、 “医学部に入ってからの数年間”は、自分の人生を大きく変える時間になるということ。
ただの知識やスキルだけじゃなくて、
- 精神的なタフさ
- 人との距離感
- 自分との向き合い方
あらゆる面で「人としての成長」を問われる時間になります。
そしてその先には、「医師」という社会的な責任を持つ職業が待っています。
だからこそ、今の自分を少しでも強くしておく。 その準備として、今回の7つのリアルが少しでも役に立てば嬉しいです。
この動画を見てくれたあなたが、 未来のどこかで、 「そういえば、あのとき見た“7つのリアル”って本当だったな」 「でも、自分はちゃんと乗り越えられてるな」 そう思える日が来ることを、心から願っています。
よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします!
それでは、また次の動画でお会いしましょう。
ご視聴、ありがとうございました!!