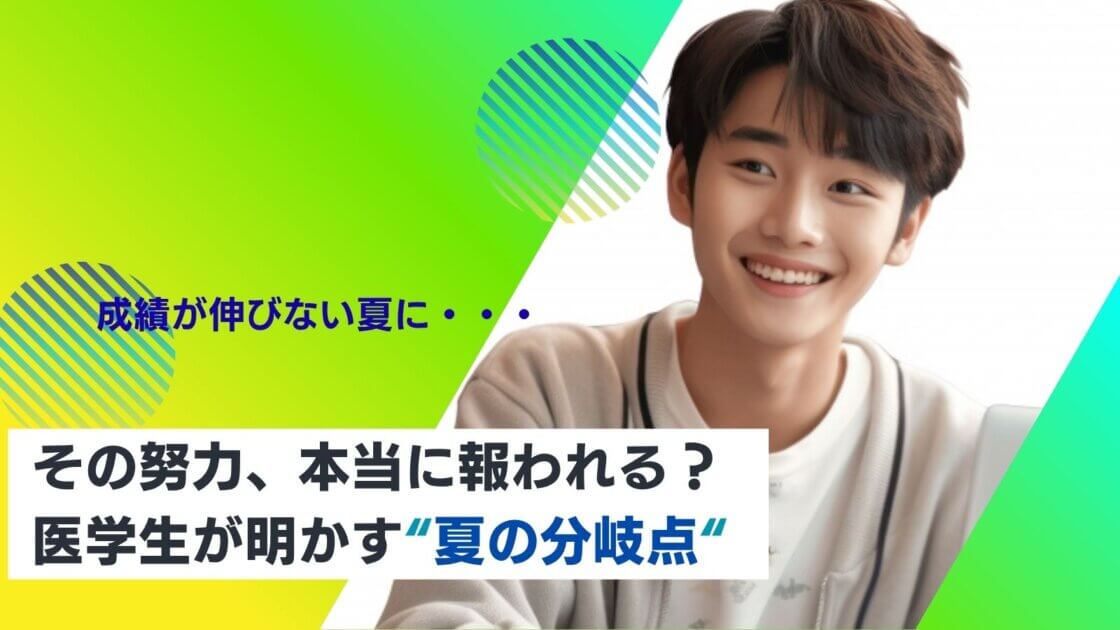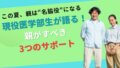こんにちは、スカイ予備校 校長の五十嵐です。
受験生にとって「夏」は勝負の季節。ですが、努力がすぐ結果に表れないこの時期、不安や焦りを抱える人も多いのではないでしょうか。
今回は、現役で思うような結果が出ず一浪の末に横浜市立大学医学部に合格した生徒が、夏の努力が報われた瞬間をリアルに綴ってくれました。
模試、苦手克服、本番での手応えなど、どれもこれから受験に挑む皆さんにとってヒントになる内容ばかりです。受験生はもちろん、保護者の皆さんにもぜひ読んでいただきたい記事です。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:模試での手応えが変わった瞬間
夏の勉強で最初に「変化」を感じたのは、8月末に受けた全統記述模試でした。
正直な話、それまで模試は常にC〜D判定ばかりで、特に数学では時間が足りずに完答できないことが当たり前でした。
そんな僕が、この模試で「時間内に解き終えた」だけでなく、「解答の手応えがあった」ことに、自分自身で驚いたのを覚えています。
手応えを感じた最大の理由は、やみくもな演習ではなく「弱点分析」に取り組んだことです。
具体的には、7月中に過去3回分の模試を徹底的に分析し、間違えた原因を分類しました。
ケアレスミスなのか、理解不足なのか、問題文の読み違いなのか。これをExcelで表にまとめ、自分のミスパターンを「見える化」したのです。
さらに、7月の終わりから8月中旬にかけては、「この分野を仕上げる」とテーマを絞って取り組みました。たとえば数学なら数列の漸化式と確率、英語なら長文読解の構造把握、化学なら無機の暗記と頻出反応。的を絞ることで、学習効率が格段に上がりました。
そして模試当日、最も印象に残っているのが「問題の解き始めに迷わなかった」こと。
いつもは最初の10分くらいで手が止まり、焦って空回りすることが多かったが、この模試では最初の大問で「これは見たことがあるパターンだ」と思えた瞬間がありました。
あの安心感が最後まで集中力を保つことに繋がりました。
模試の結果はB判定。飛び抜けた成績ではないですが、自分の中では明確に“壁を超えた”感覚がありました。
それは点数以上に、「やってきた勉強が、正しい方向だった」という確信を持てた瞬間だったのです。
第2章:解けなかった問題にリベンジ成功した瞬間
模試や過去問を解いていて、「またこのパターンか……」と悔しい思いをしたことはないでしょうか?
僕には、高校2年の終わりごろから何度も出会っては解けずにいた「空間ベクトルの問題」がありました。
図形の把握が苦手で、頭の中で立体をイメージするのが苦痛。模試の度に出てくるが、毎回手が止まる。そして、解説を読んでも「分かったつもり」で終わってしまう……。
そんな自分に終止符を打ったのが、夏休み中に取り組んだ「基礎への徹底回帰」でした。
具体的には『青チャート』の該当分野を、例題レベルから全てやり直しました。
重要なのは、解けるかどうかよりも「図を自分で描き直して、ベクトルの関係を空間的に整理する」こと。
時間はかかりますが、ノートに3D風の図形を書き込んでベクトルの向き、内積、成分を丁寧に追う訓練を続けました。
加えて、YouTubeなどで「空間ベクトルの可視化解説動画」を探しては、毎日10分ずつ視聴。
紙面では伝わりづらい空間的な関係を、視覚的に理解できるようにしたことで、「立体=苦手」の意識が少しずつ変わっていきました。
そして8月の終わり、センター試験(共通テスト)レベルの過去問を解いていたとき、ついに「手が止まらなかった」。
見た瞬間に「これは直線と平面のなす角を求めるタイプだな」と判断し、手順を逆算しながら解き進めることができました。
さらに感動的だったのは、その問題が9月の進研模試でも出題されたこと。
以前の自分なら完全に空欄だったはずが、その模試ではすべての設問を埋め、しかも全問正解していたのです。
この「苦手を克服して、同じ問題に勝った」という経験は、ただ点数が上がった以上に、「やればできる」という自己効力感を与えてくれました。
夏の努力が“点”ではなく“線”で繋がった瞬間だったのです。
第3章:試験本番で「自分はできる」と思えた瞬間
試験本番の日、教室に入って席に着いたとき、僕の心は意外なほど落ち着いていました。
それは、夏の間に築き上げた“やり切った”という実感が、緊張を打ち消してくれたからです。
共通テスト本番の朝、前日はほとんど眠れなかったにもかかわらず、心のどこかで「不思議と大丈夫な気がする」と感じていました。
というのも、12月の最終模試で過去最高の得点を出し、それに至るまでの過程が自分でもはっきり分かっていたからです。
実際にテストが始まると、これまでと違って問題文がスッと頭に入ってくる感覚がありました。
特に数学では、夏に徹底的に潰した「整数」「図形と方程式」の問題が出題され、手が自然と動きました。
英語長文でも、構文解釈の練習を繰り返したことで、段落の意味構造を見抜く力がついていました。
何よりも印象に残っているのは、試験中に「今の自分なら、いける」という自己肯定感を持てたこと。
それは、夏に培った“努力を継続できる自分”への信頼感でした。
試験が終わった瞬間、得点や判定にかかわらず、「自分は本番でベストを尽くせた」と思えました。
その実感が、合格という結果を引き寄せたのだと思います。
まとめ:努力が報われる瞬間は、あとからやってくる
夏の努力がすぐに結果になるとは限りません。
でも、夏にやったことが秋以降の模試や本番に活きてくるというのは、本当の話です。
むしろ「伸びる直前の夏」は苦しいもので、自信を持てない時期でもあります。
けれどその不安や焦りを抱えながらも、毎日コツコツ積み重ねていけた人が、最後に「報われた」と感じられるのです。
努力が報われる瞬間は、必ずしも「合格通知が届いたとき」ではありません。
小さな成功体験や変化に気づく瞬間が何度もあります。
そのひとつひとつが、合格という最終ゴールに確実につながっています。
「この夏、誰よりも努力した」と胸を張って言えるような夏を、ぜひ過ごしてください。
僕の経験が、その一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。