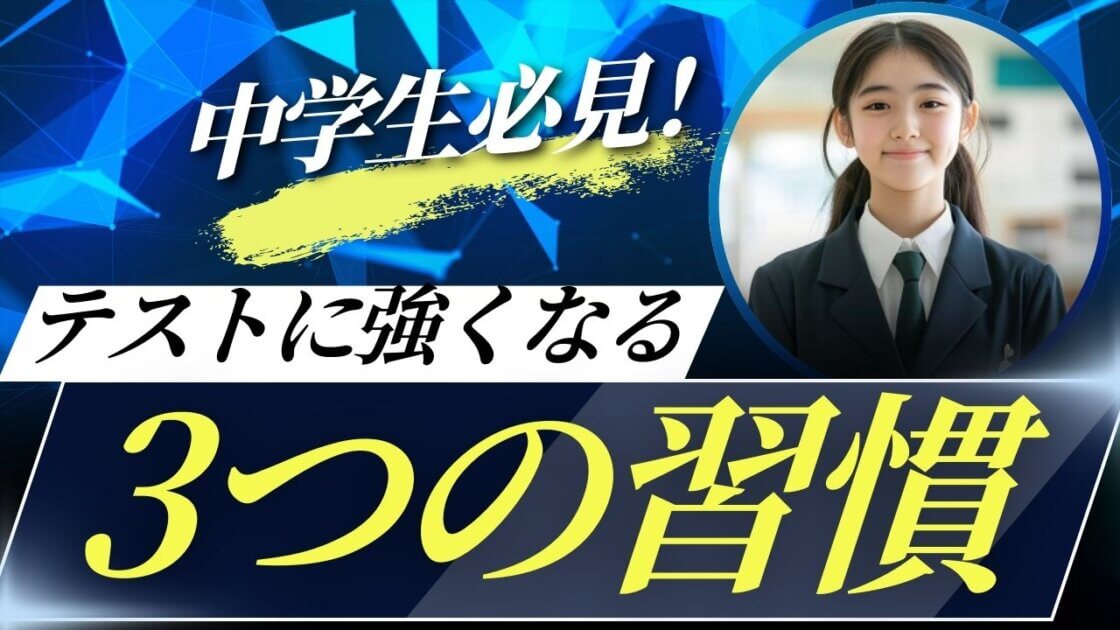例えば英語数学に関しては、中1で基礎計算や英文法の型を固め、中2で文章・図形・関数や英語の多読を増やし、中3で入試形式に触れる、といった段階設計を意識するだけで、先の不安がずいぶん軽くなります。とはいえ「何から始めればいいの?」と戸惑うこともありますよね。そこで今回は、認知科学のエビデンスを土台に、今日から実践できる学びの設計図をまとめました。結論はシンプルです。①覚えるタイミングを分散し、②思い出す練習を増やし、③問題の並べ方と暮らしの習慣を整える、この三点を押さえれば、受験期に効く「伸びる学習」を中学生のうちから作れます!

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
ゴールから逆算する勉強カレンダー
まずはゴールから逆算します。高校入試も大学入試(共通テスト・個別試験)も、知識だけでなく「限られた時間で知識を取り出し、使う」力が問われます。ですから年間→月→週→日の順に、復習サイクルと演習枠をカレンダーへ落とし込みましょう。ここで頼れるのが「分散学習(Spacing)」です。まとめて詰め込むより、間隔をあけて複数回触れた方が長期的には伸びます。「翌日→3日後→1週間後→1か月」のように段階的に広げる設計が王道です。
次に「想起練習(Retrieval practice)」を加えます。読み直しやマーカーは“わかった気”をくれますが、成績への波及は限定的。対して、小テストや白紙再現は記憶を強化し、応用の助けになります。教科書を閉じて要点を書き出す、10分の自作ドリルを解く、親や友達にミニ講義をする――そんな“取り出す学習”を日課化しましょう。さらに「実行意図(If–Thenプラン)」を用い、「もし21時になったら理科の用語20個を音読→白紙再現する」と条件と行動をセットで決めると、予定倒れを防げます。
また、時間管理もポイントです。長時間より「25分集中+5分休憩×3セット→15分休憩」のブロックが効果的。週の頭に“固定コマ”として入れてしまえば、勉強習慣の基盤ができます。
英語・数学・理科・社会の必勝パターン
- 英語は「インプット→想起→使用」の順。単語は翌日・3日後・1週間後に再テスト、文法は例文の穴埋めを白紙再現、リーディングは段落要旨を口頭で説明、など。
- 数学は「混ぜる学習法(Interleaving)」が有効。因数分解ばかり…といった“ブロック練習”ではなく、単元をシャッフルして演習すると効果的。最初は例題模倣(ワークド・エグザンプル)を挟むのもおすすめ。
- 理科・社会は「用語→因果→記述」の三層で回す。特に記述は白紙再現が抜群に効きます。概念地図も役立ちますが、最後は必ず“閉じて書く作業”を入れること。
模試や定期考査は“伸びのイベント”に変えましょう。間違いをタグ化し、同パターンを3題だけ解き直す「狭い弱点の反復」が効果的です。
成績を支える生活ルーティン
学力の土台は生活です。
- 睡眠:中学生は9–12時間、高校生は8–10時間が推奨。夜は照明を落とし、紙媒体に切り替えるのがベター。
- 運動:10–20分の有酸素運動は注意・ワーキングメモリを押し上げます。宿題前後に軽運動を挟みましょう。
- やる気対策:「If–Thenプラン」と短い指示文で迷いを減らす。「もしスマホを触りたくなったら机にしまう」といった工夫が効きます。
さらに保護者の立ち回りも大切です。宿題の直接介入より、「学ぶ理由を言語化する」「週の学習ブロックを一緒に決める」「テスト後の原因報告を聞く」といった伴走が効果的。
試験不安が強い子には“気持ちの書き出し”も有効です。直前に8–10分心配事を書き出すだけで得点アップが期待できます。
1週間の勉強プラン実例
最後に1週間のサンプルを紹介します。
- 月水金:英語(単語→文法→長文の想起)
- 火木:数学(インタリーブ演習+例題模倣)
- 土曜午前:理社(白紙再現→記述→弱点3題)
- 日曜:積み残し回収と次週のIf–Then計画
各コマ25分×3セット、前に軽運動2分、後ろに復習チェック10分を置きましょう。夜は就寝前1時間は低照度+紙媒体に切替、スマホは「タイマー起動=ロック」で。
今日からできる第一歩
受験に効く学びは、中学生のうちから作れます。ポイントは三つです。
- 「分散×想起」で翌日・3日後・1週間後の小テストを取り入れる。
- 数学は混ぜて解く、英語は閉じて書く、理社は段階を踏み、模試は原因タグ化で反復。
- 睡眠・光・運動の生活習慣を整え、If–Thenプランと保護者の伴走で習慣化を後押し。
派手な奥義より、こうした地道な型が強さをつくります。今日の1コマから、まず始めてみましょう!