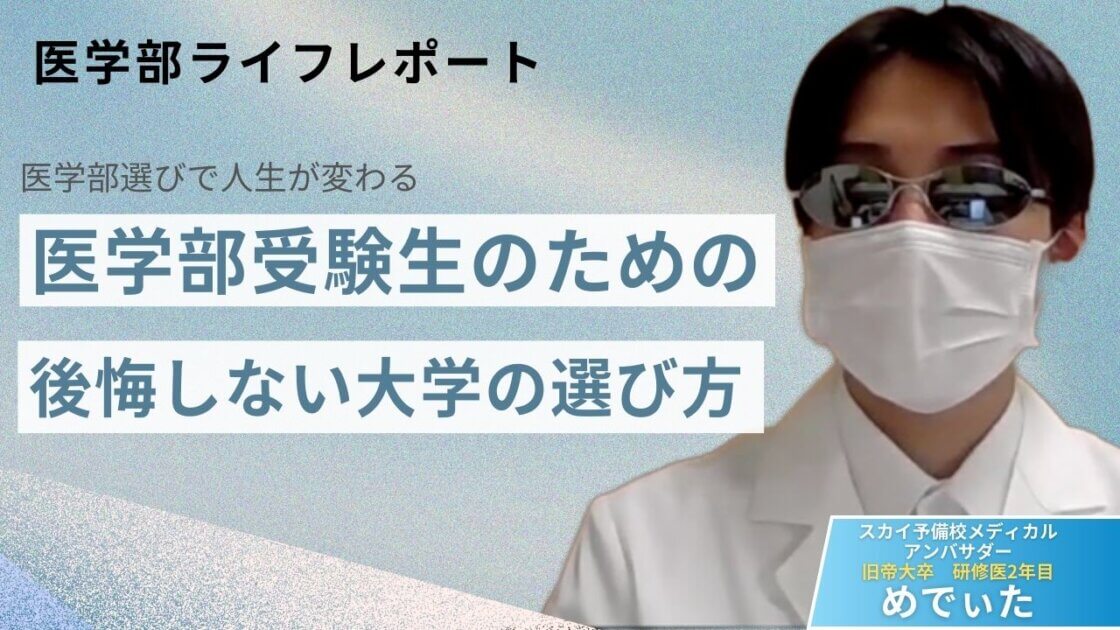【研修医めでぃた先生の医学部ライフレポート】医学部って、どこに入っても同じ?大学選びで絶対に後悔しないための3つの視点
こんにちは!スカイ予備校メディカルアンバサダーのめでぃたです。
今日は、医学部受験を考えている受験生や保護者の方に、ぜひ知っておいていただきたい「医学部の選び方」についてお話しします。
毎年この時期になると、予備校でもこんな声を耳にします。
「医学部にさえ入れれば、どこでもいいです」
「国公立なら前期のどこかに受かればそれでいいです」
たしかに、医学部に合格することは大きな目標ですし、そこに向けて努力を重ねていることは本当に素晴らしいことです。
でも…実は、医学部って「入った後」のほうが、もっと大変なんです。 今回は、国公立前期試験を念頭に置きながら、「医学部選びで後悔しないための3つの視点」を紹介します。
医学部合格が“ゴール”ではなく、“スタート”であるという前提で、ぜひ参考にしてみてください。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
「受かりやすさ」だけでなく、「卒業しやすさ」も見る!
受験のとき、どうしても偏差値や倍率ばかりに目がいきがちですが、
実際に医学部に入ってから重要になってくるのが、「6年間でちゃんと卒業できるかどうか」です。
たとえば――
- 2年次の解剖実習や生理学・生化学など、専門科目の壁
- 4年次の共用試験(CBT・OSCE)
- 6年次の卒業試験と国家試験
このあたりで脱落する学生が、どこの大学にも一定数います。
中には「進級基準がとにかく厳しくて、毎年のように留年者が出る」という大学も。
逆に「落とすより育てる」方針で、補習制度や個別指導がしっかりしている大学もあります。
また、医師国家試験の合格率も、ただ数字だけを鵜呑みにしないこと。
というのも、大学によっては“国家試験を受けさせないことで合格率を上げる”という手法をとる場合もあるんです。
だからこそ、次の点をセットで確認するのが大切です:
- 留年率(とくに2・4・6年の)
- ストレート卒業率
- 卒業生の国家試験合格率
「受かった後に、ちゃんと卒業できるか」――これは絶対に見ておくべきポイントです。
大学の立地は、6年間のQOLを左右する
これも意外と見落とされがちですが、「大学がどこにあるか」は、受験生本人の6年間に大きく影響します。
都会にある医学部は、アルバイトの選択肢も多く、交通の便も良好。
セミナーやイベント、他学部との交流など、学外の刺激を受ける機会も豊富です。
勉強一辺倒ではなく、視野を広げる6年間にしたい人には向いています。
一方で、地方の大学では――
- 公共交通機関が少ない(1日数本のバスだけ、なんてことも)
- 周辺にコンビニがない
- 気軽に息抜きできるカフェや娯楽施設がない
といったケースもあり、「静かな環境で淡々と勉強したい人」には向いているかもしれませんが、人によっては息が詰まることも。
また、将来「地元で医師として働きたい」と考えている人は、実家に近い大学を選ぶことも選択肢になります。
親御さんのサポートを受けやすく、経済的・精神的な安心感があるのは大きなメリットです。
卒業後のキャリアにも「出身大学」の影響が出ることも
「医師国家試験に受かれば、どこの出身でも関係ない」
そう思っている方も多いと思います。実際、医師免許そのものには大学名は関係ありません。
でも、実務の世界では「出身大学」の影響を受けることもあります。
特に、各大学には「医局(いわゆる専門診療科のグループ)」というものがあり、
この医局の規模・実力・人脈は大学によってかなり差があります。
例えば――
- 研究志向の大学なら、在学中から学会や論文に触れる機会が多い
- 強い医局を持つ大学は、関連病院が多く、将来の勤務先選びに困らない
- 留学支援や学術研究へのバックアップ体制が整っている大学もある
一方で、医局が閉鎖的な大学では、「外部出身者」が肩身の狭い思いをすることもあります。
これは、卒後に別の大学医局に入ろうと思っている人には、無視できない問題です。
将来、どんな診療科に進みたいか。
研究か臨床か、都市部か地方か、開業か勤務医か。
そうした“未来像”を少しでも思い描いておくことで、自分に合った大学の傾向が見えてくるはずです。
関連記事
◇医学生のメンタル崩壊率、想像以上です
◇大学受験で身につけた力が、医師になっても活きている理由
◇医学生のリアルな日常とは?6年間のセキララ体験談
◇医学部のクリスマス事情 学年別にリアル解説
まとめ:医学部は「どこでもいい」ではなく「ここがいい」で選ぼう
ここまでの内容をもう一度まとめてみましょう。
✔️ 入学後に苦労しないために、進級・卒業のしやすさを見る
✔️ 6年間の生活の質(QOL)を大きく左右する立地を見逃さない
✔️ 卒後のキャリア形成に関わる“医局”や人脈の特色も考慮する
医学部に合格することは、確かに素晴らしいことです。
でもその6年間、そしてその後の何十年の医師人生を考えたとき、
「とりあえず受かりそうなところ」ではなく、「自分に合った場所」を選ぶという視点を、ぜひ持っておいてほしいと思います。
予備校の立場からも、たくさんの卒業生たちを見てきた実感として、
“どこで過ごすか”は、思っている以上に大きな意味を持っています。
迷っている方、不安な方は、いつでも相談してくださいね。
あなたにとって最良の選択ができるよう、私たちも全力でサポートします!