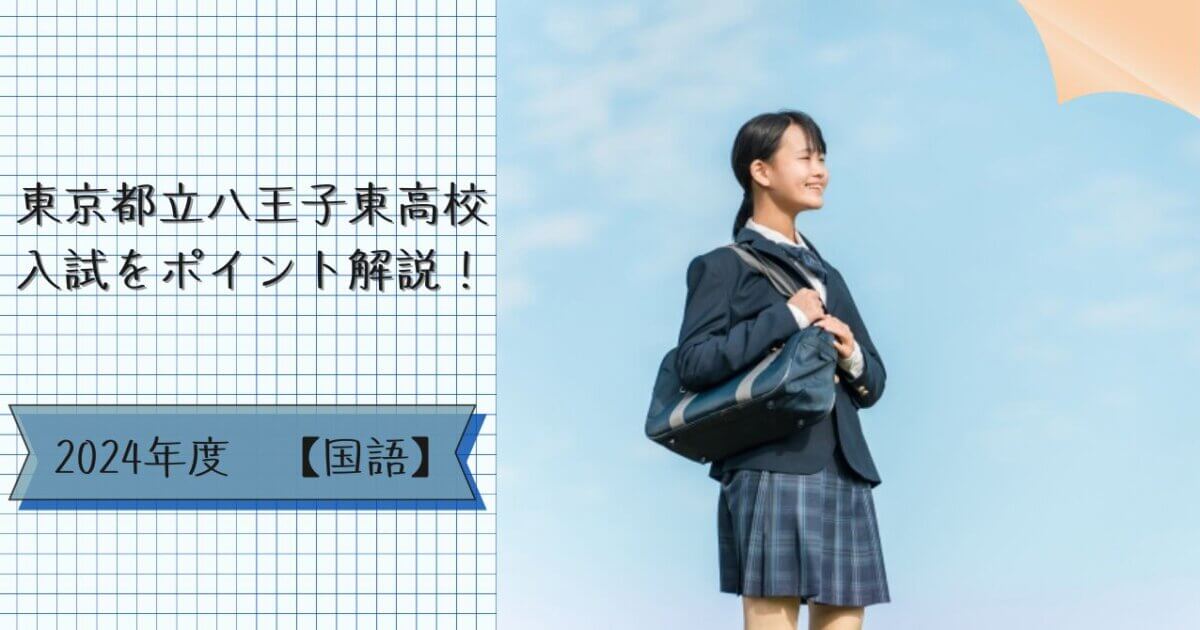2024年度東京都立八王子東高校入試では、漢字の読み・漢字の書き取り・文学的文章・論理的文章・論理的文章(俳句含む)の5題構成になっています。
↓解答はコチラ

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
大問1(漢字の読み)
〈解説〉
「逃(した)」・「清廉」・「頒布」・「焦燥感」・「徒手空拳」の読みが出題。
大問2(漢字の書き取り)
〈解説〉
「帰(した)」・「鳴動」・「照準」・「短兵急」・「起死回生」の書き取りが出題。
大問3(文学的文章)
恩田陸『なんとかしなくちゃ、青雲編』からの出題です。
〈解説〉
〔問1〕理由説明(選択肢)
傍線部直前に「ユッコのテーマ、面白い。さすがユッコだね」とある。
〔問2〕心情説明(50字記述)
掛け軸代わりに自分たちの店の赤い絨毯が掛けられているのを見て、結子がなぜそのようなことをしたのか不思議に思っている。後ろにも、「早く結子の説明を聞きたくてうずうずしている」とあ る。
〔問3〕内容読解(選択肢)
玉枝は「カネも商いも、融通無碍が理想やな」と呟いているが、「眩しいような目をして」見ているのは、あくまで孫娘である結子である。
「なんか、この子は面白いことやってくれそうやな」、「商売でもいけるけど、商売にとどまらない。えらいおっきいこと、やりそうや」と考えている。
結子に焦点を当てているア~ウのうち、アは「言葉通り」、イは「自分のこれからの生き方について自信を持って宣言する」が誤り。
〔問4〕心情理解(選択肢)
「雄大なこと」とは、「古来世界中を行き来したものが、今、当たり前の風景になってい」て、「そういう、当たり前でちょうどいい、っていう世界を造る手伝いをしたい」という結子の思いを指す。
「当たり前」というキーワードが入っているのはウとエ。ウは、「雄大なこと」を「鋭い指摘」としている点が誤り。
〔問5〕表現理解(選択肢)
アは、「読者の感情移入を促している」が誤り。
イは、「登場人物の人柄やものの考え方に違いがあることを暗示している」が誤り。エは、「登場人物の考えが二転三転し、曖昧なものになっている」が誤り。
ウについて、「語り手として直接語る部分」は、本文最後の一文のことである。
大問4(論理的文章)
多木浩二『生きられた家』からの出題です。
〈解説〉
〔問1〕理由説明(選択肢)
傍線部直後の「実体は連続して存在しているが意味の上ではこの連続が断ち切れている」という内容を、「座布団を裏返」す行為にあてはめるとどうなるかを考える。
「座布団を裏返」したとしても、それが座布団であることに変わりはないので、「実体は連続して存在している」といえる。
だが、裏返す前の座布団が「先客」のためのものだったのに対し、裏返した後の座布団は「あとからやってきた客」のためのものに変わっている。このことを「意味の上ではこの連続が断ち切れている」と表現しているのである。
〔問2〕内容読解(選択肢)
西洋の建築において、「空間」が何を象徴しているかを考えればよい。
イは、「混在」が誤り。「曖昧な領域」はあれど、「対立」はしている。また、「空間の意味が曖昧になっている」は傍線部の説明になっておらず、本文にない内容。
ウについて、空間が「抽象的なものにすぎない」ことを「象徴化」といっているわけではないので誤り。
エは、「広い空間を備えた建造物」に限定しているので誤り。また、「地域一帯」を象徴するわけではない。
〔問3〕内容読解(選択肢)
「日本の家では、物も一時的にあらわれ、必要なあいだ滞留し、やがて姿を消す」が、「部屋の機能変化は、そこに出現する机とか布団とかいう物=象徴によって生じる。あらわれる道具がちがえば、そこに生じる出来事はちがってくる」と説明されている。
〔問4〕理由説明(選択肢)
「生き生きした映像」は、例えば「かれの心があるときには宗教に、あるときには楽器にたわむれるであろうさまが、ひとつひとつの物によって感じられる」ことで浮かんでくる。物が「とりだされ、かれの手にとられ、出来事となって現象する」と述べられている。
〔問5〕作文(240字)
日本と西洋の文化の違いが見てとれるものに、庭造りがある。
日本の伝統的な庭が、自然物をそのまま配置することによって構成される一方、西洋の庭は人工的な加工を加えることで幾何学的に造られることが多い。
こうした違いが生まれた原因のひとつに、自然に対する姿勢が挙げられる。日本は自然に畏敬の念を抱き、人が安易に手を加えるのをよしとしなかった。西洋は自然を客体化し、人間がよりよい生活を送るために手を加えてもよいものと考えたのである。
大問5(論理的文章+俳句)
復本一郎『俳句と川柳「笑い」と「切れ」の考え方、たのしみ方』からの出題です。
〈解説〉
〔問1〕内容読解(選択肢)
「まず、紹巴の句であるが、五月雨のシーズンは~」の段落の内容に合致しているものを選べばよい。
〔問2〕内容読解(選択肢)
庶民性については、「井の中の蛙大海を知らず」という有名な俚諺を取り込むことで獲得している。
また、滑稽性については、「五月雨を契機として、俚諺の内容を逆転させ」ることで獲得している。
〔問3〕内容読解(抜き出し)
▢で囲まれた部分の解釈部分を読むと、「即興的に詠まれた」に該当する箇所は、「『ひやうふつ』と口から流れ出て」だとわかる(これ以外の箇所はある程度訳されており、どれも「即興的に詠まれた」の意でないため)。
〔問4〕言葉の意味(選択肢)
「ほうほうの体で」の意味が出題。
〔問5〕内容読解(選択肢)
「別種の『笑い』」とは、「あからさまな、品下る『笑い』」ではなく、「一句の中で『あはれ』と融合し、瀰漫した『笑い』」のことである。