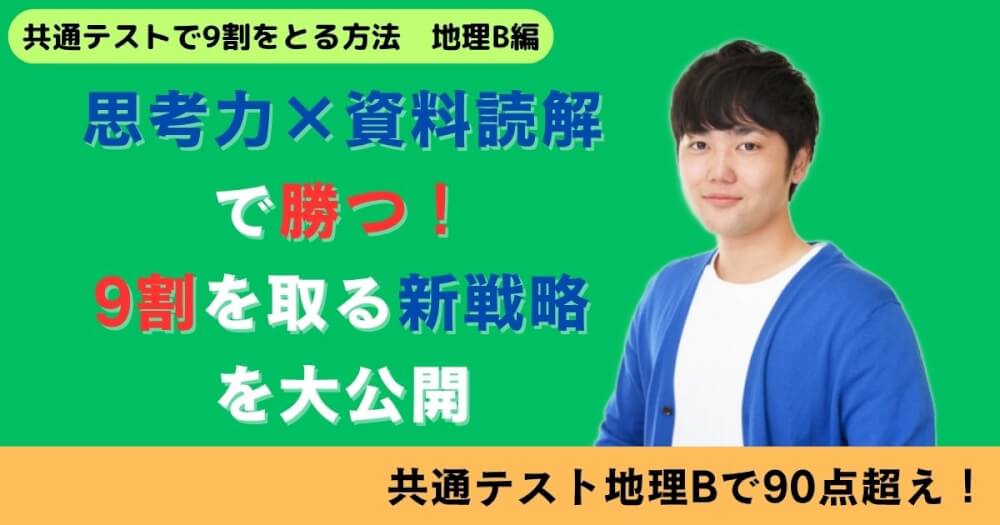「知っている」から「考えられる」へ──地理Bの本質が変わった!
かつてのセンター試験時代、地理Bは「暗記勝負」とされ、知識量が得点を決めるとされてきました。しかし、共通テストになって以降、地理Bは「思考科目」へと大きく進化を遂げています。今や重要なのは、「どれだけ知っているか」ではなく、「知っていることをどう使うか」。
本記事では、共通テストで安定して9割(90点)を狙うための、知識の入れ方から実践演習、直前対策、本番での立ち回りまでを体系的にまとめました。地理Bを武器科目にしたい人は必見です!

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:共通テスト地理Bの出題傾向と新傾向の分析
【1. 出題形式の特徴】
- 図表・グラフ・地形図・衛星画像などの資料を読み取る設問が多い
- 問題文が長く、問われている内容も一見複雑
- 「地域の比較」や「論理的推論」を要する問題が頻出
【2. 出題範囲の傾向】
- 日本の地理よりも世界地理が重視される
- 都市・農業・工業・貿易・民族・宗教・環境などのテーマで複合的に出題
- 自然地理(気候・地形・災害)と人文地理(経済・社会)を横断的に問う
【3. 高得点層がやっていること】
- 「地図帳」「統計資料集」を横に置いて勉強する
- 用語暗記ではなく「因果関係」や「地域差」の理解を重視
- 資料を見たときに、「これは何を意味しているか?」を常に自問自答する
第2章:思考力型問題に強くなる知識インプット術
共通テスト地理Bにおいては、単なる知識の暗記では対応できない“資料思考力”が求められる。その力を育てるためには、普段の知識インプットから「なぜそうなるのか?」をセットで覚える習慣が不可欠である。
【1. 「地理用語」は単独で覚えない】
- 例:「間帯土壌」という語句を覚える際、「気候→植生→腐植→土壌の形成過程」をセットで理解する
- 「用語の意味+背景知識+因果関係」の三点セットで知識を構築
【2. 地図帳・統計資料集を横断的に活用する】
- 地名だけでなく「分布のパターン」「例外となる地域」に注目する
- 統計は「順位を覚える」よりも「なぜその値になるか」を説明できるようにする
- 地域ごとの特色を「気候・産業・宗教・民族」など複数の切り口で整理
【3. 因果関係の可視化を習慣にする】
- ノートや単語カードに「原因→結果→地理的背景」を書き出す
- 例:「モンスーン気候 → 夏に雨が多い → 稲作が中心」など、1つの現象から知識を広げる
【4. 過去問・資料問題の“なぜ間違えたか”分析】
- 正答だけでなく「誤答の根拠」まで確認し、知識の誤解を修正
- 「この選択肢はなぜ×か」を説明できるようにすることで、判断力が鍛えられる
【5. 実生活やニュースと結びつける】
- 「この地域はなぜ水不足?」といった疑問をニュースや時事から学ぶ
- 「地理は現実とつながっている」ことを意識することで、知識の定着率が上がる
■第3章:資料読解と選択肢処理のテクニック
共通テスト地理Bでは、文章・図・統計・グラフなどの資料を正確に読み解き、それをもとに選択肢を処理する力が問われる。ここでは資料読解の具体的な手順と、選択肢処理の技術を体系的に紹介する。
【1. 資料読解の基本ステップ】
①まず「資料の種類」を把握する
②次に「問題文・設問」を先読みする
③資料の中から「問われている要素」を拾う
④補助情報(凡例・注釈・縮尺)も見落とさない
【2. 選択肢処理のテクニック】
- 設問形式に注意(「正しいもの」「誤っているもの」など)
- 各選択肢について、正誤の根拠を資料に照らして検証
- 明らかな誤りを優先的に除外する
【3. 選択肢が難解なときの読み方】
- 根拠をもって説明できるかで判断
- 迷ったら他の選択肢を検証し、消去法で除外
- 曖昧表現には注意する(例:「〜が見られることがある」など)
【4. 図表の数値を計算・比較するときのコツ】
- パーセンテージ・比率の計算に慣れる
- 「最大」「最小」「順位」の比較では素早い判断を
- 単位換算ミスを防ぐ
第4章:本番戦略と時間配分術
地理Bの共通テストは時間が60分。資料が多く、文章も長いため「最後まで解き切れなかった」という声も少なくない。ここでは、本番で9割を取り切るために必要な時間管理と問題処理の戦略を紹介する。
【1. 試験全体の時間配分】
- 各大問10〜12分を目安に
- 解けない問題は即スキップ
- 見直し時間の確保も意識
【2. 優先順位のつけ方】
- 読みやすい問題から先に解く
- 複雑なグラフ・地図は後回し
- 問題を「解ける・解けそう・時間がかかる」に分類
【3. 解き直し時間の確保】
- 最後の5〜7分を見直し用に
- 「消去法の最終選択肢」が妥当か再確認
- 焦ってマークミスしないように
【4. マークミス・設問形式ミスを防ぐ工夫】
- 設問形式を囲むなど明示
- マーク欄を定期確認してズレ防止
- 最後に全体チェックを忘れずに
【5. メンタル管理も得点のうち】
- 時間切れ対策には心構えが重要
- 焦らず淡々と処理すること
- 「1問ミスしても大丈夫」の意識で挑む
最終章:直前期の勉強法と避けるべきNG戦略
直前期は、知識の最終確認と実戦力のブラッシュアップが重要になる。ただし、やみくもに問題を解いたり、焦って新しいことに手を出すのは逆効果になりやすい。
【1. 確実に得点できる単元を徹底復習】
- 自然地理・農業・工業など頻出テーマは要確認
- 「覚えたつもり」の知識ほど落としやすい
- 得点源に特化するのも戦略
【2. 資料問題の過去問を繰り返し演習】
- 過去3年分の共通テスト・予想問題を演習
- 解説で選択肢の検討・分析まで行う
- 日々“資料問題の思考筋”を鍛える
【3. 統計・地図帳の見直しはピンポイントで】
- 「頻出グラフ・苦手項目・過去のミス」に集中
- 例:主要農作物、気候区分、人口密度など
- 自信のある項目を増やす
【4. 当日に向けて整える“心と体”】
- 詰め込みよりも落ち着いた確認を優先
- 生活リズムを試験本番に合わせて調整
- 試験前日はミス集・ノートでの最終確認が◎
【5. NGパターン】
- 新しい教材に手を出して不安を増す
- 復習せず問題だけ解く
- ネガティブ思考に引っ張られる
- 「わかったつもり」で復習を怠る
- 他人と比較して焦る
地道な思考トレーニングが9割への最短ルート!
共通テストの地理Bは、知識と読解力を融合させる「思考型試験」です。そのぶん、派手なテクニックよりも、日々の地道な思考トレーニングが結果につながる実直な科目でもあります。
本記事で紹介した戦略を活かして、自分のペースで効率よく対策を進めてください。9割は、あなたにも届きます。