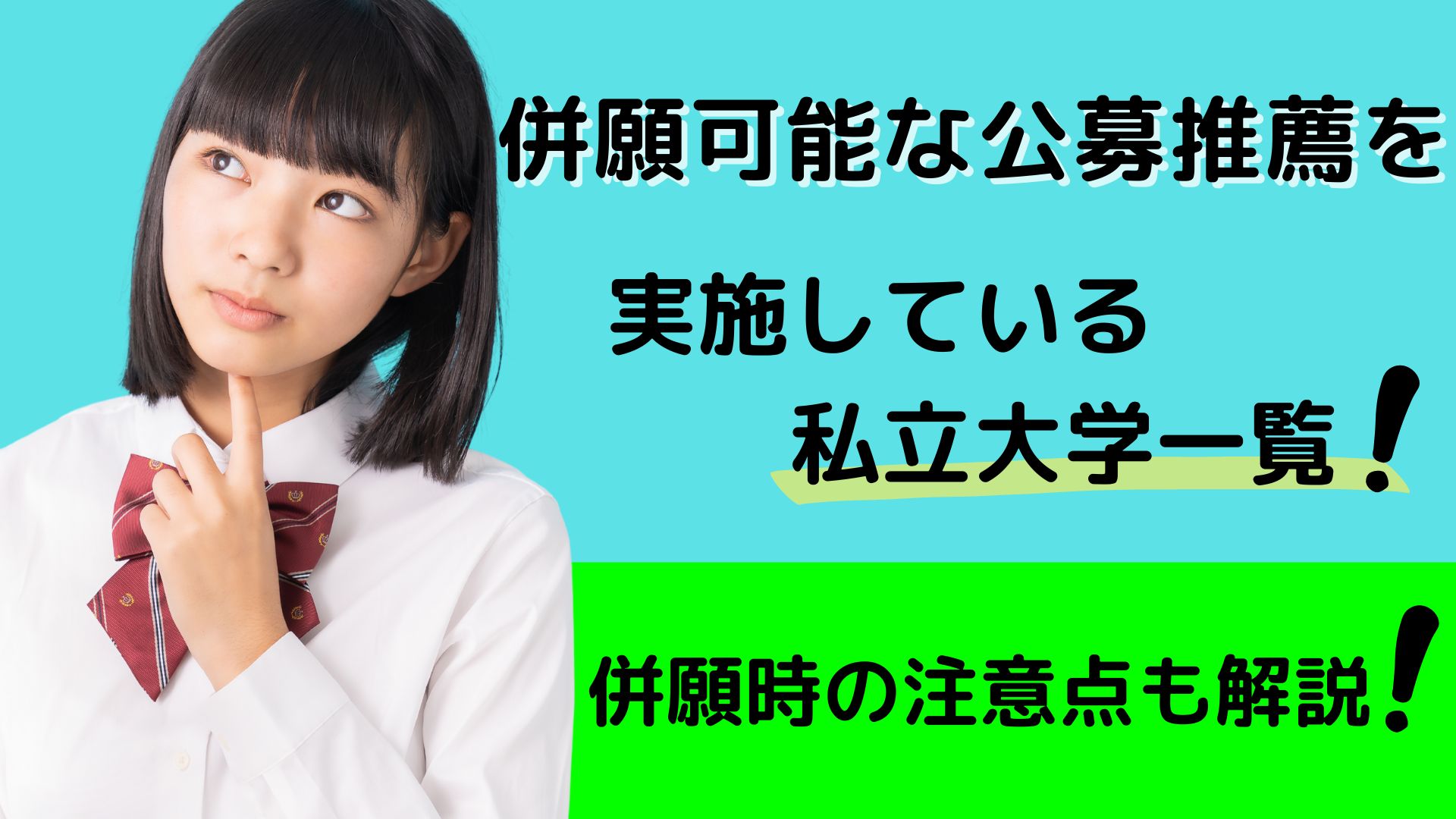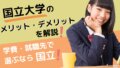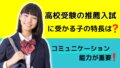多くの高校生が悩む、専願と併願の仕組みの違い 併願時の注意点
【2025年度最新情報】併願受験可能な公募推薦を実施している私立大学一覧
公募推薦(学校推薦型選抜)の利用を考えている受験生にとって、「専願と併願の仕組みはどう違う?」「併願できる大学はどこ?」といった点は大きな関心事でしょう。 本記事では、専願と併願の仕組みの違い、併願時の注意点、そして公募推薦で併願が可能な私立大学について、2025年度入試を見据えてわかりやすく解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
専願と併願の仕組みの違いは
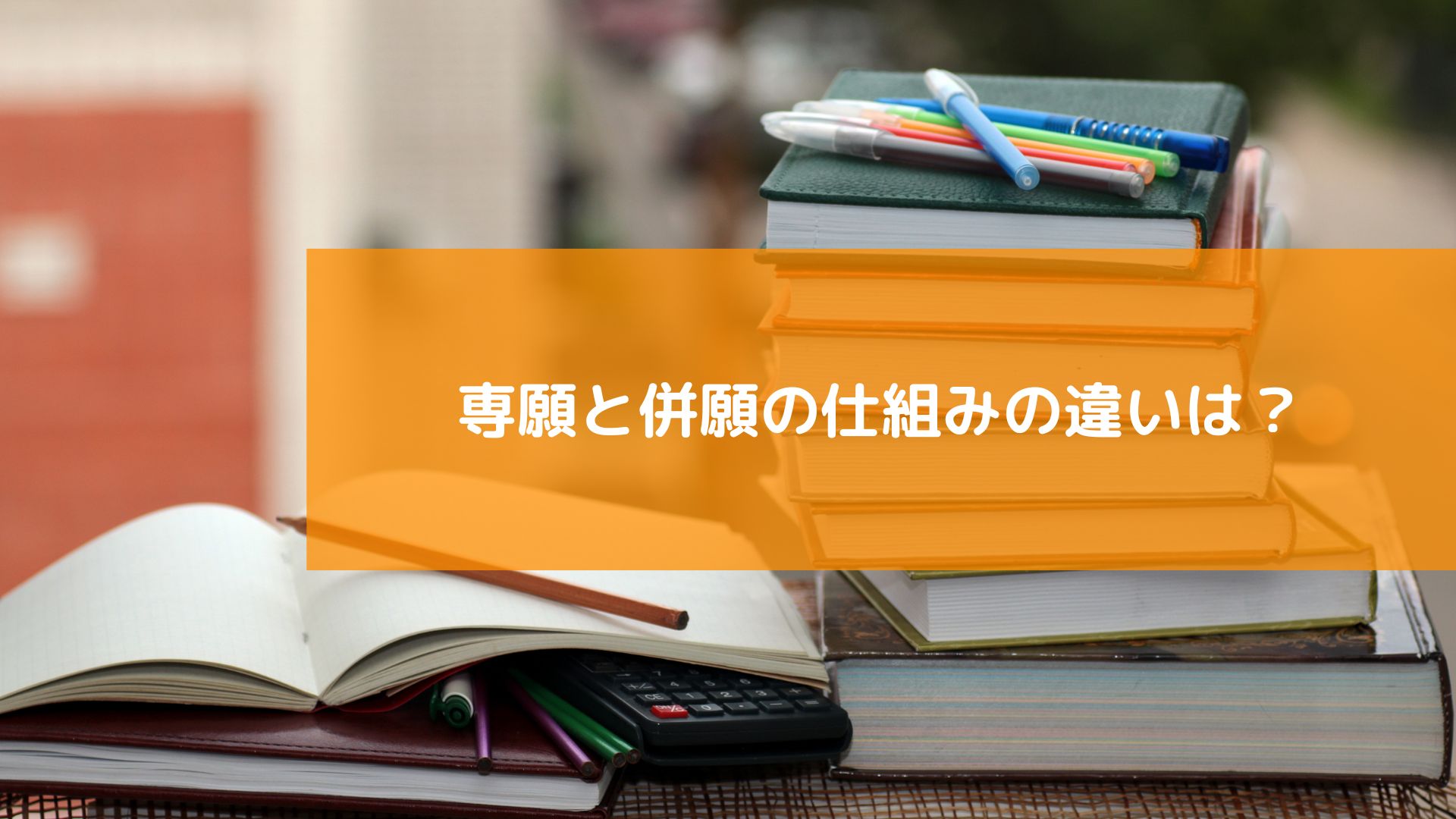
まずは専願と併願の仕組みについて理解しましょう。
専願・併願とはどのような制度なのか
専願制とは、その大学を第一志望とし、合格したら必ず入学するという条件のもとに受験する形式のことです。出願には、高校での教科の評定平均値など一定の基準を満たす必要があります。合格した場合、入学辞退は原則としてできません。ただし、これは合格した場合の約束なので、不合格だった場合に備えて併願可能な他の大学を受験することは可能です。
一方、併願制とは、複数の大学への出願が認められており、合格しても入学を確約する必要がない受験形式です。第一志望校以外の大学を受験する際は、この併願制を利用することになります。
専願と併願の受験パターン
公募推薦の専願・併願の仕組みに、他の選抜方式も組み合わせることで、多様な受験パターンが考えられます。例えば、スポーツや文化活動での優れた実績をアピールする自己推薦型の選抜と組み合わせることもその一つです。
公募推薦を受けるほとんどの受験生は、第一志望校に合格できなかった場合に備えて複数の大学を受験します。浪人を避けたい高校生は、併願が可能な大学をいくつか受験しておくのが良いでしょう。
一般的な受験パターンとしては、「併願可能な公募推薦を複数受験する」「専願制の公募推薦を本命としつつ、併願可能な公募推薦や総合型選抜、一般選抜を組み合わせる」といった方法が挙げられます。学部やコースによって行う選抜方法も異なるため、よく確認しましょう。
五十嵐写真02.png)
公募推薦で不合格となった大学に、一般選抜で再挑戦することもできます。ただし、指定校推薦は専願が基本であり、他のどの選抜方式とも併願することはできません。校内選考を通過した時点で、その大学への進学がほぼ確定します。
併願時の注意点とは

公募推薦の専願と併願、さらには他の選抜方式を組み合わせて、さまざまな受験パターンが考えられるということがおわかりいただけたと思います。ここからは、複数の大学を受験するときに気をつけなければいけない点について説明していきましょう。
専願制の受験に同時に何校も申し込むのはNG
専願制は「合格したら必ず入学する」という約束のもとで行う選考です。そのため、専願制の大学に同時に何校も申し込むことはできません。
もし申し込もうとしても、出願に必要な調査書等の提出は高校が行うため、学校側から止められるはずです。専願校の重複出願はルール違反となります。
併願校は5校以内とする
併願校の数に制限はありませんが、第一志望を含めて5校以内に絞るのが現実的です。 なぜなら、受験校が増えるほど対策が大変になるからです。
特に、大学や学部、コースによって課される科目が異なると(例:小論文、面接、プレゼンテーション、基礎学力試験の英語や数学 等)、大学ごとの対策が必要になり、時間的・体力的に非常に厳しくなります。 対策の負担を軽くしたい人は、「書類審査・面接・小論文」など入学試験の内容が似ている併願校を選ぶと良いでしょう。
受験料などの金銭的負担は許容する
私立大学の受験料は1校あたり平均35,000円程度(医療・歯学系では40,000円~60,000円程度)かかります。
併願校が増えれば、その分費用もかさみます。 また、第一志望校の合格発表前に併願校の入学手続き期限が来る場合、入学する権利を確保するために入学金を納める必要があります。
文部科学省の資料によると、私立大学の入学金は文系で約23万円、理系で約25万円、医歯薬系で約107万円が平均です。一度納付した入学金は、後で入学を辞退しても返金されないのが一般的です。 併願校が増えると金銭的負担も増えることを理解しておきましょう。
併願校の面接であっても志望度の高さをアピールする
面接では、その大学が第一志望であることを明確にアピールすることが重視されます。なぜなら、併願可能な大学でも「専願」の学生を優遇する可能性があるからです。
志望順位が低いと判断されると、合否評価で不利になることがあります。 面接で「他校と併願していますか」「本学の志望順位は何番目ですか」と質問された場合は、「他の大学も受験していますが、貴校が第一志望です」と言い切り、入学への強い意志を伝えましょう。合格後の学生生活への期待を語るのも良いでしょう。
併願受験可能な公募推薦を実施している私立大学一覧
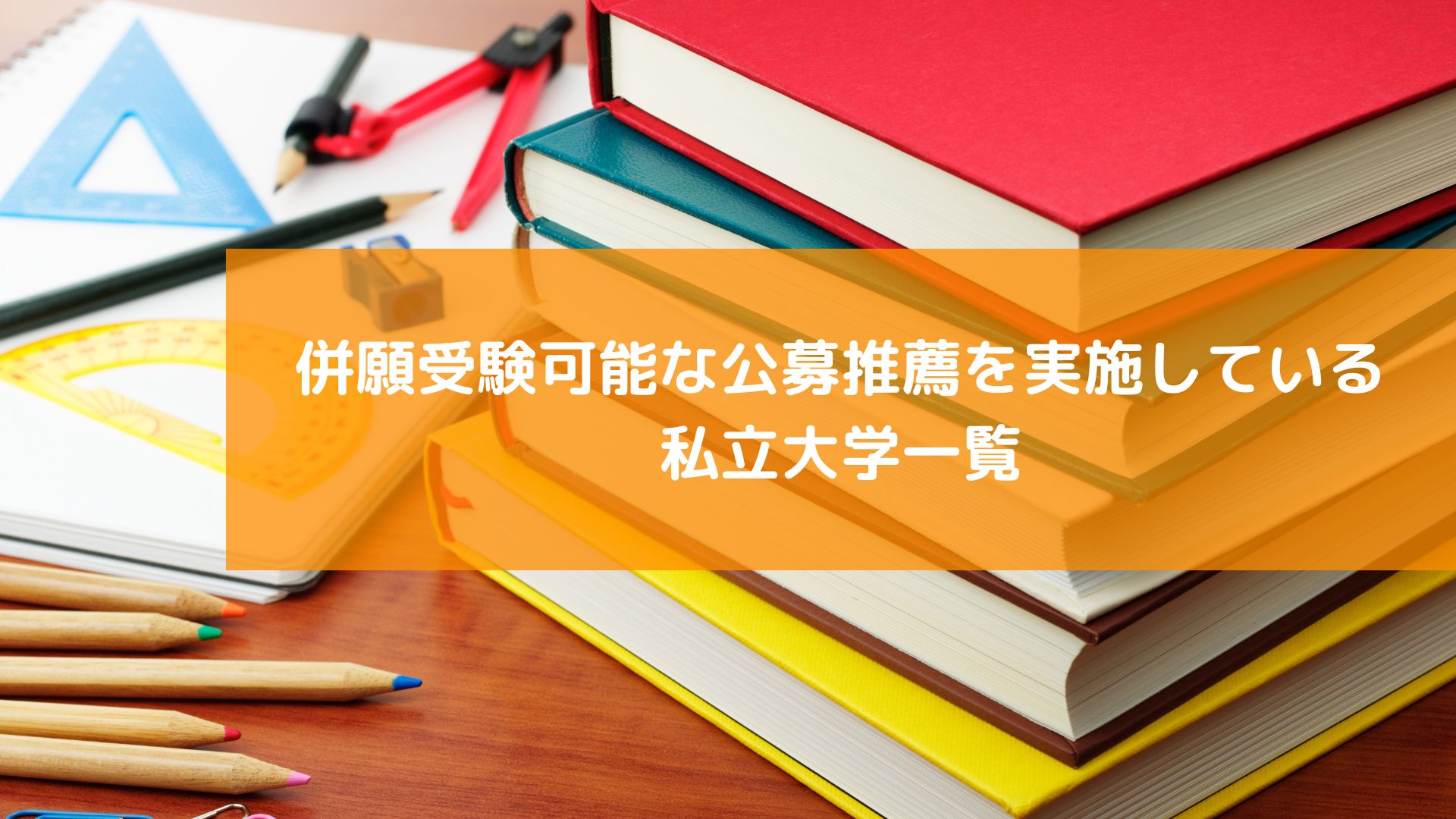
これまで見てきたように、併願制をうまく利用すれば、希望に沿った受験計画を立てられます。 ここからは、公募推薦で併願が可能な私立大学の一部をエリア別にご紹介します。ただし、公募推薦を実施する大学の全体から見れば、併願可能な大学はまだ少数派です。
本記事では関東と関西(近畿)の大学を中心に掲載していますが、北海道・東北(岩手、宮城、秋田、山形)、中部・甲信越(山梨、長野、静岡、愛知、福井)、中国(岡山、広島、山口、島根)、四国(香川、高知)、九州・沖縄といった全国の都道府県にも併願可能な大学は存在します。
特に、外国語や国際関係、医療・福祉、経営学部、芸術系などの専門性の高い学部・学科で併願可能な推薦入試を行う大学が見られます。英語の資格・検定(英検®︎ 2級以上など)のスコアを提出すると評価で優遇される特別な制度を設けている大学もあります。
最新の情報の最終的な確認は、必ず各大学のホームページや募集要項で確認してください。
関東地方で公募推薦を実施している大学(一部)
関東地方では、多くの国公立大学および私立大学で公募推薦が実施されています。以下は主に私立大学の一例です。
| 大学名 | 所在地 | 備考(2024年度実績や2025年度発表情報に基づく) |
|---|---|---|
| 青山学院大学 | 東京都 | 一部の学部で実施。出願要件が学部により大きく異なる。 |
| 学習院大学 | 東京都 | 多くの学部で実施。他大学との併願を認めていない学部が多い。 |
| 國學院大學 | 東京都 | 全学部で実施。評定平均値の基準などが定められている。 |
| 中央大学 | 東京都 | 商学部などで実施。学部により選考方法が異なる。 |
| 東洋大学 | 東京都 | 多くの学部で実施。「基礎学力テスト型」など多様な形式がある。 |
| 日本大学 | 東京都 | 学部ごとに多様な方式で実施。出願資格を要確認。 |
| 法政大学 | 東京都 | 一部の学部で実施。英語外部試験のスコアなどが求められる場合がある。 |
| 明治大学 | 東京都 | 一部の学部で実施。募集人数が少ない学部もあるため注意が必要。 |
| 立教大学 | 東京都 | 全学部で自由選抜入試(公募制)を実施。学部独自の基準を設けている。 |
| 大妻女子大学 | 東京都 | 複数の学部で実施。専願と併願可能な方式がある。 |
| 獨協大学 | 埼玉県 | 外国語学部や国際教養学部などで実施。評定平均の基準あり。 |
| 文教大学 | 埼玉県 | 多くの学部で実施。学部により試験内容が異なる。 |
関西地方で公募推薦を実施している大学(一部)
関西地方も、多くの大学で特色ある公募推薦が行われています。
| 大学名 | 所在地 | 備考(2024年度実績や2025年度発表情報に基づく) |
|---|---|---|
| 関西大学 | 大阪府 | 商学部や理工系学部などで実施。併願可能な場合が多い。 |
| 関西学院大学 | 兵庫県 | 国際学部や神学部などで実施。学部により特色ある選考を行う。 |
| 同志社大学 | 京都府 | スポーツ推薦のほか、一部の学部で公募制推薦入試を実施。 |
| 立命館大学 | 京都府 | 多様な入試方式があり、公募推薦に該当する方式も存在する。 |
| 近畿大学 | 大阪府 | 多くの学部で実施。出願者数が非常に多く、人気の高い入試。 |
| 京都産業大学 | 京都府 | 多くの学部で実施。併願可能な方式が中心。 |
| 龍谷大学 | 京都府 | 多くの学部で実施。「2教科型」「小論文型」など選考方法が多様。 |
| 甲南大学 | 兵庫県 | 全学部で実施。学部により試験日や科目が異なる。 |
| 摂南大学 | 大阪府 | 多くの学部で実施。スタンダードな2教科型選抜が中心。 |
| 大阪経済大学 | 大阪府 | 全学部で実施。基礎学力型と総合評価型がある。 |
| 神戸学院大学 | 兵庫県 | 多くの学部で実施。試験日が複数設定されている場合が多い。 |
| 畿央大学 | 奈良県 | 教育学部や健康科学部で実施。A方式・S方式など複数の評価方法がある。 |
※上記以外にも、北海道から東北、中部、中国、四国、九州・沖縄まで、全国に併願可能な大学があります。例えば長崎国際大学や熊本学園大学などでも実施実績があります。自分の志望する地域の大学情報を探すようにしましょう。
五十嵐写真02.png)
なお、国公立大学の公募推薦は、ほとんどが専願制です。つまり、その大学を第一志望とする学生でなければ出願できません。国公立大学の推薦選考を受けつつ併願校を確保したい場合は、国公立大学を第一志望校とし、合格したら必ず入学することを前提に、併願可能な私立大学を第二・第三志望として受験するパターンになります。
まとめ

専願と併願の制度、受験パターン、注意点、そして併願可能な公募推薦を行う私立大学について解説しました。 希望に沿った大学に進学し、充実した大学生活を送るため、また浪人を避けたいと考える受験生にとって、併願制度の理解は不可欠です。
高校生の皆さんは、本記事の情報を参考に、学力試験対策だけでなく、出願資料の作成や面接準備など、推薦入試特有の対策も計画的に進めましょう。制度をよく理解し、自分の活動実績や学力レベルに合った受験校選びに役立ててください。最終的な結果が良いものになるよう、応援しています。