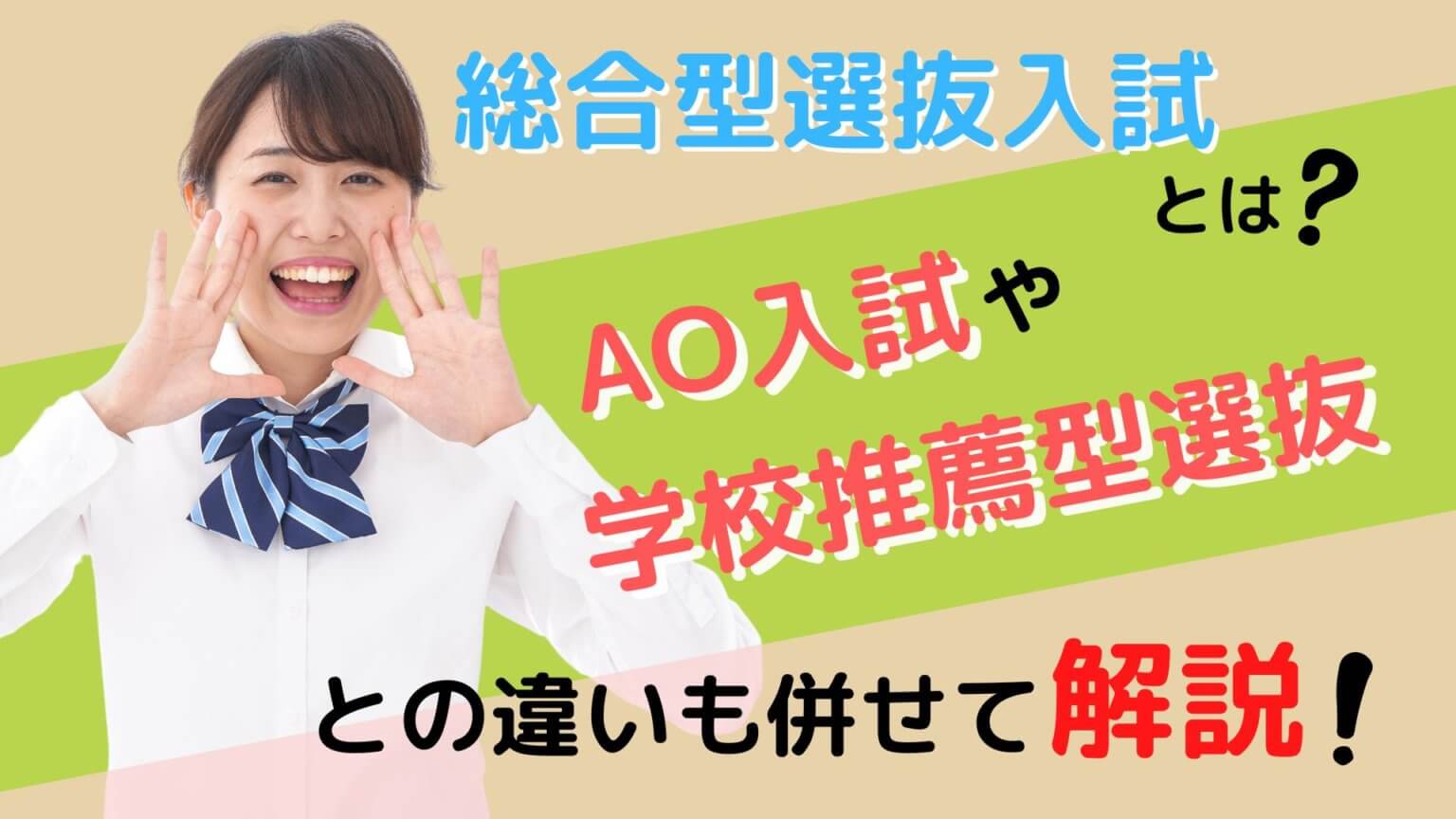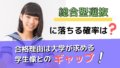総合型選抜入試って何?
大学に行きたい!そう考えたとき、その入試方式は1通りではありません。筆記テストを受ける一般選抜のほかに、『総合型選抜』と『学校推薦型選抜』という入試方式があります。
この記事では、総合型選抜入試の特徴とAO入試、学校推薦型選抜入試との違い、そして合格に向けた準備の進め方を紹介しています。
この記事を読むことで、総合型選抜入試への理解が深まり、入試方法の幅を広げて合格のチャンスを掴むための役立つヒントを得られるでしょう。将来の進路を考えるうえで、自分に合う入試方式を探す手助けになります。総合型選抜について詳しく知りたい人はぜひチェックしてみてください。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
総合型選抜とは?

総合型選抜とは、2021年度の入試から導入された制度です。それ前までのAO入試から名称が変わり、内容も一部変更になりました。まずは、総合型選抜の中心的な特徴を紹介していきましょう。
大学が求める学生像とのマッチングが重要
まず総合型選抜入試で押さえておきたい言葉が、「アドミッション・ポリシー」です。アドミッション・ポリシーとは大学の入学者の受け入れ方針のことで、それぞれの大学で、どのような学生に入学してほしいのかという基準が定められています。
この大学が求める人物像と受験生がどのくらい一致しているかを、提出された書類や試験の結果を通じて多面的・総合的にみて合否を判断するのが総合型選抜です。大学のサイトなどでアドミッション・ポリシーをしっかり確認し、自分の強みや将来の目標をどう伝えられるか考えることが第一歩です。
課外活動等も含めた総合評価を重視
では、「多面的・総合的に評価する」とはどんな点を見るのでしょうか?
選考には、調査書などの出願書類だけでなく、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」といった学力の三要素を評価することが求められます。例えば、小論文やプレゼンテーション、実技、あるいは英検®などの資格・検定試験の成績等を評価します。評価方式は大学ごとに異なるので、志望校の募集要項をよく確認しましょう。オープンキャンパスに参加して説明を聞くのもおすすめです。
さらに、志願者本人が記載する活動報告書などを積極的に活用することが文部科学省で定められており、部活動やボランティア、留学経験といった学習以外の主体的な取り組みも高く評価されることが特徴です。これらの実績は、あなたの意欲や社会への関心、人間性を伝える重要な要素になります。
私立大学では90%以上が実施
文部科学省の調査によると、近年、国公立大学、私立大学ともに総合型選抜を行う大学が増えています。国立大学でも約77%、私立大学では約91%もの大学が総合型選抜入試を実施しているのです!この割合は、大学入試改革の中心的な動きの一つと言えるでしょう。
参照:令和3年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要|文部科学省
五十嵐写真02.png)
あっという間に増加しましたね!大学側もアドミッション・ポリシーに合う学生、学ぶことへの意欲が高い学生に入学してほしいという思いの表れでしょう。
つまり、今の受験は一般選抜が全てではないといえるでしょう。
総合型選抜とAO入試との違いとは?

以前はAO入試という名前だった総合型選抜入試ですが、変わったのは名前だけではありません。変更点も比べていきましょう。
総合型選抜入試は学力も評価対象
AO入試だったころは、学力評価は必須ではありませんでした。総合型選抜入試では「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」といった学力の三要素を多面的に評価することが定められています。
そのため、各大学で決められた方式で書類審査と面接以外の試験があります。試験内容は大学によって異なりますが、小論文や、口頭試問、プレゼンテーション、特定のテーマに関するレポートなど、多様なケースがあります。
国立大学では大学入学共通テストを課す場合もある
国立大学では大学入学共通テストを課す場合もあります。その場合、合格発表が2月頃になることが多く、準備の計画を立てるうえで注意が必要です。
一般選抜との併願を考える人は、学習の負担がかなり大きくなる可能性も。しかし、第一志望の大学に入学したいという強い意欲がある場合は、チャレンジする価値が高いです。
五十嵐写真02.png)
ちなみにAO入試は専門学校の入試方式の一つとして行われています。ネットなどで検索するとAO入試という言葉がまだ出てくるのはそのためです。大学・短大では全て総合型選抜入試に呼び方が変わっています。
総合型選抜と学校推薦型選抜との違いとは?

総合型選抜と学校推薦型選抜の違いを表にまとめてみましょう。
| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 出願条件 | 出願条件を満たせば応募可能 | 学校長の推薦必須 |
| 出願時期 | 出願は9月以降 | 出願は11月以降 |
| 評価ポイント | アドミッションポリシーとの一致 | 高校生活全体の評価 |
| その他の特徴 | 受験方法は大学ごとに異なる | 指定校推薦と公募推薦で合格率が大きく異なる |
最も大きな違いは出願条件です。総合型選抜は出願条件を満たせばだれでも応募可能なことが特徴です。自分の評価を学校がするのではなく自分でするのが総合型選抜と言えるでしょう。
学校推薦型選抜入試は学校長の推薦が必須です。学校の推薦がいるから学校推薦型という名前だと覚えましょう。学校の推薦をもらうには、勉強に加えて出席日数や生活態度、課外活動なども評価の対象になるので、高校1年からの努力が大切です。
早めに知りたい!準備とスケジュールの例
総合型選抜の準備は、高校1・2年生のうちから早めに進めることが合格へのカギです。
まずは自己分析を行い、自分の強みや興味のある分野・テーマを明確にしましょう。夏休みなどの長期休暇を利用して、オープンキャンパスやイベントに参加し、大学の研究内容や環境を調べ、教員や在学生から直接話を聞くことも役立ちます。
出願書類の作成には時間がかかります。志願理由書や活動報告書は、具体的なエピソードを交え、自分の能力や意欲をしっかりと伝えることが求められます。塾や予備校の講師に相談し、サポートを受けるのも一つの手です。
以下に大まかなスケジュールの例を示します。
- 高校1・2年 基礎学力の定着、部活動や課外活動への取り組み、興味のある分野を探す
- 高校3年(4月~夏休み前) 志望校決定、オープンキャンパスへの参加、自己分析、情報収集
- 高校3年(夏休み~) 出願準備(書類作成)、小論文・面接対策
- 9月~ 出願
- 10月~ 選考(面接、小論文など)
- 11月~ 合格発表
まとめ

総合型選抜は、大学のアドミッション・ポリシーとの一致を重視し、学力だけでなく人物そのものを多面的に評価する入試方式です。
提出する書類の準備や、小論文・プレゼンテーション・面接などの対策には時間がかかりますが、しっかりと準備をすれば苦手を克服できます。塾や予備校のサポートを活用するのも有効です。
もし、強く入りたいと思う大学があるのならば、早めに情報を集め、総合型選抜へのチャレンジを検討してみてください。自分の可能性を信じて挑戦することで、きっと合格のチャンスが広がるでしょう!