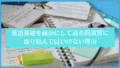「朝は机に向かうつもりなのに、気づいたらスマホを触って時間が過ぎていた」「せっかく計画表を作ったのに、三日後には白紙になっている」――こんな経験はありませんか?
多くの高校生が抱える悩みですが、意志の強さだけで解決するのは難しいものです。そこで大切なのは、科学的に考えられた“仕組み”を使って、習慣のハードルを下げること。
この記事では、行動科学や教育心理の研究をもとに、「起点」「時間」「人」の三つの角度から、毎日の勉強を自然に続けられるルーティンの作り方を解説します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
起点を整える
習慣の入り口でつまずくと、一日の学習がうまく立ち上がりません。意志力は有限であるとされ、朝の選択をいかに軽くするかが鍵です。ここで重要になるのが「起動スイッチの固定化」です。意思を働かせる前に、手が勝手に動くような“線路”を敷く発想です。
たとえば「起きる→コップ一杯の水→机の椅子に座る→昨日の“続き”を開く」という一連の流れを、一筆書きのように整理しておきます。机上には昨日の続きだけを開いた状態にし、付箋に「英語_続きから」と書いて貼ると、着席直後に思考がスムーズに起動します。
さらに、感情をほぐす“開始儀式”を取り入れます。簡単な儀式は、気持ちを整える装置として機能します。例えば「深呼吸三回→今日の一言メモ→一問だけ解く」といった30秒程度の軽い型です。重くなりすぎると逆効果なので、手軽さを意識します。
計画の見積もり誤差を減らす工夫も有効です。人は所要時間を短く見積もる傾向があるため、「計画前に過去の同種作業を3件だけ思い出す」という前処理で現実味を増します。さらに、自己評価の揺れにも対応します。「始められたらOK」「中断しても再開できたらOK」といった柔らかい基準をノートに書き込むことで、着手の摩擦を下げる“安全柵”となります。
週末には行動のみを振り返り、良かった起点・悪かった起点を一行で記録します。こうして、感情を和らげつつ、行動事実に戻す設計を組み込むことが重要です。
時間を味方にする
人には体内時計の波があります。朝がはかどる人もいれば、夕方に伸びる人もいます。理想の時間帯を無理に押しつけるのではなく、自分の“動きやすい谷と峰”を一週間だけ観察します。各時間ブロック前後に「着手の軽さ」「集中のキレ」を五段階でメモするだけで、自分の波形を可視化できます。
長時間の学習は失速しやすいため、時間を短く区切り、区切りの終わりには“終了儀式”を設置します。例えば「次にやる2行メモ→机を拭く→椅子を戻す」という流れです。終了儀式により次の起点も整い、短い散歩やストレッチで注意力の霧を晴らすことも可能です。
また、月初や学期初などの節目を利用するのも効果的です。新しいテンプレートを配布したり、着手の儀式を微調整することで、気持ちの切り替えがスムーズになります。目標までの距離感も可視化すると良いでしょう。例えば、問題集の背にシールを貼り、ブロックを終えるごとに色を塗ると、進捗が視覚化され、終盤で加速を感じやすくなります。
眠気や疲労との折り合いも現実的に調整します。就寝直前の刺激を避け、日中に自然光を浴び、短い仮眠を計画に組み込むことで、理解定着を助けます。眠気が強い場合は、短単語チェックやノート整理など軽作業に切り替えることで罪悪感を残さずに済みます。
人で支える
学習は孤独に見えますが、社会的な支えが効果を発揮します。他者の目や共通ルール、自己像の扱いを利用して、習慣を継続しやすくします。
まず、進捗の“公開度”を小さく上げます。一枚のシートに今日の着手の可否だけを記録し、家族や先生は結果ではなく「始められたね」と声をかけます。自己像も行動に結びつけて活用します。「私は朝の静かな時間に一問だけ解いてから登校する人」という短い自己像を持つと、判断が軽くなります。季節や行事で自己像を更新することも可能です。
さらに、価値観を思い出す作業も効果的です。学力や偏差値ではなく、「家族に喜んでもらいたい」「好きな分野を深めたい」といった自分の価値を一分で書き出し、今日の行動と結びつけます。価値→行動→具体の一行でつなぐことで、心と手が近づきます。
仲間との“黙々会”や先輩の手順模倣も効果的です。オンラインでカメラオフ、マイクオフでも、開始と終了の合図だけで孤独感が和らぎます。家庭内でも、スマホの置き場所や学習時間の家事音など、小さな合意を二週間だけ試すと、続けやすさが向上します。
実装の小ステップ
- 前日付箋に「次の一手」を二行書く
- 朝の開始儀式を30秒で固定
- 終了儀式で“続き”を見える化
- 一週間だけ波形メモをつける
- 着手チェック欄を家族と共有
これを“試験運用”として回し、うまくいったものは残し、重いものは捨てます。今日の“一歩が軽い設計”こそ、明日の“当たり前”を作る種になります。心身の安全が最優先であり、相談相手を増やすと視野も広がります。最終的に選ぶのは自分です。まずは、自分に合う“小さな型”から始めてみましょう。